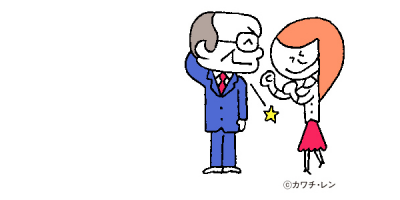学術に関わる施設の話が終わり、次の話題に移ります。
凡そ學たるものは唯タ道理を書物上にて知るのみにては可ならす。皆實驗に入らさるへからす。其實驗に二ツあり。Observation, Experience. 實驗とは現在にして眼のあたり彼より來るものなり。試驗とは將來にして己レより穿ち求むるなり。凡そ尋常の學者空理に亙るは實際に入らされはなり。學者苟も實際に入るを要すへし。
(「百學連環」第34段落)
文中に現れる二つの英語には、その左側に次のような訳語が添えられています。
Observation 實驗
Experience 試驗
では、訳してみましょう。
およそ学というものは、単に道理を書物で知るだけで済むものではない。実験が必要である。その実験には二種類がある。実験〔観察〕と試験の二つだ。実験〔観察〕とは、現在そのとき目の前で対象から来るもの〔を知覚すること〕である。試験とは、これから生じることを自らよく穿鑿することである。普通の学者が空理に及んでしまうのは、実際の物事のありさまに取り組まないからである。仮にも学者であるならば、実際の物事のありさまに取り組まなければならない。
ご覧のように、話は「実験」へと移っています。「実験」とはつまり「実際の経験」です。
西先生が「實驗」と訳した Observation は、現在では「観察」「観測」などと訳される言葉。物事のありようを、よく知覚することですね。
例えば、植物を観察するとか、天体を観測するとか、森羅万象のなにごとかについて、それがどういうものか、どのような構造をしているか、どのように変化するものかといったことを感覚を通じて知ることです。場合によっては、望遠鏡や顕微鏡その他の道具を使って、人間の裸眼や素の身体では知覚しえないものを観察することもあります。現代語訳では、先に出てきた「実験」と区別するためにも、括弧書きではありますが「観察」と加えてみました。
もう一つの Experience は、今なら「経験」や「体験」と訳される言葉です。ただし、この英語の語源に当たるラテン語の experientia という名詞には、「経験」の他に「試み」「試験」という意味がありますし、その動詞形 experior は、「試す」という訳語が充てられます。つまり、なにかを実際に試してみることです。そういう意味でも「試験」という訳でよいでしょう。
ここで面白いのは、「観察」と「試験」について、「現在」と「将来」という時間の要素で説明しているところです。「観察」はただいま現在のことであり、「試験」はどうなるか、これから行ってみる将来のこと。
また、「観察」は、対象(客体)から観察者(主体)へ伝わるという向きであるのに対して、「試験」は、試験者(主体)から対象(客体)へ働きかけるという向きがあることにも注意したいと思います。
時間と作用の向きという二つの点において、なにか「観察」と「試験」とが、対置されている様子が窺えます。
そして、学者の中に空理に陥ってしまう人がいるのは、観察や試験といった実際の経験(実験)によって、事物そのものに当たらないからだ、というわけです。
こうした西先生の見立てには、ひょっとしたらオーギュスト・コント(1798-1857)の発想が重なっているかもしれません。ここで私たちが読んでいる「百学連環」の「総論」でも、あとでコントの「実証主義」という考え方が論じられるはずです。このコントという人は、「実証」「観察」「経験」を重視した学問論を主張しているのです。
その学問の見立てを要約すれば、彼は人間の知識が三段階を辿ると考えています。つまり、「神学(虚構)段階」「形而上学(抽象)段階」「科学(実証)段階」です。
神学段階というのは、例えば、神話の世界がそうであるように、自然現象を神という虚構で説明するような段階です。雷はゼウスが投げる武器だという「説明」などがこれに該当すると思います。
形而上学段階というのは、神様のような超自然的なものに頼った説明こそしませんが、本当にそうかどうかとは別に、物事を抽象的な理屈で説明しようとする態度のことです。例えば、地球は宇宙の中心に静止した特別な天体であり、太陽その他の星々がその周囲を回っている、といった考え方を思い浮かべてもよいでしょう。
ここまでの二つの段階は、コントによれば、観察よりも想像を優先する態度です。
第三段階の科学段階で、ようやくこの優先順位が逆転して、人間が考える「こんなふうになっているのではないか」という想像より、実際に観察されることが優先されるようになる、というわけです。例えば、さまざまな観察・観測結果から、地球が太陽の周囲を回っているということを実証する態度です。想像が観察によって訂正される段階です。
「およそ学というものは、単に道理を書物で知るだけで済むものではない。実験が必要である。」という西先生の議論もまた、実証(実際による証明)の必要を強調する点において、コントの発想に重なっているのではないかと感じた次第です。