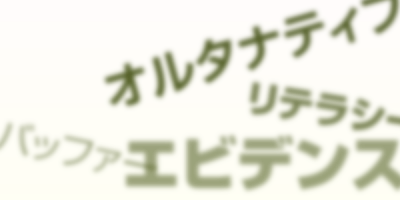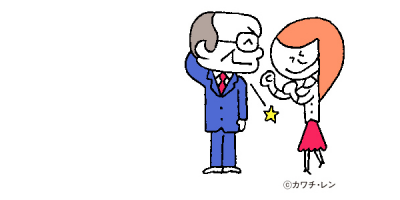西先生は、演繹の概要を理屈で説明した上で、今度はそれを具体的な譬えで重ねて説きます。こんな具合に。
之を猫の鼠を喰ふに譬ふ。猫の鼠を喰ふや、先ツ其の重なる所の頭より始め、而して次第に胴四足尾に至るなり。古昔聖賢の學も孔子は仁智と言ヒ、孟子は性善を説く。孔子の如きは更に論しかたしと雖も、孟子言ヘハ必稱堯舜と、卽ち性善を説くものにして、仁智と言ひ、性善と言ふも皆重なる所の記號にして、是よりして幾緒の道理を引き出すなり。古來儒者たる者その理にして、經書を學ふ者は之を重とし、歴史は歴史を重とし、總て其重とする所よりして種々の道理を引き出す、是則ち猫の鼠を喰ふ演繹の法なり。
(「百學連環」第37段落第7文~第11文)
いくつか補足します。まず、「記號」には、その右に「カンハン」とルビが振られています。また、「經書」「儒者」の「儒」「歴史」はそれぞれその右に「孟子」「學」「論語」と添えられています。
では、訳してみましょう。
これを猫がネズミを食べる場面に譬えてみよう。猫がネズミを食べる場合、まずその重要な部分である頭からとりかかり、それから次第に胴、四足、尾へと至る。昔から、聖賢の学においても、孔子は仁智と言い、孟子は性善を説いた。孔子のほうは更に論じるのは難しいが、孟子のほうは、「必稱堯舜」と〔必ず堯と舜を引き合いに出して〕、性善を説く。「仁智」といい、「性善」といい、これはいずれも重要な部分についての記号であり、ここから様々な道理を引き出すのである。古来、学者たる者は、〔そうしたものを〕理にして、経書を学ぶ者であれば経書を重要なものとするし、歴史を学ぶ者は歴史を重要なものとする。いずれの場合でも、その者が重要だとするところから種々の道理を引き出すのである。これがつまり、猫がネズミを食べる演繹の方法である。
なんとも意外な譬えが出てきました。西先生は、演繹法を猫がネズミをどうやって食べるかということに譬えています。ここで「重なる所」をどう読むかで、少し迷いました。最初、私は「かさなる所」と訓読みをしたために、はて、どういう意味だろうかと首をひねったのでありますが、これは恐らく「おもなる所」「じゅうなる所」と読むべきでしょう。要するに、何を重要なもの、重きを置くべきところ、勘所とするかというわけです。ここから翻って考えれば、「かさなる所」と読んだとしても、種々のものにおいてかさなっている部分という具合に理解できそうです。
この譬えは、ここだけを読むと、ちょっと意味を分かりかねます。猫がネズミを食べるとき、ネズミにはいろいろな部位があるけれども、その重要な部分である頭から食べるだろう、それと同じように演繹法は……というのですが、私はかえって混乱してしまいました。皆さんはいかがでしょうか。この譬えの意味は、後に帰納法について同様の譬えが持ち出されるところで、腑に落ちるかもしれません。
ただ、この譬えを読んでこうも思いました。ひょっとしたら、ここで大切なことは、厳密な理解というよりも、そのままでは捕らえどころのない抽象的な話を、身近で誰でも想像できるような、具体的な姿形で思い浮かばせることかもしれない、と。さらに進んで想像を逞しくすれば、この譬え自体が、一種、記憶の便宜にもなりそうです。
古代ギリシア以来、西洋で長い伝統を持っていた記憶術では、覚えたいことをただ覚えるのではなく、脳裏に強烈なイメージとセットにするというコツがありました。「演繹法」という極めて抽象的な、言語や論理の操作を、猫がネズミを食べる場面に譬えれば、受講者は「演繹法」といえば、なにはさておき、この猫とネズミのことを思い出すかもしれません。現に私自身、「百学連環」の中でも、この譬えは忘れがたいものの一つになっています。
さて、西先生は、そのように譬えて、聴講者にとても具体的なイメージを与えた後で、今度はまた別の角度から例を出します。ご覧のように、中国古典、儒学の例です。
孔子や孟子を思い出してみよと西先生は言います。恐らくこの講義を聴いていた人びとにとって、孔子や孟子は、現在よりずっと身近な例であったでしょう。江戸時代の藩校などでも、孔孟は教科書として使われ続けていました。孔子は「仁智」と言うし、孟子は「性善」と言う。そして、彼らはいわばこの一つの鍵概念から、様々な道理を引き出してくる。というわけで、猫とネズミの譬えから、もう少し本来の演繹に近い例を出しています。
ところで、「記號」に「カンハン」とルビが振ってあるのが、少し気になります。「カンハン」とはおそらく「カンバン」のことだと思います。これは何々だ、と号(しるし、名前など)を記したものということでしょうか。 同じ箇所を、「百学連環」の「乙本」で見てみると、やはり「記號」に「カンハン」とルビが添えられており、さらにその右に白丸で圏点が三つ振ってあります。その上、その行の上部余白に「據り處」とあり、この文字にも黒丸が三つ振ってあります。
いま仮に、「記號」を「據り處(拠り所)」と置き換えて、当該箇所を読むと、こうなります。
仁智と言ヒ、性善と言ふも、皆重なる所の一つの據り處にして、是より幾緒の道理を引き出すなり
(「百學連環」乙本)
「仁智」や「性善」という鍵概念を重要な「拠り所」として、ここから様々な道理を引き出す。これは、「記號」に比べて、私たちにもいささか腑に落ちやすいのではないでしょうか。