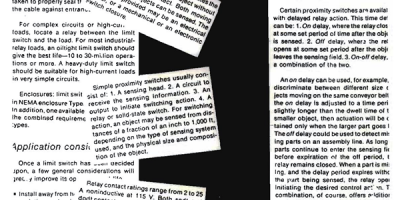東浩紀氏の指摘による「世界のデータベース化」(前回)は,しかしながら,「登場人物には物語は不要」という考えとは切り離して理解すべきかもしれない。というのは,東氏のデータベース消費論そのものに対する否定ではないものの,この理論がそうした物語不要論という文脈で展開されたことには,反対の声が上がっているからである。宇野常寛氏は,登場人物が物語から独立するというのは「幻想ではないだろうか」,登場人物は「物語とその共同性から無縁ではいられないのだ」と繰り返し述べておられる(宇野常寛2008『ゼロ年代の想像力』pp.43,47,東京:早川書房)。氏の考えがよく現れていると思える箇所を次の(1)に挙げておく。
(1) データベース消費モデルは,むしろ物語の力を肥大させる。登場人物は決して「小さな物語」を超越しない。個々の小説,映画,漫画作品を越境して共有されることはあったとしても,それらの作品を規定している共同性を決して超越することはない。登場人物は表現の空間からは独立するかもしれないが,物語には隷属するのだ。 [宇野常寛2008『ゼロ年代の想像力』p.48,東京:早川書房]

こうした議論のゆくえは,「物語」という前提概念の定義次第で左右される部分も大きいだろうが,ここでは,これまであまり話題にされていないと思えることを述べてみたい。それは,この問題を,(一次創作者であれ同人誌などの二次創作者であれ)創作者の視点ではなく,鑑賞者,それも多くのごく普通の鑑賞者の視点でとらえてみればどうなるか,ということである。
話はいきなり私自身の幼少時代(1960年代後半)に飛ぶ。その頃の多くの男児と同様,私もテレビ番組『ウルトラマン』や映画『ゴジラ』シリーズに登場する怪獣に興味を持っていたが,「怪獣博士」と呼ばれるような一部のオタクとは違って,さほど詳しくはなかった。所持している怪獣のソフトビニール製人形(いわゆるソフビ)も数体に過ぎず,そのうち1体は正体もわからない,謎の人形だった。これは今は亡き奈良ドリームランドという遊園地の土産物店でなりゆきで買い与えられたもので,他の怪獣とは少し違った素朴な形状をしていたが,ごわごわの透明ビニール袋には何の説明もなかった。実は怪獣ではなく,単に恐竜トリケラトプスの人形だったのではないかと今は思っているが,当時はそんなことはどうでもよかった。私の頭の中で,そいつは鈍重だがおそろしく力の強い怪獣と設定され,レッドキングやガバラといった他の凶悪な怪獣どもと連日死闘を繰り広げた。もしもウルトラマン第8話『怪獣無法地帯』(レッドキング登場)やゴジラ映画『オール怪獣大進撃』(ガバラ登場)を「物語」と呼んでよいのなら,私の部屋,私の脳内で日々展開されていた彼らの死闘もれっきとした「物語」である。
どこかの国の兵隊の人形,名もない人形,そんなものでも,私たちは遊び楽しむができる。そしてその時,私たちの頭の中では,自分で作り上げた物語が動いている。一切の物語を想像せず,登場人物を活動させず,ただ眺めることで楽しめるオタクがいるのかどうか,私は知らない。が,少なくとも多くの鑑賞者は,創作者から提供されたものであれ自前のものであれ,登場人物を物語の中で楽しむのではないだろうか。