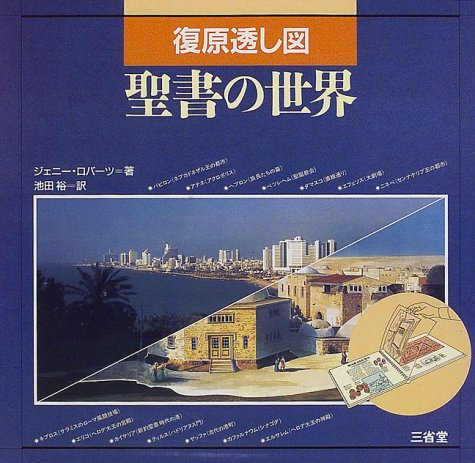三省堂 辞書ウェブ編集部による ことばの壺
聖書思想事典 新版
- 定価
- 6,820円
(本体 6,200円+税10%) - 判型
- A5判
- ページ数
- 1,008ページ
- ISBN
- 978-4-385-15349-0
-
改訂履歴
- 1973年11月21日
- 初版 発行
- 1999年12月15日
- 新版 発行
聖書の理解に最適なキーワード事典。
聖書の理解に最適なキーワード事典。
刊行以来四半世紀、ミレニアム(千年紀)を迎え、新共同訳聖書に準拠した待望の新版。
聖書の内容を知るためのキーワード331語を選択して解明。
特長
さらに詳しい内容をご紹介
「聖書思想事典」の内容より
序論
CD-ROM版聖書思想事典(品切)より採録
I 聖書の思想
本事典は、元来は、聖書の用語に含まれている教義的・霊的意味を説明するために発案されたものである。しかし、実際に仕事にあたってみると、一つの言葉には一貫した深い統一のあることが明白な事実としてただちに浮かび上がってきた。つまり、聖書記者たちの生きた時代や環境、遭遇した歴史的出来事は多種多様であったにもかかわらず、彼らの精神と表現には真に共通した面がみられるのである。このような聖書全体の統一性は、根本的には信仰の所産であり、具体的には個々の用語を通して確証される。
1.聖書の総合的把握 聖書は、人間に与えられた神の言葉である。人間は聖書の内容を研究し、その声に耳をかたむけ、その表現方法を探究しながら、要するに、自分自身神の言葉の純粋なこだまになろうと努めながら、聖書の思想を体得してゆく。その際、神の言葉を種々の角度から考察して総合的にとらえる必要がある。この総合はすでに聖書のなかでなされているが、その展開や自覚には、啓示の発展段階に即して差異がみられる。たとえば、ヤーウェ伝承と申命記伝承における歴史観、祭司伝承と知恵文学における説明、また共観福音書各書間にみられる視点、パウロの手紙とヘブライ書における主題、ヨハネの黙示録とヨハネ福音書における描写は、それぞれ異なっており、それなりの根拠をもった思索つまり“神学”を提示している。しかしながら、もっと広い観点に立って考察すれば、聖書は全体的なまとまりをもっているといえる。したがって、聖書記者たちの種々の思索のなかに有機的な連続と関連を見いだそうと努めつつ、聖書全体の深い統一を指摘することができる。これがいわゆる聖書神学の任務である。
イ.聖書の統一性 聖書に統一性があることを確信をもってさとし、これと他の書物との区別を認めさせるのは、一つの共同体の信仰である。エノクの譬(たとえ)やソロモンの詩編のように、宗教的にすぐれた価値を有し正典書のもっとも美しい部分にも匹敵する書が、正典に数えられていない反面、民衆的な英知からでた諺(ことわざ)でありながら、正典の格言書のなかにはいっているものがある。実際、正典を識別する際の基準となるものは、神の民の信仰以外にはない。信仰こそは、旧約・新約両聖書の種々の書物を有機的なまとまったものに仕上げるのである。神の民と信仰をともにしない人も、聖書思想の総合的理解の出発点にはこの信仰があることを知らねばならない。 聖書の統一性は抽象的なものではない。それは、聖書の中心に位置を占める方からくる。キリストを信ずる者にとっては、ユダヤ教の正典書は、旧約聖書として全聖書の一部分となっているにすぎない。旧約のこれらの書き物は、この世に来臨し旧約のすべての約束を実現する方を、告知し準備するものである。この方とは、イエス キリストである。新約の諸書は、イエスの歴史における出現を中心思想とし、世の終わりにおける彼の再臨を指向している。旧約聖書は、約言すれば、イエスを準備し前表している書であり、新約聖書は、彼がすでに来臨し、かつふたたびくることを告げる書である。このような根本的な真理については、イエス自身、「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである」(マタ5:17)という句で明確に指摘している。教会の教父たちは、この基本的な原理に関してうまずたゆまず思索をめぐらし、これを表わすもっとも適確な比喩(ひゆ)を聖書そのもののうちに探しだそうとしている。その好例として、旧約を水に新約をぶどう酒にたとえて、水がぶどう酒に変化したことを指摘している。本事典の各項目は、イエスの福音によってすべてが新しくされるとき、旧約時代に前表として生起した事柄は実現するという、聖書思想の根本を浮き彫りにするよう執筆されている。このような方針から、数多くの結果が生じることになる。たとえば、結婚に関する創世記の教えと処女性に関するイエスやパウロの教えとを分離することはできないし、また、人間の典型は創世記に示されたアダムではなく、第二のアダムなるイエス キリストであり、人類はただ彼においてのみ兄弟となりうるということが明らかになる。 次に、聖書には統一性があるといっても、それは、人間の諸体験に特別の意味を付与し人類の歴史に方向づけをおこなう軸のようなものからくるとだけ考えてはならない。聖書の統一性は、救済史のいたるところに現存する神の命に、そしてたえず働きつづける神の霊に由来する。聖書神学は、神の民がその歴史の諸段階において受け取り、彼らの思考の実体ともなっている神の言葉のこだまにすぎない。ところで、この神の言葉は、なにかを教えるものであるよりも、まず一つの出来事・招きとして告知される。神の言葉は、言いかえれば、自分の民に語るべくすでに訪れた神、今もたえず訪れている神、終わりの日にイエス キリストにおいて万物を復興させてその救いの計画を完成させるために来臨する神自身でもある。神と人間との親密なかかわりのうちに織りなされてゆくこの出来事を、聖書記者たちは、神の契約・選び・現存など種々の概念を用いて表現している。概念そのものはそれほど重要ではなく、実際の出来事の認識は、神の民の全成員に相互の精神的親近感、さらに同じ信仰と世界観とを生みだす。このようなことは、たとえば、聖書記者が近隣諸国の文化・思想・宗教から提供される遺産にどのように対処しているかをみても明らかである。彼らは、これらを異教的要素から清めて摂取する。その際、これらはつねに、方法は異なっても同じ精神に基づいて、真の啓示に奉仕させるために用いられている。その例として、メソポタミアの創造神話や洪水(こうずい)伝説、カナン神話にでてくる嵐(あらし)の象徴的な意味、ペルシア思想における天使の概念、サテュロス(鬼神)やふきつな獣を登場させる民間伝承などがあるが、いずれも、その救いの計画を人類の歴史のなかで展開させる創造主なる神への信仰によって純化され、新しい意味づけがなされている。聖書の諸伝承や宗教的な諸概念には、このようにその全体を通じて一貫した精神が流れているがゆえに、聖書神学、つまりただ一つの神の言葉を種々のかたちのもとに総合的に理解することが可能となるのである。
ロ.聖書の総合性 聖書は以上のように、神自身がそうであるように、単一なものであると同時に、神が創造した宇宙のように広大無辺である。神だけが、宇宙万物を一望のもとにとらえることができる。本事典は、神の業の単一性と神の視線の総合性とを前提としている。そして実際には、この総合性を各用語の分析という形式を用いて紹介することになるけれども、それはけっして、聖書の統一性を理解しようとする読者の意欲をくじくためではなく、ただ、抽象的な体系化を押しつけることを避けたいからである。このような体系化は、ある場合には独断的なものとならざるをえないのである。読者も、このような本書の主旨を諒(りょう)とされ、一つの項目から他の項目へとゆきつもどりつし、これらを比較・分類しながら、聖書内容の正しい理解に努められるよう要望する。 それにこの方法は、聖書の本来的なあり方に忠実である。たとえば、サムエル書と歴代誌の見解を続けて理解することにより、ダビデが在世中と以後のイスラエル人の記憶のなかでいかに把握(はあく)されているかについて微妙な相違を認識することができる。同様に、イエス キリストの奥義についても、四福音書記者のそれぞれ異なる観点に留意しながら読むことにより、より深い理解が得られる。このように“用語事典”としての本書は、神の民・神の国・教会などそれぞれの時代に用いられた種々の表現、アブラハム・モーセ・ダビデ・エリヤ・洗礼者ヨハネ・ペトロ・マリアなどの代表的人物、契約の箱・祭壇・神殿・律法などの諸制度、預言者・祭司・使徒など契約の保持に努めた人々、さらに世・反キリスト・サタン・獣など約束の実現に逆らう諸要因を説明しながら、契約の奥義をよりよく理解するよう助ける。また、神の前における人間の態度については、祈り・礼拝・賛美・沈黙・跪(ひざまず)く・感謝・祝福などの項目から一つのまとまった理解が導きだせるであろう。 聖書の世界にはいってゆくためには、神があらゆる場所と時間のなかに現存していることも知るべきである。歴史の主なるヤーウェは、そのなす業すべての上に自らを反映させているからである。また聖書がとりあげている人間に関する概念のなかには、特定の文化圏に従属していて相対的価値しか有せず、合理的批判に服すべきものもあり、これらは正しく評価することが肝要である。そのためたとえば、人間を霊魂と肉体という二つの部分からなる合成物としてではなく、霊・魂・体・肉などの種々の側面を通して全体的に自己を表現する人格的存在として総合的に把握するよう努めねばならない。これらの諸観点はたしかに見落としてはならないものであるけれども、実は人間に関する基礎的な概念を示しているにすぎず、その点では第二義的な意味しかもたない。というのは聖書によれば、人間は、ギリシアの哲人を感嘆させた小宇宙としてそれ自体が分析されているのではなく、あくまでも、神の似姿として神の前に立つもの、しかもキリストを通してこの似姿を回復すべきものとしてながめられているからである。 他方、聖書が語る出来事・制度・人物をもとに、一種の歴史に関する神学を粗描し、神がその業を成就してゆく道を知ることができる。この歴史の神学の理解にあたっては、セム人は、時間を人間の行為によって満たされてゆく空の枠(わく)とは考えていないことに留意すべきである。彼らによれば、歴史は、創造主の命が躍動する世代の連続によって構成されている。そしてこの聖書的文化圏が提供する歴史観を認めた上で、その特異性に注意し、時間に関する聖書固有の概念を理解しなければならない。近隣諸国の神話の場合とは反対に、時間は、神々の原初の時間が人間の世界のなかで反復されているものとは考えられていない。また祭儀においては慣習によって認められた祝祭暦が採用されているけれども、そこには新しい意味づけがなされている。つまりそれは、人類史の初めと終わりにあたる“創造”と“主の日”という二つの時の間におかれている。さらに、人間の歴史も年・週・日・時によってくぎられているが、実はこれらの時間単位はすべて、主の現存により、主のこの世への来臨の思い出により、そして主の再臨の希望により、単なる反復のたいくつを免れている。このようにして万物の終わりが到来するのであるから、二つの都なるエルサレムとバビロンの戦い、善と悪の対決、敵との戦いは、もはや破局的な戦いではなく、無窮の平和の序曲であり、そしてこの平和は、神の霊が生きている教会の存在によって現在すでに保証されている。 神はその業を通して、ついに自らの心を現わし、人間に自己の真の姿を知らせる。人間は、罪を罰する神の怒りや憎しみについても語らねばならないが、実はこのようにして、自分が受ける罰のうちにおいてさえ、教育し命を与えようとする神の愛の認識に近づく。そこで人間は、自分の生き方の模範を神のなかに認め、これによって自分を律しようと努める。そして人間が身につけるべき柔和・謙遜(けんそん)・従順・忍耐・単純・憐(あわ)れみ、さらに勇気・誇りなど、すべての徳は、生ける神と聖霊の力のなかにいるみ子イエス キリストの現存によって真正の意味を帯びるようになり、かつ堅固なものとなって効果を発揮する。同じく人間の種々の状況についても、その真の意義が説明される。すなわち、喜びと苦しみ、慰めと悲しみ、平和をもたらす勝利と迫害、命と死などすべては、神の言葉が啓示する救いの計画のうちにおかれるのである。かくていっさいは、主イエス キリストの死と復活のうちに意味と価値とをもつようになる。
2.表現の相対的性格 聖書の理解可能な内容全般を支配している宗教的・精神的構造は、特有の表現形式をつくりだすまでに至っている。そこで、聖書の表現の問題に言及する必要がある。たしかに聖書のなかでも、用いられている言葉は、他の一般の書物の場合と同様時代とともに変遷している。そして、霊感の働きは、概念や思想だけでなく、それを表現する言葉にまで及んでいるといえる。新約の啓示通有の言葉として、“新約聖書的”コイネ ギリシア語を認めることができる。このギリシア語は、旧約聖書のギリシア語訳である七十人訳聖書の用語法に密接に依存している。このような連続性から、少なくとも聖書独得の思想を表現するために、この世界固有の言葉があるといえないだろうか。この点も、聖書の思想を旧約から新約にかけて用語別に略述するようふみきらせた理由の一つである。だからといってもちろん、純粋に意味論的・語義論的説明を展開しようという意図はなく、ただ、聖書の世界にみられる種々の描写と象徴をとりあげ、その意味するところを明らかにしたいのである。聖書にでてくる種々の表現は、当時とまったく異なる精神的環境に生活している人々にとってもなおも価値あるものであろうか。これはたしかに、多くの現代人がいだく疑問であろう。天上の奥義は、今日でも、新約聖書が使っているような描写、たとえば、楽園や幾層にも積み重なっている諸天、あるいは宴会や婚礼の比喩を使って告げるべきであろうか。今でも、神の怒りについて語ることができるだろうか。イエスが“天にのぼり”、“神の右に座った”とはなんの意味であろうか。聖書思想の内容の叙述にあたってはかなり容易に得られる意見の一致も、こと表現法を明確にする点になると破られるのではないだろうか。啓示の真髄に達するためには、用語の“非神話化”が必要なのではないだろうか。今ここで、聖書用語の非神話化という全般的な問題を解決しようなどとは思わないが、ただ、言葉なるものがいかなる意味で真理の媒介であるかを、深浅二重の段階に分けて指摘したいと思う。
イ.比喩と現実 人間の精神は、神の啓示にふれるとき、相反する二つの動きによって反応を示す。すなわち一方では、啓示を伝える出来事をできるだけ明確に描写しようとし、他方では、啓示の教義的内容を少しずつ正確な言葉で表現しようとする。そして実は、出来事の実存的描写も教義的内容の表現も、いずれも、それが生まれた文化的環境によって左右され、変形される危険にさらされている。しかし、その際こうむる危険は二つの場合において同じではない。出来事の描写の場合は、なんら超自然的意味をもたない文字どおりの単なる報告になってしまい、信仰による精神的帰依を少しも促さない危険がある。教義的内容の表現の場合、それを生んだ出来事から離れて奥義を抽象的な思弁に引き下げる危険がある。とはいえ啓示においては、いつもこの二つの表現方法、つまり事実の具体的描写と抽象的な定義とが前提となっている。ところで、祭儀における信仰宣言(申26:5~10)とか信仰の定義(ヘブ11:1)などにみられるように、本質的な事柄が端的に表明されている場合もあるが、ふつうは、神の民が生きている契約の奥義を具体的出来事を通して示唆するという実存的描写が用いられている。ここで最初に着手すべき仕事は、聖書の表現方法を非神話化し、その内容を現代人の心性に合わせることではなく、むしろ、その内容を健全に理解できるような接近の道を発見することである。 聖書を読んでまず気づく表現法としては、簡単な比喩がある。イザヤの「森の木々が風に揺れ動くように」(イザ7:2)などはその一例である。比喩的表現は、啓示の用語を富ませうるとしても、それ自体直接に啓示を伝えることはできない。比喩は、それを生んだもとの経験を離れて、それを用いる者の嗜好(しこう)と想像力に応じて自由におき換えられうる性質のものであり、啓示の表現法においては、取り替えのきく衣のようなものにすぎない。しかしこの衣は、聖書の表現法のなかでは想像も及ばないほど大きな場所を占めている。というのはセム人にとっては、この比喩を通して、語源的意味がいつもいきいきと働いているからである。このようなことは、他の言語意識にはあまりないのではなかろうか。たとえば、“栄光”を意味するヘブライ語カーボード(ヘ:k?bod)は、しだいにさんぜんたる光輝というような意味も帯びてくるようになるが、やはり原意の“重さ”とか“富”という概念を背景として保っている。パウロが選ばれた者のために天に備えられている栄誉を「重みのある永遠の栄光」(IIコリ4:17)という言葉で指摘しているのも、そのためである。 最初の語意は、このように文化の衣装をまといながらも恒久的なものとして留(とど)まるが、他方では命あるもののごとく弾力的な道をたどる。その場合、多様な表現を用いながら、一つの言葉がもつ本来の意味を保持しようとの努力もなされている。この現象は、七十人訳聖書の翻訳のなかでとくに目につく。その例をいくつかあげると、まずこの翻訳では、ふつうの用法とは明らかに異なる意味をギリシア語に与えてヘブライ語の内容をじゅうぶんに表わそうとの試みがなされている。たとえば、ヘブライ語のカーボード(ヘ:k?bod)を“重いもの”ではなく、“意見”とか“風評”を意味するギリシア語のドクサ(ギ:doxa)で訳している。次に混同の危険のある礼拝的な響きの言葉のなかには、訳者が使用を避けたものがある。たとえば、ベラーカー(ヘ:ber?k?h“祝福”の意)の訳語として、エウフェーミア(ギ:euph?mia)のかわりにエウロギア(ギ:eulogia)が選ばれているが、後者は、前者ほどヘブライ語の意味合いを表わしえないとはいえ、中立的で順応性に富むという利点をそなえている。第三に、ギリシア語の助けをかりて、ヘブライ語のあいまいな意味が明確にされている場合がある。たとえば“契約”という言葉についていえば、自己の財産を処理する遺言とか、それをおこなう意志を表明する行為をさすギリシア語(ギ:diath?k?)が、本来は協定とか契約を意味するへブライ語(ヘ:berit)の訳語として用いられることにより、神の超越牲が強調されると同時に、イスラエルの民を起こし律法を授けるとき、神がどれほどへりくだったかも明らかにされる。以上のような翻訳上の言語操作は、言葉はそれを利用する人間の精神ほどたいせつなものではなく、人間は言葉を用いて自分の道をきり開いていくことを示している。しかし、言葉がこのようにあやつられるということは、その限界の告白でもある。このことは、人間の言葉は、どんなにすぐれていても、神に関する体験を言い表わしえない点に如実に示される。神は、言うまでもなく、描写と比喩の範疇(はんちゅう)外にあるからである。聖書の言葉は、表現の限界を認めながらもそれを用いつつ、あくまでも人間の体験のなかに根を張った具象的なものであり、かつ物質的描写を通して霊的次元の事柄を表わそうと試みるのである。たとえば幸いや報いに関する最初の描写はすべて、人間が体と魂をもってあずかる地上の幸福を想起させる。イスラエルの希望がより霊的なものとなっても、これらの描写は、消え去ることはなくなおも存続するが、しかしそのときには、人間を待つ幸福の経験を直接に表現するよりも、適切な言葉では表現することのできないより高遠な希望とか神の待望を象徴するものとなる。この段階に達すると、地上的現実から借りた描写と比喩が、啓示を表わすためのふつうの手段となる。もっともそれらは、それ自体では啓示の価値を有しないが、聖書用語としてのその歴史、よび起こす連想、ひき起こす反応などによって、神の言葉を伝える媒介となる。したがって、このような描写とか比喩はじゅうぶんに尊重しなければならない。
ロ.象徴と啓示 他の次元の表現に難なく適用されうる比喩と異なり、聖書の象徴は、これを生みだした啓示とたえずつながりを保っている。本事典の諸項目は、世のなかの種々の要素、神の民が体験するさまざまの出来事、いろいろの習慣や制度が、いかに神が人間と交える対話の糸口になるかを示そうと努めている。実際、神はすでに、創造の業を通し、あるいはみずから導く歴史を通して人間に語りかけているのである。 聖書では、天は、自然の“天”と超自然の“天”というように2種類に区分されておらず、ただ目に見える天のなかに神とその業の神秘がながめられている。たしかに、第一の天と第一の地は消え去るにちがいない。しかし、それらが存続しているかぎり、天とそれが人間に与える印象とは、かけがえのない意義をもっている。天の表象によって、天上の神の超越性と親近性とが同時に表明されたり、イエスは“天にのぼって”栄光を受けたという奥義が告げられたりする。バビロニア神話では、無秩序の混沌(こんとん)の世界の化身である粗暴な“海”は、マルドゥク神によってその力を奪われる。聖書における海は、神に従う被造物にすぎないが、神がその計画を実現するためにうち破るべき敵対勢力という象徴は依然として保っている。この意味で海は、人間を脅かす“死”の力を連想させる。宇宙の大部分の実在についても同じことがいえる。大地・天体・光・日・夜・水・火・風・嵐・陰・石・岩・山・荒れ野などはみな、つねに創造主なる神の主権に直接に服していると同時に、啓示においては象徴としての意味を豊かにもっている。 とはいえ、聖書的象徴の真の価値は、救いの出来事との関係にある。たとえば、夜は、死のように恐ろしいものであると同時に世界の誕生の場合のように不可欠のものでもあるという相反する面をもっているが、これは大部分の宗教に共通にみられる象徴である。聖書もこの象徴的解釈を知っているけれども、それだけで満足せず、夜に独特の意味を付与する歴史的背景のなかでこれを再解釈する。この歴史的背景とは、イスラエル人が夜の神秘的意味を体得した過越の夜のことであり、この夜は聖書では中心的体験となっている。雲とか日など多くの象徴にも言及したいが、ここではただ荒れ野についてだけふれよう。神の民は、シナイ半島の砂漠(さばく)地帯を通らねばならないが、この体験によって、荒れ野そのものが価値あるものになったのでもなければ、荒れ野への逃避という一種の神秘主義が是認されるようになったのでもない。たしかに、イエスの行動と新約聖書の教えは、キリストを信ずる者が彼らなりにいまだにある種の荒れ野に住んでいることをさとしている。しかし、以後このような表現は、信仰者の外的な行動ではなく精神的生活に関係づけられるようになる。荒れ野の象徴的用法はこのようにして、すたれてゆくのではなく、キリスト教生活の真のあり方を表わすためになくてはならないものとして残る。 神の民が身をもって経験したかずかずの出来事は、このように啓示の表現方法に取り入れられ、いまや、跳躍板のように離れ去ることのできる単なる比喩ではなく、啓示伝達の媒介としての価値を保っている。遠くエジプトでの隷属状態やバビロンでの流謫(るたく)に思いをいたすことにより、信仰者は、罪への隷属状態から購(あがな)われたものという自分の姿を実感することができる。洗礼を受けた者は、“洪水”から救われたのであり、かつ霊的に“割礼”を受けて精神的なイスラエル人となる。そしてこの世とその欲に対して“十字架”につけられている。彼らはまた“アブラハムの真の子孫”であり、真の“マンナ”で養われている。このように歴史は、象徴のかたちをとって、いわば啓示の表現方法のなかにはいっている。つまり、救済史上の出来事をさす言葉が、啓示を表わすために使用されている。したがって他方では、この象徴的表現方法が、自分のでてきた救済史を想起させながら、救いの奥義を告げ知らせるのである。 さらに、神のみ子が人間となり、人間の生を全うしてから、人間の生活にかかわる諸現実も、今述べた表現方法のなかにはいってくる。たとえば、種まきや刈り入れなどの農夫のしぐさは、神の国の成り行きを描いており、食事・仕事・休息・眠りなどの人間の行為は、神の世界の現実を示唆している。結婚・母性・誕生・病気・死なども、目に見えない奥義に至る道に人間の精神を引き入れる類比の意味を帯びている。けっきょく象徴は、人間のもとにくる神と人間との出会いを表わすためのすぐれた手段である。そしてこの象徴は、人間を奥義に導くや、人間とともに沈黙のなかに沈む。
3.啓示の完成者なるイエス キリスト 神のみ子は、人類の間にきて住み、啓示の象徴的表現法を認めてこれを完成する。人間となったみ言葉(ロゴス)は、それだけで行為による啓示である。イエスは、言葉と行為の完全な融合を実現する。彼の一つ一つの言葉は行為であり、彼の一つ一つのしぐさは人間に語りかけ呼びかける言葉である。アウグスティヌスの言葉によれば、「キリストは神の言葉そのものであるから、み言葉の行為は、われわれにとって言葉である」。キリストにおいて、もっとも卑賤(ひせん)な地上的現実も、イスラエルの祖先たちの歴史にみられる輝かしい出来事のように意味のあるものとなる。イエスは、この地上の現実を生きることにより、その真の意味を啓示する。人間の想像力によって現実が比喩に変わるのと逆の道を通って、イエス キリストは、自分に先だって自分を告げたあらゆる現実の前表的意味を明らかにする。このときから、地上の現実は、人間となったみ言葉という唯一無比の“現実”の象徴となって現われる。パンも水も、道も門も、人間の命も光も、決定的な価値を有する恒久的“現実”ではない。これらのものの根本的存在理由は、人間にイエス キリストを象徴的に語ることにある。
(X.Leon-Dufour)
II 聖書成立の概要
聖書批判学上の諸問題を紹介することは、この種の事典の領域外であるが、これを無視することはできない。聖書中の種々の主題をその歴史的発展過程に即してとらえつつ、神の教え方の跡をたどろうとするこの事典では、聖書本文や参照箇所を羅列(られつ)するだけでは足りない。聖書の各本文にはそれぞれ歴史的背景があり、本文をその文脈からきり離して用いれば曲解を免れない。啓示は実に、歴史の歩みに沿って発展しているからである。聖書成立の発展をよりよく理解するのに役だつものはみな、同時に、神の道をもよりよく把握(はあく)させるものであることを忘れてはならない。神はみ子を通じて人類に語るに先だち、「多くのかたちで、また多くのしかたで」(ヘブ1:1)、イスラエルの祖先たちに語っている。この“多くのかたち”と“多くのしかた”を知ることは、神の言葉の内容を正しく評価するために重要である。したがって、さまざまの主題の分析的説明にはいる前に、現在では一冊の書物となっている聖書が、具体的にはどのようにして編集されていったかを全体にわたって一瞥(いちべつ)することも、また有益なことと思われる。
旧約聖書
旧約聖書の成立を語るのは容易ではない。現在の聖書は、聖書中の各書を著作年代を考慮に入れず、歴史書・預言書・教訓書の3部門に大別している。ほとんどの書物の場合、その著作年代は聖書学者に問題を投げかけているが、これについてはふつう、蓋然(がいぜん)的な仮説しか立てられない。これらの仮説にふれないことは、怠慢のそしりを免れないし、またふれずにすませるものでもない。ところで、多くの仮説のなかから選択をおこなうことが必要である。ここ百年間に批判学者によって提起された仮説はみな、聖書を神の言葉と認める研究と合致するわけではない。これらの仮説のなかには、イスラエルの宗教の自然的進化を前提としているものもあるが、このような考え方は合理主義者の仮定に由来するものであり、聖書本文の客観的研究の結果とは相いれない。他方では、まったく客観的で学問的基礎のある批判と、一部の人々が試みるような偏向的な推論とを区別することも必要である。このような問題の探究にあたっては、信仰をもっているということは、立場を不利にするものではない。信仰者は、聖書の証(あかし)の精神にふかく結ばれて聖書を“内面から”読みながら、神の民の宗教思想の発展が、種々の歴史的要因に影響されているとしても、まず第一に、つねにその基準であった神の言葉によって導かれてきたことを知るのである。それにもかかわらず、聖書中の各書がしばしば複雑な歴史をもっていることはいなめない。ユダヤ教から教会に遺産として伝えられた概略的説明によると、モーセ五書は、その全体がモーセの筆になるものとみなされている。また詩編は、全編がダビデの作、知恵文学はみなソロモンの作とされ、イザヤ書は、1章から66章までことごとく前8世紀の一預言者の著とされている。ところが今日では、問題はそんなに簡単ではないことが知られており、このような見解に満足することはできない。もちろんこの伝統的見方にもよい点があることを認めねばならないが、補足すべき点も多い。この補足をおこなうことによって、聖書に関する知識を相当に具体的なもの・豊かなものにすることができる。というのは、このようにして聖書中の各書が、それが書かれた実際の歴史的環境におき直されるだけでなく、各書間にある相互の連関が明確にされるからである。
1.聖書の起源 聖書は、口伝のなかにその根を張っている。この事実を見落としてはならない。聖書が成文化されていくのは、比較的後代のこと、正確には、ダビデ王朝の確立後のことなのである。それ以前の太祖時代・モーセ時代・イスラエル人のカナン入植時代・士師時代・サウルの王制時代などはみな、口承時代に属する。しかしこの時代にも、種々の記録や一定の形式に従った作品が皆無であったわけではない。たとえば、契約法典(出20:22~23:33)や十戒(出20:2-17 申5:6-21)などの法文、デボラの歌(士5:1-31)やヨタムの寓話(ぐうわ)(士9:7-16)などの詩文が古くから記録されていたことは、一致して認められている。しかし、イスラエルの書記が保管してきたこれらの古い文献と並んで、口承は依然として、古い時代の思い出・慣習・祭儀・信仰を伝える主要な手段とされる。神の民は、数世紀の間、この祖先伝来の宝を生活の糧として生きるが、実はこの遺産は、現在伝えられているような形態に固定されるまでに、時代を経るにつれてますます豊かなものとなっていく。もっとも、太祖・モーセ・士師などの信仰上の証は、このようにして実生活を通して忠実に保たれているとはいえ、これらをイザヤやエレミヤの証の場合と同じように直接にとらえることは不可能である。 ダビデ、とりわけソロモンが、王国の行政部門に書記職を設け、これに公式の地位を与えてから、これらの伝承資料が集成されるようになり、同時に史料編集事業が起こる。ここで注意すべきことは、史料編集者たちが、過去の時代の精神的遺産を文書に記し、イスラエル民族成立の跡をたどることだけに専念しているのではない点である。イスラエルの宗教文学は聖所の陰から起こる。それは最初から、神の民の信仰を養うことを主要目的としている。そして史料の編集ということになると、救済史を示唆することにもっぱら注意が払われる。モーセ五書の分析にはまだ仮説の域を脱していない部分もあるけれども、このなかには、一個人または一団の編集者の仕事を識別することができる。それは通称ヤーウェ伝承記者とよばれている。つまりこれが最初の伝承収集であり、このなかには天地創造からイスラエル人のカナン入植までの救済史が収録されていたものと思われる。この伝承の精神および関心の中心は、ヨシュア記・士師記中の種々の記述、サムエル記上中のサウルの即位に関する記述(Iサム9:1~10:16)、ダビデとその王位継承に関する記述(IIサム2:1~I王2:12)のなかにも見いだされる。聖書のこの部分は、前10世紀ごろエルサレムにおいてだいたいの形態ができあがったと思われるが、続く前9世紀の間にもさらに増大していったにちがいない。このような集成物の一部を利用するときには、そこには二重の証が含まれていることを忘れてはならない。すなわちその一つは、記者たちが忠実に伝えることを主要目的として集めた古い時代の遺産としての証であり、もう一つは、この証を総合するにあたって、自分独自の神学を反映せざるをえなかった記者自身の証である。彼らの目には、神の計画の歴史は、太祖への約束・シナイ山の契約から、ダビデ王朝の決定的選び(IIサム7:8-16)・エルサレム神殿の建立(I王8:22-61)に至るまで、段階を追って展開している。こうして十二部族の宗教連合(アンフィクティオニア)から生まれた神の民は、“ヤーウェに注油された者”に統治される中央集権的国家を形成するに至る。 ここで注目すべきは、ヤーウェ伝承よりもかなりのちに、他の伝承収集者が同じ遺産を、これとはいくらか異なる精神をもって使用していることである。彼らはエロヒム伝承記者とよばれており、その記述には、最初の預言者であるエリヤやエリシャの影響がうかがわれる。彼らは、おそらく北王国の諸聖所(シケムについては異論がある)で、古代イスラエル人から遺産として伝えられた資料の収集と記録とにあたったにちがいない。これとかなり類似した教義上の配慮は、エリヤとエリシャの伝記、および王制に対してあまり好意的でないサウルの即位物語のなかにもみられる(Iサム8:4-21 Iサム10:17-25 Iサム12:12-17)。ヤーウェ伝承とエロヒム伝承は、後年、おそらくヒゼキヤ王の治下で(前8世紀末)一つにまとめて編集されたものと考えられ、その内容は現在創世記から列王記上にわたる数書のなかに分配されている。聖書の最初の集成がなされた過程はこのように概観することができるが、詳細にわたっては不確実な点もかなりみられる。とはいえこのようにして、少なくとも、神の民が形成され、約束の地に定住した時代の思い出が、どのような道を通って今日にまで伝えられたかを瞥見することが可能なのである。 他方、このようにして収集された伝承とか、この伝承によって運ばれる法文的・詩文的資料のほかに、その後も生きた伝承がずっと存続していたことも指摘しなければならない。時代とともに発展していったモーセ伝承からでた慣習法や祭儀上の規定は、文書には記されていなくとも、イスラエル人の生活上の指針となっている。同じく、上古に始まる宗教詩(民10:34-36)も、みずからも詩人であったダビデ(IIサム1:17-27)の時代以後作品を増し、エルサレムの神殿はその文学的開花に好都合の場を提供する。さらにソロモンの時代になると、他のオリエント諸国の文化や思想をヤーウェの信仰と調和させながらイスラエルに移植した学者の知恵が、イスラエル古来の民衆の知恵に接ぎ木される(→I王5:9-14)。詩編および最古のものとみなされる格言(箴10:1~22:16 箴25:1~29:27)のなかには、この時代にまでさかのぼるものが多い。このように記述預言者の時代にはいる前に、聖書の文学類型をなす種々の思潮が、くっきりと姿をみせるのである。これらの思潮の背後には、聖書の伝承を後世に伝えた主要な階級の活動が認められる。すなわち、伝承の骨組みをなす律法と史料の保管者である祭司、神の代弁者である預言者、知恵の教師である書記官などの活動である。しかし、これは啓示の第一段階にすぎない。だが、この段階においても、啓示はひじょうに堅固な教義上の原理をうち立てており、のちにくる世代はこれを深めていくだけである。
2.預言者の時代 預言者の活動は、イスラエルではきわめて古い。しかし前8世紀以前の預言では、出所のたしかな託宣(神の言葉)(IIサム7:1-17 I王11:30-39)、あるいは、これに類似した部分(創49:1-27 民23:1~24:25 申33:1-29)は、ごくわずかである。エリヤとエリシャの弟子は、自分の師の活動の思い出を残しているが、教えの内容は書きとめていない。しかし、間接的記録を通してそれを知ることができる。前8世紀以後になると、預言者の弟子、あるいはときとして預言者自身が、その教説・託宣・伝記(とくに彼らの召命に関する)などを集めて一巻の書としている。これらの書が言及している歴史的出来事から、たびたびかなり正確にその年代が推測される。預言文学はこのように、それぞれの時代の生活と問題にふかくはいりこんでいるため、その歴史を確立することができる。前8世紀から前5世紀にかけては著名な記述預言者がつぎつぎに登場する。前8世紀中葉には、イスラエルにアモスとホセアが、前8世紀後半にはユダにイザヤとミカが現われており、前7世紀末には、ゼファニヤ・ナホム・ハバククの名がみられ、とりわけ、エレミヤは前625年から前587年にかけて活躍している。ついで前6世紀には、エゼキエル(前593~571)・ハガイ・ゼカリヤ(前520~515)、前5世紀には、マラキ(前450年ごろ)とオバデヤが現われており、またヨエルの活躍もおそらくこの時代であろう。 しかし、このように預言者の名を単に列挙しただけでは、預言書の複雑な事情をじゅうぶんに理解することはできない。というのは、ここに列挙した預言者名を冠した諸書は、実際には、彼らの弟子・後継者・霊感を受けた注釈者などの寄与によって、時の経過とともにその内容を増していったものなのである。たとえば、エレミヤ書でさえも、たしかにその大部分はバルクの手になるものであり(エレ36:1-32)、それよりものちの時代のものも含まれている(エレ50:1~51:64)。同じようなことは、アモス書(アモ9:11-15)とかミカ書(ミカ7:8-20)についても指摘できるが、さらにエゼキエル書(エゼ38:1~39:29)についてもいえるかもしれない。ゼカリヤ書の後半(ゼカ9:1~14:21)は、アレクサンドロス大王時代の無名の記者の手になる付加らしい(前330年ごろ)。イザヤ書はといえば、そこには多くの人の手の跡と年代的にずれのある歴史的背景とが認められるが、今日伝えられているままのイザヤ書は、預言文学のりっぱな集約ともいえる。そこには、詳細な注釈のほかに、はっきりとした特徴を示すいくつかのまとまった部分がある。たとえば、前545年ないし前538年に書かれた流謫(るたく)者への慰めの使信(イザ40:1~55:13)、ほぼ同時代に書かれたバビロンに対する託宣(イザ13:1~14:23)、パレスティナヘ帰国のころに書かれたらしい黙示文学的部分(イザ34:1~35:10)、前6世紀末葉を背景とするイザ56:1~66:24、年代については諸説のある(前485年から前3世紀の間)より規模の大きい黙示文学的部分(イザ24:1~27:13)などである。このように、ひとりの人物名でよばれている預言書を分析して各部分の正確な出所を知ろうという努力がなされるのは、単に本文の信憑(しんぴょう)性を解決するためだけでなく、本文の霊感をじゅうぶんに尊重しながら、各部分の記者が直面したにちがいない具体的な種々の問題に徹して、その教義的価値をより正確に評価するためでもある。 預言者は、直接に神の言葉の保管をゆだねられており、かつこれを同時代の人々に伝える責務を負わされている。しかし、彼らを時代から遊離したものと考えてはならない。神の民は、彼らを中心としてその歴史を生きているし、この時代よりも前に始まった他の文学思潮は、預言文学から恩沢をこうむりながら発展している。慣習法の中心をなすモーセの律法の古い編集と諸伝承の最初の収録については、先に述べたが、前8世紀から前7世紀にかけてこれらの法文の改正がなされる。申命記法典(申12:1~28:69)となって跡をとどめているこの改正は、おそらく北王国の聖所の律法的伝承を出発点としながら、時代の要請にこたえるためになされたものであろう。この法典は、ホセアやエレミヤのような預言者の精神とも明白なつながりをもっている。その上この法典は、宗教文学全体の中心となって種々の主題をかなでている。たとえば、申命記の祭司的訓話(申1:1~11:32)と古い資料の内容を含むカナン征服から捕囚に至る期間の歴史である(ヨシ・士・Iサム・IIサム・I王・II王)。ところで、イスラエルはこれらの書物をもちながら王制の終局と捕囚時代を迎えることになるが、そのころエルサレムの祭司階級も、彼らの慣習・祭儀・法を成文化することに専念している。申命記法典に対応し、エゼキエル書との類似点も多い神聖法典(レビ17:1~26:46)は、前7世紀末ごろ起草されたものと思われる。そしてこの法典を中心として、ヤーウェ伝承・エロヒム伝承記者もすでに展開した諸伝承に基づく祭司伝承の救済史を枠(わく)組みとしつつ、宗教上の諸規定が出エジプト記・レビ記・民数記のなかに収められ、蓄積されてゆく。他方、この仕事と並んで、宮廷の書記官によってみがかれた知恵文学の伝承は、新しい格言を加えて豊かになっていくが、このなかには預言者たちの道徳的教えが容易に看取される。また宗教詩のなかにも、預言者たちの影響の跡が認められる。バビロン捕囚時代に、流謫のユダヤ人は、彼らの民族だけでなくこの民族に結ばれた宗教も生きながらえるように、これらの過去の時代の文学的遺産をすべて収集する。これが、彼らが手にしていた全聖書である。そして聖書文学のその後の発展は、この聖書との接触によってなされ、その影響をふかく受けることになる。
3.聖書編集の時代 捕囚時代まで“行動の人”の活躍によって鼓吹されていた預言的思潮は、帰国後のユダヤ教時代の最初の2世紀間にしだいにすたれていく。そしてのちに律法学者とよばれるようになる書記の時代にはいる。祭司階級に属すると否とを問わず、彼らは、神の言葉への奉仕にその才能を傾注する。口伝のものであれ成文化されたものであれ、古い伝承が、いつも彼らにとって生きた環境となっており、彼らの作品はそこに根をおろしている。とはいえ、彼らの関心の中心・精神的態度・作品の構成などは、すぐ前の時代の先輩にかなり依存している。ペルシア時代(前520~330)とギリシア時代の前半(前330~175)は、この時代を細部にわたって再構成しようとする歴史家にとっては不明な点が多い。しかしこの時代も、作品成立の点からすれば、不毛ではない。 まず第一に語るべきは、祭司階級に属する書記の仕事である。彼らは、あらゆる律法的資料とそれにまつわる諸伝承を一つにまとめ、現在のモーセ五書にみられるとおりの決定的形態を律法(トーラー)に与える。律法のこのような固定化は、エズラの活動と関係があるものと推定されている(前447,前427または前397)。同じく、ヘブライ語聖書の区分による《前預言者》(ヨシ・士・Iサム・IIサム・I王・II王)にも、もはや変化はみられなくなる。《後預言者》(イザ・エレ・エゼ・十二小預言書)には、わずかな付加があったり、ときとしては編集者の単なる注釈が加えられたにすぎない。しかしいまや、新しい文学形態が発展するようになる。それは、宗教的教えを伝えることを主眼として構成される教訓物語の出現である。この傾向は盛んになり、イスラエルの地に根をおろす。ヨナ書やルツ記(前5世紀)もこれに属するが、これはどのような伝承から生まれたものかは確証できない。歴代誌記者(たぶん前3世紀)も、これに類する精神をもって、しかしもっと堅固な歴史的資料を用いつつ、ネヘミヤ記およびエズラ記に至るまでのイスラエル全史を再編集している(I代・II代・ネへ・エズ)。これらの諸書の叙述の裏には、つねに記者の神学がひそんでおり、出来事の紹介にも影響を及ぼしている。 しかし、捕囚以後しだいに好結果を生んでいくのは、知恵文学である。人生についての実際的反省に向けられたこの文学は、少しずつその研究分野を広め、ついには人間実存の問題や報いの問題など教義的な難題にまで迫る。これらの問題について伝統的な解決をするための基礎を提供するのは、以前に記された書物であるけれども、知恵文学は、ときとしてこれを批判することも新しい見解を述べることも辞さない。この文学思潮の出発点におかれるのは箴言の書であり、この書には、編集者がかなり新しい様式の序文を付している(箴1:1~9:18:前5世紀)。これに続くのが、ヨブ記(前5または前4世紀)・コヘレトの言葉(前4または前3世紀)・トビト記(前3世紀)・シラ書(前180年ごろ)などである。詩編にも知恵文学の影響が認められるが、これは驚くにあたらない。後代の作であるいくつかの詩編には、知恵の問題を扱ったり(詩37:1-40 詩73:1-28 詩112:1-10)、人間にとって真の知恵の源である神の律法を称賛したり(詩1:1-6 詩19:2-15 詩119:1-176)している。それは、詩編の収集に最終的形を与えた聖歌隊が、神殿における祭儀と聖書の黙想をおもな仕事とする環境に生活していたからである。正典に収録されている詩編には、古いものにも新しいものにもみな、聖書のあらゆる文学思潮、イスラエル人のあらゆる歴史的体験、ユダヤ人のあらゆる精神面がこだまし、鏡のように映っている。このように、神の啓示の本質的要素はみな、神の息吹きを受けたこの祈りの基盤となっている。
4.旧約時代の終わり マカバイ時代の危機とともに、旧約時代は最後の転換期にはいる。この時代にきかれる最後の預言は、黙示文学という新しい形態をとる。ダニエル書の著者(前165年ごろ)が迫害下のユダヤ人に慰めの使信を伝えるために用いているのは、実にこの文学類型である。彼は、約束を伝える終末的な示現(ダニ2:1-49 ダニ7:1~12:13)に教えの基礎となる教訓的叙述(ダニ1:1-21 ダニ3:1~5:30 スザ1-64 ベル1-42)を加えている。当時のユダヤ教は、この種の記述を好んで用いている。エステル記は神の民の典型的な救いについて述べ、ユディト記は、マカバイ一族の抵抗に呼応するような宗教的・軍事的抵抗をたたえている。他方、アンティオコス エピファネスの迫害およびそれに続く聖戦は、事件にほど近い資料、すなわち、マカバイ記上・マカバイ記下によって伝えられている。この両書は、いろいろの面でギリシアの史料編集の影響を受けている。このほか、種々の部分の組み合わせからなるバルク書と前1世紀にアレクサンドリアでギリシア語で書かれたソロモンの知恵の書がある。以上が、アレクサンドリアのユダヤ教、およびそのあとを継いで使徒時代の教会により正典と認められている旧約の諸書である。 以後、ユダヤ人の宗教文学は、正典聖書の外側で発達していくが、これらの作品を通して教義上の発展の跡をたどることができる。しかしこの発展は、まだ生きた伝承のなかでおこなわれているとはいえ、往々にして、著者や編集者の属する宗派に固有の精神によってゆがめられている。外典とよばれるこれらの書には、エッセネ派系のもの(エティオピア語エノク書・ヨベル書・十二族長の遺訓・モーセの昇天)、あるいはファリサイ派系のもの(ソロモンの詩編・エズラ記(ラテン語)・シリア語バルク黙示録)などがある。クムランの写本の発見によって、今日では純粋にエッセネ派の著作にも接することができる(宗規要覧・会衆規定・ダマスコ文書・聖書の注解)。アレクサンドリアのユダヤ教は、聖書のギリシア語訳(七十人訳聖書)のほか、哲学者フィロンの著作を主とする一連の文学作品を所有している。最後に紀元2世紀以後ファリサイ派の学者の庇護(ひご)のもとになされたラビたちの編集になる諸書は、もっと起源の古い伝承を集めている(法規集であるミシュナ、その注解書であるタルムード、聖書本文の説明書であるミドラシュ、聖書本文のアラム語による翻訳ないし注釈であるタルグム)。これらの作品は、もはや聖書本文のような関心をよばないにしても、少なくとも新約聖書が生まれるころの環境がどのようなものであったかを教えている。
新約聖書
イエス キリストは、なにも書き残していない。ただ自らの教えと人類の救いが実現した出来事の思い出とを、弟子たちの記憶にゆだねただけである。正典として伝わっている新約聖書の源泉には、このような口づてによる伝承が存在していたことをけっして忘れてはならない。この伝承は、だれもがかってに行動する無名の集団にゆだねられたのではなく、最初から、イエスからその使信を伝える責務を負わされた人々の証に委託されている。使徒時代に書かれた物はいずれも、なんらかの方法でこの伝承に源を発している。新約聖書の文学的発展は、旧約聖書の場合と異なり、はるかに短期間で成し遂げられている。それは、おそらく60年間ぐらいのことであろう。もっとも新約聖書の成立にも、現在の聖書の論理的分類と正確には一致しないかなりの多様性がみられる。
1.共観福音書と使徒言行録 今日伝わっている最古の新約聖書の本文は、使徒の手紙である。しかしこれらの手紙は、それに先だつ福音伝承の存在を前提としている。すなわち、ついには、一方ではマタイ・マルコ・ルカの共観福音書、他方ではヨハネ福音書となって結晶するに至る伝承である。確実に紀元2世紀にまでさかのぼるある文献は、最初の福音書はマタイによって“ヘブライ語”(実際にはアラム語)で書かれたと断言している。しかし、この福音書は現存していない。ただ共観福音書の背後にその存在を推測できる程度である。エルサレムのキリスト者の共同体では、ひじょうに早くからアラム語とギリシア語の二つの言語が使用されていたから(使6:1-15)、福音の内容も、この二つの言葉で伝えられたにちがいない。使徒言行録中の種々の説教(使2:22-39 使3:12-28 使4:9-12 使5:29-32 使10:34-43 使13:16-41)は、使徒たちの宣教の最初の形態を伝えている。これらの説教は、人類の救い主であるイエス キリストという人物を紹介するために、福音の内容を分類していた全体的な枠組みを示すよい参考資料である。 この図式的な枠は、マルコ福音書の内容配列の基礎となっている。ペトロの説教を反映しているこの福音書は、より古い文献に基づきながら、65年から70年の間に記されたとみることができる。ルカ福音書は70年から80年の間に世にでたにちがいない。ルカの著書はマルコ福音書の限界をはるかに越えている。それは2巻からなり、一方では福音書が、主イエスの証人の思い出に基づいて彼を紹介しており、他方では使徒言行録が、救いの使信が、エルサレムから始まり、異邦世界とその主都ローマに伝播(でんぱ)していくありさまを語っている。この2巻の書は、二つで一つの作品を形成しており、著者はここで、マルコ福音書の場合以上に、自分の神学的思索を述べようと意図していることがうかがわれる。現在伝えられているマタイ福音書は、古い伝承(パピアス)がマタイに帰しているアラム語マタイ福音書と密接な関係を有するであろう。それは少なくとも、この原本を敷延してなされた改作であり、かつ、著作の年代についても、その教訓的意向についても、ルカ福音書との間に類似点がみられる。 したがって、福音書がそれぞれ現在に伝えられているようなかたちをとるようになった経緯を理解するには、二つの異なった段階を研究しなければならない。第一は、福音書記者がくみとる資料の源泉である使徒たちの伝承の段階であり、第二は、出来事の紹介とかイエスの言葉の選択や表現法が各福音書記者固有の教義的観点によって最終的に編集される段階である。そして第一の伝承は、往々にして記者が編集する以前にすでにその表現様式までも決定している。この最初の段階からすでに、神学的な思惟が働いているが、それは、使徒たちの証が、過去の恬淡(てんたん)たる報告ではないことに基づく。この証は、当時の共同体の精神的需要にこたえる表現をとり、かつ教会の生活のなかで根本的な役割を果たしつつ、なによりもまず信仰を養うことを目的としている。それは具体的には、イエスの言葉と行動のなかに啓示され、その生涯(しょうがい)と死去と復活のうちに成就した救いの奥義を明るみにだすかたちでなされる。
2.使徒の手紙 したがって、福音の口伝あるいは一部成文化された伝承は、使徒時代から伝えられている他の書き物、つまり使徒たちの手紙よりも前から存在していたことになる。使徒の手紙は、系統だった抽象的な神学の説明書ではない。それは、おりにふれてしたためられたものにすぎず、使徒たちやその直弟子たちの司牧活動と深いかかわりをもっている。 現在の聖書では、これらの書き物のうち、まずパウロの手紙が収録されている。使徒言行録は、この手紙に貴重な歴史的背景を提供する。パウロの手紙は、異教の土地における彼の使徒的活動の種々の局面を反映している。彼は第2伝道旅行中、テサロニケの人々へ二つの手紙を書き(51年)、次の旅行の間に、フィリピ書(56年ごろ、他の説によると61~63年ごろ)・ガラテヤ書・Iコリント書・IIコリント書(57年)・ローマ書(57~58年)を書き、ローマにおける捕らわれの間に(61~63年)、コロサイ書・フィレモン書・エフェソ書を記している。このほか“司牧の手紙”とよばれる一連の書き物があるが、これらの背景については、使徒言行録からはなんの知識も得ることができない。パウロの最後の布教活動は、Iテモテ書とテトス書に反映しているが、IIテモテ書は、殉教につながる彼の再度の監禁を前提としている。この三つの手紙は、他方、その信憑性について微妙な問題を投じている。パウロはここでは、少なくとも秘書を使っていることが推測されるからである。この秘書は、パウロの思想に依存しながら、自分自身の文体の特徴を残している。ヘブライ書の場合は、事情はまったく異なる。古い伝統は、これをパウロの著作の分類中に加えているが、この書の起草者は、自分自身の文体で独創的思想を述べている。彼の思想はパウロのそれとは明らかに対照的な面をもっており、アレクサンドリア的な起源を有することを示唆している。とはいえ、この書は70年より前に書かれたものであろう。エルサレムの滅亡も神殿における祭儀の終息も知らないようだからである。 “全キリスト者への手紙”という部類に属する書き物は、これよりもはるかに変化に富んでいる。Iペトロ書の場合、筆記者の名があげられているが、それは、パウロの昔の協力者なるシラス別名シルワノである(Iペト5:12)。この手紙では、ペトロが殉教したネロの迫害が背景となっている。ヤコブ書は、44年以後エルサレム教会を指導した“主の兄弟”ヤコブと結びついており、この手紙は、説教集のかたちをとっている。ユダ書は、キリスト教の信仰を腐敗させる偽教師の影響とすでに戦っている。この手紙の背景は70年~90年ごろであろう。IIペトロ書はユダ書を利用しており、その著者は使徒の時代をかなり遠くにながめている。したがって、ペトロの証はそこには、弟子の筆を通して間接に反映しているにすぎない。
3.ヨハネの著作 最後に、使徒ヨハネの教えに関係のある種々の書き物について述べなければならない。黙示録はこのなかで最古のものらしいが、70年直後にまず書かれ、そして最終的にはドミティアヌス帝の迫害下の95年ごろ完成したものと思われる。この文学形態はダニエル書によって始められ、新約聖書の他の書き物、たとえば福音書(マコ13:1-37 マタ24:15-31 ルカ21:25-28)とかパウロの手紙(Iテサ5:1-11 IIテサ1:3-10 Iコリ15:35-53)にも、ときおりみられる黙示文学の類型に属する。IIヨハネ書とIIIヨハネ書は短信にすぎないが、Iヨハネ書は説教の形式をとっており、そこにはきわめて独創的な神学思想がまぎれもないセム的表現で叙述されている。これと同じ文体はヨハネ福音書にもみられ、ヨハネは、自分の思想が書物になる前にすでにそれを説教していたはずである。古い証言によれば(2世紀および3世紀)、ヨハネ福音書の著作年代は1世紀の終わりである。したがってこの福音書では、当然のことながら、イエスの言葉と生涯の思い出が、粗雑な配置ではなく、洗練された文脈のなかに織り込まれており、かつ、著者の神学と扱おうとする材料とがこんぜんと融合している。ヨハネはキリストの使信と奥義とを長い間黙想しつづけたからこそ、自分が語る出来事の深い意味と収録した言葉の隠れた響きを明らかにすることができたのである。なお、ヨハネの教えからでた諸書の間にみられる表現とか文体の相違は、これらの書の最終的編集がヨハネの弟子の手になることを示唆している。
4.結び 以上略述したとおり新約聖書は、いつの時代の人もその恩恵をこうむることができるように使徒たちの証を集めている。キリストから授かり、聖霊の働きによって理解できた啓示のにない手である使徒たちは、これをまずキリスト者の生きた共同体にゆだねる。この遺産は、ほどなく定まった形態と内容をもつようになる祭儀・宣教・教育を通して教会のなかで忠実に伝えられていく。教会はその後、おもな主題をさらに掘り下げながらも、この全体的骨組みを保持する。もっとも、霊感を受けた書き物は、すでに使徒時代より、証が従うべき指導理念を永久に決定しながら、生ける伝承がけっして離れてはならない基準を定めている。
(P.Grelot)
目次
日本語版への序文 (5)
日本語新版への序文 (6)
編集者のことば (8)
執筆者 (10)
凡例 (12)
序論
I 聖書の思想 (17)
II 聖書成立の概要 (26)
項目 1
付録
聖書思想一覧 892
事項索引 895
聖書引用検索 939
古代オリエント語索引 964
ギリシア語索引 967
翻訳監修者あとがき 970