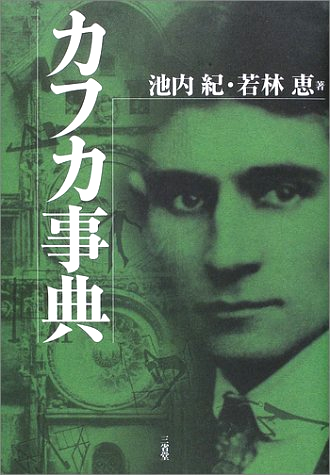三省堂 辞書ウェブ編集部による ことばの壺
カフカ事典
20世紀のもっとも注目すべき小説家カフカの人と作品を集大成。
20世紀のもっとも注目すべき小説家カフカの人と作品を集大成。
小説から草稿・断片まで、カフカの全作品を最新の資料をもとに解説。
健康法、金銭、映画、女性、動物、散歩など、幅広い視点から新しいカフカ像を提示。
カフカ、キーワード、カフカへの解釈、年譜、ブックガイドなど、周辺情報も充実。図版多数。
特長
関連リンク
下記より見本ページなどをご覧いただけます。
さらに詳しい内容をご紹介
「カフカ事典」の内容より
著者紹介
池内紀(いけうち・おさむ)
1940年、兵庫県姫路市生まれ。ドイツ文学者。主な著書に『ウィーンの世紀末』(白水社)、『見知らぬオトカ ム――辻まことの肖像』『無口な友人』(みすず書房)、『日本の森を歩く』(山と渓谷社)、『マドンナの引っ越し』(晶文社)ほか。訳書に『カフカ短編集』『カフカ寓話集』(岩波文庫)、ジュースキント『香水』(文藝春秋)ほか。『海山のあいだ』(角川文庫)で講談社エッセイ賞、『ゲーテさん こんばんは』(集英社)で桑原武夫学芸賞、『ファウスト』の新訳(集英社)で毎日出版文化賞、『カフカ小説全集』(白水社)で日本翻訳文化賞。
若林恵(わかばやし・めぐみ)
東京生まれ。1997年、東京大学大学院博士課程単位取得退学。現在、東京学芸大学講師。ドイツ文学専攻。『週刊朝日百科 世界の文学4ゲーテ、グリム兄弟ほか』等に分担執筆。訳書に『現代スイス短篇集』(共訳、鳥影社)。
カフカの甦り‐はじめに
カフカは死なない。くり返し甦る。そのつど、ちがった姿でもどってくる。 一九二四年六月、喉頭結核で死去。四十一歳だった。同時に小説家フランツ・カフカも死んだ。そのはずである。生前、本にしたものは七冊。それなりの数であるが、どれも発行部数は千か二千だった。なんともおぼつかない数字である。まがりなりにも本になったにせよ、読者の手にわたったのは、たかだか数百。とりわけカをそそいだ長篇三作は、どれも未完であって刊行のあてがなく、ノートのままにとどまっていた。 一九二四年の死はあきらかに元労働者傷害保険協会勤務、一等書記官フランツ・カフカの死であった。新聞もそのように対処した。つまり、その死を無視した。 ほんのひとつまみにせよ、たしかに上質の読者がいた。書評というかたちで薄っぺらな本をとりあげた者たちだ。小官吏のかたわら、ひっそりと書いている特異な才能に注目した。そこには批評家フランツ・ブライや作家クルト・トゥホスキー、またへルマン・ヘッセといったより抜きの読み手もまじっていた。 アントン・クーは自分ではほとんど書かず、鋭い警句をしゃべり散らしたウィーンの文士だが、カフカの死後すぐに新聞に追悼をのせた。文壇の空騒ぎのなかで、誰ひとり気づいた者はいないにせよ必ずや「のちの世が遭遇するにちがいない作家」だというのだ。フランツ・ブライはもっとも早くにカフカの短篇を自分の雑誌に掲載した人である。そして並外れて早い時期に一つのカフカ論を発表した。それはこんな書き出しをもっていた。「カフカを悩ませたものは、自分のいる状態の根源的な奇妙さだった」。 カフカがウィーン郊外のサナトリウムで死んだ一週間前、オーストリア首相暗殺未遂があって新聞はそれでもちきりだった。第一次世界大戦の敗戦国ドイツを襲った大インフレは、ようやく沈静したばかり。前年、ヒトラーが「ビアホール一揆」とよばれる騒動を起こした。右翼新聞は「ユダヤの陰謀」を連日のように書き立てていた。 そんな状況である。まさしく「断食芸人」さながら、痩せこけたあげくの死とともに、プラハの一ユダヤ人作家もすみやかに忘れられた。そのはずだった。 死後一年して長篇『審判』が友人マックス・ブロートの編集によりベルリンで出た。 翌年に『城』、さらにつぎの年に『アメリカ』が出た。出版社が代わってライプツィヒで刊行。あまりの売れ行きの悪さにベルリンの版元が拒否したからだ。『アメリカ』はカフカが最初に取り組んだ長篇であって、カフカ自身は『失踪者』のタイトルを予定していた。 未完の短篇が『万里の長城』のタイトルで一巻にまとまったのは一九三一年である。三たび出版社をかえてのことからも難産ぶりがうかがえる。一九三五年、ベルリンのショッケン書店が『カフカ全集』の刊行を承諾した。全六巻の予定だったが四巻で中断。マックス・ブロートはプラハの小出版社と交渉し、一九三六年から三七年にかけて残りの二巻をまとめた。 ともかくも主だったものを活字にした。ブロートには深い思いがあっただろう。単に出版社を見つけるというだけではなかった。ドイツではヒトラーの独裁のもとにユダヤ人弾圧が激しさを増していた。ナチス・ドイツにとって「好ましくない作家」に、つぎつぎと執筆・出版の禁止が申し渡され、トーマス・マンをはじめとして亡命があいついでいた。一九三八年、ナチス・ドイツ、チェコのズデーテン併合。ユダヤ人大虐殺、いわゆる「水晶の夜」事件が起こる。ドイツ軍がプラハに入る前日、ブロートは急濾イェルサレムへ向かった。トランクのおおかたを友人の残したノートが占めていた。 四つの書店にまたがってカフカの遺作がちらばっていた。いずれも限りなく部数は少なく、そもそも読者の目に触れたかどうかもさだかでない。ユダヤ人作家の禁書、焚書があり、図書館収蔵のものも破棄を命じられていた。 だが、カフカは死ななかった。それは自然界の不思議な現象にも似ていた。あちこちで、ときならぬ芽ばえがある。ハンス・フロニウスといった若い画家がいて、はやくも一九二〇年代に版画つきのカフカ本を出した。第二次世界大戦直前に『万里の長城』の仏訳が出た。パリの文芸誌にジッドやヴァレリーと並んでカフカの名があった。アンドレ・プルトンが作品を語り、マックス・エルンストが絵をつけた。一九四一年、詩人オーデンがフランツ・カフカという名の「二十世紀の知られざる神の僕」について語った。 本格的な甦りは、戦後のサルトル、力ミュらによる実存主義的なカフカ発見にはじまる。ニューヨークに亡命していたショッケン書店よりあらためて全集が出た。ブロートは二度にわたって部分的な改訂はしたが、当初の編集と構成は変えなかった。みずからの解釈も同様だった。シオニスト・ブロートにとって、友人カフカは何にもましてユダヤの神の国の僕でなくてはならない。 一九五〇年代の終わりごろだそうだ。イギリス・オックスフォードのドイツ文学教授マーコム・パスリーが授業を終えて出てくると、一人の学生に呼びとめられた。フランツ・カフカの姪の息子にあたる者が、ここで法律を学んでいる。会ってみる気はないか? その学生に会ったところ、思いもかけぬ依頼をされた。母がちかぢか、フランツ大伯父の残したノート類を相続する。母は買物にはくわしいが文学のことは西も東もわからない。相談にのってやっていただけないか? カフカの両親は一九三〇年代にあいついで死去した。三人の妹はいずれも強制収容所で殺された。わずかに姪にあたる人が生存していて相続権を得た。カフカの残したノートのおおかたがオックスフォード大学ボードレイアン図書館に収まっているのは、このような偶然による。遺稿の移動そのものが、カフカの小説さながらの不条理性をおびていた。 一九六八年、マックス・ブロートはテル・アヴィヴで死去した。それを待っていたようにパスリーを中心として、新しい全集編纂の仕事がはじまった。手稿をつき合わせ、書き文字を克明に読み直す。気の遠くなるような忍耐のいる作業だった。全巻がまとまるまでに二十年あまりかかった。 一九九六年、私は手稿版全集の翻訳許可を求めて版元に手紙を出した。しかしながら、待てど暮らせど返事がこない。やがてドイツてはなくニューヨークに問うべき次第が判明した。しかし、そのニューヨークの宛名先は名のみあって実体がないらしいのだ。少なくともなんの返事もない。くり返し送っても、ナシのつぶて。ところが二年ちかくたって、急にかすかな反応がはじまった。「検討中」「いましばらく待て」。待っていると、またもや、まるきり応答がとだえる。長篇『城』のケースと同じで、近づくにつれて遠ざかる。あるいは、やにわに消えてしまう。 三年が過ぎ、ほとんど諦めかけていたとき、ある日突然、許可の返事がきた。ただし、仮のものであって「正式の通知はのちに送る」とある。それがまた一向に届かない。正式の許可は翻訳をあらかた終えたころに舞い込んだ。多少ともヤキモキさせられたにせよ、これはこれで、けっこう楽しい甦りに立ち会ったらしいのだ。 これはフランツ・カフカを知るためのささやかな一冊である。小説家カフカを知るためには作品があり、必ずしも人間カフカを知る必要はない。しかし、人間カフカを知っているほうが、カフカの小説が、よりおもしろいこともたしかである。 カフカの小説には、数々の謎がある。謎は謎として楽しめばいい。ことさら首をひねるまでもない。だが、謎解きがカフカを読む楽しみを倍にすることも事実なのだ。この本にはそんな読者のための多くのヒントがあるだろう。 カフカには、ある定まったイメージがある。それがいかに不当で、どんなに誤ったものであるか、ここに収録した事項がおのずと語ってくれるのではあるまいか。 フランツ・カフカは二十世紀が生んだ小説家のなかで、もっともつましく、もっとも上質の一人だった。だから二十一世紀に、あらためて甦る権利がある。
作品解説(天井桟敷にて)
*天井桟敷にて Auf der Galerie 推定1917年1~2月。初出:『田舎医者。短篇集』ミュンヘン・ベルリン、1919年。著作集『田舎医者。短篇集』(ミュンヘン-ライプツィヒ、1919年)所収。
サーカスの曲馬団の少女の曲芸が、天井桟敷の若者の視点から描かれる。前半では少女が情け容赦ない団長にひどい扱いを受け、観客の前で無理やり過酷な曲芸を続けさせられる様子が語られるが、特徴的なのは、これが全て事実としてではなく、仮定の出来事として「かもしれない」の領域に移されていること、そして引き続いて後半では、前半とは正反対のことが「事実」として述べられるということである。前半で言われたようなことは若者の空想であり、実際にはそんなことは起きないのだ、と述べられる。事実は少女は団長にとても大事にされ、観客の大喝采を浴びて幸福である。そうして天井桟敷の若者は「手すりに顔をのせ、しめくくりの行進曲を聞きながら、せつない夢に沈みこみ、われ知らず涙にくれる。」 (池内紀訳) 当時ルーヴル美術館にあったジョルジュ・スーラGeorges Seurat(1859-91)の『サーカス』という絵画がカフカにインスピレーションを与えたらしい。前半部分での「情け容赦のない団長」が示唆しているのは、権威と服従の関係に規定された労働世界であり、ここでは曲馬団の少女と団長との間、また少女と観客との間にある承服しがたい依存関係が批判的に描かれ、その変更が求められている。文法的に非現実話法が用いられている前半部分に対し、後半部分では「事実」を記述する直説話法が用いられ、前半とは裏腹に少女と団長・観客との関係が親密な愛情に満ちた優しい関係として提示される。よって前半部分で述べられていることは絵空事であり、後半での優しい関係、即ち支配者たる団長と従属者たる少女の主従関係の消滅もしくは逆転した状態こそが事実であるということになる。しかしこの「事実」は欺瞞である。支配と従属の関係の逆転はたんなる見せかけにすぎず、団長のへり下った態度はその「獣のような素振りで」仮面を剥がされることになる。団長にとって曲馬乗りの少女は、いくら偶像にまで高められていようと所詮は対象物にすぎないのであり、元来あるべき人間的関係は歪められている。ということは逆説的なことに、前半では非現実話法によって現実が、後半では直接話法によって錯覚・欺瞞が表現されていることになる。こうして天井桟敷の若者は、現実世界での矛盾に満ちた体験ゆえに進むべき方向を見失い、いかなる行動の可能性を見出すことができない。どうすることもできない状況の中で完全に自己の内面へ引きこもる外はない。仮象と実在(見かけと実体)の区別ができない彼に残されたのはただ同情的な諦念のみである。
解釈例
1.サーカスの団長は、旧約聖書の罰を与える神エホバを具現し、「やめろ!」という叫びは、この厳格な神に対するプロメテウス的拒絶である。 2.常に円を描いて機械的に廻るだけの生命のない人形の世界の比喩としてのサーカス。現代社会における人間存在の危機がテーマである。
作品解説(田舎医者)
*『田舎医者』1917年。初出:文芸年鑑「新文学」、ライプツィヒ、1918年。著作集『田舎医者。短篇集』には『新しい弁護士』『田舎医者』『天井桟敷にて』『一枚の古文書』『掟の門』『ジャッカルとアラビア人』『鉱山の客』『皇帝の使者』『父の気がかり』『兄弟殺し』『夢』『ある学会への報告』の12篇が収められている。
田舎医者は吹雪の中10マイル離れた村の重病人のところに行かねばならないのに、馬車を引く馬が過労で死んでしまい困っていた。しかし豚小屋から突然2頭の馬が現れ、馬は馬車に繋がれる。その間、馬丁が女中のローザに気があるそぶりを見せ彼女を抱きしめ、ローザは嫌がって逃げ回っていた。医者は馬丁をローザのもとに残して行くわけにはいかないと主張するが、馬車はあっという間に疾走し、瞬時のうちに重病患者の家の前に着いてしまう。患者の若者を診てみると、彼は健康そのものである。しかし馬がいなないた時、若者の腰のあたりに大きな傷口があるのに気が付いた。そのあと医者は裸にされて患者の横に寝かされる。若者の家族は心配して成り行きを見守り、小学生の合唱隊がわけのわからない歌を歌い、患者の若者は医者の無能を非難する。そして医者は慌ただしく馬に飛び乗って逃げ出すが、馬車は今度はのろのろとしていっこうに進まず、背後には子供たちの「間違った」歌が響いている。こうして医者は馬丁の悪行を思い浮かべつつ欺かれたと感じ、冬の夜を彷徨う。 主人公のモデルはカフカの叔父で村医者であったジークフリート・レーヴィ。若い頃カフカはしばしば休暇をこの叔父のもとで過ごした。1917年にフェリーツェ・バウアーと二度目の婚約をするが、同年8月最初の喀血、12月には再び婚約解消。 全体に夢のような非現実的な経過の精確な描写ともいうべきこの物語では二つの領域が相対峙している。一つは独身の田舎医者が女中ローザと暮らしている場所(現実的生活の場)、そしてもう一つは彼を待ち受けている患者の家(芸術の世界)。この二つの領域の間には隠れた関連がある。即ち女中の名前ローザ(Rosa)は若者の薔薇色(rosafarbig)の傷口に対応し、また医者の家の豚小屋から出てきた強靱な馬が馬車を患者の家へと引っ張ってゆく。このように二つの領域は決して隔絶しているのではなく、繋がっており、医者は両領域間を移動する。また呼び鈴が鳴ったとき、医者は馬車に乗って患者のもとへ出かけるのと引き換えに、残忍な馬丁にローザを引き渡さねばならないのであり、現実的生活を去って芸術の世界に赴くためには女性を置いて行くことを余儀なくされる。 カフカは早いうちから、婚約者との生活は作家としての自己と相容れないことを自覚していた。彼にとって詩作とは認識を促し、真実に向かい、それゆえに心を癒すものだったが、詩人として生きようとするならば、その代償としてローザが具現しているような具体的感覚的な生き方は放棄せねばならないと感じており、詩人・作家としての生は女性との関係を破壊する危険性を孕むものだった。カフカは発病が女性との別離にとって決定的なものであるということを直観的に認識するが、それでも彼は明確な決断を自ら下すことができない。かくして田舎医者は自分とローザを救うために帰ろうとするが、芸術と現実的生活との葛藤の中でついにどちらにも決断できぬまま挫折する。彼は2つの領域の間の在り得ぬ場所を彷徨い歩き、そして希望のない果てしない雪平原に姿を消す。
解釈例
1.夜に鳴った呼び鈴は超自我、即ち主人公を見知らぬ天命へと引き渡す父権的な権威の間違った呼び声を意味するという解釈。 2.病気の症状、即ち精神的崩壊を描写した物語であるという解釈。 3.田舎医者は社会的な力を予測不可能で見通しのきかないものと誤解しているがために社会的に孤立し、それが彼を挫折へと導くという解釈。 4.脅迫観念に脅かされた人間の悪夢を表現した物語であるという解釈。
あとがき
カフカの事典、フランツ・カフカの人と作品について、知っておきたい事柄をまとめた本、それをつくっ ておきたいと思った。カフカ研究とカフカの読者とのあいだに、あまりにも大きなへだたりがある。それを 痛感したからだ。 フランツ・カフカの死後、二十年あまりして、この特異な作家が「発見」された。以来、カフカ論、カフ 力研究は途方もない数にのぼる。世界中から集めれば、それだけで大きな図書館ができるだろう。 カフカの生涯をめぐって、いまや何年何月の何時にフランツ・カフカが何をしていたかまで、おおよそ突 きとめられている。 カフカの作品をとりあげ、主人公の言動すべてが意味解きされてきた。 カフカにかかわり、カバラ思想とも、ユダヤ人存在とも、官僚制とも、ありとあらゆるテーマで論じられ てきた。 その一方で、カフカの読者は、遠くに置きざりにされている。生前はほとんど無名で、つましいサラリー マンであったこと、保険業務にたずさわり、産業社会の裏側をよく知っていたこと……。基本的なことが、 きちんと伝えられていないのだ。そのせいか「むつかしい小説」といった先入観が、いつまでも消えない。 読者のための事典である。そんな本の必要を思っていた。しかしながら、こちらは、そういう仕事におよ そ無能である。ながらくエッセイ体の文章を書いてきた。それは事典風の記述とは犬と猫のようにちがう。 犬にはとてもニャーと鳴けない。 若いドイツ文学者の若林恵さんとは、これまで何度か一緒に仕事をした。その人となりをよく知っている。 事典として大切な部分を書いてもらうことにした。クルミの実にあたるもの。こちらはまわりのやわらかい 外皮を受け持ったぐあいである。 とりかかると、やはり手間どった。はじめてから五年ぐらいになるのではなかろうか。若林さんのところ はできたのに、こちらの担当がはかどらない。当時、出ていた「三省堂ぶっくれっと」に連載したり、「ユ リイカ」のカフカ特集号を引き受けたりして、少しずつためていった。 事典であれば、どのようにくわしくもつくれる。ドイツで出ている同種のものを参考にして量を考えた。 あれもこれも、言いだせばキリがない。さしあたりカフカ理解に必要と思われる範囲にとどめた。 カフカについては、まだまだ未知がある。かつて定説であったかなりが訂正された。「全集」ですら大き く変わった。長篇小説『アメリカ』のタイトルが消えて『失踪者』となったのは、ごく近年のことである。 この点でもさしあたり、事実とされるところを書いた。 やっと本になるまでにこぎつけた。若林恵さんに、あらためてお礼を言いたい。いろいろとお世話いただ いた三省堂編集部の松本裕喜さん、どうもありがとう。
日経新聞・紹介記事(2003.7.31)
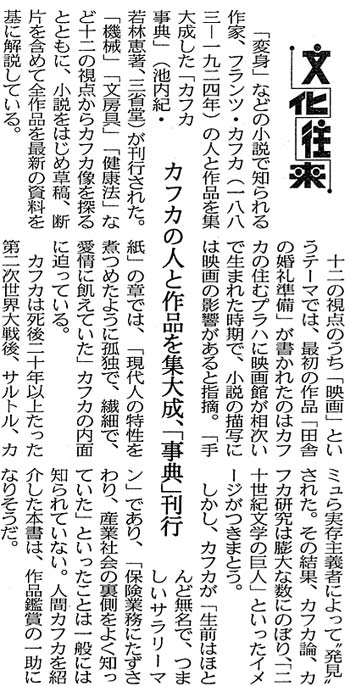
目次
カフカの甦り
はじめに
フランツ・カフカ
人と作品
カフカ文学をめぐる十二章
機械 文房具 健康法 金銭 本づくり 性 映画 女性 家族 動物 散歩 手紙
カフカの作品I
小説
『失踪者』
『審判』
『城』
『観察』
街道の子供たち ペテン師の正体 突然の散歩 腹をくくること 山へハイキング ひとり者の不幸 商人 ぼんやり外を眺める もどり道 走り過ぎていく者たち 乗客 衣服 拒絶 持ち馬騎手のための考察 通りの窓 インディアン願望 樹木 不幸であること
『判決』
『火夫』
『変身』
『流刑地にて』
『田舎医者』
新しい弁護士 田舎医者 天井桟敷にて 一枚の古文書 掟の門前 ジャッカルとアラビア人 鉱山の来客 隣り村 皇帝の使者 家父の気がかり 十一人の息子 兄弟殺し 夢 ある学会報告
『断食芸人 四つの物語』
最初の悩み 小さな女 断食芸人 歌姫ヨゼフイーネ、あるいは二十日鼠族
カフカの作品II
新聞・雑誌への発表作
女性の聖務日課 祈る人との対話 酔っぱらいとの対話
プレシアの飛行機 ある青春小説 永の眠りについた雑誌
リヒャルトとザームエル 大騒音 マトラルハザ便り バケツの騎士
カフカの作品III
草稿・断片
田舎の婚礼準備 ある戦いの記録 村の教師 下級検事 エルバーフェルトの馬 中年のひとり者ブルームフェルト 墓守り 橋 狩人グラフス 万里の長城 中庭の門をたたく こうのとり だだっ子 隣人 雑種 よくある出来事 人魚の沈黙 プロメテウス アフォリズム集成 父への手紙 夜 却下 掟の問題 徴兵 ポセイドン 仲間同士 町の紋章 舵手 試験 禿鷹 小さな寓話 こま 出発 弁護人 ある犬の研究 一つの注解(あきらめろ) 寓意について 夫婦 棺 帰郷 巣穴
カフカ・キーワード
妹オットラ K/ヨーゼフ・K グスタフ・ヤノーホ 父親へルマン ドーラ・ディマント 日記 フェリーツェ・バウアー プラハ プラハ・ドイツ語 マックス・ブロート ミレナ・イェセンスカ 夢の形式 労働者傷害保険協会 ローベルト・ヴァルザー