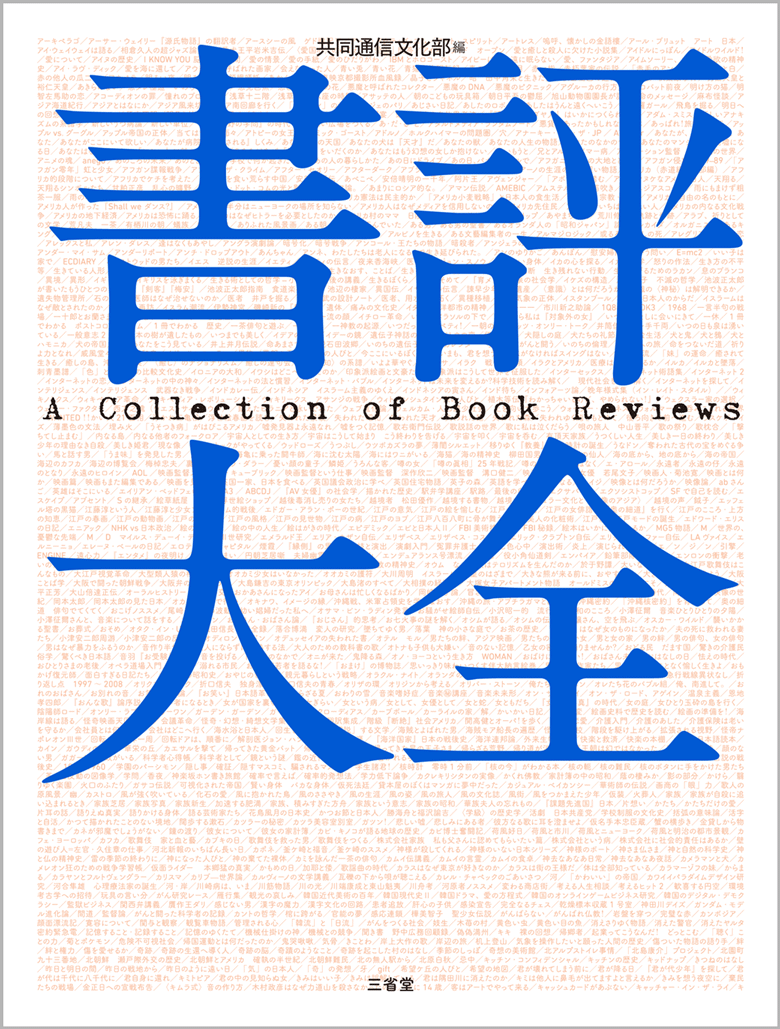三省堂 辞書ウェブ編集部による ことばの壺
「百学連環」を読む
- 定価
- 3,520円
(本体 3,200円+税10%) - 判型
- A5判
- ページ数
- 528ページ
- ISBN
- 978-4-385-36522-0
-
改訂履歴
- 2016年8月20日
- 発行
150年前の知のマップを眺望する。
西周の私塾での講義「百学連環」は当時の西欧諸学を相互の連関の中で見渡そうとする試みであった。
その講義録を現代の言葉に置き換え精読することで、文化の大転換期に学術全体をどう見ていたかに迫る。
特長
関連リンク
- ことばのコラム「百学連環」目次ページへ
この書籍の元になった著者による連載をご覧いただけます。
さらに詳しい内容をご紹介
著者プロフィール
山本貴光(やまもと・たかみつ)
文筆家・ゲーム作家。
1971 年生まれ。コーエーにてゲーム制作(企画/プログラム)に従事の後、2004 年からフリーランス。代表作のゲームに『That's QT』『戦国無双』など。
著書に『心脳問題―「脳の世紀」を生き抜く』(吉川浩満との共著、朝日出版社。後に『脳がわかれば心がわかるか―脳科学リテラシー講座』として改題増補改訂、太田出版から刊行)、『問題がモンダイなのだ』(吉川との共著、ちくまプリマー新書)、『コンピュータのひみつ』(朝日出版社)、『文体の科学』(新潮社)など。訳書に『MiND―心の哲学』(吉川との共訳、ジョン・R・サール著、朝日出版社)、『ルールズ・オブ・プレイ』(サレン/ジマーマン著、ソフトバンククリエイティブ)などがある。
「哲学の劇場」主宰。
はじめに
これからご一緒に、ある文書を読んでみたいと思います。今回注目するのは西周の「百學連環」です。いまではほとんど顧みられなくなった、というより、これからお話ししてゆくように、そもそも目に触れることの少なかった文章です。詳しくは読み進めてゆく中で述べるとして、読解にとりかかる前に、少しだけ前置きをしてみます。
この「百學連環」という文書は、明治3年頃につくられました。西暦で言えば1870/71年、いまから150年ほど前のこと。後に明治維新と呼ばれることになる一連の動きによって、江戸幕府が倒れ、明治時代が始まった頃のことです。
西周(にし・あまね、1829-1897)は、江戸から明治にかけて活躍した人でした。江戸幕府や明治新政府の一員として働くと共に、従来の日本における知をベースにしながら、当時はまだ誰もが当たり前のように知っていたわけではない西洋の知を理解・吸収し、翻訳や講義や著述を通じて公にするという活動を続けました。ときに「明治啓蒙知識人」「啓蒙思想家」などと呼ばれています。ごく簡単にその経歴を見ておきましょう。
西周は、1829年(文政12年)に石見国(いまの島根県)の藩医の子として生まれ、はじめは儒学を、後に洋学を学びます。蕃書調所に勤め、1863年(文久3年)には、津田真道らとオランダに留学。ライデン大学の法学教授シモン・フィッセリング(Simon Vissering、1818-1888)について政治、法律、経済、統計、哲学などを学び、帰国後は、徳川慶喜の顧問としてフランス語を教えたり、私塾を開いたりしています。
維新後は、新政府で軍事制度の設立などに携わりつつ、やはり私塾を営み、そこで本書の主題である「百学連環」などの講義も施したのでした。森有礼らと結成した明六社の刊行物『明六雑誌』に同人として論考を寄せたり、論理学、心理学、美学など、多方面にわたる著述や翻訳も精力的にこなしています。1897年(明治30年)に没するまで、東京師範学校校長や東京学士会院会長、貴族院議員などを歴任という経歴から窺えるように、この転換期を、政治家・学者・教育者として生きた人物でした。
より詳しくは、清水多吉『西周──兵馬の権はいずこにありや』(ミネルヴァ日本評伝選、ミネルヴァ書房、2010) などをご覧になるとよいでしょう。また、当人による「自伝草稿」(『中公バックス日本の名著34 西周 加藤弘之』、中央公論社、1984)には、幼少時から維新以前までの範囲とはいえ、折々にどのような書物を読んだのか、あるいは留学にでかける旅路のことなども臨場感たっぷりに書かれており、すこぶるつきに面白いものです。また、親類であった森鷗外が、西周伝を残しております。
さて、先ほど本書では、西周の「百學連環」を読むと言いましたが、実際にこの文書を書いたのは弟子の永見裕という人物でした。ちょっとややこしいのですが、「百學連環」は、もともと西先生が私塾で行った講義の記録なのです。その講義を聴いていた永見が、西先生の言葉を筆記したという次第。
この文書、ありがたいことに現在では、活字に起こしたものが『西周全集』(宗高書房、1981)の第四巻などに収録されています。ただ、手に入れづらいこともあって、必ずしもよく読まれているとは言えないのが現状です。そこでなんとかしてこの「百學連環」を、改めて読みやすく手に入りやすい形にできないだろうかと思っていたところ、ご縁があって「三省堂ワードワイズ・ウェブ」という三省堂が運営するウェブサイトを使わせていただけることになったのでした。そこで「「百学連環」を読む」と題して、2011年から2013年まで、毎週1回のペースで全133回にわたって書き継ぐことになりました。その連載をまとめて全面的に改稿したのが本書です。
それにしても、どうしてわざわざ150年も前の講義録を、いま読み直そうというのでしょうか。本書を読むかどうかを判断する手がかりにもなろうかと思いますので、少し述べてみます。事は「学術」に関わっています。とりわけ、その全体をどう捉えるか、どう考えるかという大きな問題に関わっているのです。
目下、学術がどのような状況にあるかということは、例えば、各種大学の編成から垣間見ることができます。それぞれの大学は、多くの場合、複数の学部から構成されており、学部はさらに複数の学科に分かれています。学部を例にとると、工学部、理学部、農学部、医学部、薬学部、文学部、法学部、経済学部、教育学部等々、といった具合です。もっと大まかには、学問全体を、理系/文系といった分類や、自然科学/人文学、あるいは自然科学/人文学/社会科学と分類することもあります。
このような学術の分け方は、人類の歴史のなかで生まれたり消えたり変化してきたものです。でも面白いことに、こうした学術の分類は、私たちにとっては、最初から、つまり自分が物心ついたときには、すでにそういうものとして存在していたりします。そして、そういうものについて、人はしばしば「どうしてそうなったのか」という来歴を忘れます。来歴が分からなくなると、その必然性も見失われかねません。
もう少し具体的に身近なところで考えてみましょう。例えば、高校の段階で、文系か理系かというコースを選ばされたりすることがあります。そのとき、なぜそんなふうに分かれているのか、不思議に感じたことはないでしょうか。まるで世の中には2種類の学術領域があって、その二つは水と油であるかのように分けられている。誰がいつそんなふうに分けたのか知らないけれど、とにかくそういうものなんだからどちらかを選べというわけです。そして、一旦いずれかを選ぶと、ほとんどの場合、それ以降、選ばなかったほうの領域は縁がないものとして積極的な関わりを持たなくなったりもします(ここで「そんなことはないぞ!」と憤慨していただければ、むしろ幸いです)。
あるいは、小中高の授業が複数の「科目」に分かれていることについても似たようなことが言えます。例えば、国語と数学と歴史は互いに関係のない別の科目だと考えられています。国語とは日本語を扱う科目ですが、その中心となる材料は文学です。でも、考えてみるまでもなく数学も歴史ももともと日本語(自然言語)で書かれたものです(数学の記号は元来自然言語で書いていたものを抽象化したものです)。では、どうして国語では数学や歴史の文章ではなく、文学だけを扱うのか。誰がそういう区別を考えて、いつからそんなふうにしているのか。思えば謎だらけです。
いずれにしても、私たちは物心ついたときから、学術がいろいろな領域に分かれている状態を当然のことと思って生きています。また、学術が進展するにしたがって、細分化され専門化が進むことは必要があってのことです。ここで問題だと思うのは、いつしかそうした学術全体を見渡してみようという試みがなくなって、細分化した領域相互の関係がどうなっているのかということ、あるいは学術の全体像というものがあまり顧みられなくなっていることです。しかし、学術に限らず、全体を顧みないまま限定された部分ごとの最適化ばかりに注目しすぎた結果、例えば公害や環境破壊のような問題が深刻化したのはご存じの通りです。目の前だけを見ると、一見、経済的には効率のよいことが、長い目、あるいは広い目で見ると、巡り巡って自分たちの生きる環境を損ない、自分たちの首を絞めてしまうという非効率を生むわけです。
昨今「エコロジー」と日本語で言えば、なんだか環境保護の話のように思えてしまうかもしれません。しかし、言葉の元来の意味でエコロジカルに考えてみることも必要だと思うのです。つまり、エコロジー(ecology)とはドイツの生物学者エルンスト・ヘッケル(Ernst Heinrich Haeckel、1834-1919)が、生物を考察する上でその個体だけでなく、その生物が周囲にある他の生物や自然環境と取り結ぶ「あらゆる関係」を視野に入れて検討する試みに名付けた言葉でした(Ökologie)。この意味でのエコロジーは日本語で「生態学」と訳されます。話を戻せば、いわばそういう意味で個々の学術だけでなく、学術のエコロジーを考慮してみる必要があると思うのです。
本書で「百學連環」に着目してみたい理由は大きく二つあります。一、この講義は、当時の西欧学術全体を相互の連関のなかで広く見渡してみようという試みです。二、この講義を行った西周は、西欧学術が日本に輸入される際に、それまで日本語にはなかった多くの言葉を造った人物でもありました。現代日本語の大恩人の一人です。現在でも、彼が翻訳・造語した言葉は、学術その他の領域で使われています。そうした言葉の起源を知ることは、自分たちが現在行っていることの足元を確認するためにも必要なことです。という具合に、現代における学術の全域を捉えなおすためのよすがとして、「百學連環」の試みは、幾重にも手がかりを与えてくれると睨んでいるのでした。もちろん現在とは学術を取り巻く状況やその編成が違います。しかし、これから見てゆくように、学術やその分類の発想自体は、さほど大きく変わっていません。そういう意味で、「百學連環」は、来し方を見直し、現在を見る目を養い、さらには行く末を占うための一つの材料として、うってつけの文書だとも思うのです。
とはいえ、なにしろ150年前のものですから、そのまま読もうと思っても、にわかには分からないことも多々あります。そこで、原文をご一緒に眺め、じっくり一文ずつ現代語に直しながら、そこに書かれていることを吟味してみようというわけです。
というわけで、前置きはこのくらいにして、さっそく読解にとりかかりましょう。
電子書籍版のご案内
配信日:2016年8月12日
レイアウト:リフロー型
備考:フルカラー
※価格・対応端末は、電子書籍を配信する各サイトでご確認ください
※表示環境によっては、旧字などの字形が正しく表示されない場合があります。