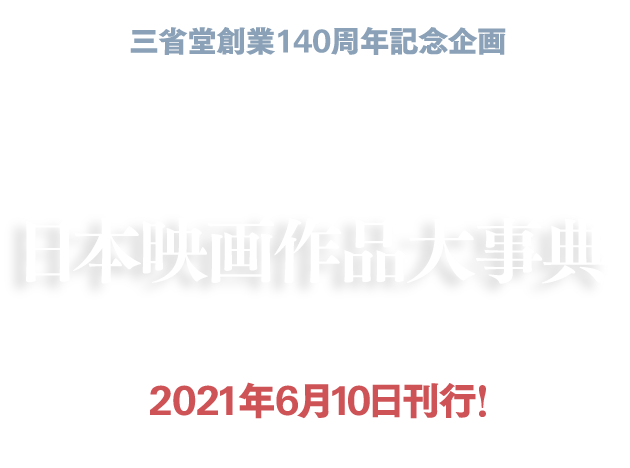司会 第二部は、聞き手が鈴木一誌さんから山根貞男さんに替わって、「本文レイアウトから造本設計へ」と題し、事典のブックデザインに話を移していきたいと思います。
組版ソフトの選定
山根 僕は事典のいろいろな内容について20年ずっとやってきて、その都度どういう形、どういうデザインになるのか、随所で報告を受けていたので、全く知らなかったわけではありません。でも具体的な変遷はよく知らないので、細かい話になるかもしれませんが、聞いてみたいと思います。すごく初歩的なことから伺いますが、映画の事典を作ろうと思った時に、横書き・B5判、それは最初から決まっていたのですか。
瀧本 1999年1月の社内文書では既にB5判です。実は途中で、B5判と少しだけ違う四六倍判に変えたのですが、最終的にB5判に戻りました。ちょっとした変化はありましたが、B5判・横組・3段組は、最初から大体決まっていたと思います。
山根 鈴木さんとしては、それは別に問題はなかったのですね。
鈴木 欧文や数字も入るし、横組でよいと思いました。
山根 実際に作業を始めた頃、組版の方式は、いろいろあったのですか。
鈴木 組版の方式はいろいろあって、2000年当時は、まず組版のソフトについてかなり悩んだ時期ですね。組版ソフトの多くは米国製で、縦組よりは横組が得意なのです。クォーク社のクォークエクスプレス、アドビ社のインデザイン、どちらがいいのかの分岐点で、実はかなり迷いがありました。『昭和の劇 映画脚本家 笠原和夫』(2002年)や、深作さんと山根さんの共著である『映画監督 深作欣二』(2003年)はクォーク、『遊撃の美学 映画監督中島貞夫』(2004年)もまだクォークですが、『映画の呼吸 澤井信一郎の監督作法』(2006年)あたりからインデザインが射程に入ってきて、かなりの過渡期でした。
山根 何が大きく違うのですか。
鈴木 詰め打ちの性能など、かなり違います。2000年当時は、デザイナーの戸田ツトムさんと「季刊d/SIGNデザイン」というデザイン批評誌を創刊しようとしていて、来たるべき組版はどういうシステムがいいのか彼と話し合いました。『日本映画作品大事典』が7、8年はかかるという長期的な視野に立った時に、どちらのソフトがいいのかという話もしました。インデザインがよかったのは、一つは組版をかなり自動化できた。例えば、データ上ある特殊な鍵括弧を使って、文字をその括弧で挟んで、書体や大きさを指定しておけば、自動的に組版ができたのです。全部手でやる必要がなくなります。1000頁もの事典なので、自動化できるかどうかは、かなりのポイントになりました。もう一つは、文字同士をピッチによって変えて詰めること。この理由は後で言いますが、このためには、インデザインというソフトと、フォントワークスの筑紫明朝体というオープンタイプのフォントが必要でした。このインデザインの開発に加え、筑紫明朝体にも戸田さんが携わっていました。戸田さんが携わりその人脈によって見えてきたソフトとフォント、インデザインと筑紫明朝、この二つが映画事典を後押ししたのです。この筑紫明朝体は横組がきれいだった。だから、この事典の陰には戸田ツトムがいると僕は考えています。また、パソコンで事典を作るのは、20年前はかなり怖いことでした。情報量が多いので、全体が1000頁だとすると50頁ずつぐらいの仕事に分けないといけない。これを、ジョブを切ると言います。例えば「あ」「い」「う」「え」「お」の音別にジョブを切って編集して、最後に校了になったら合体させる必要がありますが、見開き起こしにすると白頁が出る可能性があり、この処理がかなり厄介だと予想されました。フクインという印刷会社がノウハウを持っていて『JIS漢字字典』で実績があったので、最初フクインに頼んでいたのですが、パソコンやソフトの性能も上がり、三省堂の高山隆嗣さんの奮闘もあって、三省堂内で進めることになり、仕事の風通しがかなりよくなりました。
瀧本 組版はプログラムも含め、三省堂データ編集室の高山が担当しました。製本、印刷は三省堂印刷ですが、鈴木さんのご指導の下、結局、出版社の社内でプログラムによる自動組版をやったのです。そういうことを2000年当時できたかというと、ちょっと考えられなかったと思います。
山根 僕が編集の中身について20年間じたばたしたように、そういうことも変わっていきつつ、どこかで決まったわけですよね。
鈴木 基本的な組み合わせとしては、2000年頃に決めていました。フラットになる本文レイアウト
山根 見本組が4通りありますが、基本的に何が変わっているのですか。
鈴木 一つには文字詰めの性能。例えばひらがなの「り」と「へ」、横組では「り」は縦長、「へ」は横長ですね。こういう極端に形が違うかな文字をどう詰めるかという問題があります。
山根 日本語は、漢字、ひらがな、カタカナ、数字が混じっていますね。僕の本や「キネマ旬報」の連載「日本映画時評」なども鈴木さんにレイアウトしてもらっていますが、漢字、ひらがな、カタカナのフォントはそれぞれ違うのですか。
鈴木 「日本映画時評」とこの事典では書体は違いますが、書体デザインは、共通して博多にあるフォントワークスという会社の藤田重信さんによるもので、統一性があります。その書体も、時代と共に文字そのものの性能や組版の精度が上がったりして、文字の詰まり方、詰め方が微妙に違ってきます。
山根 詰まり方というのは、先ほどの「締め上げる」というのと……(会場笑)。
鈴木 どこまで締め上げるかが、時代によって違ってきた。
山根 1行に入る文字数は同じですか。
瀧本 かなを詰めていくので、かな文字が多ければ1行に入る字数が増えます。
鈴木 今、21字から22字入っています。18字からスタートしたので、それだけ文字収容量が増えているということですね。締め上げましたので(会場笑)。
山根 タイトルはゴシックですが、これは一貫して同じものですか。
鈴木 同じですが、タイトルも字間は詰まっています。
山根 見本組①の『大幹部 無頼』で「大幹部」の後のスペース、これは最終的にはこんなに空いていないですよね。資料6

瀧本 スペースは全て半角にしたこともあって、詰まっていますね。
鈴木 最初の見本組では、作品名の前の行送りを半行多めにしています。それを全部同じ1行送りにしました。これは、『阿片台地 地獄部隊突撃せよ』で見たような、作品タイトルの処遇の問題と同じです。メインタイトル、サブタイトル、角書きなど、タイトルの中の階層をどんどん減らしていったように、組版の方も階層を減らしてフラットにしていきました。フラットにすることで、1行空きがすごく効いてきたり、作品名の太い文字が効いてきたりすることを見せたかったのです。それで、本文に見合った形で、組版もフラットにしていきました。日本語は詰め打ちをしないと、漢字の画数によって濃淡のでこぼこができてしまいます。例えば「鬱」という文字があると、そこだけボコっと真っ黒に見えてしまう。紙面がなかなかフラットにならないというのが、日本語組版の宿命です。それを解消するため、文字詰め、文字をピッチによって詰めていくことで、紙面がフラットになっていく。スペースのグレー化とも言いますが、紙面として、均等なグレーに近づけようとしました。
瀧本 昔は活版印刷で、鉛の活字を手で組む、それが組版でしたが、辞書はその時代から、縦組の場合、縦3分の2に平たくした形のひらがな、カタカナを使うなどして、今鈴木さんがおっしゃったことを何とか実現して、グレーが綺麗に出る工夫をしていたのです。それをインデザインなどのソフトを使って、かなり極限までを進めていただいたと受け取っています。「コンサイス英和辞典」など横組の場合は、左右で圧縮をかけた長体のかなを使っています。
山根 3段組も、最初からですか。
鈴木 そうです。2段組では行長が長すぎ、4段組では短い。
瀧本 この判型、本文の文字の大きさからすると、3段組が一番いいということになりました。
山根 僕が内容を編集している中、デザインに波及することなので、いつも一番気になっていたことがあります。年月が経てば経つほど、作品数も監督数も増えていくわけで、分量の問題にどのように対応されたのか。単に頁数を増やせばいいということではないですよね。
鈴木 締め上げるのと関係しますが、インデザインでは、詰め具合を選択できるのです。どのくらい詰めるかによって、文字の入り方が違ってきます。いわゆるウィドウ・オーファン問題とも呼ばれる、行頭に1文字だけ残ったり、段の最上部に1行だけ残ったりした場合に、インデザインの機能では、強く詰めれば入るという指定ができる、その調整がすごく楽なのです。これが1文字全角の活字だったら、大変なことになります。
瀧本 活版の時代はそういう時、職人さんが活字を削ったり、微妙な字間を作るためチリ紙を詰めたりしたという伝説が残っていますけれども、それはまさに手仕事にっぽんの世界なので、今やるのは難しい。
澤井信一郎監督の作法への接近
山根 柱が上に来たというのは、なぜですか。
鈴木 なぜでしょうか(会場笑)。組版的には、二つの重大なことがありました。プロポーショナル字詰が一つの勘所だったのですが、もう一つはこの柱スペースを下から上に持ってきたことが、小さな革命、転機だったと思います。
山根 上下どちらでもいいのですか。
鈴木 どちらでもいいといえば、いいのです。例えば、英語の組版では、柱のことをランニングヘッドと言って、頁の上部にないと駄目らしいのです。でも僕はどちらでも構わない。ヘッドではない柱にして、欧文を組んだこともあります。ただ、柱があろうとなかろうと、少なくとも下に余白は必要ですよね。下にあった柱を上に持ってくることで、頁の上下の余白が合体して、余白が増えた気がする。紙面では、上の13ミリの余白が白い帯のように走っている。柱を下から上に移動して、余白を散らさず固めて配置するというのが、このブックデザインの一つのコツでした。それに気がつくのが、なぜこんなに遅かったのかとも思いますが、2002年から2009年の間にその変更をした。プロポーショナル字詰めで、グレースペース、フラットな紙面が実現した。そして柱を下から上へ変更することで、余白を合体して配置し、広く大きく見えるようにした。この二つについては、ちょっと話が飛びますが、2000年代初めに僕は澤井信一郎監督にインタビューしていて、澤井さんの監督作法に、デザインが接近した結果ではないかという気がして仕方がない(会場笑)。澤井さんは、顔で演技するな、怒鳴るな、等身大で喋れと演技指導した。つまりフラットにしろと言っているわけです。それをブックデザインでどう実現するか、確証はないですし、どう繫がったのかわからないですが、フラットにという指向があったかもしれません。
山根 デザインでは、普通、フラットというのを……。
鈴木 嫌いますね。
山根 ですよね、色気がないとか。
鈴木 フラットを嫌うのは、顔で演技しろというようなものですよね。だから、澤井さんの映画監督作法にどこかで影響を受けているのかもしれません。柱を上へ持ってきて余白同士を合体して、余白があまねくではなく偏ってあるようにする、偏在ですね。これも緩急をつけるという、澤井さんがおっしゃっていた、マキノ雅弘直伝の作法の影響があるかもしれない。顔で演技するな、フラットにいけ、緩急をつけろ。マキノ雅弘から澤井さんに通じる監督作法が、2000年代初めの組版に影響を与えたのではないかという気がします。
山根 事典の大部分の項目では、監督の履歴、紹介があってフィルモグラフィーがついていますが、フィルモグラフィーがついていない項目もありますね。戦前の監督など、経歴やどういう作品を撮ったかという監督解説だけで終わる監督項目も結構ある。戦前には200本以上撮っている監督も結構いるし、ものすごく苦労して調べてもフィルモグラフィーが違っていたり確定できなかったりしたこともある。フィルムも1本も残っていない。だから、そういう監督のフィルモグラフィーは無理だ、監督解説のみでやろうと決めました。監督見出しのデザインとして、監督名の横に黒い縦罫がありますが、たしか以前は、そのような項目は、違うデザインでしたよね。
瀧本 3種類の罫線を使い分ける予定でした。全てのフィルモグラフィーがある監督、ごく一部のフィルモグラフィーがある監督、監督解説のみで作品を紹介した監督と、3種類の罫線で扱いの違いを明示するつもりでしたが、結局やめました。
山根 読めば分かるから、記号で示す必要はないということですね。そういう意味でも、余計なものを取っていったわけですね。
鈴木 フラットなデザインにしていった。
山根 デザイナーの仕事としては、すごく逆説的ですね。
瀧本 そうですね。もう一つ編集上の理由としては、全フィルモグラフィーとは何かという大変な問題があるのです。「全」という定義がとても難しい。8ミリ、ビデオ、テレビ映画のほかにも、公開形態もさまざまな作品があって、当初は執筆規約で、最終的には凡例で、作品の収録基準を何とか定義してきました。でも、フィルモグラフィーの範囲を定めるのは、実はとても難しい。編集上もそういう分け方はしない方がよいということになりました。
鈴木 最近まで2種類の罫線の使い分けは残っていましたね。かなりギリギリで1種類にしました。
排除されたビジュアルな要素
山根 ところで、映画ファンは、映画の事典なのでどこかに写真があると思われるのではないでしょうか。キネマ旬報社の『日本映画監督全集』などにも監督の顔写真が入っていますが、この事典には映画関係のビジュアルな要素はありません。でも、最初はちょっとビジュアルなところもありましたよね。
鈴木 音節見出しのバックに画像を入れようかと思いましたが、やめました。
瀧本 「あ」「い」「う」「え」「お」などの音節見出し、今はスミベタの部分です。スチール写真に濃いアミをかけて、何の作品か分かるようで分からないようにした画像を使う案がありました。
鈴木 例えば「い」の見出しで、伊藤大輔の作品を使うとしても、本当に伊藤大輔でよいのか、さらに伊藤大輔のどの作品にするのか、と大変なことになります。それでやめました。
山根 鈴木一誌というデザイナーは、写真の扱いがめちゃくちゃおもしろい。僕が長く連載している「日本映画時評」でも、初期はスチールを切り貼りして、アクロバティックなくらい紙面が動くようにしていました。書籍のカバーも鈴木さんがデザインすると、やはり写真が躍動的に使用されています。それを全部禁欲的にされたのは、画期的ではないですか。
鈴木 2010年ぐらいから、ブックデザインは世界を可視化できないのではないかと感じているのです。例えば、世界を動かしている一大原理である金融は、絵にならなくなっています。昔は、兜町の株式市場の電光掲示板を見せれば、金融だとわかってもらえましたが、今はわからないですね。仮想通貨なんて絵になるのかと考えると、わからない。2010年以降、ブックデザインは世界を可視化できないと思う方がよいのではないかと感じていて、それはすごく細かいことで見えてきます。この間、四六判の1000円台の並製の本で、相模原やまゆり園事件のドキュメンタリー、裁判記録の本を装幀したのですが、全く絵にならない。やまゆり園の施設と献花台と判決が出た横浜地裁の建物の写真がありますが、それがあの事件の表象になっているかというと、全くそうは思えない。ウイルスの問題を含めて、どんどん見えなくなっていることを痛感せざるを得ない時代が来ていて、その結果、この事典では、いかにビジュアルをやめて装幀するかという発想になりました。
山根 今、書籍や雑誌でスチール写真を使うと、だいたい1点3万円ですね。例えば100枚スチールを使うと300万円制作費がアップするというような具体的なことも出てきますが、そういう経済的な問題ではないのですか。
鈴木 経済的な問題もあります。が、映画会社がスチール写真をデジタルで保存しようとして1作品あたり20点くらいにしぼるのですが、しぼるセンスが悪くて、ろくなスチールが見つからないことが多い(会場笑)。例えば『昭和残俠伝 死んで貰います』で、「これが喜楽の味だね」とか「秀さん、血は争えねえな」とか、そういう場面のスチールを探しても全くないのです。高倉健さんが亡くなった時にグラフ雑誌を作ったのですが、『幸福の黄色いハンカチ』のスチール写真のデータが印刷物からの複写で驚いた。センスがない人が選んでいる上に、どんどんスチールを捨てているという中で、お金をかけて選んでもろくなことがない。とりあえず本文はそこからスタートしました。ところどころ入れてもいいのですが、それは逆に難しい。それで根こそぎやめることにしました。ただ最終的には、装幀でビジュアルをやめてしまえるかという結構難しい問題がありました。例えばカバーをつけたり、普通の4色で刷った箱に入れたりすると、何かビジュアルを要請されてしまう。だからビジュアルな装幀を要請されないような製本と箱の仕組みにしました。あの箱は真っ黒で、どう考えてもスチールを入れてくださいとは言えないですよね。
山根 結果としてはなんにもない。黒い筒箱に赤い布張りの本が入っている、本当にシンプルで、余計なものはなんにもない。けれども、逆にすごく大きい感じ、広い感じがする、というのが僕の感想です。今あるような形は出来上がるまで見たことがなかったので、びっくりしました。
鈴木 書影という概念をなくした、という側面もありますね。本の姿を写真に撮っても、どうにもならない。
瀧本 確かにそうですね。書影は普通、表1正面、いわゆるおもて表紙を長方形の形で見せることが多いのですが、そうすると黒と白しかない。斜めにすると赤い布クロスの背が出ますが、それでも黒と白と赤しかない。その3色しか使っていない。
山根 僕は、鈴木さんのデザインワークがどんどん余計なものをそぎ落としていく方向へ進んで行ったと聞いて、中身についても苦労してずっとやってきたことと全く歩調が合っているなという気がします。余分なものは極力そぎ落とそうと、原稿執筆の方たちにすごく注文をつけて、ほとんど喧嘩みたいになることもありました。苦労して書いた原稿にいろいろ注文をつけられて、編集部から返されて、これはこういうふうに直してくださいなんて、怒るのも当然です。自分の書いた原稿ではなくなるから、名前は出ないようにしてほしいという要請もありましたし、辞める方もいました。それは、結局何をやっていたのかと考えると、やはり枝葉をそぎ落とすことだったと思いますね。
鈴木 別にビジュアルにしなくても、読んでもらえれば分かるという最終地点がありますよね。それは、先ほどのあらすじの書き方と一緒だと思いますが、とにかく読んでもらえれば、どういう姿勢で書いたか分かる。
映画という動体を定着させる
山根 事典の「まえがき」でも書きましたが、映画というものは静止体ではなくて、動体、動くものですよね、それを文字として定着しないといけないので、とても苦労しました。動く生き物である映画を、文字として、活字として定着する作業に22年かかってしまった。出来上がった事典は、そのことを、まさにデザインとしても表象していると思います。
鈴木 印刷物として定着させたにもかかわらず、止まっていない感じを出す、動くように感じさせながら定着させるという作業だった。今から思うと、この事典と構造がよく似ているのは漢和辞典ですね。漢和辞典の「のぎへん」を例にすると、「のぎへん」という項目の中に「のぎへん」を使った漢字が画数順に並んでいる。この「のぎへん」が、例えば小津安二郎だということです。小津安二郎の中に作品が公開順で並んでいるという構造は、漢和辞典に近い。
瀧本 その話は、初期の2000年の編集会議で出ていて、監督インデックスを採用するなら、漢和辞典のように冒頭に作品名五十音順索引をつけてはどうかという意見もありました。漢和辞典は大抵、冒頭索引で、音訓索引、総画索引などがあります。結局採用しませんでしたが、そうしてもよかったかもしれないと思います。
山根 僕の記憶では、巻末に何頁か日本映画史を書けと言われたことがありましたね。
瀧本 巻末の付録は、いろいろなアイディアがありました。山根さんの日本映画の歴史のほかにも、戦前からの非常に複雑な、製作会社の興亡史、会社と撮影所の変遷を重ね合わせたような年表をビジュアルでつけてはどうかという案もありました。その年表は、実はえらい苦労して下書きまではなんとか作ってみたのですが、確定するには、また大変な作業になる。
山根 あと2、3年はかかります(会場笑)。
鈴木 先ほどの「のぎへん」の話ですが、部首は画数で分類されていますが、なぜこの位置にあるのかという合理的な説明を聞いたことがない。これは康煕字典がそうだからとしか言いようがない。部首の順番は康煕字典という権威に頼っている。同じように、この事典は監督名の五十音順ですが、五十音もある種の権威なのではないでしょうか。なぜ五十音なのか、生年順で並べたらどうかという意見もありました。
瀧本 監督インデックスだとして、なぜ五十音順で並べるのか、監督の生年月日順に配列をしたらどうかという案もありました。でもそれでは、監督の生年の見当がつくような、相当プロの方、研究者でなくては引けなくなってしまう(会場笑)。とはいえ、五十音順でなくてはいけないのかと考えると、五十音順というものも、やはり恣意的なものなので、初期の議論では、恣意性を徹底して疑いたかったのでしょう。
山根 いろいろなことを思い出して、こんなにごちゃごちゃあって、さまざまなことが整理されていったのだなと思う22年の歴史でした。別にこの事典の仕事ばかりしていたわけではないのですが。今日話をするために2、3日前に、完成した事典の凡例をまた読み直しました。3回目くらいです。凡例とは、この事典はこういうルールで作りましたと示すものですけれども、当初は執筆規約という形で、原稿をどのように書いていただくか執筆依頼の際にお見せしました。最初は簡単なルールですが、まずはそれでやってみる。ずっとやっていくと、一旦決めたのに、ルールをはみ出すものがどんどん出てくる。また変えなくてはいけなくなる。そのようにしょっちゅう改訂して、今の凡例が決まったのは、今年2021年3月、刊行する直前でした。映画は、そんなふうに凡例をはみ出してくるものなのです。映画を凡例に合わせるわけにいかないので、凡例のほうを合わせる。凡例を見ると、これが出来上がる過程が22年だったのだなと一目で分かります。映画とはそういうものなのだと思います。
ひらかれた孤独な書物
鈴木 この本を作って今感じているのは、徹底的に孤独な本を作ったということです。この事典は回し読みできないし、貸し借りできない(会場笑)。読書感想文などありえない、個々に読むしかない。もちろん『広辞苑』も持ち運ぶのは大変ですが、汎用性がありますよね。家族の誰かに聞かれて引いたりする。この事典で、例えば『花芯の刺青 熟れた壺』を家族の誰かが引くことは、なかなかない(会場笑)。引いてもよいけれど、記述を消化しないと、対話が始まらない。この事典の読者を想定すると、夜中にテーブルの上に事典をベタっと開いておいて、DVDなどを見ながら、このあらすじのまとめ方がいいとか悪いとか言ったりする、そんなものすごく孤独な光景が見えます(会場笑)。もう一つの孤独な感じは、国語辞典の記述を読むのと全然違うということです。『新明解国語辞典 第八版』の「ほんぶん(本文)」という語釈が書きにくい項目では「〔注・解説・付録などに対して〕書物・文書の本体となる部分」とありますが、『日本映画作品大事典』の記述の質は、この記述と全く違う、誰かが見て書いたという身体性がすごく生々しく残っています。それが先ほどの、印刷物として定着しているけれども動きを止めていないという感じに繫がっていく。この事典の記述に向き合うには、徹底した孤独性が必要なのではないか。僕の体験では、これ以上孤独な本はたぶんできないのではないか(会場笑)。
山根 国語辞典は言葉の説明、漢和辞典は漢字の説明が書いてある。この事典は、映画という生き物の説明をしているわけですね。その生き物をどうやって取り押さえるか、それが結果的にうまくできているかどうかはわからないですが、そのことが出ているということですね。
鈴木 主観は排除しようとしつつ、見て書いたという身体性は残す。黒沢清監督作品については、一本の映画の中に、ホラーとメロドラマのように異なるジャンルが混じり合うという視点で書きましたが、これは主観でなく、見たという身体的記憶だと思いたい。とにかく、それを見て原稿を書いた人がいる。その人も孤独だと思いますが、そこに向き合わないと読んだことにならない。
瀧本 校閲の過程で、原稿の文章にかなり手を入れさせていただいて、そのことで軋轢が生じたこともありました。そうやって過剰な主観性みたいなものを削ってきたはずなのに、誰かが映画を見て書いた身体性が間違いなく残っていますね。
鈴木 でも、孤独、孤独と言う一方で、紙の事典として作ってよかったなともすごく思います。かなり多作の監督でも2見開きでだいたい一望できる。小津安二郎や黒澤明でも3見開き、マキノ雅弘で8見開き、舛田利雄、中島貞夫で3見開きですね。大体の監督が2見開きで一望できるのは紙というメディアならではで、電子書籍にはなかなかできない。
山根 作っている時に使命感があったわけではないのですが、「こんなものをよく紙で作られましたね、紙で出したことがすごい」と言う方が何人もいらっしゃいました。
鈴木 孤独ではあるが、紙であることによってひらいている。紙であることにおいてひらいているがゆえに、孤独が際立つ。
瀧本 そうですね。そもそもこの事典を通読される方というのは……(笑)。ひょっとするといらっしゃるかもしれませんが、怖ろしい映画好きの方が世の中にたくさんおいでになりますので。それにしても、「哀川翔」から始まって毎晩毎晩ちょっとずつ読んでいくというのは、鬼気迫る感じがします。普通の辞書や事典では、そういう読み方はされないのではないでしょうか。
山根 これからいろいろな方に見ていただいて、どう評価をされるでしょうか。こちらが苦労したこととは関係なく、中身については皆さんに判断していただくしかない、いくら精一杯やりましたと言っても、言い訳にしかなりません。僕としては、今日、いろいろな話の最後に、ひらかれた孤独な書物という言葉を聞いて、おもしろい、そこへ来たかと思いました。皆さん、ひらかれた孤独な事典をよろしくお願いします。
(終)