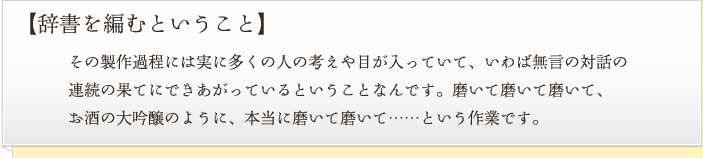辞書も『大辞林』ぐらい大きなものになっても、専門の人だけが読めればいいということではないですよね。どういう人が使ってもわかりやすいようにするっていうところは、エンターテインメントの精神に近いものがあるんじゃないかなって勝手に思ったりしています。
辞書は実用書なんですよね、究極の。学術書ではない。高度な専門的知識を背景にもって作られているので専門性は高い。でも、きわめて大衆的な書籍です。専門性と大衆性って普通はまじわりようがないのだけれど、辞典というものは、その二つが実用性の一点でまじわっている希有な書籍ではないかなと考えています。
専門の先生が何人も、辞書づくりにたずさわって、それぞれが最先端の研究をなさっていて、その成果を語釈にぶつけていると思うんですけど、その先生が書いた専門書を読んでも素人にはわからない。でも、研究の積み重ねが、多くの人にわかる形で辞書に反映されている。岩波新書でも、読んでいて「ごめん、わからない」っていうことがある。みんな向けのはずなのに、そういうものが中にはありますからね。辞書って最先端の研究をちゃんとみんなにわかりやすい形で、使える形で説明してくれているっていう、そこがすごい。
辞書の編集者としての役割のなかでは「多くの人にわかっていただけるものになっているかを点検する」ということ、これがすごく大きいんです。一項目一項目の語釈には多くの執筆者がいるわけですけれど、専門の学者の先生に書いていただく正確な元原稿をできるだけわかりやすくするというのが編集者の腕の見せ所といいますか……。
編集者の方が一番目の読者。小説の場合でもよく言われるけれど、辞書も同じで、編集者は辞書の最初の読者であり使用者だから、ここをこうしたほうがいいとか、著者の先生とは違う視点で指摘ができる。それによってより多くの人に届く形に練っていくということですよね。
専門書の場合だと、できあがった原稿に編集者が意見を言うことは、その内容が専門的であればあるほど少なくなるわけです。でも、辞書の場合は正反対。一番最初の、出発点の原稿から赤字(朱)が入るんです。編集者がそこで何をしているかというと、ひと言で言うとわかりやすくしているということなんですね。
そういう内容点検は編集者の方だけでやるんですか?
編集者、校正者、内容校閲をされる編集委員など、多くの人が、それぞれの役割に応じて内容点検をします。私が辞書づくりにかかわる人間として、辞書をお使いいただいている読者の方々に一番お伝えしたいのが、『新明解国語辞典』のように個性がはっきり出ている辞典でも、たった一人で編むということはなく、その製作過程には実に多くの人の考えや目が入っていて、いわば無言の対話の連続の果てにできあがっているということなんです。磨いて磨いて磨いて、お酒の大吟醸のように、本当に磨いて磨いて……という作業です。そういうイメージで辞書を見ていただければと。
そうして大勢の人が目を通して、晴れて出版されると、今度は辞書を使う人からの意見がどんどんきて、ますます研磨されるということですね。
はい。だから版を重ねている辞典は中身が練れていますね。どの辞書も完璧を期してつくるわけですけれど、初版というのはやっぱり、内容があちこち暴れている、バランスがとれていないという面がでてきます。それが個性と言えば個性なのかもしれないけれど……。
『大辞林』をはじめ、版を重ねている辞書の編集者の方って、次の版ではここをこういうふうにしようという準備をされますよね。使っている側からすると、「ええっ、そんなところ全部直すのは大変じゃないですか!」と思うようなことを考えていらっしゃる。「でもそのほうが正確ですし、使い勝手もいいと思うので……」みたいな感じで、すごく真剣に考えていらっしゃいますよね。
『舟を編む』では、作中の辞典『大渡海』の刊行祝賀パーティーの席上で、「明日から早速、改訂作業をはじめるぞ」という編集者の言葉が出てきますが、本当にそうなんですよ。できあがった時ほど嬉しくて怖ろしい瞬間はありません。正直言うと、できたばかりの辞書を正視できない。誤植とか、まずい部分を見つけたらと思うと見られない。だけど翌日ぐらいになると、早くも付箋が貼られているんですよ。その話をすると、そんなに間違いがあるんですか、ひどいじゃないですかと言われるんですけれども、間違いがなくても、直したいところが必ず出てくる。
ここは、もうちょっと解釈を深められたかも、というようなことが見えてくるんですね?
はい。すべての辞書はできあがったと同時に改訂のプロセスに入っていく。みんな本当にそう思っていて、ほぼ無意識に改訂を始めてしまう。
すごいことですねえ。私の場合は小説を本にしていただいても、読み返すことは、ほぼないんです。担当の編集者の方から「できました!」と送っていただいて、ついに形となったとうれしいんですけど、怖いからあまり開かない。
星新一さんは、自身の作品の書き直しをずっとなさっていたそうですよね。
そう、もう信じられない。文庫になる際に大幅に加筆修正する人もいるけれど、私は基本的にはしませんね。心臓に悪いですもの。
三浦さんは文庫化される時に手を入れたりはなさらない?
極力、入れないようにしています。ウワッて思っても入れないです。単行本の時に読んだ人に「文庫ではなんだか印象が違うな」と思わせては悪いというのもありますし、自分の精神が耐えられないということもあります。