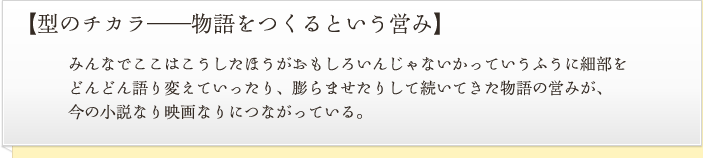今、学校では伝統文化に親しもうという学習が行われているのですが、三浦さんは文楽や歌舞伎がお好きですよね。文楽や歌舞伎をおもしろいと思った、それらと出会ったきっかけはどのようなものだったのですか?
文楽も歌舞伎も私が中学生の時の教科書には載ってなかったと思いますが、歌舞伎のほうは、友達に好きな子がいたので中学生の時から見に行っていました。幕見という八〇〇円ぐらいで見られる席があるんです。でも文楽のほうは、文楽というものの存在すら知らなくて、大学に入ってから初めて見たんです。伝統芸能が勉強の範囲に入っている学科で、その授業のなかで見るように薦められたんですね。それまで全然知らなかったので、まあ見てみるかという感じで見に行ったら、これが性に合った。とても波長が合ったんです。歌舞伎を初めて見た時は衣装が豪華できらびやかで楽しいというのがあり、文楽を初めて見た時は、三味線の音がすごく迫力があって、音楽としてかっこいいなと思いました。

これらの伝統芸能には型がありますね。
芸や話の型は、歌舞伎にも文楽にもありますね。たとえば我が子を主君の子どもの身代わりにするというようなストーリーがけっこうある。人気の出た作品の、いわば王道のパターンを使って「さて次はどういうふうにアレンジするか」みたいな感じで、次々にパロディ化していくんですよね。それがおもしろいなと思います。私はそういうものが好き。任侠ものの映画とかにも型がありますよね。組織のなかで裏切りがあって、屈辱に耐えて耐えて、それでもやっぱり最後は殴り込み、みたいな。そういう型があるものに私は惹かれるみたいです。型を踏まえて、細かく細かく細部を変えるとか、別の解釈で語り変えるとか。ロマンス小説などでも、だいたい素敵な男女が出会って、でも誤解が生じて離れそうになるんだけれど、最後には愛してるよでハッピーエンドという型があって、それが、こっちの話ではお相手がどこかの大地主だけど、こっちではアラブの大富豪みたいな。伝統芸能はそういうところがおもしろいなって思います。オリジナル信奉一辺倒ではないところというか。
語り直しですね。
すべての創作はそういうことなんじゃないかなって思うんです。本当のおおもとのオリジナルは何かっていうところは誰もわからない。それが物語のおもしろいところ。物語というのは、ある意味では物事を単純化することなんですよね。でも、ただの単純化に終わらせず、普遍性へとつなげるために、どういう味付けを細部にこらしていくかというところが勝負なのではないかと私は思っているんです。みんなで知恵をふりしぼって、細部を変えていきつつ、物語の型を生み出してきたのではないでしょうか。
「四谷怪談」にしても、人物関係はかなり複雑ですが、物語の骨格だけを抜き出したら単純ですよね。
ありふれた怪談と仇討ちの骨格なんだけど、そこに忠臣蔵という味付けを持ってきたりする。批判精神が投入されているし、そういうところがすごいなと思います。ゼロから作っているのではなく、型がいくつかあって、それに乗って、利用しながら作っている。
「物語にはオリジナリティーがなければならない」と考えること自体が間違っているのかもしれません。
オリジナリティーというのは幻想なんじゃないでしょうか。大昔、人類がたき火を囲んで「こんな話があったそうだ」と語っていた頃から、みんなで、ここはこうしたほうがおもしろいんじゃないかっていうふうに細部をどんどん語り変えていったり、膨らませたりして続いてきた物語の営みが、今の小説なり映画なりにつながっている。物語という要素をもっている表現すべてが語り変えの歴史を持っていると言えるんじゃないかなって思います。
実は私は、ここ十数年、日本映画の作品事典に関わっているのですが、三浦さんは、たとえば「昭和残侠伝」シリーズとか、お好きでしょう?
はい、もちろんです。
あのあらすじを三〇字くらいで書くとすると、どれもみんな、ほとんど同じになってしまいます。
一緒ですよね。高倉健の職業が違うだけ(笑)。あの辺りのシリーズものはだいたい同じですよね。「仁義なき戦い」シリーズだったら違った展開があって、一応あらすじも変わってくるんですが。
にもかかわらず、そういうシリーズが映画としておもしろいというのは、なんなのでしょう?
役者も展開も、骨格はみんないっしょなのに、続けて見ていっても飽きない。ついつい見ちゃう。料理人なのに健さんの包丁さばきがたどたどしいとか(笑)、いろいろありますよね、見所が。
先ほどの物語に関するお話と一脈通じるものがあるように思いますね。