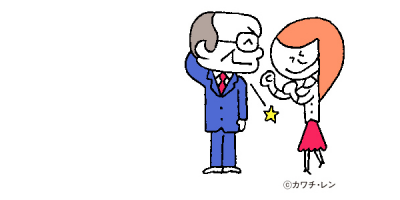今度は、話が positive のほうへと転じてゆきます。
近來佛國の Auguste Comte なる人の發明せし語に、總て何事にもあれ最初より都合克く遂るものにあらす、其を遂んには stage 卽ち舞臺、或は場と譯する字にして、其場所三ツあり。始めの一ツより次第に二ツを經て、第三に至りて止ると云へり。其の第一の場所とは Theological Stage 卽ち神學家、第二は Metaphysical Stage 卽空理家、第三は Positive Stage 卽ち實理家、此に至り始めて止ると言へり。總て此の如きものにして、其第一第二の場所を踏むの長短、久不久はありて其實理に至るの遲速ありと雖も、皆第三の場所を踏まされは實理に至るの道あらさるなり。
(「百學連環」第42段落第11文~第14文)
では、訳してみます。
近年、フランスのオーギュスト・コントという人が次のようなことを発案している。どんなことであれ、最初から都合よく成し遂げられるものではない。ことを成し遂げるには、「段階(stage)」を踏まねばならない。その段階は三つある。第一段階から第二段階へ、そして第三段階へ至って終わるというわけだ。さて、その第一段階を「神学段階(Theological Stage)」という。第二段階は「空理段階(Metaphysical Stage)」。そして第三段階は「実理段階(Positive Stage)」であり、ここでようやく終わるのである。すべてこのような次第であり、第一段階や第二段階には、それぞれ長所・短所や〔継続する〕時間の長さ・短さがあって、実理に至るのが早い場合もあれば遅い場合もある。とはいえ、いずれにしても第三段階を踏まなければ、実理に至る道はないのだ。
いかがでしょうか。ここでは、フランスの哲学者で、社会学の創始者として知られるオーギュスト・コント(Auguste Comte、1798-1857)の説が援用されています。
このくだりで言われている三段階説は、コントが学術に関わる人間精神の辿るステップとして論じたものです。例えば、『社会再組織に必要な科学的作業のプラン(Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société)』と題された1822年の試論では、次のように述べられています。
人間精神の性質そのものによって、人間の知識の各部門は、必ず次の三つの理論段階を次々に通るコースをとるものである。それは、神学的すなわち虚構の段階、形而上学的すなわち抽象の段階、そして、科学的すなわち実証の段階である。
(「社会再組織に必要な科学的作業のプラン」、霧生和夫訳、
『中公バックス 世界の名著』第46巻、中央公論社、1980、80ページ)
上の西先生の講義では、Metaphysical Stage を「空理段階」、Positive Stage を「実理段階」という具合に、西先生の訳語のままにしてみました。いま引用したコントの文章では、それぞれ「形而上学的段階」「実証的段階」と訳されています。
まず、簡単に補足すれば、神学的段階とは、例えば、自然現象を神のような超自然的な発想で説明しようとする段階のことです。
次の形而上学的段階、空理段階とは、神様を持ち出すのは止めて、もう少し自然に近い説明をするけれど、本当かどうかは分からない段階です。理屈はつけているものの、空理である可能性があるというわけです。
最後の実証的段階、実理段階とは、単なる理屈にとどまらず、観察や実験を通じて、実際に確かめられる段階といってよいでしょう。つまり、学問はこの段階に至ってはじめて学問たるというストーリーです。このことについて、コントの言葉をもう少し見ておくと、こんなふうに言っています。
第三の段階は、あらゆる学問の最終的方式である。前の二段階は、この段階を徐々に用意するだけのものでしかない。この段階では、事実を関連づけるのは、事実自体によって示唆され確認される、全く実証的な種類の一般的観念や法則などである。こうした観念や原則は、ときとして、単に原理の域にまで高めることができるほどに一般的な事実であるにすぎない場合もある。この原理をできるだけ少ない数に還元しようとする努力は払われるが、いつかは観察によって検討できるようなもの以外には仮説を立てるようなことはなく、いかなる場合でも、原理を現象の一般的表現手段としてしか見ないのである。
(前掲同書、81ページ)
少し長くなりましたが、これを読むと、西先生が Metaphysical を「空理」と訳したのは、見事だと感得されます。もちろん、Metaphysics を積極的に捉える文脈では、「形而上」(形あるものを越えたもの・理念・抽象)、つまり「形而下」(形あるもの・物質・具象)と区別されたことと訳せばよいわけです(ついでに申せば、これはいずれも『易経』に由来する語彙でした)。しかし、コントの文脈ではどちらかというと、第三段階の「実理」に至っていない段階、「実証」されていない段階という意味合いが強いので、「空理」とすると腑に落ちやすいと思います。
西先生は、これに続けて、例によって具体例で説明を施します。どんな例が出てくるでしょうか。