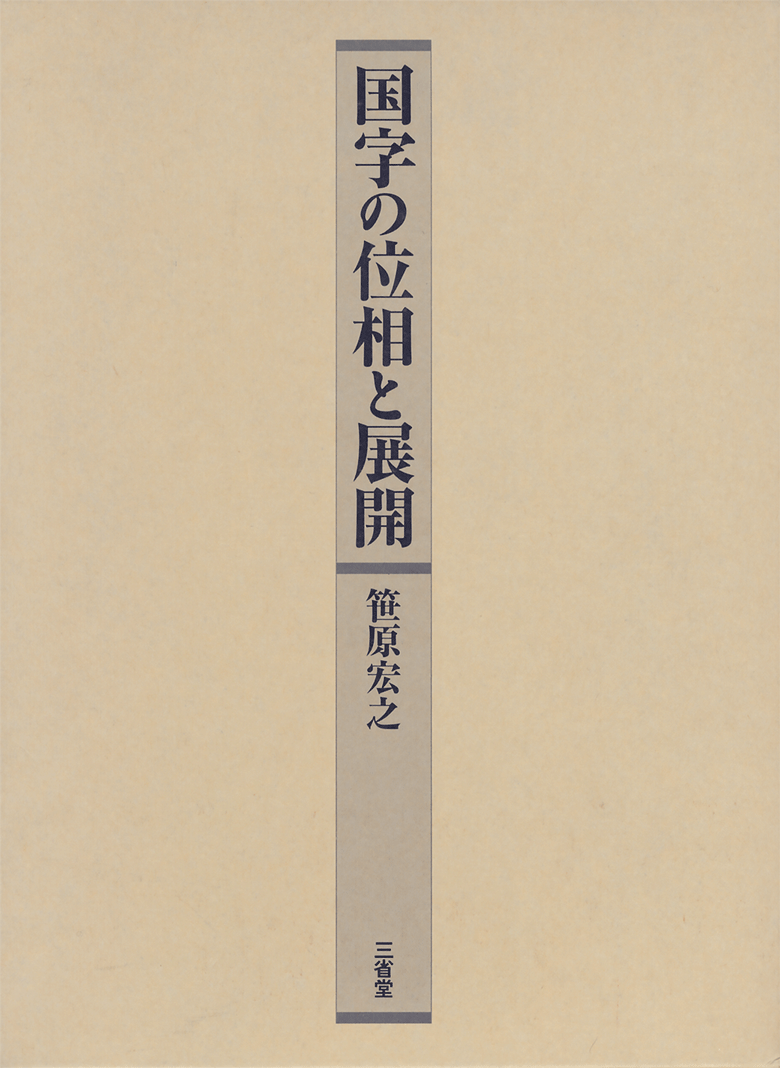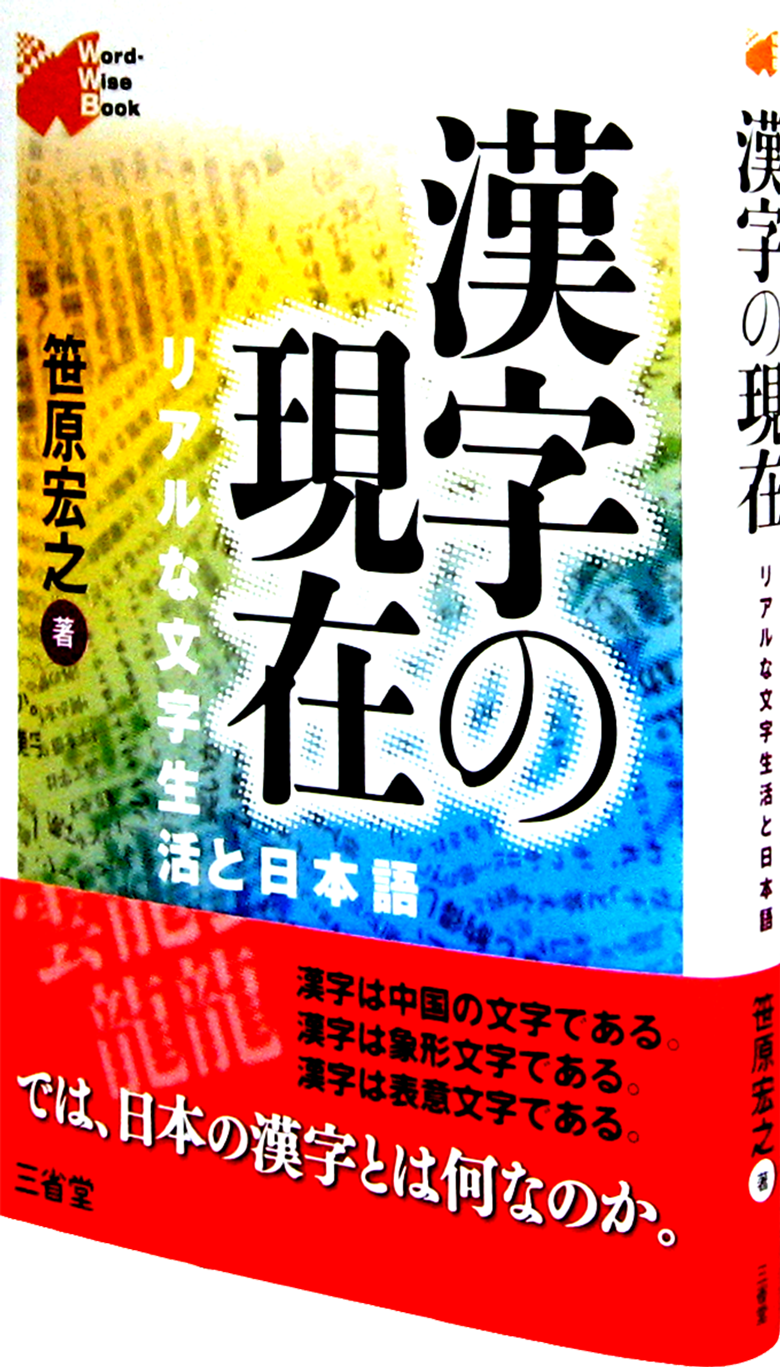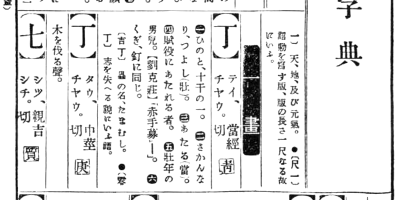この夏は2つの温泉地を訪ねた。そういう地ではたいてい「温泉饅頭」が湯気を立てて売られている。小麦粉などでできた皮の中には、黒くて甘いアンコが入っているのが相場だ。中身が小豆になったのは、禅宗の影響で肉を入れることを避けたためともいわれる。日本では、「饅頭」は「マンジュウ」と読む。かつての国語辞書である『節用集』のテキストの一つにも饅頭屋本がある。この「頭」の字の「ジュウ」は唐宋音といわれ、宋代以降、比較的新しく日本に伝わってきた漢字音である。この食品の伝来が中世期であったことを物語っている。
日本で売られている「中華饅頭」、略して「中華まん」の中身としては、餡つまりアンコのほか、豚肉・野菜が主流といえるだろう。日本で、この「饅」という字で料理の「ぬた」を指すことがあるのは、その中身と関連するものであろうか。

お隣の韓国ではどうだろう。88(パルパル)オリンピック直前にその地を旅した時、激辛の料理の名前しか知らなかったため、友人と食堂で辛味との格闘を毎食続けていた。ソウルから南下して帰国日が迫る釜山(プサン)に至り、何やら辛くなさそうなものを食べている客を見かけ、店の人に尋ねると、それは「マンドゥ グク ペクパン」とのこと。漢字語の部分を漢字で書けば、「饅頭しる(汁)・白飯」だ。韓国で初めて、辛さのない食事をした幸せから、連日そこで朝食をとったものだ。やっと辿り着けたそのスープの中に入った「饅頭」(マンドゥ mandu)には、肉や野菜が包まれており、餃子や中国の包子(パオズ)に似たものであった。
さて、これらの「饅頭」という語は、元をたどると中国に発祥するものである。古く諸葛孔明が川の神に人頭を捧げる蛮族の風習を改めるために創りだした、と信じられてもいる。これは宋代以降の文献に現れる伝承で、人間であるかの如くに作るために、皮の中に牛肉・羊肉を詰めた、とある。「饅」という漢字は、ただその物のためだけに造られた形声文字であり、会意を兼ねたものとも解されている。かつては「蠻(蛮)」「曼」など同音で別の漢字が当てられることもあった。ただし、現代の中国では、普通話(共通語)で「饅頭」(マントウ man2tou)といえば、それは小麦粉だけでできたもののことを指しており、通常、中身は何もなくなっている。
ベトナムには、「マンタウ Màn thầu」という食品がある。「マンダウ mãn đầu」と言うこともあるが、「饅頭」に対する伝統的なベトナム漢字音は「man đầu」である。恐らく、中国南方辺りの方言からベトナム語へ流入した発音なのであろう。その中身は、中国の「マントウ」と同じく何もないもののほか、中国の「包子」の類に似たものがあるが、肉だけでなくキクラゲ、卵、マカロニのようなものなどを入れるそうで、やはり独自性が生じているようだ。
漢字圏に属した四つの国で、現在、「饅頭」の中身がこのように異なっているのは、それぞれの時代の風習や嗜好に合わせて変わった結果なのだろう。韓国のものが古い状態を比較的よく残している、といえるのかもしれない。
そして発音だけでなく、表記までも差が生じている。中国大陸では簡体字で「馒头」、日本や香港、台湾などでは「饅頭」と字体が分かれ、そして韓国ではハングルで「만두」、ベトナムではチュウ・クオックグウ(国語ローマ字)で「man đầu」などと、もっぱら書かれるようになっている。
ここでは日本が古い状態を維持しているようであるが、その日本でも、食偏が「飯」と同様に簡易化されることもある。さらに店によっては「万頭」、さらに「万十」など、日本漢字音に基づく、簡易な当て字が現れている。とりわけ「万十」という表記は、九州一帯において、かなりの広まりを見せている。「所変われば品変わる」というが、この食品の文字もまた、変化を呈している。