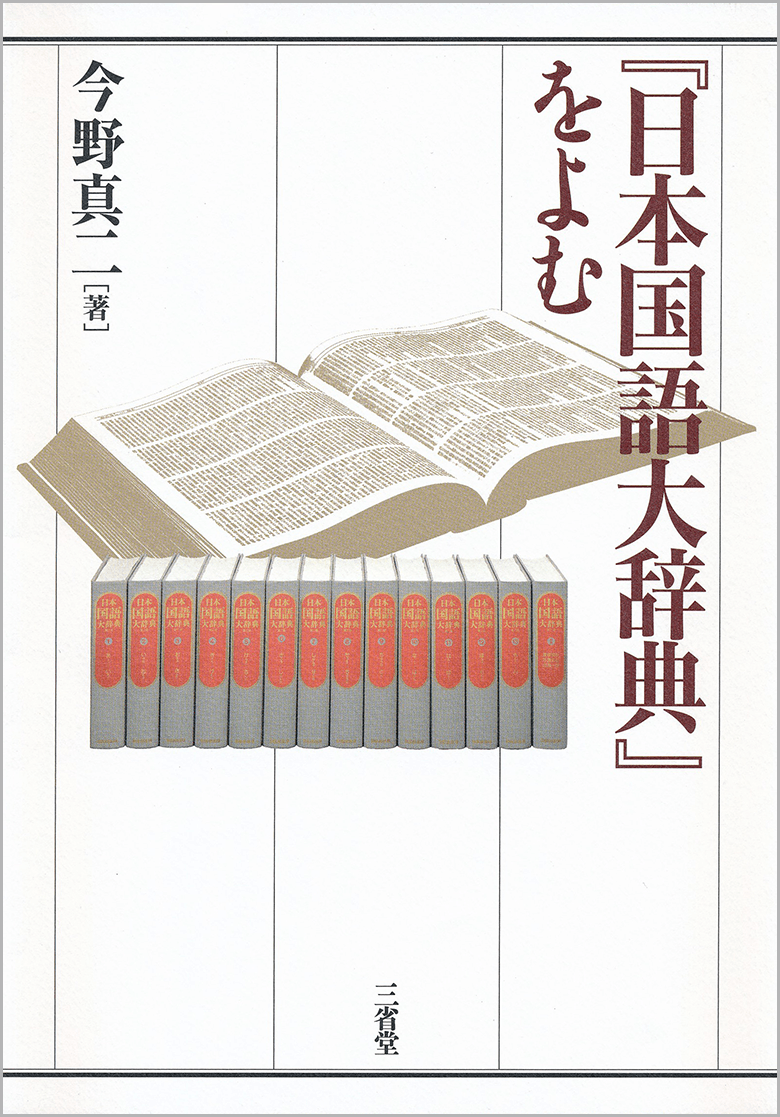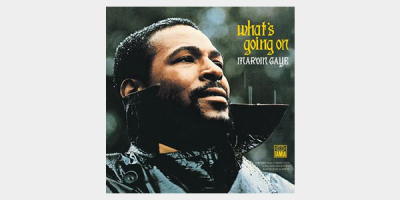『日本国語大辞典』では見出し「かしゅう[何首烏]」と見出し「カシュー(英cashew)」とがこの順で並んでいます。今回はこの二つの見出しを話題にしようと思います。まず、見出し「かしゅう」には次のように記されています。
かしゅう【何首烏】〔名〕(1)植物「つるどくだみ(蔓蕺)」の古名。また、赤褐色の塊状に肥大した根の称。漢方では強壮・強精剤とする。*和漢三才図会〔1712〕九六「何首烏(カシュウ)」*書言字考節用集〔1717〕六「何首烏 カシュウ 本名夜合藤」(2)「かしゅういも(何首烏芋)」に同じ。《季・秋》*和名集并異名製剤記〔1623〕「何首烏 かしゅう 〈略〉日本にも大山のふもとなどにあり、葉はやまのいもの如くにして少し黒みさすなり。根まろくしてひげ多し」*大和本草〔1709〕五「黄独(けいも)〈略〉本草曰。土芋一名黄独。可二蒸食一レ之。今案、是世俗にあやまりて何首烏と云ものなり」*俳諧・滑稽雑談〔1713〕八月「黄独(カシウ)」*物類称呼〔1775〕三「黄独〈略〉東国にてかしゅうと云。薬種の何首烏(かしゅう)にあらず。同名にして異なり」
(2)の使用例としてあげられている『物類称呼(ぶつるいしょうこ)』は俳人であった越谷吾山(こしがやござん)(1717-1787)が著わし、安永4(1775)年に刊行された全国方言集のような書物です。越谷吾山は「薬種の何首烏(かしゅう)」とは別に「かしゅういも」があると述べていますね。インターネットで調べてみると、カシュウイモには大きなムカゴができ、それが「air potato」と呼ばれているようです。
今回話題にしたいのは、(1)の「かしゅう」です。『日本国語大辞典』は「漢方では強壮・強精剤とする」と説明していますね。『大漢和辞典』を調べてみると、「何首烏」を「薬草の名。つるどくだみ。多年生蔓草。根の芋を薬用とする。何首烏といふ人が此の薬を服して百三十歳に至つても頭髪が猶黒かつたので、此の薬草に其の名をつけたといふ。唐の李翺に何首烏伝がある。九真藤」と説明しています。この説明の中にも「つるどくだみ」が出てきます。
インターネットでツルドクダミを調べてみると、すぐに画像が出てきます。植物に関心がある方は、「ああ、あれか見た事がある」と思われるかもしれません。葉がドクダミの葉のようなハート型をしているので、ツルドクダミという名前がつけられたのだと思いますが、ツルドクダミはタデ科で、ドクダミはドクダミ科なので、植物としてはまったく異なるものです。
『日本国語大辞典』が使用例としてあげている『書言字考節用集』を確認してみると、「何首烏(カシュウ)」を見出しにして「本名ハ夜合藤」と記し、ウの部にも関連する見出しがあることを示しています。現在の辞書でいえば参照見出しですね。そのガイドに従って、ウの部を見てみると、見出し「夜合藤(ウバガツヅラ)」に続いて漢字列「何首烏」が見出しとなっており、振仮名の位置に「同」とあるので、これも「ウバガツヅラ」であることになります。つまり「カシュウ」の別名として「ウバガツヅラ」もある、ということですが『日本国語大辞典』はこの「うばがつづら」は見出しにしていません。
さて、『日本国語大辞典』の見出し「いいひついばら」の説明の中にも「つるどくだみ」がでてきます。
いいひついばら〔名〕植物「つるどくだみ(蔓蕺)」の古名。*温故知新書〔1484〕「何首烏(イヰヒツイハラ)」
『温故知新書』は文明16(1484)年に成ったと考えられている辞書です。この頃につくられた辞書は見出しを「いろは」順に並べていますが、この『温故知新書』は見出しを50音順に並べています。この辞書が「何首烏」に「イヰヒツイハラ」という振仮名を施しているのです。「イイヒツ・イイビツ」は〈飯を入れる木製の容器〉つまり「お櫃」ですが、なぜ「カシュウ=ツルドクダミ」が「イイヒツイバラ」と呼ばれていたのかは(現時点では)うまく説明することができません。
さて、稿者はこのコラムの第7回「タヌキとサルトリイバラ」でサルトリイバラの別名をあげました。その中に「イビツイバラ」という別名が含まれています。インターネットで調べてみると、サルトリイバラは和歌山県では「イビツ~」という語形で呼ばれているようです。この「イビツ」は〈歪んでいる〉という語義の「イビツ」ではなくて、「イイビツ」が変化したものではないか、と思いました。サルトリイバラの葉で餅などを包む地域もあるようなので、そうしたことと「イイヒツ」がかかわりがあるのかもしれないと思ったりもします。インターネットの画像や説明をみるかぎり、ツルドクダミにはサルトリイバラにあるようなトゲはないようです。そして、サルトリイバラとツルドクダミの葉の形状はかなり似ています。
さてここまで述べてきたことを整理してみましょう。サルトリイバラの別名「イビツイバラ」が「イイヒツイバラ・イイビツイバラ」の変化したものであるとすると、「イイヒツイバラ・イイビツイバラ」と「ツルドクダミ」は別の植物の名前であったが、葉の形状が似ているところから、呼び名として、混同されることがあったのではないか、ということです。これが『日本国語大辞典』の「いいひついばら」の項目をみて、考えたことです。
さて、もう一つの見出し「カシュー」です。『日本国語大辞典』には次のようにあります。
カシュー〔名〕({英}cashew )ウルシ科の常緑小高木。熱帯アメリカ原産。高さ一〇~一五メートル。葉は革質で長卵形。小形の花は白色または淡桃色で、枝の先端に円錐花序をつくる。果実は食用、樹脂は塗料、幹は用材とされる。(以下略)
植物の種子の中身を仁(にん)と呼ぶそうですが、カシューナッツはカシューの仁にあたります。これもインターネットで調べるとすぐに画像がでてきますが、果実全体はちょっと驚くような形状なので、是非御覧になってください。カシューはウルシ科の植物で、「樹脂は塗料」と記されています。骨董などが破損してしまった時に「金継ぎ」をすることがあります。漆を使って継ぎ合わせた上から、金粉をおいて装飾的になおすのですが、漆のかわりにカシューを使うと比較的簡単に「金継ぎ」風になおすことができます(ただし、平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、現在では、カシュー塗料は直接口に触れるものへの塗装には使用できなくなっています)。このカシューがカシューナッツのとれる樹木の樹脂だったのですね。たまたま見ていたテレビで綾瀬はるかさんが金継ぎは上手にできそうだから、今後もっとやっていきたいと話しているのをみました。綾瀬はるかさんは、筆者のような「なんちゃって金継ぎ」ではなく、本格的な金継ぎをされたのでしょうね。
漢方薬として使ったり、お餅を包んだり、実を食べたり、接着剤として使ったり、植物はずっと身のまわりで生活と密着していたから、いろいろな呼び名があるのでしょうね。