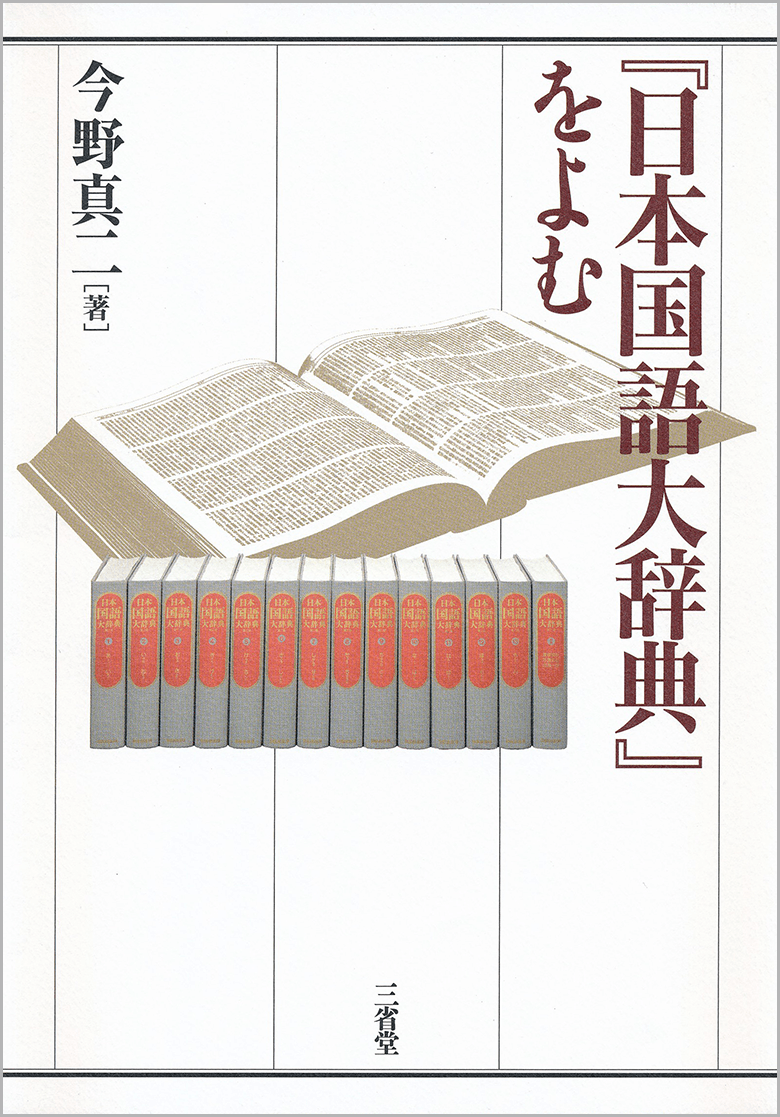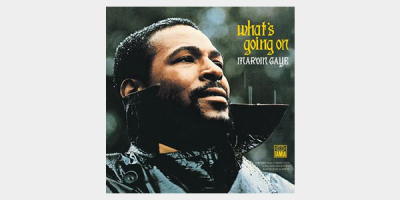タイトルの「胃」「胆」はいずれも「常用漢字表」に載せられていて、「胃」には音「イ」が認められ、「胆」には音「タン」が認められています。「常用漢字表」はどちらにも訓を認めていません。『日本国語大辞典』の見出しは「い[胃]」「い[胆]」の順で隣り合わせに並んでいます。
「常用漢字表」は「胆」に訓を認めていないのですが、古くは「い」が「胆」の和訓だったと思われます。『日本国語大辞典』の見出し「い[胆]」には次のように記されています。
い【胆】〔名〕胆嚢(たんのう)。きも。*霊異記〔810~824〕上・一「小子部栖軽は、泊瀬の浅倉の宮に二十三年天の下治めたまひし雄略天皇〈大泊瀬稚武の天皇と謂す〉の随身、肺脯(しふ)の侍者なり〈興福寺本訓釈 肺脯 上音之反訓支毛 下普音反訓伊〉」*大智度論天安二年点〔858〕六〇「諸天子其れが胆(イ)の力を益す」*十巻本和名類聚抄〔934頃〕二「膽 中黄子云膽〈都敢反以〉為中精之府」*日葡辞書〔1603~04〕「I (イ)〈訳〉胆嚢。しかし、複合してでなくては用いられない。例、クマノi (イ)」
『日本国語大辞典』があげている『日本霊異記』(興福寺本)の使用例をみると、「肺脯」の「肺」の訓が「支毛(キモ)」で、「脯」の訓が「伊(イ)」であるという「訓釈」が附されていることがわかります。また、『和名類聚抄』では見出し「膽」(=胆)に「以(イ)」という和名が配されていることがわかります。ちなみにいえば、「膽」のつくりは「セン・タン」という音をもっていて、「擔」も現在は「担」という字体を使っていますね。
さて、『日本書紀』の景行天皇の40年7月以降は、東夷の反乱を平定するために、日本武尊が「東征」に向かう記事が記されていますが、「近江胆吹山」に「荒神(あらぶるかみ)」がいると聞いて草薙剣を置いて近江に向かいます。その後、伊勢にもどった日本武尊は天皇に東征の報告をした後、崩ずることになります。この「近江胆吹山」は現在滋賀県と岐阜県にまたがっている伊吹山のことと思われます。固有名詞なので、伊吹山(イブキヤマ)の「イブキ」がどのような語に基づいているかはわかりませんが、冬に北西の方角から吹く「伊吹おろし」でも知られ、薬草の宝庫でもあります。「イブキ」を〈呼吸・風・生気〉という語義をもつ「イブキ(息吹)」と結びつけることもあります。現在は「伊吹山」と文字化しますが、これは漢字「伊」の音「イ」を使った、「音仮名」による表音表記です。「胆吹山」は「イ」に漢字「胆」の和訓「イ」を使った、「訓仮名」による表音表記ということになります。
古くは〈胆嚢・きも〉という語義の1音節の和語「イ」があったのですね。『日本国語大辞典』の見出し「くまのい」には次のように記されています。
くま‐の‐い 【熊胆】〔名〕(1)胆汁(たんじゅう)を含んだまま、熊の胆嚢を干したもの。ひじょうに苦く、主に胃腸薬として用いられる。ゆうたん。*本草色葉抄〔1284〕「熊膽(クマノイ)」*壒囊鈔〔1445~46〕七「熊のゐ、榎子(ゑのみ)三程を水に能々をろして、夏子のひひるのこ三銭、是二つを合入て」*浄瑠璃・曾我扇八景〔1711頃〕三部経「さすがの熊も大力の時宗にしめつけられ〈略〉跡を見かへる熊のゐの、にがいかほしてうせにけり」*読本・椿説弓張月〔1807~11〕拾遺・五〇回「熊胆(クマノヰ)はとり易からず。故にその価最(いと)貴し。これを腹せば心を清し、肝を平にし、目を明にして翳(かすみ)を去、蛕蟯虫(はらのなかのむし)を殺す」*日本読本〔1887〕〈新保磐次〉二「熊のゐは苦く、わかきほほづきも亦苦し」(以下略)
「クマノイ」は「熊の胃」だと思っていた方がいらっしゃるのではないでしょうか。そうではなくて「熊の胆」だったのですね。そして「イ(胃)」は1字の漢語、「イ(胆)」は1音節の和語で、語義も同じではないにしても、まぎらわしいといえばまぎらわしいですね。 実は「胃」の(日本語としての)発音は[wi]、「胆」の発音は[i]なので、仮名で書くなら、前者「胃」は「ゐ/ヰ」、後者「胆」は「い/イ」で「古典かなづかい」(=歴史的かなづかい)では異なります。しかし、[wi]と[i]とは発音がちかかったために、12世紀の末頃までに[i]に統合されていったと推測されています。統合されるまでは、発音が[wi][i]と異なっていたわけですが、統合後は発音に区別がなくなってしまいました。発音に区別がなくなると、仮名でどう書くのかということ=かなづかいもわからなくなってきますし、ついには「胃」と「胆」とのことばの上での区別も曖昧になっていきます。易林本『節用集』には「熊胃(右振仮名クマノヰ)」という見出しがみられます。易林本『節用集』が編まれた、室町末期頃には漢語の「ヰ(胃)」と和語の「イ(胆)」との区別がはっきりしなくなっていることが窺われますね。