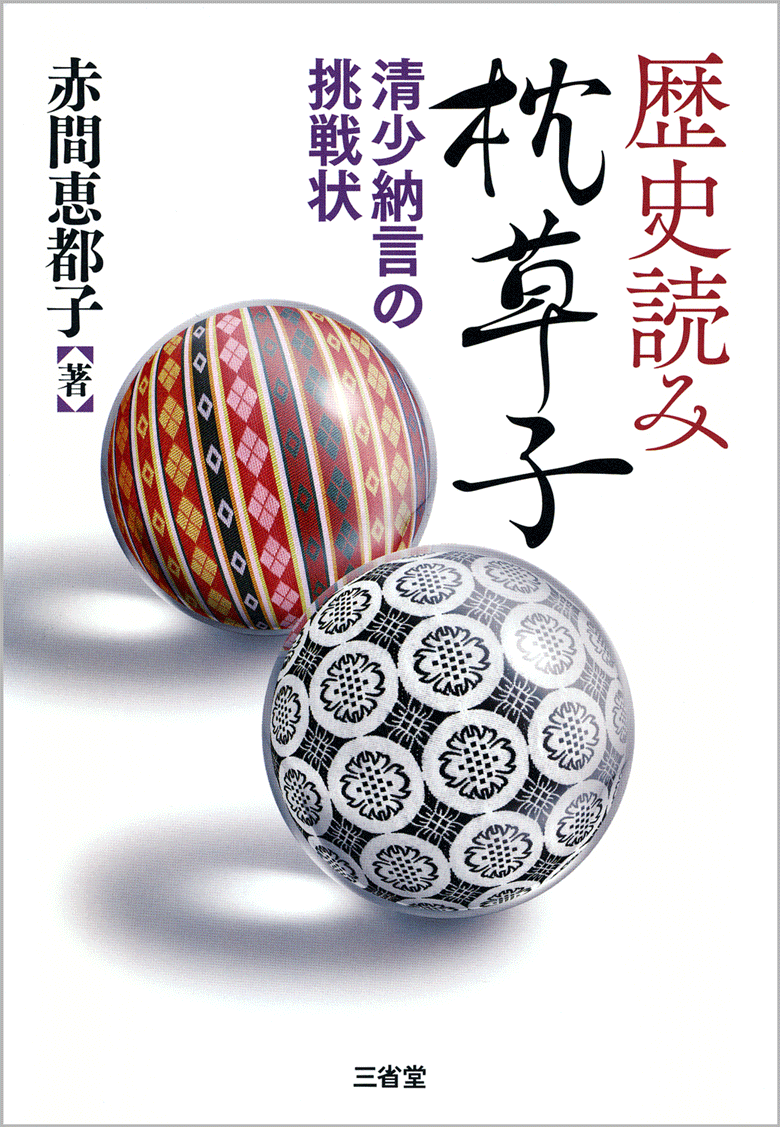長徳元年夏以降の『枕草子』の章段には、華やかな衣装を纏(まと)ってこれまで登場していた中関白家一族の姿がすっかり消えてしまいました。その代わりに登場してくる人物が藤原斉信です。斉信は道隆の従弟にあたります。かつて斉信の妹は花山帝女御でした。しかし、妹妃が亡くなり花山帝が退位して、外戚として出世する道が途絶えて後は権力者に追従し、道長の配下になっていきます。出世欲が強く、昇進争いに勝って人の恨みをかった逸話が多く残っている人物です。
そんな斉信が、『枕草子』には、中関白家以外の男性貴族の中で最もたくさん登場しているのです。それはなぜなのでしょうか。斉信は正暦五年に蔵人頭になりました。蔵人は天皇の側近として働く役職です。当然、中宮方に出向く機会も多くなります。そのような必然的な理由の他に、喪中ですっかり色を失った定子周辺に彼を登場させることによって、作品内に華やかさを取り込むためだったとも考えられます。
斉信の姉妹にあたる為光の娘たちは、花山天皇の后になって寵愛を受け、御子を宿したまま亡くなった同母妹の忯子(よしこ)の他、三女、四女とも美女だったということですから、斉信も容姿は悪くなかったでしょう。『枕草子』に華麗に登場する斉信は朗詠も得意で、清少納言をはじめ後宮女房たちはこぞって彼を称讃しています。それは、正暦期に登場していた伊周の描写とそっくりです。
定子後宮が服喪期間に入って描くべき対象がなくなったとき、その人物の実体はともかく、外見的に華やかな斉信を描くことが、作者が選んだ『枕草子』執筆継続の応急措置だったのではないでしょうか。加えて、世の趨勢(すうせい)に敏感な斉信が出入りする後宮をアピールしようという意図もあったかもしれません。
斉信が『枕草子』に初めて登場するのは長徳元年二月末、あらぬ噂を真に受けて清少納言を誤解し、一方的に絶交している状況で始まる章段です。清少納言の方では彼女らしく、言い訳などしないで無視していたのですが、そんな状況に耐えられなくなった斉信からある日、文が届けられます。自分のことを嫌っているはずなのに、いったい何が書かれているのか。どきどきしながら文を開けた清少納言の目に入ったのは次の白楽天の漢詩の一句でした。
「蘭省ノ花ノ時、錦帳ノ下(あなたは宮殿で、花の季節、皇帝の錦帳の下に伺候し栄えている)」
定子に見せようと思っても、ちょうど天皇がいらっしゃって就寝中です。使者は返事を急(せ)かします。さあ、困った、ここからが清少納言の才知の見せ所です。斉信から問われた漢詩の続きは、以下の句になります。
「廬山ノ雨ノ夜、草庵ノ中(私は廬山で、雨の夜、草庵の中に一人わびしく暮らしている)」
もちろん即答できますが、女だてらに漢字を書くのは体裁がよくありません。そこで、漢詩の意味を和歌に置き替え、当代きっての教養人藤原公任が使った連歌の下句「草の庵(いほり)を誰かたづねむ」を拝借しました。用紙は届けられた紙の余白を使い、筆の替わりに消え炭を用いて筆跡をごまかします。清少納言の返事は相手に評価の糸口を与えないばかりか、反対に連歌の上句を要求するものになっているのです。
清少納言の返事を見た斉信は「おお」と思わず声をあげ、「いみじき盗人を。なほえこそ思ひ捨つまじけれ。(とんでもない泥棒だよ。やっぱり無視できそうもないな)」と言って、それまでの清少納言に対する考えを改めました。それが殿上で評判となり、清少納言に「草の庵」というあだ名が付けられたという逸話です。
この章段以降の約一年間、斉信と清少納言の交流が『枕草子』に描かれていくのですが、二人の駆け引きは、背後に流れる歴史的事件を考えて見ていくと微妙なニュアンスが読みとれるように思われます。