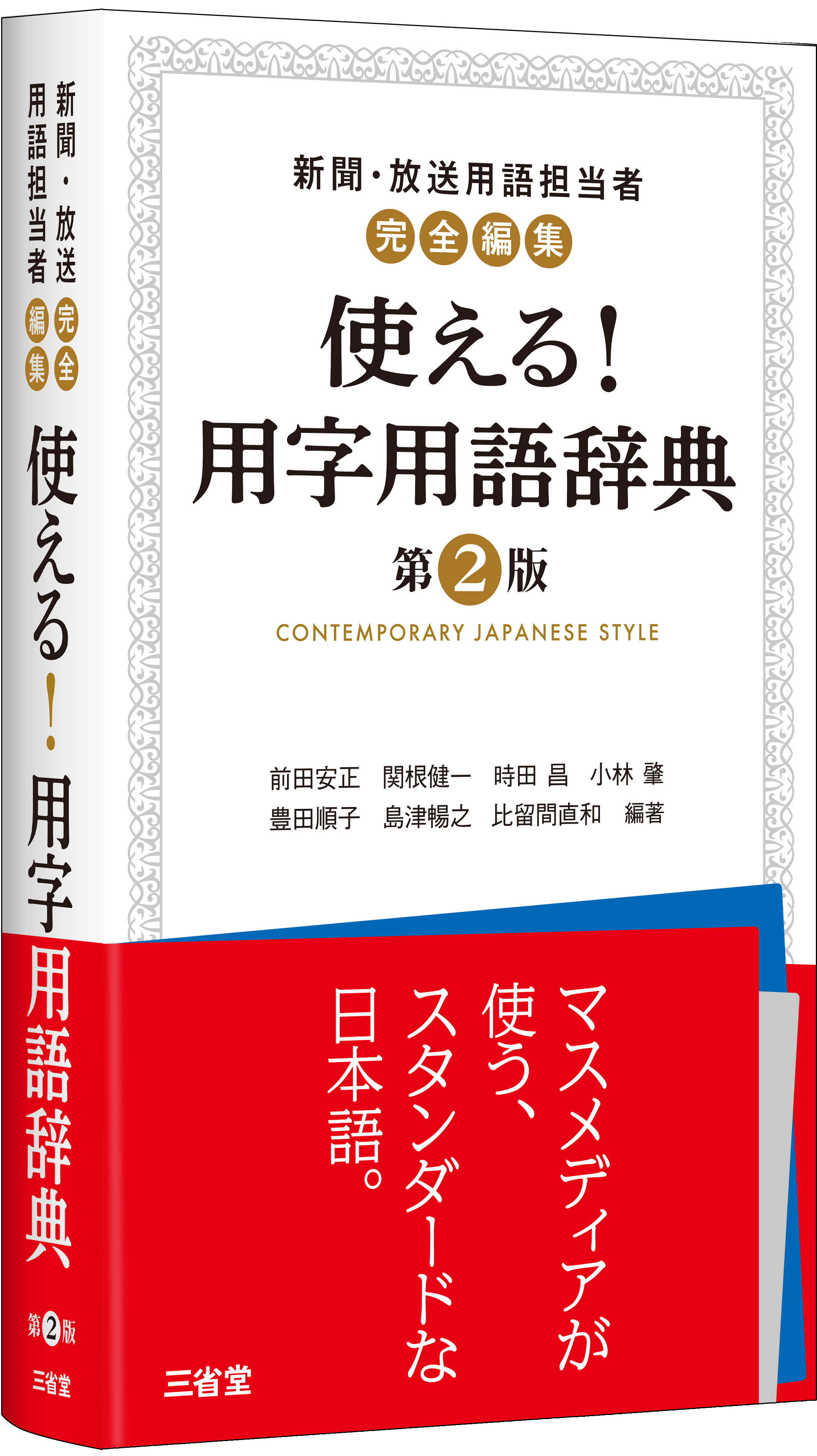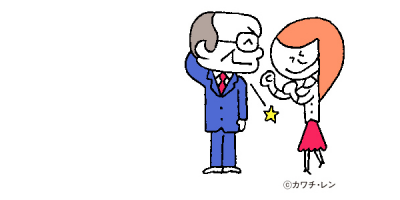「洞窟をタンケンする」「海洋タンケン家」というときのタンケンを漢字でどう書きますか? 国語辞典を引くと、【探検/探険】の二つの表記が載っているはずです。explorationの訳として、明治20年頃から新聞記事で使われ始めた和製漢語です。「探険」は中国語に古くからある語を借りたようです。「探検」のほか、当時はケンが木偏やこざと偏以外に手偏のもの、また「探見」の表記もありました。やがて、「探検」「探険」が多くなりますが、どちらかに集約されることはありませんでした。『宝島探険物語』(昭和2年 金の星社)、『宝島探検物語』(昭和5年 アルス)はどちらも同じスティーブンソンの小説の翻訳のタイトルです(原文は旧字体)。
「検」は「調べる・取り締まる」、「険」は「けわしい・危ない」の意です。調べて探し求めるなら「探検」、危険を冒して探すなら「探険」と、書き分けるやり方もあるでしょう。とはいえ、調査も危険も「探ケン」にはつきもの。表記によって指し示す内容が大きく異なるわけではありません。そこで、国語辞典でも、一つの見出し語でまとめ、併記しているわけです。
「探検」と「探険」は、意味の違いに注目するなら同音異義語といえるかもしれません。しかし、その違いが極めて僅かで、内容はほとんど変わらないとすれば、表記は異なっても同じ語であると考えて差し支えないでしょう。多くの人は、タンケンという音とともに、熟語全体で意味を理解しており、構成している漢字一字ずつに分析して、それを再構成したイメージでとらえたりはしません。新聞では、こうした表記が異なるだけで意味や使い方は同じという語については整理・統一し、標準表記を決めています。
▶書名に「探検」を含む例
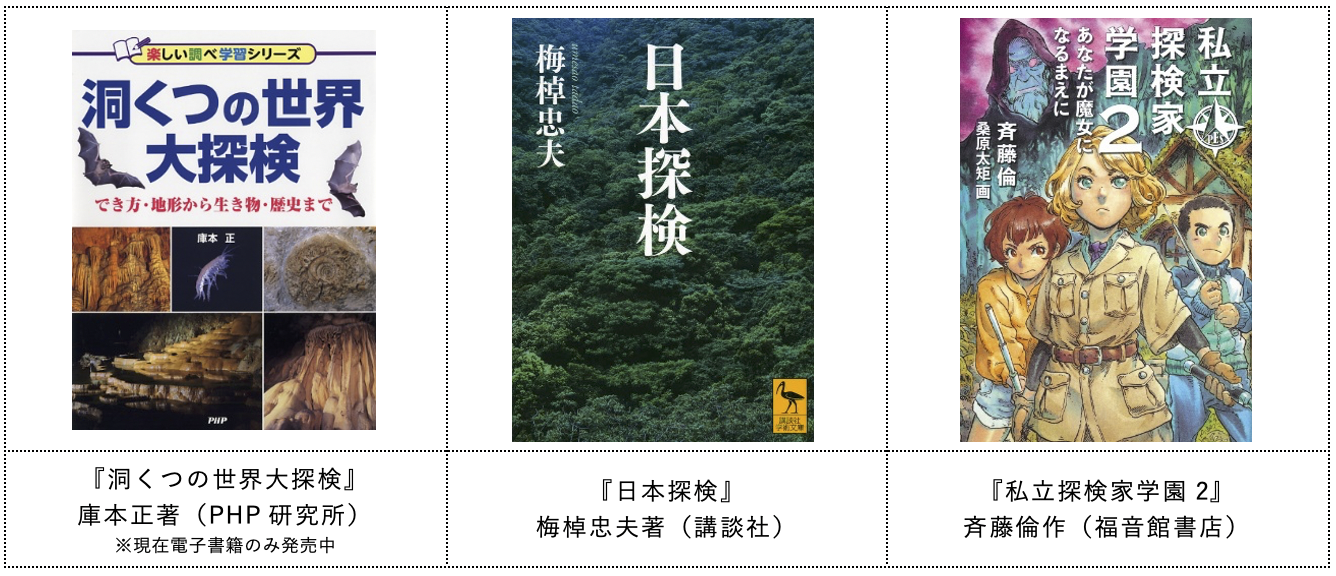
▶書名に「探険」を含む例
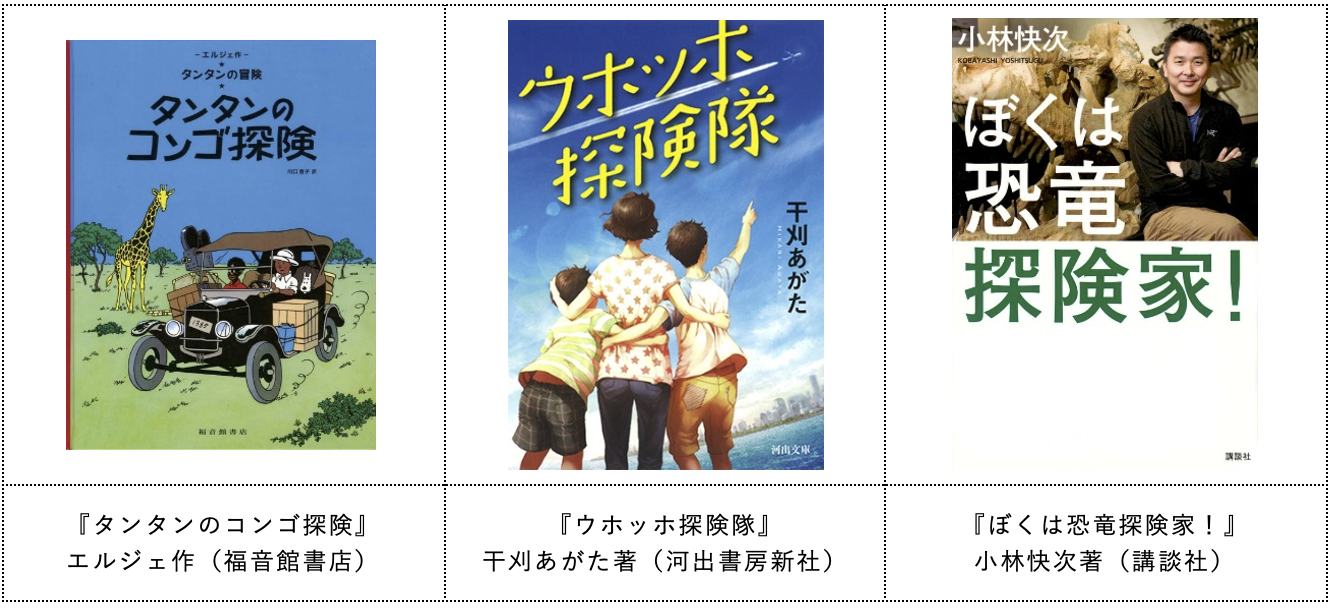
どちらだっていいじゃないかと思うかもしれません。漢字を採り入れた日本語表記の宿命ともいえます。複数の書き方の存在は、日本語の豊かさ、融通性を表しているという見方もあるでしょう。書き分けることで繊細なニュアンスを表現することもできます。そのためもあってか、多くの国語辞典では一つに絞って標準表記を提示することにためらいがあるようです。
一方、必要な情報を簡潔にすばやく伝えることを目的とする報道の文章では、書き手の恣意的な主観が入りやすい微細な書き分けは、文章を理解するうえでのノイズになりかねません。同じ記事、同じ紙面で、二様の表記が混在していたら、それが気になって記事の中身が頭に入ってこないおそれもあります。標準表記の統一は、文章の「分かりやすさ」を担保する大事な要素の一つと言えるのです。
統一するにあたっては、語源や個々の漢字の意味、過去から現在に至る使用頻度の変化など(それらは国語辞典の見出しの並び順にも反映しているはずですが)はもちろんですが、どのような表記を用いるのが読み手に分かりやすく伝わるかという観点を重視しています。伝統性(本来はこう書いていたから)、広範性(現在は広く用いられているから)だけにこだわらず、新聞の見出しなどで使っても一目で頭に入ってくるような、伝わりやすい表記はどうあるべきかということに留意し、総合的に判断しています。
国語辞典では別語として見出しを別にしていたり、同一見出しでも意味の違いを説明したりしているものについても統一している場合があります。そういった区別が文章全体を理解するうえで役に立つかどうかという観点から、標準表記を決めているのです。
暑さ寒さの変化が少ないのをいう「温和」は、性質については「穏和」も使われます。といっても、気温と人柄で書き分ける利点はどのくらいあるでしょうか。
性格が柔らかなのは「柔順」、逆らわずに従うのは「従順」で、歴史的仮名遣い(字音仮名遣い)も「ジウ―」「ジユウ―」と異なり、明らかに別の言葉ですが、現在では同じ発音になり、素直な態度を表すという点でも同じように使われています。
カルメンがホセに投げるバラのイメージは【真紅/深紅】? 悪事を企てる中心人物は【首謀/主謀】? 肝が据わって何事にも動じない様子は【豪胆/剛胆】?——漢字の違いが醸し出すニュアンスが、語全体が伝える内容にまで及んでいるかどうか。そこが書き分けるか統一するかの判断の分かれ目です。
【気運】時勢のなりゆき。また、その中で高まろうとする一定方向への動き(広辞苑)と【機運】時のまわりあわせ。おり。時機(同)は、国語辞典の語釈の書きぶりがかなり違います。それぞれ、「気」(なんとなく感じる動き)「機」(兆しやきっかけ)という漢字の意味を踏まえているのでしょう。
「気運」はある方向への動きに、「機運」はその時点に注目していると解釈すれば、「気運」は「高まる」、「機運」は「熟する」と使い分けるのが“正しい”のかもしれません。けれど、語全体でとらえたとき、どちらも「ちょうどいい段階に入りつつある」という状況は変わらない気がします。
「改革のキウンを逃すべきでない」「首脳会談実現のキウン」といったときに、「気」と「機」の意味に遡って書き分けるのはかなり難しいのではないでしょうか。仮に書き分けるとしたら、読み手にもその微妙な意味の違いを踏まえて理解することを要求することになります。
『使える!用字用語辞典』では、統一している標準表記をはっきり示しています。もちろん、あくまでマスメディアでの決め事であり、それに従わなくても誤りではありません。別の表記は参考情報として[ ]内に掲出しています。そちらの方が自分の感覚に合うと感じたら使っても問題ありません。ただ、不特定多数の読み手を想定して、情報を分かりやすく発信する目的で書く場合は、標準表記ということを意識すべきでしょう。
さて、では、ここまで紹介してきた語の標準表記はどちらか?——知りたくなってきたのではないでしょうか。ぜひ、新版の『使える!用字用語辞典』で引いて、確認してみてください。