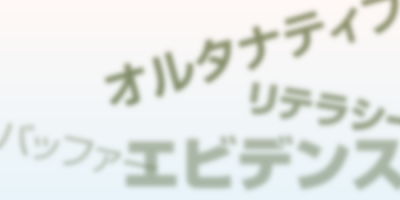さて、真理に迫る方法について考えるに当たって、西先生が、ジョン・スチュアート・ミルの『論理学体系』を引き合いに出したところでした。
先を読み進める前に少し補助線を引いてみます。西先生は、その著作や翻訳書の中で、しばしば論理学に言及しています。関係の大きなところで言えば、明治7年に刊行した『致知啓蒙』があります。当世風に言えば『論理学入門』となるでしょうか。
同書は、論理学の語義と歴史を概観してから、その内実についての詳しい解説が展開されるという構成をとっています。その巻頭で、西先生はこう述べています。
學テフ語ヲ、言ヲ異テ説ナバ、大學ニ知ヲ致ストナム云ヘル、是ゾイト能適ヘル。
訳せばこうなりましょうか。
「学」という言葉を、言い換えるなら、『大学』に「知を致す」という表現がある。これは誠に適切なことである。
西先生が、logicを「致知」と訳したことは、前回見た通りですが、その訳語の出典が『大学』であることがここから分かります。『大学』の冒頭は、学問の仕上げとして学ぶべきは徳であることが主張された後、徳を身につけるために必要な事柄、その根本が次々と辿られるという面白い流れになっていました。
今、その要点だけを抽出すれば、徳⇒国⇒家⇒自分⇒心⇒誠意⇒致知⇒格物という順序です(『大学』では、この順序が示された後に、今度は「格物」から「国」や「天下」へと戻ってゆきます)。
ここで特に注目したいのは、最後の二つです。「知を致すは物に格るに在り」、つまり、知に致ろうと思えば、その前に事物に格(いた)る必要があるという次第。 このくだりは、ここまでの西先生の講義に即して言えば、言葉で学をなすといえども、言葉だけに惑溺してはならず、必ず実証、実験が必要であるという議論にも重ねて読める箇所です。といっても、『大学』自体に、西洋学術の経験主義がそのまま重ねられるということではなく、西洋学術を見知った目で読めば、そうした重ね読みをしたくなるというほどの意味であります。
話を戻せば、西先生が「学」を「致知」と言い換えていることに注目しておきたいと思うのです。「知を致す」ことが「学」である。その「致知」を logic の訳語に選んだということから、西先生が「学」と「致知学(論理学)」の間に非常に強い関係を見ていたことが窺えます。
その一例として、先ほどの『致知啓蒙』冒頭の続きを見ておきましょう。こう続きます。
此書ハ、欧羅巴ノロジカ〔拉 logica、佛 logique、英 logic、日 logik、蘭 redeneerkunde〕テフ學ヲ、論ツラヒテ、吾人ノ致知ノ法ヲ、示サムトテ、マヅロジカテフヲ、支那ノ語に翻シテ、致知学ト名ケツ。(略)サテ致知學テフハ、此日本ノ國ニモ、支那ニモ、昔ヨリ、サル學ビノナキモノカラ、人イト嘲ミ思フベケレド、學ビノ道ニ、心ヲ寄ナム者ハ、何ノ學ビニモアレ、得モ缺マジキ、手解キノ學ニテ、中ニモ、形而上ノ論ラヒニツキテ、此學ビノナカリセバ、數ノ學ビナクシテ、格物ノ學ヲ、事トスルガ如クナルベシ。
ご覧のように、ヨーロッパ諸語に見えるlogica(ラテン語)を、中国語を使って「致知学」と名付けたという旨が述べられています。略した箇所では、『大学』で言う「致知」には、論理学のような「致知ノ術」はないという比較がなされています。
そして、上記のように、従来、日本にも中国にも論理学というものはなかったため、余人はこれを「嘲(あさ)ミ思フ」、つまり、軽んじたけれども、学に従事しようという程の者であれば、不可欠の学問であると、その重要性を主張しているのです(論理学が当時どのように軽んじられたのかは興味のあるところです)。論理学を学ばずに形而上に関わる議論をするのは、あたかも数学を知らずに物理学をやるようなものだというわけです。
これに続いて、西先生は、論理学が古代ギリシアのアリストテレスが論理学の父であるという淵源から始めて、古典ギリシア語におけるロゴスの意味を説き、ハミルトンがこれを「思慮の法の学」と定義したことなどに触れます。このように従来の論理学を巡る文脈を確認した上で、ジョン・スチュアート・ミルこそが、『論理学体系』においてこの学問の面目を新たにしたと位置づけています。
その要点は、「新タニアル理リヲ、發明スルコトニ、用ヒタリ。是ゾ、近頃ノ致知學ノ新シキ發明ナル」、つまりミルは論理学を、新しい理を発見することに使った点で注目に値すると言われているのでした。
では一体、ミルの論理学の新しさ、「新しい理の発見」とは、どのように成されるものなのでしょうか。それこそが問題なのでした。