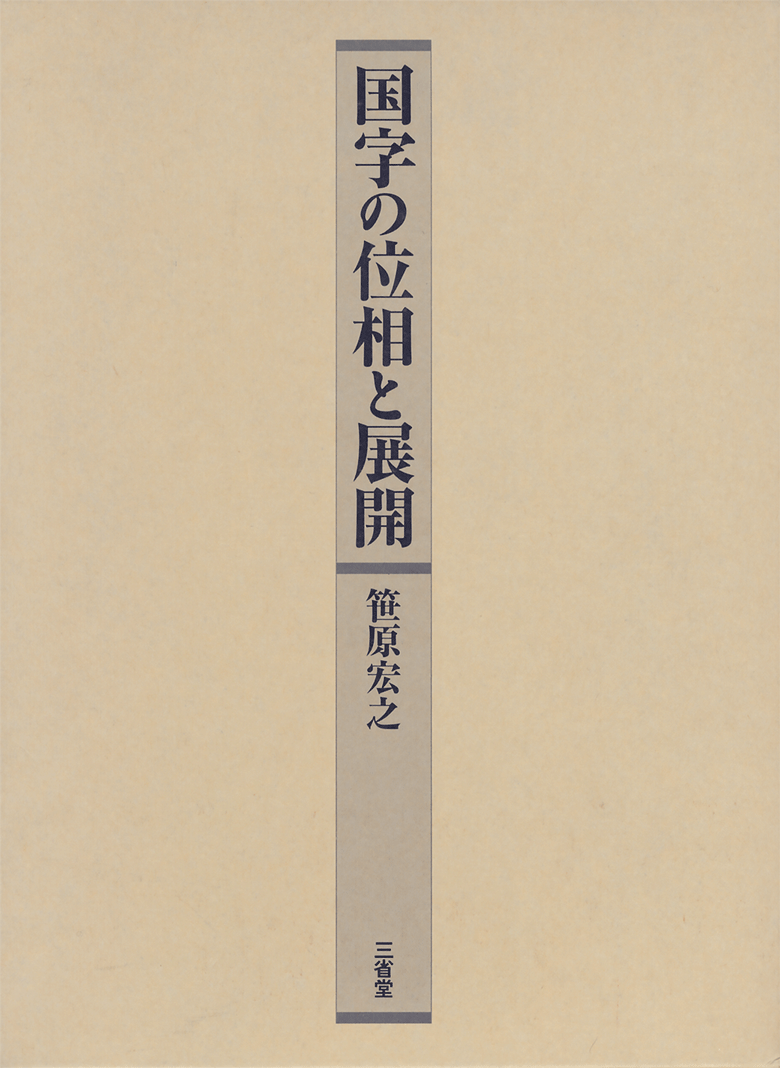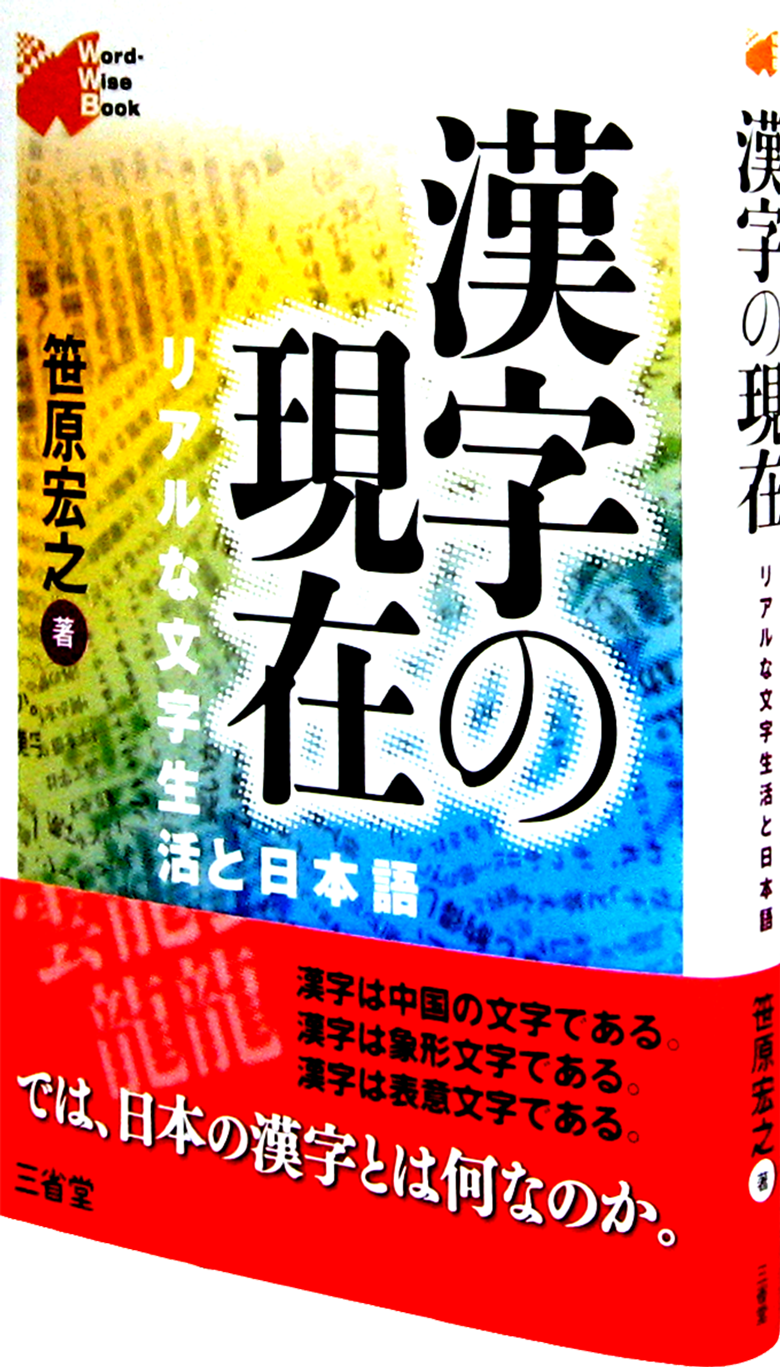韓国のある学会に呼ばれ、発表する機会をいただいた際に、別室で発表者たち一人一人に、お礼にと手渡されたそれは、ウォン(원)札の束であった。その金額の響きと封筒の厚みが心に残ったが、ざっと換算してみると、旅費・宿泊費込みで一般的な額であった。日本での、こっそりと用紙に何やら記入してもらって、後日、振り込みをするといった方法とは対極にある。韓国ではいろいろな場面で、直接的あるいは明確な形で人を喜ばせようとするサービス精神に富む文化というものに触れられる。

【写真1 那覇市内にて】
ウォンは、通貨危機を何とか脱したようだ。北朝鮮も、同じウォンという名称の貨幣単位を使っているそうだが、そちらはどうなのだろうか。ともに漢字で表記していた時代には、「圓」という漢字で表記されており、その漢字の発音がウォンなのであった。以前には「圜」(ホァン 환 Hwan)を用いた時期もあった。これも円いという意味ももつ漢字であり、その場合には「圓」と同音の字であった。「ウォン」という語も、朝鮮半島ではハングル表記に変わったため、原則としてその簡易な表音文字でしか記されなくなっている。韓国でも「円」という字体が使われたことはあったが、それは日本からの影響によるものであった。
「圓」には、中国では古くから「 」という「口」の部分を「厶」とする程度の略字ならば生み出され、しばしば使われてきた。日本では、平安時代から僧侶の間で、より大胆な略字が生み出され、使用され始めた。「囗」の中の「員」をただの「|」に変えた「
」という「口」の部分を「厶」とする程度の略字ならば生み出され、しばしば使われてきた。日本では、平安時代から僧侶の間で、より大胆な略字が生み出され、使用され始めた。「囗」の中の「員」をただの「|」に変えた「 」である。これは、筆記経済を求めての結果であるが、古くは、かの空海の筆跡から見られる。
」である。これは、筆記経済を求めての結果であるが、古くは、かの空海の筆跡から見られる。
概して日本人は、漢字には深い意味が込められており、それは字の形に現れている、つまり文字面から見出せるものだという認識が強くある。そうして漢字にイメージを付与する傾向は、中国よりも強固となっている。昨今でも「人という字は」、「食という字は」、「優しいという字は」などといった話は、挙例に事欠かないほど出回っていて、それがまた妙な説得力を伴って人々の間に受け入れられている。それは、中国で行われた拆字(たくじ)のたぐいも及ばないほど、日常化してしまっている。
ただし、僧侶たちは、「菩薩」を草冠以外の部分を省いて「ササ」のように略記する。こうした方法は唐朝に発達した速記法であるが、それが日本に伝来し、さらに中世期以降、独自の応用を続けたのである。これを抄物書きと呼ぶことがあるが、僧侶たちは、必要な情報を合理的に記録しようとする精神を持ち合わせていたといえる(その一方で、梵字を神秘視するような方向に進む者もあった)。カタカナの成立と展開もまた、そうした動向と関連づけられよう。空海は遣唐使船に乗って、唐に渡っているが、彼の地で数々の略字を目にして、その意識と方法を身に付け、さらに独特の略字を編み出したのであろうか。
その「 」という字体は、次第に一般に広まっていく。僧侶の間の位相文字としての性質が使用層が拡大することで薄まっていくのだ。『万葉集』の元暦校本巻6や『雲州往来』という手紙文例集など、中古、中世と時を経るごとに次第に「
」という字体は、次第に一般に広まっていく。僧侶の間の位相文字としての性質が使用層が拡大することで薄まっていくのだ。『万葉集』の元暦校本巻6や『雲州往来』という手紙文例集など、中古、中世と時を経るごとに次第に「 」と下部が徐々にせり上がってくる。この中の「|」は書いてみると分かるのだが、長すぎる。そしてその線は短いほど字を速く書き上げられる。時代とともに筆記に経済化が進展していくのは、漢字体系内で共通する大きな傾向であった。
」と下部が徐々にせり上がってくる。この中の「|」は書いてみると分かるのだが、長すぎる。そしてその線は短いほど字を速く書き上げられる。時代とともに筆記に経済化が進展していくのは、漢字体系内で共通する大きな傾向であった。