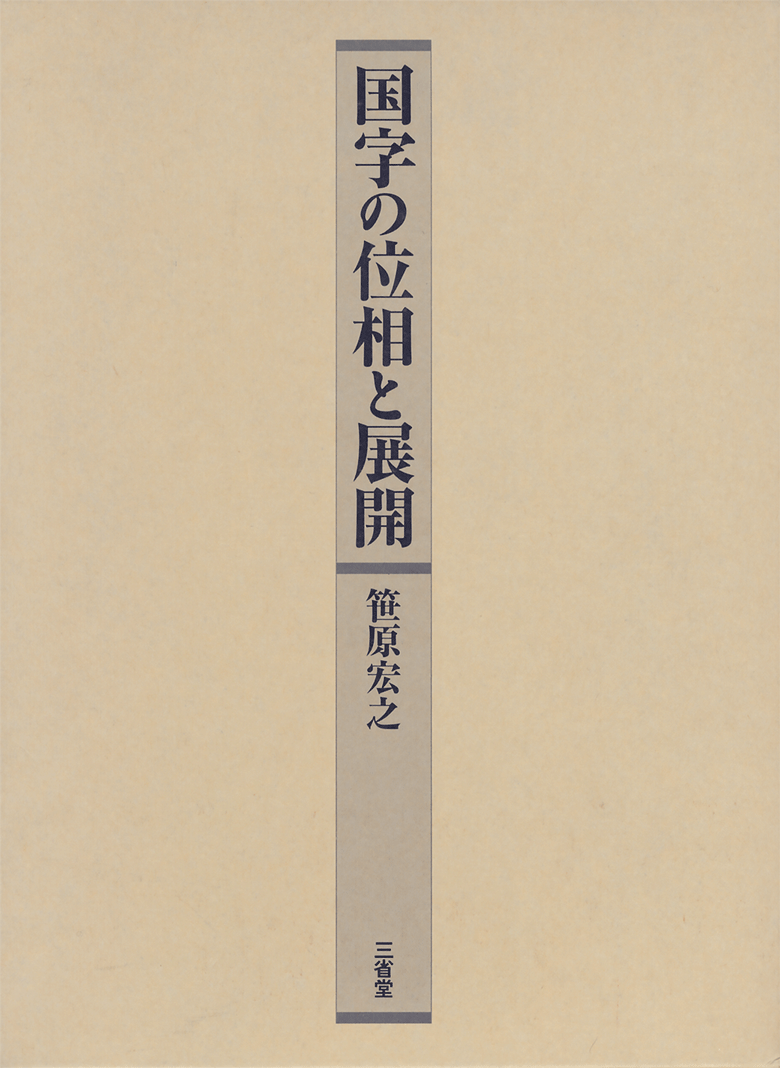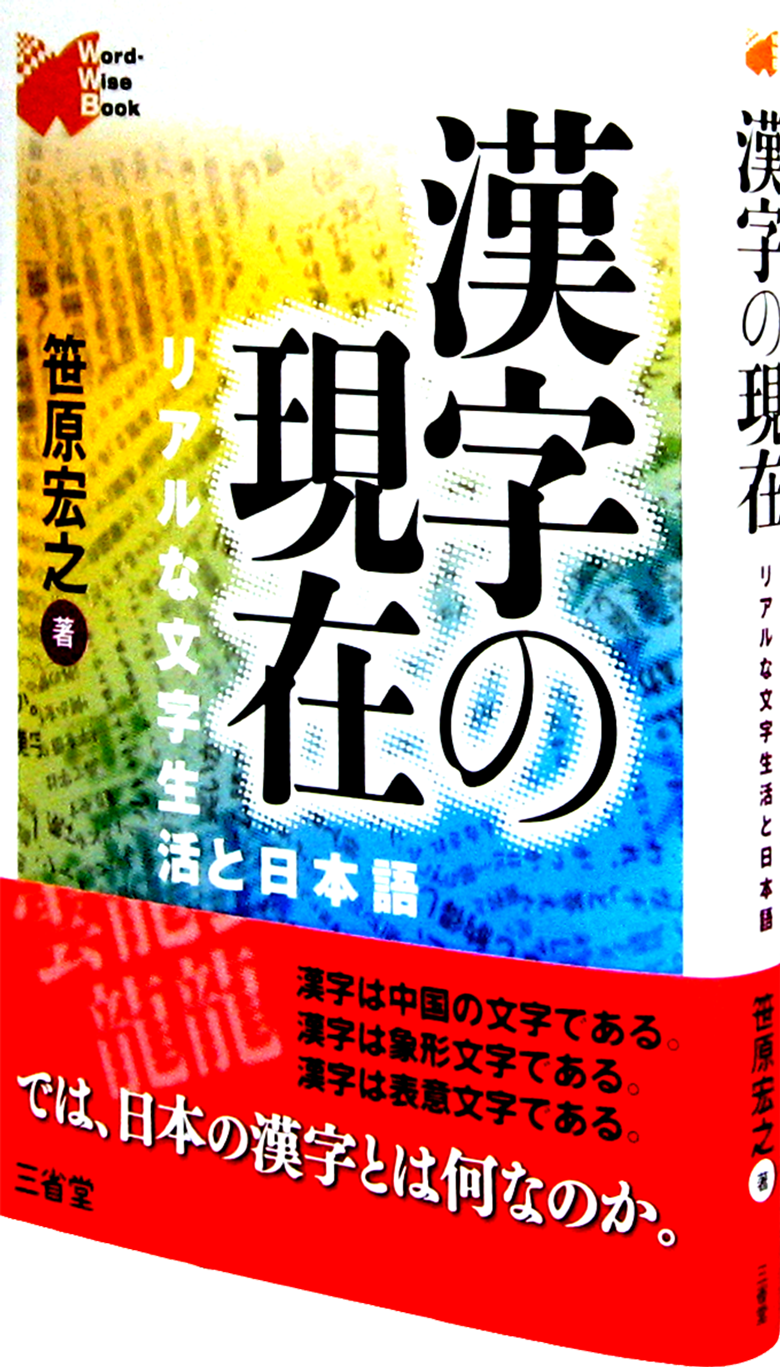チュノムが意外なことに現在でも書かれていることは、すでに述べたとおりである。中国に住む最大の少数民族壮(チワン)族だって、今でもチュノム風のチワン文字を書くことがあるらしい。考えてみれば、西夏文字も、西夏王国が滅んだ後、明代まで細々と受け継がれていたことが分かっている。エジプトのヒエログリフやメソポタミアの楔形文字が生活の中では死んだ字となり、完全に研究者の解読の対象となり、あるいはアニメや趣味の世界の小道具として残るだけというような状況とは訳が違う。

藤堂明保氏の辞書の付録で、これを見た時の衝撃は忘れられない。その後も、いろいろな書籍で、チュノムの説明に出てくる。世界史の教科書には、用語としては登場していた。チュノムに、形声文字が多いのは、中国語と同様に、ベトナム語も単音節であることと関連しよう。訓読みになる固有語が、漢語(字音)のような響きをもっているのだ。字音による仮借が、声調を含めて近似音まで容認さえすれば、作製自体は比較的容易にできてしまうのだ。後からの解読は困難を伴うわけだが、当座は字音で対応できてしまう(まれに字訓も利用された)。
チワン語は、ベトナム語と異なりタイ系の言語であるが、やはり同様の性質を持っている。彼らは、中国の広西(クアンシー・カンシー)省を自治区とする最大の少数民族であり、民族としての名を変えてベトナム北部にも少数民族として居住している。そうしたタイ系言語の基底の上に成立した少数民族語や広東語などの方言にもそれはいえ、それぞれの造字は形声が目立っている。
韓国語も、日本語のような長い音節をもつ語が比較的少ないことが、同様の形声文字好みを誘発したのであろう。さらに広げれば、インド・ヨーロッパ語族の梵語や、アルタイ系とされる鮮卑語などに対する造字も、そのように理解できるだろうか。中国で六朝期に「先人」を組み合わせて「老」とするたぐいの会意文字が好まれた現象は、戦乱による混乱状況の影響の中で、鮮卑など北方の異民族を含めた人々が言語の性質の差はともかくとして、漢字に覚えやすさを求めたことによるものだったのかもしれない。日本語はそういう点から見ると、会意を誘発する語の発音体系をもっていたといえそうだ。

(クリックで拡大)
チュノムを見ていると、文章でも辞書でも、「竜」が音符として多く用いられている。表音的に漢字を選んだ結果なのであろうが、建国伝説に基づき、竜の子孫を自認しているベトナム人らしいとも見えてくる。文学者以外の庶民は、チュノム(ノム字)もことばも違っていたのに、辞書には載らない、出てこないと嘆く先生がいらした。辞書にはほとんど文学の言葉や文字しか載らないそうで、それは日本と共通しそうだ。農村の古文書、寺の由来、諺、歌などを記した民間の文書や碑も辞書の材料とする必要があるというのは、日本では一歩進んでいるようだが、それぞれの国でさらに開拓の余地が広がっていそうだ。
研究者の一人が、勤め先という「漢喃研究院」に図らずも連れて行ってくれた。ハノイにあるのだが、まさか訪問できるとは思っておらず、幸いだった。チュノムで書かれた文章も額に入れて掲げられている(前回の写真参照)。漢字が見られるが、額や掛け軸、文献、碑文などの中のもので、研究対象としての素材とされているようだ。現在では、実用から離れ、閉ざされた中での漢字使用と見え、この施設でも部屋の案内表示や掲示はクオックグウだけだ。歴史、地理などの部屋があるが、チュノムを地理的な視点から研究するというわけではなさそうだ。自由な雰囲気で「服務」しているようだ。広めで片付いた部屋も羨ましい。
そこにあった資料で、「宗」は「TÔN」と記されている。皇帝の称号に使われてきたため、韻尾の「G」が避諱された結果だ。「宗」を「示」の「二」を「一」しか書かない欠筆も行われた(古代には中国にもあった形ではある)。諱を避ける際に、省略するのが末尾の画とは限らないことは中国と共通だ。さらにベトナムでは、偏と旁を入れ替えて、上に「巛」を加える方法も採られていた。このように字が煩雑になる傾向を有したが、独自の略字もまた、手書きや版本において量産された。これらが大量のチュノムと相俟って、独自の漢字の世界を構築していったのである。