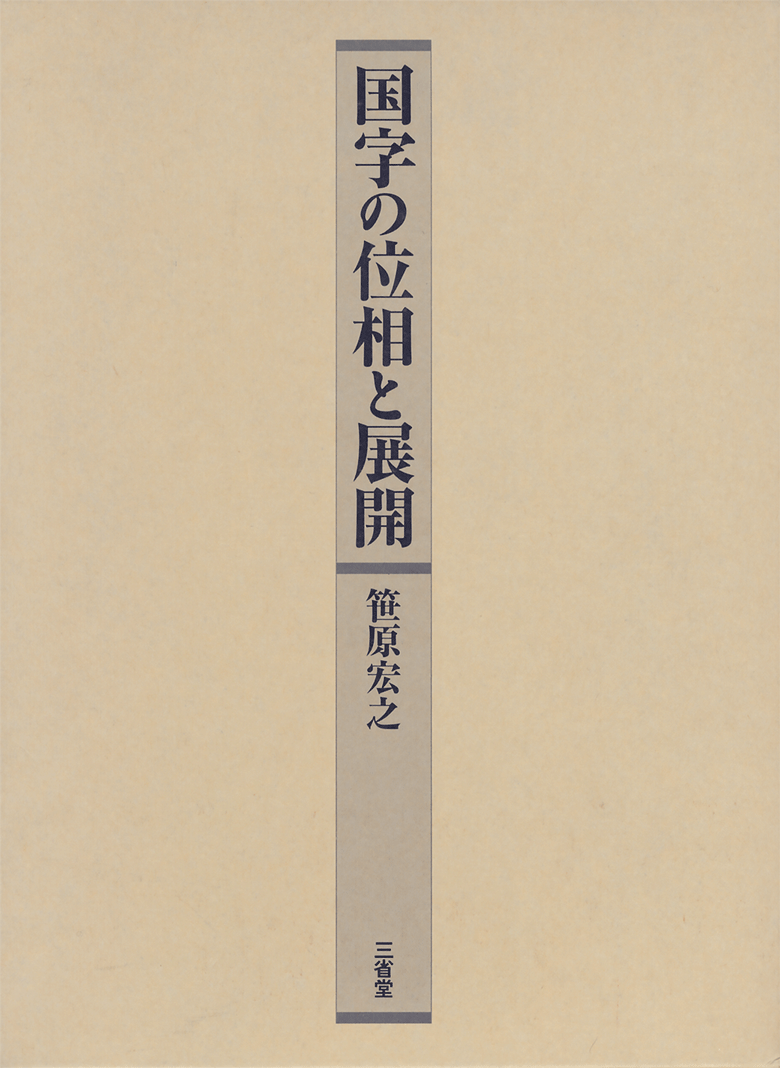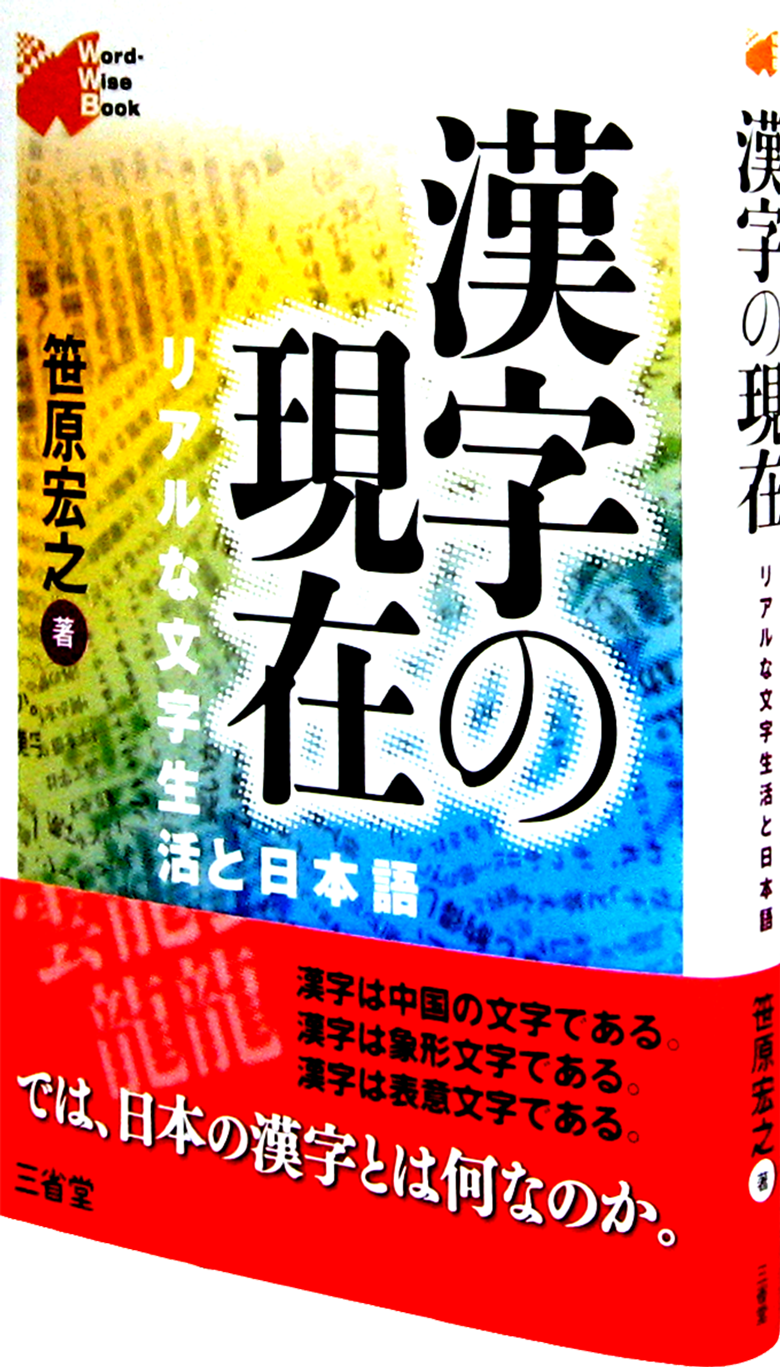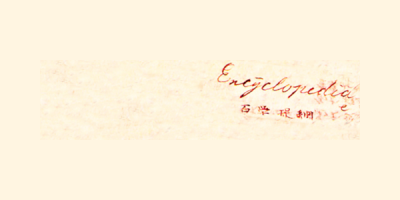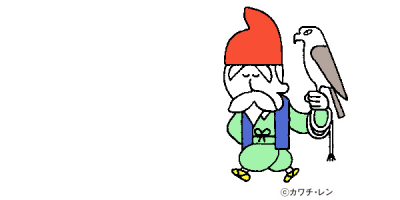ベトナム人は、「福」のほかに「心」という字も好むようだ。「心」は、日本人だけでなく中国の人も好きで、紙に大きく書いて貼っているのを見たことがあるが、こういうふうに1字だけ書いたものを、ベトナムほどたくさんは売ってはいないように思える。元は心臓(子供のそれと指摘する方がいた)の象形文字として即物的な文字であり、ハートマークとの関連も想起される。台湾の人は、「心」1字が街に貼ってあれば、何かの宗教のようだと評したが、ベトナムに並ぶ「心」「忍」などからは、日本と通じる精神性が浮かんでくる。「心」「忍」「徳」「禄」「壽」などは、縁起物に書かれて、よく販売されている(第94回・第103回・第114回)。三教と民間信仰などに支えられた価値観なのだろう。「登科」という字には、科挙の受験社会としての名残が読み取れる。

(画像はクリックで周辺も含めて拡大します)【「天心」など。文廟前のお香・宗教用品店の看板に。】
つまり、ベトナムでは縁起物・土産物・宗教用品に、漢字が書かれるのである。提灯・古銭の模型に見られるのも、その延長線上にとらえられよう。縁起物の布袋像の土台に鋳込まれた漢字列となると、中国製かどうか見分けが付かない。

(画像はクリックで周辺も含めて拡大します)【泰山石敢當】元を撃退した武将と皇帝、祠を修理した儒者ほかを祀るために18世紀に建てられた玉山祠で。「石敢當」は中国や沖縄でもこの3字が見られる。
社名に見られる漢字は、ロゴとしてのものであり、ベトナム人向けに古来の印象や中国の雰囲気を作り出すためか、中国人に見つけてもらったり読んでもらったりするためであろう。寺社は、新しい建物でも漢字を用いている。それも横書きの扁額、祭壇の類は右から記しているものがあり、伝統を継承しようとする姿勢がうかがえる。
漢字は、第一義的には現代の中国語を、表記しているとみられるものも多かった。もちろんそれは、古典漢文と共通するものもある。ベトナム語と単音節語、孤立語、声調言語などの性質や語彙に共通点が多い。なおかつ、歴史的、経済的、文化的にも接点が多く、学習者・習得者が多い。中にはベトナム語としてもそのまま理解できるものもある。

(画像はクリックで周辺も含めて拡大します)【禁煙(簡体字)区。掲示に。】
中国語の看板には、文章もあるが、やはりロゴタイプのほうが多いようだ。中華料理の店以外は、主に中国・台湾からの観光客など中国人向けで、中国語として読んでもらうためのものであろう。繁体字は台湾人向け、簡体字は中国人向けのように単純には思えようが、古来の俗字体や筆写体も見受けられる。これは、中華街においても同様なのだろう。

(画像はクリックで周辺も含めて拡大します)【功徳箱】文廟で。繁体字、中国語であろうか。日本語としても読める。
漢字を日常的に使い慣れていないことは、以前に触れたようにその筆跡にもうかがえるようだが、そのためであろうか誤字と言わざるをえない例も散見された(例:下の写真)。

(画像はクリックで周辺も含めて拡大します)【列火の部分の「一」が抜けた明朝(宋)体。】
さらに、赤い字の「囍」がマークとして、車の前後の窓ガラス・建物・店先・菓子の包装などに非常にたくさん見受けられた。マイクロバスの前のガラスに何度も見つけ、家内が繰り返し指摘する内に、やがて私の目にも入るようになった。昨年の当て字辞典編纂のせいか歳のせいか、少し目が見えにくくなった。これでメガネを取り換える決心も付いた。時には車体の後ろにもそのマークが付けられている。店の入り口の横にも、時には左右に貼られていた。
家内は、これがベトナム滞在中に一番よく見る「漢字」だったという。この日本とは細部が違う、「 」という形であることも中国風だ。このマークは、中国で明清のころから流行っているもので、二人の喜びを端的に表現していたものである。宋代の王安石まで遡るとの伝承もある。ベトナムでは、剪紙よりも、筆字風のシールが多かった。縁起物なのに、剥がれかけたものも街中で見られた。
」という形であることも中国風だ。このマークは、中国で明清のころから流行っているもので、二人の喜びを端的に表現していたものである。宋代の王安石まで遡るとの伝承もある。ベトナムでは、剪紙よりも、筆字風のシールが多かった。縁起物なのに、剥がれかけたものも街中で見られた。
ベトナムの先生たちによれば、昔から結婚式で使われ、結婚(式)を表すとのことで、中国の影響が濃いことがうかがえるが、使用している車や壁面の例を見ると、中国での結婚式よりも、意味が広がっているようだった。ホアンキエム湖近くの旧市街の紙細工店が並ぶ通りで、色々な店にこれがたくさん売られていたそうだ。私の講義している時間に、口がハート型になっている物なども、家内たちが写真に撮っておいてくれた。ただ、そこここにある洋風の結婚式の衣装屋に、それは見当たらなかったが、キリスト教の十字架のある建物の下にはあったとのこと、用途が種々に複雑化しているようだ。
「囍」は、日本ではラーメンの丼の模様としてすっかり定着しているが、文字としての用途も生じており、JIS補助漢字や第4水準に採用された。韓国でも文字として、それも国字とみなされることもあり、寺の壁面や陶器の底にも書かれるようになった。土産に買ってきた陶磁器を見て、母はこれが底に書かれていなければよかったと残念がっていたのを思い出す。ベトナムでは、「喜」という字は皆がよく知っている漢字なのだそうだ。その意味を知らない人もいるが、そのままこのマークを使っているとのことだ。
中国の人が何となく発するxi3という語形のとおりに読まれることがあるが、非言語表記のシンボル・記号として、ベトナムでも根付いて使われているようだ。