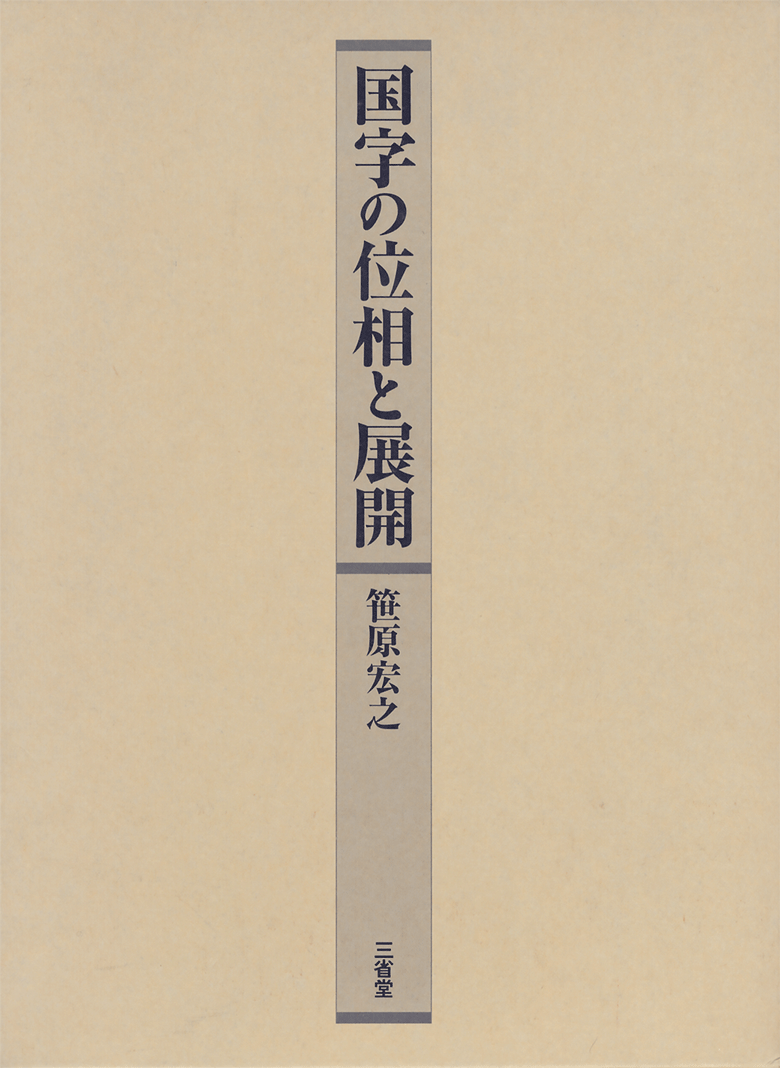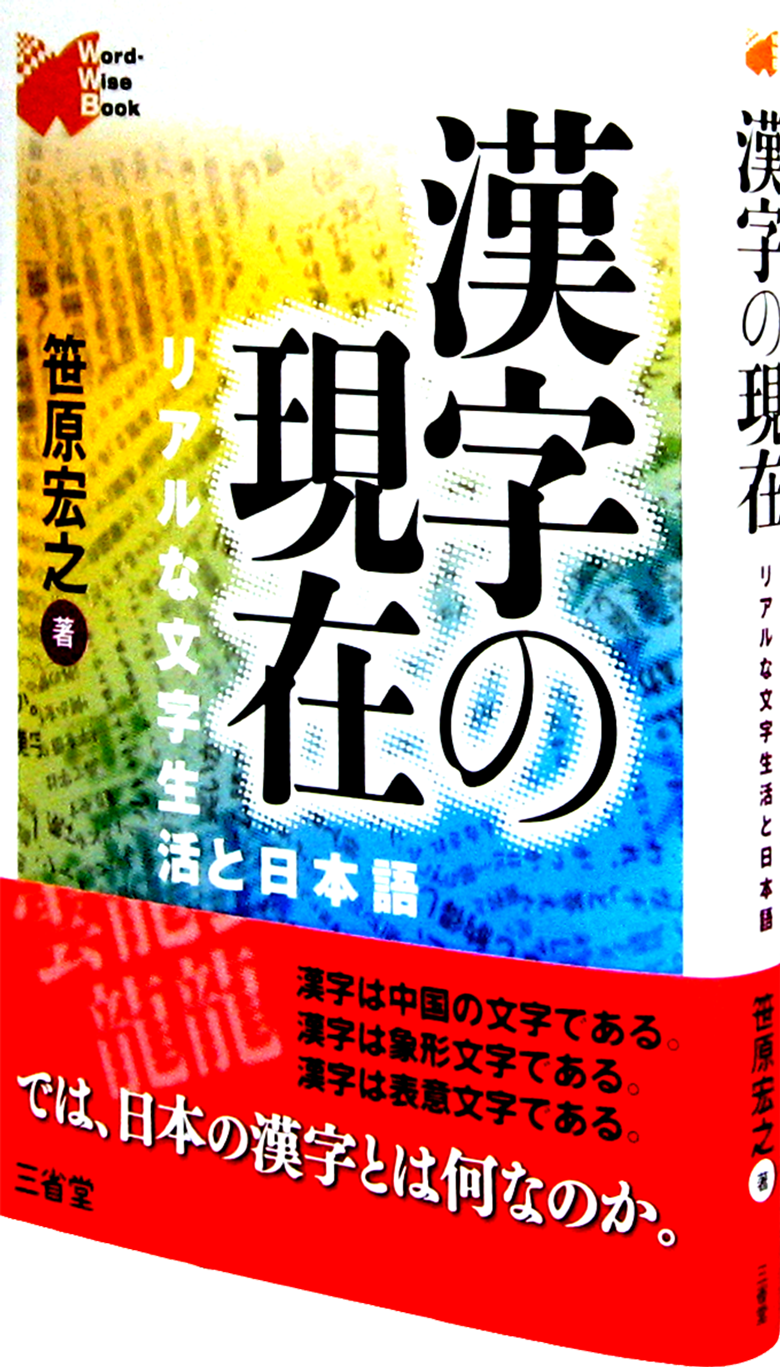新潟では、「えがらし」さんのカルテが見つからなくて困っていたところ、実は「五十嵐」さんだったこともあったそうだ。当地では色鉛筆が「エロインピツ」となり、「イチゴの越後姫」もイ・エが逆転する。電話で高齢者と話すと、区別しようとして「アエウエオの「エ」」と言われても、イかエかどっちか分からないことさえあるそうだ。東京暮らしが長い方は、あの「イ」と「エ」の母音がもう話せなくなったが、あれを聞くと「いいなあ」と思うとのことだ。
新潟市内の地名もそうだが、発祥地とされる下田(しただ 三条市)の五十嵐神社や五十嵐川は正式には濁らない。古く、「い(そ)」が五十を意味した。県内では「いがらし」も案外あるが、濁らない「いからし」という読みのほうが多く、新潟出身の方には五十嵐をみな「いからし」と読む方もおいでである。「嵐」という字は、頻用される地では、中の「ノ虫」は「点々」で済まされる傾向が各地で地名や名字に顕著だが、ここも例外ではないそうだ。「凡」とは区別される。東京よりも見かけ、よそ者の視点から言えば、やはり筆記される使用頻度が高いからだろう。
母音の訛語(いわゆる訛り)は、人名にも現れることがある。ズーズー弁で知られる東北地方では「悦」(エツ)が「一」(イチ・イツ)の代わりに使われることがあり、「匡」もタダシなのかタダスなのか、当人も分からないというようなケースがさほど稀ではなかったそうだ。地名でも、福島県の「橲原」はジザハラ・ズサハラの両方の表記が行われていた。子音では、奈良の「椣原」にはシデハラのほかヒデハラという訛音(地元のお寺の方は訛りとおっしゃっていた)があり、京都にも「七条」にシチジョウ(まれにナナジョウ)ではなくヒチジョウ、さらにヒッチョウという発音が見られる。「七」はヒチで、七福という大阪の社名も同様であることが、会社のサイトのアドレスから分かる。「シ」が「ヒ」に転ずることは江戸っ子に限るように思われがちだが、実際にはさらに質屋がヒチヤとなり、看板でも「ひち」のように書かれていることは、名古屋以西では珍しいことではない。漢字音も、長い時代の中で現地の音韻規則の中に溶け込み、多くは変化を免れなかった。
先の「ヒッチョウ」と同様の、伊勢の「松阪」がマッツァカ、福井の勝山がカッチャマと呼ばれるというたぐいの促音化による子音の発音変化も、母音のほうが子音よりも優位で丁寧に発音されるとされる関西地方に意外と目立つ。
新潟では、人名に「たのむ」という字を使いたいという漢字に詳しい方もいらした。「恃」で、人名用漢字にも入っていない。かつて子の名前に関する裁判で使用を得られなかった「矜持」の名は「矜恃」とも書くことを思い出す。

関川村の「杁差岳」は「えぶり」なので、漢字の「朳」が本来的なのだが、「新潟日報」でも「いり」の字体を用いることがあったそうだ。JISの制約によるのかと思うと、1978年以前から「えぶり」は「杁」と書かれた例がかなりあり、この地名でも同様だった。「朳」が常用されず、字源も一般に不明確であり、そして尾張圏では「杁」は「いり」であっても、この地ではそれと衝突しなかったためであろう。
「デンキ」の漢字表記は?
「石丸電気」「ベスト電器」「ヤマダ電機」「ケーズデンキ」など、揺れがある。これらの「でんき」は、意識の上でも語レベルの揺れといえるものなのだろうか。こちらでも、各社が進出したりつぶれたりしながら、地元の方々の記憶にだいぶ焼きついているようで、話がスムーズに通じた。が、解答の声はやはりバラバラとなる。人間の記憶はあやふやなものだが、それよりも現実の意義の乏しい、しかし大切な使い分けをする日本の漢字の一つの姿だ。不景気で、統廃合なども進むことだろうが、こうしたものは不統一感があっても、それぞれに設立当初からの理由などもあるため、今後とも残ることだろう。