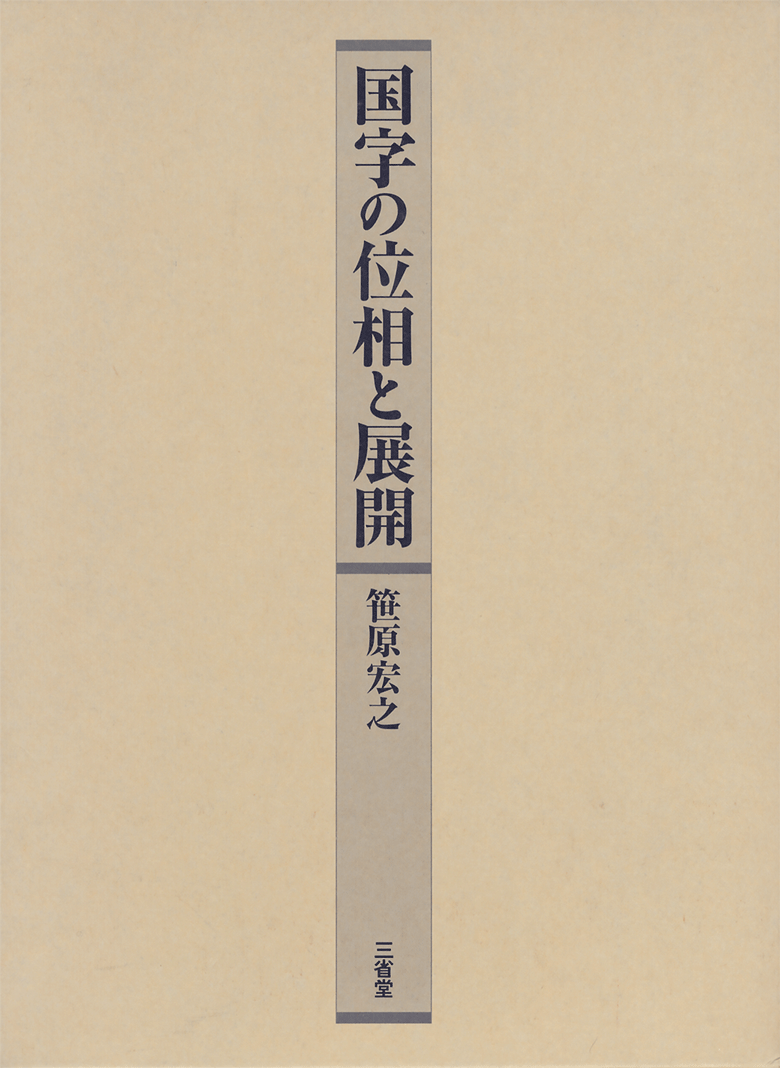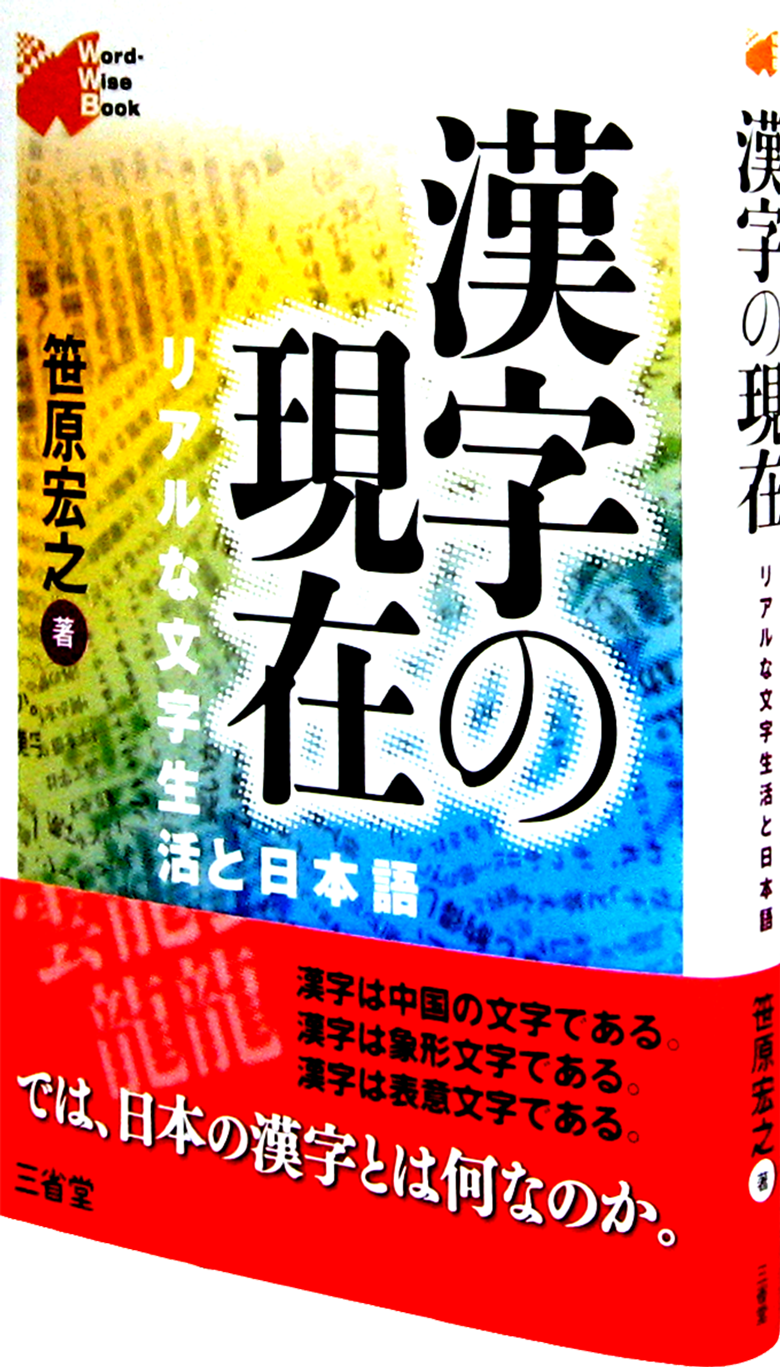「しんにょう」は注目を集める構成要素だ。前回記したとおり、「辶」ばかりが大幅に崩れたのだが、それはなぜだろう。過去には足にょうもないではなかったが、一般化はしなかった。もはや楷書とは思えないほどに、手書きでは「丶フフ乀」と続くグニャグニャとした筆画を持つことに、それを教室で習う小学2年生の多くは、衝撃を受けながら大きく書いて真似をする(私もそうだった)。教室で、なんだこれは、と思った記憶がある。はらいまで巧く書けたと納得できると、気分がよくなった。巧拙の実に目立つ字だ。
煩瑣な字体の使用頻度の高さは、筆記経済の希求につながる。意味から、字形にいかにも行く感じを出そうとした、というような俗解的な要求や二次的字源意識も作用しなかったとはいえない。構成要素の「彡」にも問題ははらんでいた。それを「彳(ぎょうにんべん)」だととらえたとしても、意味の認識はなお希薄で、イメージが取りにくい。そしてその書きにくい筆の方向と、改善へ向かわせるための条件が揃った。
筆字では、隷書や崩し字はともかく、楷書では1点で下は「フフ」と曲げる形が多かったが、そうでない2点で下を曲げる形も、楷書の完成期である隋唐の頃にも見られ、以後も消えることなく根強く伝承された。「彡」が2点となった根拠だとする分かりやすそうな解釈もあり、そう見ても良いのだが、実例から言ってもさほど厳密な見方とはいえない。一方、活字となると2点が原則であり、歴代の版本・活字の印刷物の明朝体風の字形は、そのようになっていた。
つまり、「しんにょう」は筆字では歴代、1(ときには2)点で曲げた。それを受けて明朝体では2点では下は曲げない、1点では下は曲げるという傾向があった。ただしこれを正則のように呼ぶには、明版などでは2点で下を曲げる例が、楷書と同様に散見されるので、やはりはばかられる。

2点しんにょうの明朝体は書体を超えた一種の「瞬間冷却」だった。当用漢字の新字体は、この点で画期的な転換をもたらした。常用漢字表の前書きも、ごく基本的にはその事象を反映した記述となっている。現在では、手書きと活字の間の表現の差が、硬筆とフォントの影響で意識されなくなってきたことは、「令」の字にも顕著に表れている。「鈴」や「玲」などで、登録された字と違うと窓口でもめるという話は何度も聞いた。
固有名詞を中心として、何かの表や辞書などを基準にした規範意識が発揮される機会が多いのだが、文字の伝達機能を考えれば、現代でも、手書きのほか、明朝体やゴシック体などのデザイン書体で、この点の数は、改定された常用漢字表にも一部示されているとおり、許容の内にとらえるのが妥当ではと考えている。こうした人間による柔軟な歴史的事実を踏まえて、伝達時には、使い手にも不安や躊躇がなく、受取手にも無用な摩擦の意識が生じなくなることを願っている。
「しんにょう」は、よく使ったために簡易化が進み、草書のような違例の楷書に仕上がった。もし篆書こそ正しい旧字体の手本などと主張するならば、『康煕字典』などを超えて「辵」にまで戻る必要が生じてくる。いや、もっと古い時代にまで遡る必要だって出てくるだろう。歴代の辞書でも、本編の中でさえもこの字体の揺れは見られた。
「走」は「にょう」で、「足」は偏で定着した。「辵」は、単独では使われないために、そして部首としてはよく使われたため、小さい部分として他の「食偏」「示偏」などと同様に筆記時に部首として簡易化が進展したという面も指摘できる。そして、「走」「足」との差別化の目的も働いた可能性もあり、三様の楷書化を展開したのである。
このように、字源と頻度の差など使用のダイナミズムとを考え合わせれば、「しんにょう」と「走にょう」との共通点と相違点は浮き彫りとなり、「辶」の点の数や、新潟でよく見られる「越」の書写体風の異体字への眼差しも変わってくることだろう。