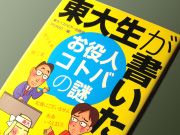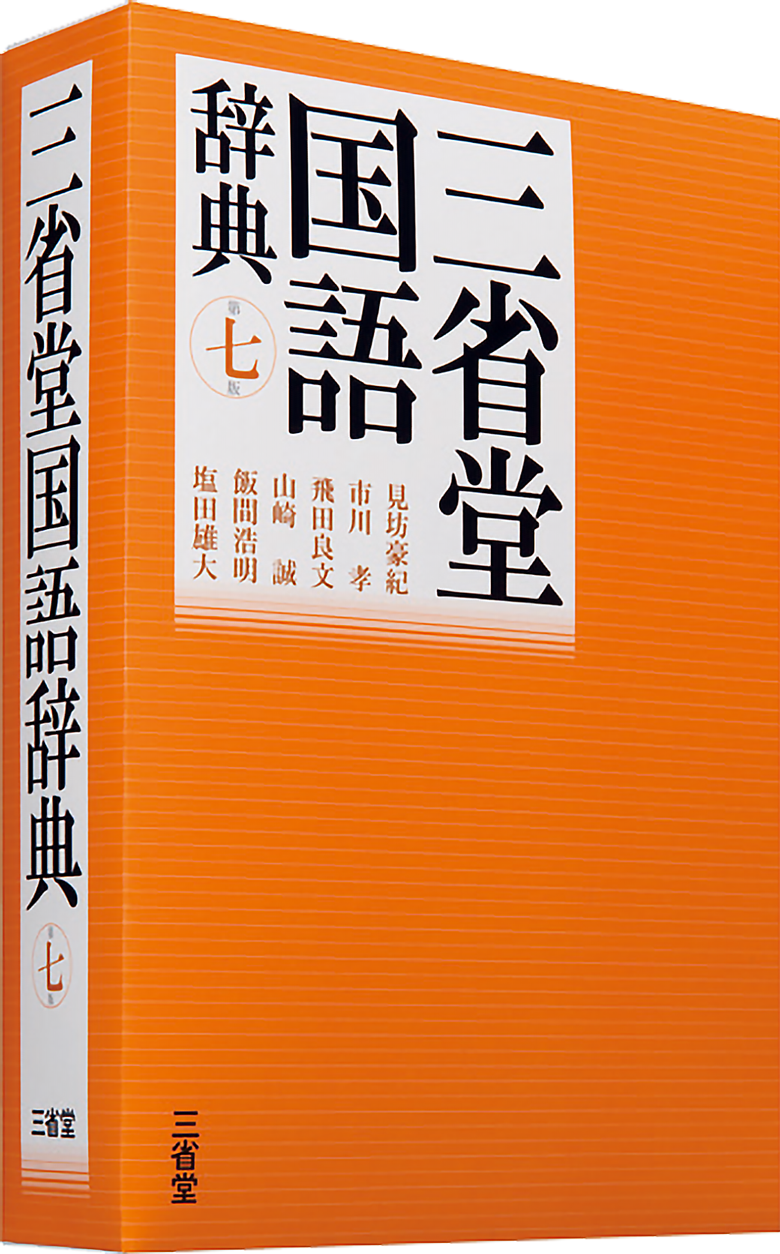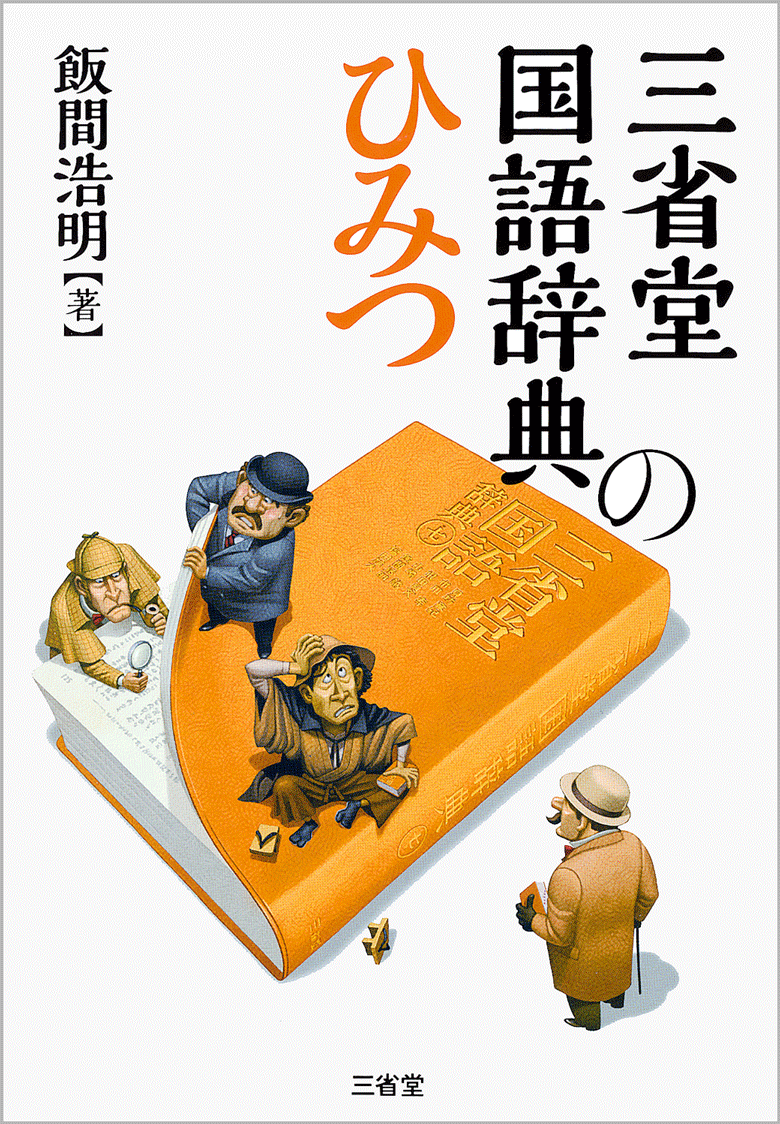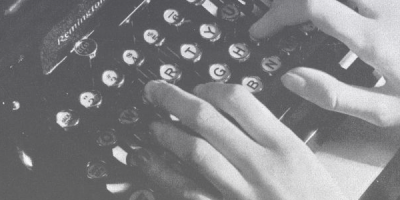インターネットのサイトを見ていると、『三省堂国語辞典』でおもしろい語釈や例文を見つけたと紹介されていることがあります。個性的な語釈・例文というと『新明解国語辞典』のそれが思い浮かびますが、『三国』を見てにやっとする人もあるようです。
たとえば、「マダム」の例文に「バーのマダムといっても、やとわれマダムです」とあるといいます。なるほど、おかしみを誘うかもしれません。第二版からで、「雇われマダム」ということばを示すためだったのでしょう。後の版で「雇われマダム」は別に立項されましたが、この例文は残り、今に至ります。今回の第六版では、「雇われマダム」は項目にせず、「雇われの身」などとともに「雇われ」の用例としました。
あるいは、「さすが(に・の)」の項目で、「さすがは田中君だ」「さすがに田中だ、よくやった」などと、4つの例文すべてに田中君が登場していたという指摘もあります。これも第二版からです。たしかに奇妙というわけで、第五版では「山田君」「中川」「中村」などと改められた代わりに、田中君は消えてしまいました。
第六版の改訂時に問題になったのは、「役所」の例文です。なにしろ「お役所仕事は のろくてこまる」というのです。ひとつしかない例文がこれでは、役所勤めの人は憤激するかもしれません。

辞書によっては、「役所」の項目で「お役所仕事」ということばに触れ、形式的で遅い仕事ぶりのことだと説明したものもあります。『三国』の「役所」の例文も、「お役所仕事」を説明するつもりで「……のろくてこまる」と書いた可能性はあります。ところが、『三国』には別に「お役所仕事」の項目があるため、やはりこの例文は不必要なのです。

これも、くしくも第二版からのものです。『三国』の第二版は、主幹の見坊豪紀(けんぼう・ひでとし)が初版の刊行後に着手した用例採集の成果が盛りこまれ、ユニークさの度合いが高まっています。私の好きな版であることは断っておきます。
第六版では、「役所」の用例は「お役所ことば」に改め、あわせて「お役所仕事」への参照の印をつけておきました。必ずしもこれで辞書のユニークさが弱まったとは言えないでしょう。私個人としては、役所に対していろいろ言いたいことがありますが、辞書を編集するに際しては、個人の不満・憤懣を表すのは控えておきます。