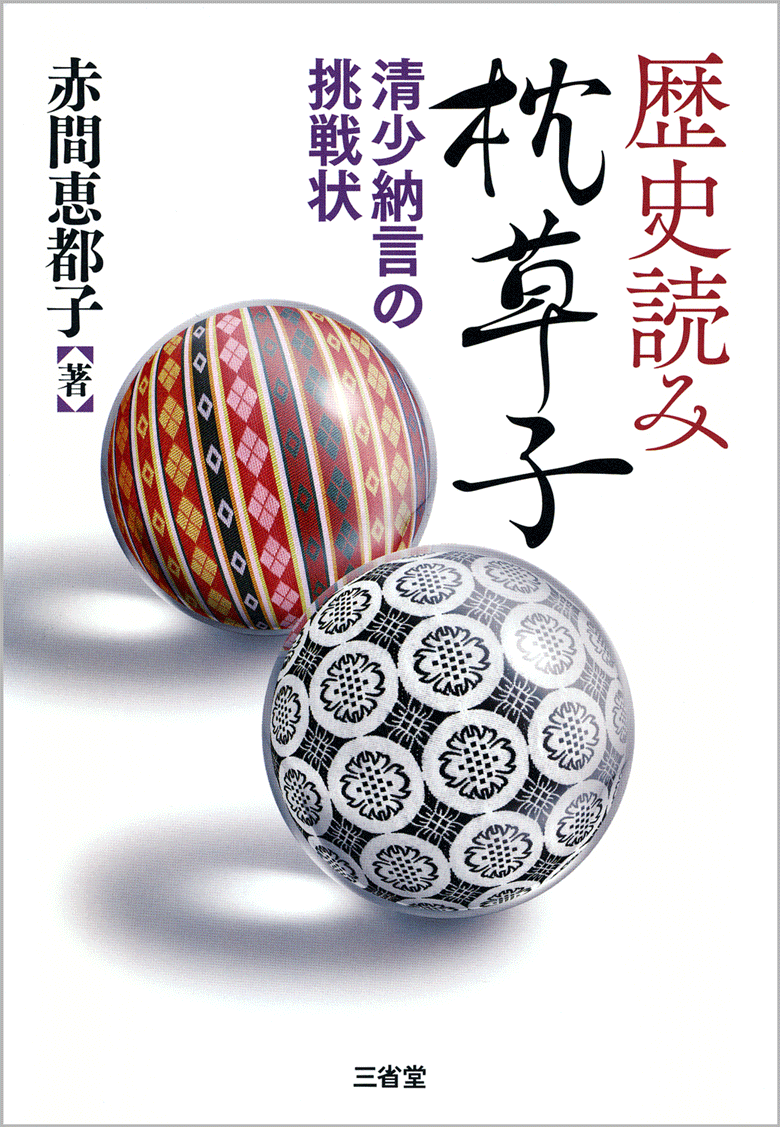長徳元年四月に中関白道隆が亡くなり、中宮定子後宮は一年間の喪に服します。紅梅襲(こうばいがさね)が好きだった定子の衣装も色とりどりの女房達の十二単も、すべて喪服の鈍色(にびいろ)になりました。その変化は気をつけて『枕草子』を読まないと分かりません。父道隆の死を悲しむ定子の姿も、葬儀の事も、いっさい記されていないからです。
その中で、道隆の服喪中であることを冒頭に示して始まる章段が二つあります。「故殿の御服のころ」の段は、長徳元年の六月末、宮中の大祓えの神事に際して服喪中の定子が内裏から退出し、太政官庁の朝所(あいたどころ)に仮住まいしたときの記事です。朝所は、儀式の折に官僚達の会食場所となった建物です。
そこは清少納言が普段見慣れた宮殿とは異なる瓦屋根の背の低い建物で、格子がなくて簾だけがかかっている簡素な造りでした。興味津々の女房たちは庭に下りて探検をはじめます。時報の鐘を打つ陰陽寮のすぐ横に当たるので、鐘の音が普段より間近に聞こえます。若い女房たちは面白がってそこまで行き、大胆にも階段から高楼に登ります。その様子が次のように書かれています。
これより見あぐれば、ある限り薄鈍の裳、唐衣、同じ色の単襲、紅の袴どもを着てのぼりたるは、いと天人などこそえ言ふまじけれど、空よりおりたるにやとぞ見ゆる。
(こちらから彼女たちを見上げると、全員が薄墨色の裳と唐衣、単襲に紅色の袴を着けて登っている様子は、まるで天女のようだとは言えそうもないけれど、空から下りてきたのではないかと見える)
ここには、女房たちの衣装がすべて喪服であることがはっきりと記されているのです。けれど、彼女たちがいる場所は、普段女性が居るはずもない高い楼閣の上です。それを天から降りて来たように見えると作者は書いています。調子づいた若女房たちは、さらに内裏の建春門付近まで行って大騒ぎし、建物内の椅子に登る、倒すの仕放題です。彼女たちの行動は度が過ぎていますが、華やかで活気にあふれた定子後宮の生活が、一転して服喪による謹慎生活になった鬱憤をここで晴らしていたとも考えられます。そして作者は、不謹慎な彼女たちの行動を描くことによって、喪中の内実から読者の視点をそらしているのです。
さて、太政官庁の建物は、真夏の夜の暑さが尋常ではなかったので、女房たちはたまらず御簾の外に出て臥していたようです。また、古い建物だったのでムカデが一日中上から落ちてきたり、大きな蜂の巣に蜂が群れていたりして大変恐かったとも書かれています。『枕草子』は、王朝女流文学の中でも、日常的に目にする害虫について多く扱っている作品です。「虫は」の段には、松虫や鈴虫など和歌に詠まれる風雅な昆虫の他に、蝿や蟻など人間の生活に入り込んでくる不快な昆虫が登場します。また、「にくきもの」の段では、蚊や蚤が平安貴族たちを困らせていたことを教えてくれます。貴族文学でも気取らない生の生活感覚を伝えてくれるのが『枕草子』の魅力です。
もう一つの「故殿の御ために」で始まる章段には、道隆の法事を開催した長徳元年九月十日の出来事を扱っています。ここで作者が法事について記したことは、清少納言お気に入りの美僧清範の説教が大変心に染みいって悲しかったので、女房たちがみんな泣いたことだけです。この段の中心人物は、法事の後の宴会で朗詠を披露し、定子や清少納言の称讃を得た藤原斉信(ただのぶ)です。彼は「故殿の御服のころ」の段の後半にも登場していますが、長徳元年の『枕草子』に登場し、注目される斉信という人物については次回、取り上げましょう。