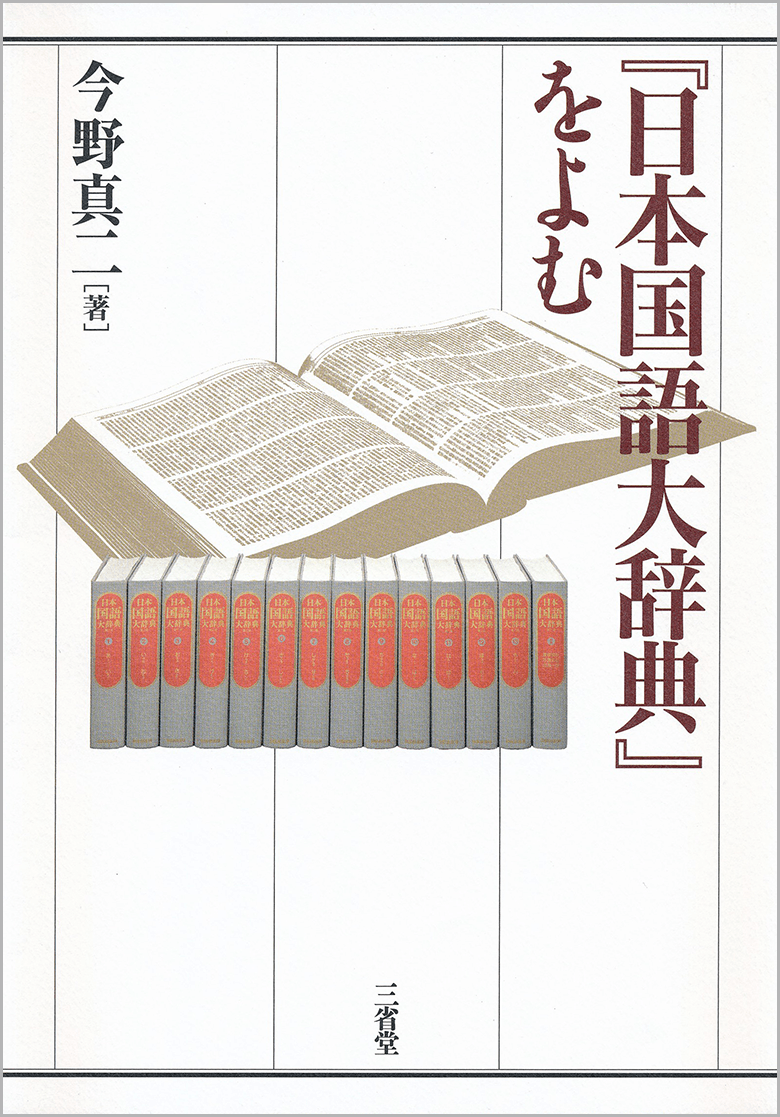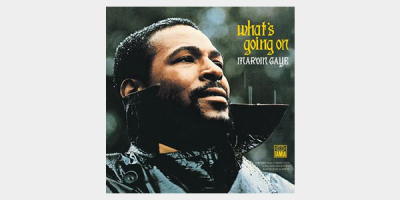『日本国語大辞典』は見出し「あらい【荒・粗】」をまず「整った、あるいは整えられた状態になく、調和のとれた理想的状態になっていない。緻密(ちみつ)でない」と説明しています。「整えられた状態になっていない」「調和のとれた理想的状態になっていない」「緻密でない」状態が「アライ」だとすると、「アライ」の対義語は「整えられた状態」や「調和のとれた理想状態」をあらわす語、あるいは「チミツ(緻密)」ということになります。
「アライ(アラシ)」は和語で、例えば935年頃にはできあがっていたと考えられている、紀貫之『土左日記』には「うみあらければ、ふねいださず」というくだりがあって、10世紀頃にはすでに使われていたことが確認できます。〈海があれている〉という意味の「アラシ」の対義語は何でしょうか。漢語「チミツ(緻密)」でないことはたしかですね。
「波がアライ」だったら「波がオダヤカダ」が対義になりそうです。「ことばづかいがアライ」だったら「ことばづかいがテイネイダ」でしょうか。
現在出版されている小型の国語辞書においては対義語が示されていることが少なくありません。『三省堂国語辞典』第八版(2022年)は「あらい(荒)」「あらい(粗)」二つの見出しをたてています。つまり漢字「荒」をあてる「アライ」と漢字「粗」をあてる「アライ」とを別の語とみていることになります。それに対して『日本国語大辞典』は同じ一つの語とみています。これは「とらえかた」の違いで、どちらが正しいということではありません。
そして、『三省堂国語辞典』は「粗い」の語義を「①つぶ・模様などが大きい」「②まばらだ」「③なめらかでない」「④大ざっぱだ」と語義を四つに分けて説明し、語義②の対義語として「細かい」をあげています。②の使用例としては「目があらい」があげられています。つまり『三省堂国語辞典』は「粗い」の①③④、「荒い」には対義語をあげていないことになります。つまり、「アライ(アラシ)」の語義全体に対しての対義語はなさそうだということになります。
さて、『日本書紀』の神功皇后摂政前紀には「和魂服二王身一而二寿命一、荒魂為三先鋒而導二師船一。[和魂、此云二珥岐瀰多摩一。荒魂、此云二阿邏瀰多摩一]」というくだりがあって、漢字列「和魂」は「珥岐瀰多摩(ニキミタマ)」、漢字列「荒魂」は「阿邏瀰多摩(アラミタマ)」をあらわすという注がつけられています。
『日本国語大辞典』の見出し「にきみたま」には次のように記されており、上の『日本書紀』神功皇后摂政前紀が使用例としてあげられています。
にきみたま【和御魂・和魂】〔名〕(後世は「にぎみたま」とも)柔和精熟などの徳をそなえた神霊。神霊の静的・穏和な側面をいう。にきたま。にこみたま。↔荒御魂(あらみたま)。*日本書紀〔720〕神功皇后摂政前「和魂は王身に服(したか)ひて寿命を守らむ〈略〉〈和魂、此をば珥岐瀰多摩(ニキミタマ)と云ふ〉」*出雲風土記〔733〕意宇「及(また)、海若等(わたつみたち)、大神の和魂(にきみたま)は静まりて、荒み魂は皆悉くに猪麻呂が乞(こひの)む所に依り給へ」
『日本国語大辞典』は「アラミタマ」を「荒々しく勇武な神霊。神霊の動的、勇猛な側面をいう」と説明しています。この〈荒々しい〉という語義の「アラ~」の対義語が「ニキ」あるいは「ニコ」と思われます。現代日本語では「ウブゲ」を使うことが多いと思いますが、同じような語義の語として「ニコゲ」があります。『三省堂国語辞典』は「にこげ」を見出しにして「やわらかな毛。うぶげ。わたげ」と説明しています。
〈葉や茎の柔らかい草〉は「ニコグサ(和草)」、〈松・栗などの柔らかい材を焼いて作った、火力は弱いが炎の立つ炭〉は「ニコズミ(和炭)」、〈やわらかな土〉は「ニコツチ(和土)」ですが、「ニコヤカ」の「ニコ」も同じ語義の「ニコ」です。『日本国語大辞典』の見出し「にこやか」をあげておきましょう。
にこやか【和─・柔─】〔形動〕(「やか」は接尾語)(1)ものやわらかなさま。しとやかなさま。にこよか。*日本書紀〔720〕雄略七年是歳(図書寮本訓)「天下の麗(かほよき)人は吾が婦に若くは莫し。茂(こまやか)に綽(さはやか)にして諸(もろもろ)の好(かほ)備れり。曄(あからか)に温(ニコヤカ)に、種(くさくさ)の相(かたち)足れり」*霊異記〔810~824〕中・二七「夫に随ひ柔(ニコヤカ)に儒(やはらか)にして、練りたる糸綿の如し〈国会図書館本訓釈 柔 音爾夏及 爾古也可二〉」*源氏物語〔1001~14頃〕梅枝「いたう、な過ぐし給ひそ。にこやかなるかたのなつかしさは、ことなるものを」*評判記・満散利久佐〔1656〕薩摩「底心かしこく、をしだまりて、にこやかにみゆ」(2)なめらかなさま。*大唐西域記長寛元年点〔1163〕三「其の窣堵波の基の下(もと)に石有り。色黄白を帯びたり。常に津(うる)ひ膩(ニコヤカナル)こと有り」(3)建築物などが立派で美しいさま。*大唐西域記長寛元年点〔1163〕五「城の中に天祠有り。瑩飾(かざれ)ること輪奐(ニコヤカナリ)」(4)心から嬉しそうなさま。にこにこしているさま。にこよか。*日葡辞書〔1603~04〕「Nicoyacana (ニコヤカナ) ヒト〈訳〉うれしそうな、つまりほほえんでいる人」*浄瑠璃・雪女五枚羽子板〔1708〕中「空のかんばせにこやかふくやかにっこりほやりの笑顔は誰だア」*狐の裁判〔1884〕〈井上勤訳〉三「思ふ心ろを色にも見せず莞爾(ニコヤカ)に」*虞美人草〔1907〕〈夏目漱石〉八「甲野さんが問ひ懸けられた時、囅然(ニコヤカ)な糸子の顔は揺(うご)いた」*ある小官僚の抹殺〔1958〕〈松本清張〉六「それまでは遠い距離だと思っていた上司がこうまでにこやかに近づいてくるのである」
となると、「ニコニコ笑う」の「ニコニコ」はこの〈ものやわらかな〉という語義の「ニコ」が重なったものということになりますね。