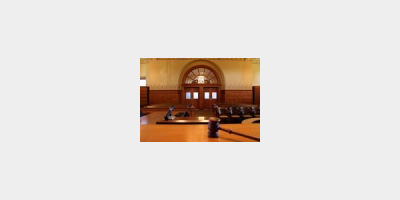〈黒き鳥窓をよぎりて四角い空白に耐ふる朝となりけり〉。六十代半ばになって短歌を始めました。これは初めの頃の歌です。朝の倦怠は若い頃からありました。いまは、老いゆく者のそれです。目覚めのもやもやを断ち、一日を開始しなければなりません。曖昧な、危ない時間帯です。黒い影が窓を横切ったと思ったとき、茫漠たるものが意識されました。拒みえないものとして。歌は、[窓枠によって区切られた]四角い空白に「耐ふる」、となっております。辞書の仕事は、たいていは、こうした朝に始まる日日のなかでなされてきました。
机の上にさまざまの辞書を広げて、『クラウン独和』の原稿を書いておりました。部屋に入り、椅子に腰掛ければいいのです。だがこの部屋に入るのをひそかに避けようとしている自分に気づきます。何か理由をつくっては部屋に入るまいとしていました。そのうちに理由などこしらえることもなくなってゆくのであります。おそろしいことです。しかし幸いにも、私はすでにこの部屋のなかにおります。そして何時間も出ることはありません。
〈うたた寝の靄立ちくればうなじには堅き一枝生えいでてゐむ〉。うたた寝の朦朧のなか、ぼくのうなじから、木の枝が生え出ている、と、まどろみの中で感じているのです。椅子の背に凭れたままのうたた寝です。首筋が、硬くかたくなっています。――〈いまのこの椅子とひとつになりしわれ六本脚のけものなるらむ〉。じっと椅子に腰掛けているうちに椅子と一つになっていました。机に向かっているのは六本脚の獣、でありました。
〈身をかがめ辞書に耽るも朦朧のとき訪れるもこの部屋のなか〉。つまり、身をかがめて辞書を読み耽るのも・朦朧のときが訪れるのも・この部屋のなか、ということです。無論、食事のとき以外にも部屋を出ることがあります。たいていは、何をすることもなく戻ってくるのです。〈何せんと部屋を出でしか真夜中の体重計にのぼりをりたり〉。