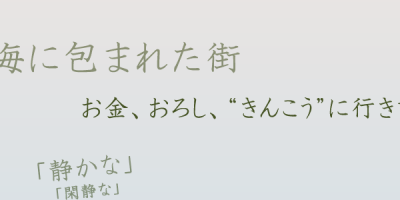ボルドーでの会議を受けて,スロベニアのリュブリャナ大学で開催されたキャラクタのワークショップでは,私は「キャラクタとは何か」ということよりも,むしろ「キャラクタとは何でないか」を話すことになった。ボルドーで受けた質問やコメントの中には,「キャラクタ」という日本発の新しい考えに対する誤解に基づいているものが少なくなかったためである。
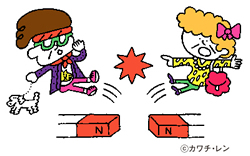
誤解のうち,最も根本的と思われたのは,「キャラクタは,既存の理論枠組み(たとえばバフチンのポリフォニーやゴッフマンの自己呈示,オクスの社会的アイデンティティ,ガンパーツの文脈化,さらには批判的談話分析)と対立し競合する,一つの理論だ」というものである。これが誤解であることを,私は以下のように説いた。
キャラクタは,今日では若者にかぎらず沢山の日本語母語話者が日常生活の中で口にし,意識にのぼらせる概念ではあるけれども,それ自体は「理論」ではない。キャラクタは,既存の理論枠組みと何ら競合的な関係に立つものではない。キャラクタはそれらの理論枠組みを否定しないし,正当化もしない。
ではキャラクタとそれらの理論がまったく関係ないかというと,そうでもない。多くの理論はキャラクタという概念を取り入れることによって,説明力を増すことができるだろう。キャラクタに関して理論間に対立・競合があるとすれば,それは,「キャラクタという概念を受け入れられる理論」と「キャラクタという概念を受け入れられない理論」の間にしかない。
「キャラクタという概念を受け入れられない理論」とは,人間のコミュニケーション行動として意図的な行動しか認めない理論である。この理論は,たとえば「あくびが伝染る」,つまりAさんが思わずあくびしたところ,その場にいたBさんが思わず釣り込まれてあくびするという現象や,「もらい泣き」,つまりAさんが泣いてしまい,その様子を見ていたBさんまで思わず感涙するという現象を,コミュニケーション行動として認められない。この理論の前提には「人間は目的を達成するために,状況に応じてスタイルを変える。スタイルは状況に応じて変わるが,人間じたいはどんな状況下でも(病理的な多重人格にでもならないかぎり)変わらない」という,伝統的な人間観がある。これまで述べてきたように,キャラクタという現象は,この伝統的な人間観では受け入れられない。
こんなことを私に言われて,参加者たちがカンカンになって怒ったかというと,どうもそんなことはないようだ。というのは,ワークショップ終了後に,私は,リュブリャナ大学が発行している英文オンラインジャーナルACTA LINGUISTICA ASIATICAで「キャラクタ」の特集号を組まないかというお誘いをいただいたからだ。この雑誌が出るのはもう少し先だが,私自身だけでなく,いろいろな方々に論文投稿をお願いしたので,ぜひご覧いただければと思う次第である。