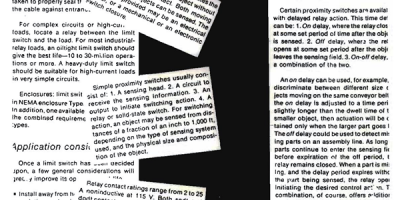学生:お金、おろし、“きんこう”に行きました。
教師:ああ、“おかねをおろしに”“ぎんこう”に行ったんですね。
学生:はい、“きんこう”に行きました。
(教師:“砂金”でも集めてきたんかなぁ……)
という会話があったとする。教師が“ぎんこう”と言っているのに、学生は二度目も“きんこう”と言っていることについて、いくつかの解釈が可能である。
一つは、教師の“ぎんこう”という発話が学生には“きんこう”に聞こえている場合。二つ目に教師の“ぎんこう”を“ぎんこう”と聞き取り、自分の発音が正しくなかったことに気づきながらも“ぎんこう”と発音できない場合。三つめは、教師が、“さりげなく正しい形にした返事”(リキャスト[recast])をしたことに気づかなかった場合である。(まだほかにもあるかもしれない。)
一つ目は聴覚音声学[auditory phonetics]の問題であり、二つ目は調音音声学[articulatory phonetics]の問題である。いずれも日本語の音声の習得の問題だといえる。三つ目のリキャストのケースは次回以降に回すとして、ここでは音声と文法(統語:うんと簡単に言えば語順の習得)の問題に触れたい。
音声の習得は一定の年齢を過ぎると難しくなることが多いようである。あることがらの習得に最も適した時期を臨界期[critical period]というが、第二言語の習得についていえば、習得に適した年齢を過ぎると母語話者のレベルに到達するのが難しくなるということであろう。第二言語習得の臨界期については、さまざまな条件で研究がされており、一定の見解が得られているとは言えない。しかし、音声の習得と文法の習得については臨界期の存在を指摘する研究が少なからずあるのに対し、語彙についてはその数が少なく(長谷川2008)、語彙習得には年齢の上限がないとするものもある(例えば Singleton, 1998)。少なくとも語彙に関しては自分の得意分野を作れば母語話者に勝ることができる。
ここに「言語教育の民主化」を考えるヒントがある。つまり母語話者教師が母語話者の特権的な地位に安住して非母語話者である学習者に対して力を振るうような教育(例えば「きんこう」を厳しく「ぎんこう」に直そうとするような教育)を回避するヒントがあるということである。音声や文法に力を入れすぎると、母語話者と非母語話者の違いが前面に出やすい。音声や文法のモデルは、意識、無意識を問わず、母語話者のものとされていることが多いからである。それに対して語彙は、直接に意味を担っており、どのような語彙を使うかには学習者一人ひとりの個性が出せる。音声や文法が少しぐらいできていなくても、自己表現することで、母語話者との間でも対等な人間関係を築けるのである。例えば専門的なコンピュータの知識を、不正確な音声と文法で説明されたとしても、内容がきちんと理解できれば、おそらくその人はコンピュータの専門家として尊敬されるであろう。
誤解のないように述べると、音声や文法の習得が不要だと言っているのではない。ただ、今の(日本国内の)日本語教育は全体的に初級で文法項目に力を入れすぎている感じがする。もう少し初級から自己表現や生活場面のための語彙に力を入れてもいいように思われる。「お金、おろす」と言われれば“きんこう”ではなく“ぎんこう”に行ったことがすぐわかるというように、文脈を補うことで発音や文法が不正確なのを補うことができる。それも語彙の力だといえる。
現在、日本国内の日本語教育では文法を基本にしたシラバス構成の初級教科書が多い。そこで取り扱われる項目は、順序こそ多少前後しているが、概ね似ているものが多い。しかし、世界のさまざまな日本語教科書を見ると、語彙についてはかなりバリエーションがある。すべての学習者に必要な初級語彙は文法や音声に比べてかなり限られたものであるように思われる。その学習者が必要とする語彙を学習すればいいのであり、それは日本語を使う場所、年齢、目的などによって、相当に違ってくるはずである。
引用文献
Singleton, D. (1998). Age and the second language lexicon. Studia Anglica Posnaniensia, 33: 365-376.
長谷川朋美(2008)「第二言語習得における臨界期仮説・年齢要因―日本語を対象とした研究に向けて―」日本言語文化学研究会増刊特集号編集委員会編『第二言語習得・教育の研究最前線 2008年版』凡人社