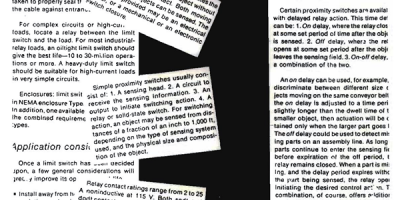コミュニケーションにはさまざまな「力」が働く。それが悪い形で現れると「言いたいことが言えない」ことになる。それは多くの場合、言語教育にはマイナスだ。
教育の場にはたいてい先生がいて生徒がいる。先生は社会的に「力」をもつ「成績」をつける立場であることが多い。そのような力は教育の場から質問・議論や対話を奪う原因になる。頭が悪いと思われたらどうしよう、成績が悪くなったらどうしよう、と萎縮したら発言できなくなるだろう。
知識や技術を持っていること自体が力だとも言える。例えば、原発のことを知りたいと思って、原子力工学の専門家に尋ねるとする。そこでいろいろと説明を受けても、専門家でなければ、それが正しいかどうかを評価できない。つまり知らない人間は、質問はできても議論はむずかしい。
私の専門である日本語教育の現場にも、一つの見過ごせない「力」がある。それは「母語話者性」である。「日本語では△△とは言いません。○○と言います」という訂正は、ある程度避けて通れないが、やりすぎると学習者は縮んでしまう。多くの場合、学習者は教師の知識を評価することができないので、教師の言うことは絶対であり、それに従うしかない。
日本語母語話者の日本語教師が、第二言語としての日本語[Japanese as a Second Language: JSL]の教育に、日本で従事する場合は特に注意が必要である。周りの多くが日本語母語話者であり、学習者は言語的少数者(マイノリティ)である。自分の言っていることは何か間違っているんじゃないかと、知らず知らずのうちに、常に意識するようになりやすい。また、生活や学習のために日本語が不可欠な環境であることが多く、日本語の正誤に敏感にならざるを得ない。敏感であることはある意味で必要だが、敏感になりすぎると萎縮する。教師によるマイノリティ心理への配慮が不可欠なのである。「日本語では△△とは言いません。○○と言います」あるいは、「日本では△△のようなことはしません。○○のようにします。」を言うべきかどうか、相手の顔を見て判断する能力が必要なのである。
日本以外の場所で外国語としての日本語[Japanese as a Foreign Language: JFL]を教える場合、日本語母語話者の教師が教えていても、教師のほうがその土地では言語的・文化的に少数者であることが多い。例えば、中国で日本語を教えるとすれば、中国のことは学習者のほうがよく知っている。教室での話題が日本のことになれば教師のほうがよく知っていることが多いが、そのような話題になっても学習者が萎縮することは少ない。マイノリティが感じやすい心理的圧力がないからである。日本語が上達しなくても今日、明日の生活に困ることはない。教室では、教師対学生という力関係と多数者(マジョリティ)と少数者(マイノリティ)の力関係のバランスがとれる。
このようなマイノリティ心理への配慮は、言葉の通じにくい、なじみのない土地で現地になじむ努力をして生活した経験を持つ人には理解しやすい。その土地の言語を学ぶ努力をして、上級レベルまで学んだ人であればなおさらである。失敗が続けば、たいていの人間はへこむ。日本語が通じないところで、その土地のことばを、非常な緊張感を持って使った経験のある人も多いのではないだろうか。日本語教師には日本語をよく知っていることも必要だが、母語以外の言語の学習経験(特にうんと格闘して上級レベルまで頑張った経験)もまた、学習者心理の理解という点において大きな利点なのである。
次回はこのようなマイノリティ心理を緩和して、民主的な言語教育を実現するには語彙学習が大切だということを述べたい。