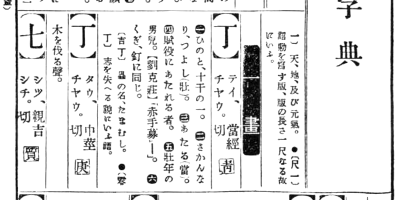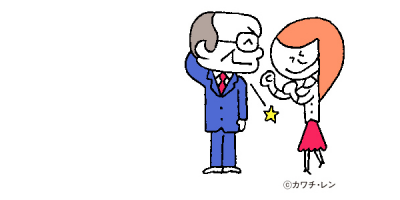儒学の伝統に根ざした学術の検討が続きます。
知は其の上向を知るのみならす、又其の下向を知らさるへからす。善を知るときは又其害を知るか如き、表裏兩なから之を知らさるへからす。
(「百學連環」第15段落第1~2文)
訳します。
知については、上に向かう場合を知るだけでなく、それが下へ向かう場合についても知らなければならない。例えば、「善」について知るのであれば、同時に「害」についても知るようなもの。〔知の〕表裏を両方とも知るのでなければならない。
知について「上向」「下向」とはどういうことか、と思って読んでゆくと、「善」と「悪」の例が持ち出されます。西先生は、ことさら「上向」と「善」、「下向」と「悪」と対応させているわけではありませんが、語の並び順からいってもそう対比させてよいでしょう。
ここでもまた上下という垂直方向の区別が現れています。そういえば『論語』には「上知」「下愚」といった対語もありました。どちらかと言えば上方向は優れたもの、価値の高いものを、下方向は劣ったもの、価値の低いものを意味している様子が窺えます。
これまでよく検討してみたことがなかったのですが、古今東西のさまざまな文化において、上下に対するこうした価値づけはどんなふうになされてきたのでしょう。例えば、天上にある天国と地下にある地獄。王座は高きにあったり、上座下座も「上>下」という優劣観を前提にしています。なぜ上が優れ、下が劣るという対応になるのか。たいそう気になるところですが、ここでは措きます。
さて、西先生の例に則って言えば、知については、善いことだけ知ろうとしても足りないのであって、同時にその反対とされる悪いことについても知るべきであるというわけです。
もう一つ例を出しましょう。ときどき、ものを知るらしい人物が「Xはよくないから読まないほうがいい」と学生や若人にアドヴァイスしているのをお見かけします(Xには任意の人名や書名が入るとお考えください)。
これは一見すると親切な助言です。助言の主は、ひょっとしたら自分でXを読んでみて、「ああ、こりゃダメだ。こんな本に付き合うのは、おおいなる時間と手間の無駄だ……」と感じた経験があるかもしれません。そうした自分の実感を込めて、まだそれを体験していない人に向けて、上のようなアドヴァイスをしたというところでしょうか。
でも、こういう場合、助言を受け取る側としては、ちょっと立ち止まってみる必要があります。もしこの親切な助言を鵜呑みにして、「そうかXはよくないのか。じゃあ読まずにおこう」と思い込む学生がいるとしたら、よほどおめでたいことです。学術の徒としては、かえって問題でしょう(先達の言うことをよく聞いてエライと誉められるかもしれませんが……)。なぜなら、自分の眼や頭で現物を確認することなく、伝聞や他人の下した評価で価値判断をしてしまおうというわけですから。他の場合はともかくとして、学術の領域においては致命的です。
この場合、「そうか、Aさん〔助言主〕はそう感じたのか。どれ、実際のところはどうだろう。自分の眼で確かめよう……」と考え、実践することのほうが、学術の取り組みとしてはよほど大切です。その上で、現在の自分はどう判断するかと考えてみればよいわけです。
西先生はここで、「知は広いほうがよい」というここまでの主張の意味を敷衍しています。ともすると、人はよい(とされる)ものだけを知りたがり、悪い(とされる)ものを知りたがらない。そういう傾向に対して警告を発しているようにも読めます。「よいもの」だけを知ろうとする態度は一見合理的ですが、「悪いもの」との対比でこそ、いっそう「よいもの」のことが判るし、逆も真なりであることを考えると、本当に「合理的」かどうか怪しくなってきます。
ここで西先生が例に採っている善し悪しという価値判断は、相対的なもの(状況によって変化しうるもの)だけにいっそうのこと対比や比較が重要になります。なぜなら、よりよく比較するためには、新旧も含めた広い知を視野に収めて検討せよというのが西先生の持論だからです。
そう考えると、先のAさんの「助言」は、果たしてよい助言たり得ているのか。むしろAさんは、学生にこう言ったほうがよかったのではないでしょうか。「私はXについて、とてもよいとは思えない。でもそれはそれとして、君も自分で読んでごらんよ。なにがダメかを実感できれば、自分がその愚を繰り返さないためのよすがにもなるからね。それに、どうかしたら、こう言っている私の判断のほうにこそ問題があるかもしれないのだから」と。