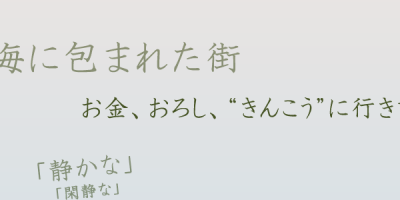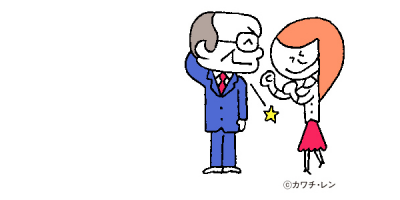味覚表現についてこれまで引き合いに出したのは,おもに食卓での会話,エッセイ,そして,グルメ漫画というテクストでした。味のことばに関する考察の最後は,味覚表現の華,小説のことばで締めくくりたいと思います。
まずは,以前にも取り上げた『ショコラ』の例です。目の前にあるチョコレートに「つまんで。ためして。とろかせて」とささやきかけられていると感じた登場人物は,思わずそのチョコレートを口にしてしまいます。翻訳は私の手によるものです。オリジナルの英語については第32回を参照ください。
(66) これは明らかに違う。チョコレートの殻は唇が触れるとわずかに抗い,そして柔らかなトリュフがとろけ出る……上品なワインが薫るように味わいが幾重にも重なり,かすかな苦味と挽き立てのコーヒーの芳醇さをもたらす。温められて香りはいっそう引き立ち,鼻腔を豊かに抜けてゆく。悪魔の味わいに身が悶える。 (ジョアン・ハリス『ショコラ』)
チョコレートが口に含まれて,その香りが鼻先に悩ましく抜けていく様子が,細やかにそしてややエロティックに綴られていきます。味覚の表現としてはとても饒舌な部類に入るでしょう。

しかし,『美味しんぼ』のときに感じたような不自然さや過剰感は感じられません。なぜでしょうか。
もうひとつ例を見ておきましょう。岡本かの子の短編「食魔」から採りました。少し長い引用になります。このくらい長いほうがいいと思います。ちなみに,アンディーブ(チコリー)は写真にあるようなキク科の野菜です。
(67) 「食って見給え」
[中略]
鼈(べつ)四郎(しろう)はフォークを妹娘の胸さきへ移した。
お絹は滑らかな頸(くび)の奥で、喉頭をこくりと動かした。煙るような長い睫(まつげ)の間から瞳を凝らしてフォークに眼を遣り、瞳の焦点が截片に中(あた)ると同時に、小丸い指尖(ゆびさき)を出してアンディーヴを撮(つま)み取った。お絹の小隆い鼻の、種子(たね)の形をした鼻の穴が食慾で拡がった。
アンディーヴの截片はお絹の口の中で慎重に噛み砕かれた。青酸(あおずっぱ)い滋味が漿液(しょうえき)となり嚥下(のみくだ)される刹那に、あなやと心をうつろにするうまさがお絹の胸をときめかした。物憎いことには、あとの口腔に淡い苦味が二日月の影のようにほのかにとどまったことだ。この淡い苦味は、またさっき喰(た)べた昼食の肉の味のしつこい記憶を軽く拭き消して、親しみ返せる想い出にした。アンディーヴの截片はこの効果を起すと共に、それ自身、食べた負担を感ぜしめないほど軟く口の中で尽きた。滓というほどのものも残らない。
「口惜しいけれど、おいしいわよ」
お絹は唾液がにじんだ脣(くちびる)の角を手の甲でちょっと押えてこういった。
ここでも食材が口中でもたらす味の移ろいが記されます。「淡い苦味が二日月の影のようにほのかにとどまった」「軟く口の中で尽きた。」繊細に,しかし,しっかりと,味の痕跡がことばにとどめられます。美味の表現がもっとも生き生きと立ち現れるのは,やはり小説だと思います。
留意すべきは,小説の味覚表現はそれなりに饒舌であるにもかかわらず,グルメ漫画のような不自然さや過剰感を感じないところです。
グルメ漫画の表現にはグルメ漫画特有の事情がありました。読者に対して味覚を伝えるという巨視的な要請を背負った登場人物は,過剰であろうと読者に説明をせねばならなかったわけです。しかし,登場人物同士の会話という微視的レベルで眺めると,つまり,日常の食卓のことばの基準に照らし合わせて考えると,その表現は説明が勝ちすぎて過剰に感じられます。
小説の味覚表現にも読者に味覚を説明するという巨視的要請がかかっているはずです。それでも説明くさくならないのには,小説言語に特有の理由が存在するはずです。
それは何か,次回以降で考えていくことにしましょう