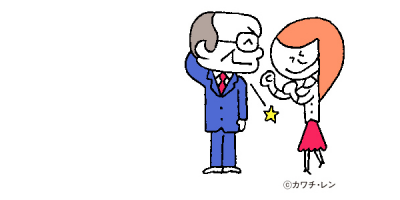「城の崎にて」は次の一節からはじまります。なお,分析に当たって『志賀直哉全集』(岩波書店)を参照しましたが,ここでの引用は,読みやすさの便を考えて岩波文庫から採りました。ルビは少し減らしてあります。
(80) 山の手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした、その後(あと)養生に、一人で但馬(たじま)の城崎温泉へ出掛けた。背中の傷が脊椎カリエスになれば致命傷になりかねないが、そんな事はあるまいと医者にいわれた。二、三年で出なければ後は心配はいらない、とにかく要心は肝心だからといわれて、それで来た。三週間以上――我慢出来たら五週間位いたいものだと考えて来た。 (編集部注:ルビは実際には傍ルビ)

冒頭の文章は,淡々と畳み掛けます。前文の内容を少しずつ重ねながら,次の文に移ります。述語だけ取り上げると,(けがをした養生に)「出掛けた」,(けがをしたから)「と医者にいわれた」,「といわれて、それで来た」,「と考えて来た」。次々にリズムよく重ねられた文章は,ゆっくりと静かに時間が流れる物語本体部分に比べると,あわただしく感じられます。
城崎での滞在について語る本体部分では,語り手はじっと静かに生と死を見つめます。それとは対照的なこの冒頭(と最後の終幕)の文章は,あたかも城崎へ至るまでの(そして城崎からの)移動(旅行)のあわただしさを表しているかのようです。ここはせかせかとあわただしさが感じられるくらいのほうが,後の静けさが引立つのかもしれません。
なかでも最初の一文が目を引きます。通常,「山の手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした、その後養生に、」というふうに読点で連ねるかたちでひとつの文にするでしょうか。句点でふたつの文に区切るか((81a)),「怪我をした」ことを名詞節のかたちで「(後の)養生」に修飾させる((81b))のが,普通のつなぎ方ではないかと思います。
(80) a. 跳ね飛ばされて怪我をした。その後養生に、 b. 跳ね飛ばされて怪我をした(後の)養生に、
ところが志賀は,「怪我をした、その後養生に」と軽く読点による小休止を置くだけで,次の節(「その後養生に、一人で但馬の城崎温泉へ出掛けた」)をつなぎます。「怪我をした」は形式的には終止形か連体形なのに,文がそこで終わるわけでもなく,体言に連なるわけでもありません。句点と読点の使い分けに厳密な規則は存在しないので,破格とまでは言えないかもしれませんが,通常のつなぎ方からは外れています。
なぜ,このようなつなぎ方をしたのでしょうか。
(81a) のように,「跳ね飛ばされて怪我をした。」と句点で文を切ってしまえば印象はどう変わるしょうか。電車に跳ね飛ばされたのなら大事故です。小説とは言え,読者の心はその事件性の大きさに動きます。友人に「電車に跳ね飛ばされたんだ」と言われたら,「えーっ,うそー,ちょっと待ってそれマジで」とあわてふためいた対応にならないでしょうか。それと同じことです。読者の心は,いきなりこの事件に,そしてこの事件のみに奪われてしまいます。
しかし,電車にはねられて死の危険に直面したことに対する意味付けは,物語中盤のネズミが必死に死を逃れようともがく様子を目撃するところで行われます。だから,事故のてん末や評価については,あらかたの事情を与えるだけで淡々と話を進めてゆきたい。そこで,読点を挟むだけで,やや強引に次の「その後養生に」へとつなぐわけです。読者に有無を言わせぬ展開をするために,ここは句点でなく,読点でなければならないのです。
他方,(81b) のように,体言のなかに押し込んでしまうと,電車事故のことを(読者にとっては既知の)前提として扱う度合いが強まります。しかし,読者にとって事故のことはまったくの新情報ですので,この言い方もふさわしくありません。
つまり,第1文は (81a) や (81b) のような形式をとれないのです。第1文のかたちは動かせません。
「城の崎にて」の冒頭部は,いわば絵画の額縁の部分に当たります。作品全体からすると重要性は低い。しかし,そのような部分にも作者の細やかな注意と意図が息づいています。
「城の崎にて」の文章と言えば,谷崎潤一郎が『文章読本』でほめたたえたハチの飛翔の記述が有名ですが,この冒頭の文章だってそう簡単にまねできるものではないと思います。