先日、日本語学会の仕事で沖縄県に出かけてきた。宿を那覇市内に取ったのは、交通の便だけでなく、「那覇」について調べたいことがあったからだ。
地名を語としてみた場合、「なは」(那覇)が沖縄の「なわ」と実は同源らしい。また琉球方言で那覇は「ナーファ」と発音されるなど、興味深いことはあるが、この目で知りたかったのは漢字についてである。「覇」には、月の暗い部分(*1)という不思議な意味をも持つらしい、といったことも面白いが、現地で確かめたかったのは、その字体についてである。「那」の左の「二」が『康煕字典』(*2)にあるように右の縦線を貫くかどうか、「覇」が旧字体の「雨」冠や「襾」となっているか、といったことは、現地に行かずとも結果が想像できる。
かつて、読売新聞の記者たちが漢字の実態とその背景を必死に追いかけた記録がまとめられている。『日本語の現場』という、1970年代なかばに刊行されたシリーズだが、そこには日本語学(当時は国語学と呼ぶことが主流だった)とは無縁という記者たちの奮闘の軌跡が、その時代の息吹とともに収められている。そこに、日本復帰から間もない沖縄県の那覇では、「覇」の字体が独特に省略されるという現象が指摘されていた。「革」の部分を「関」の門構えを取り除いたように書くという略字「 」である。いかなる漢和辞典にも国語辞書にも収められていない、沖縄でしか見られない地域限定の略字であった。こうした地域に顕著な漢字は実は方々に見つけることができ、それらを私は「地域文字」と呼んでいる(*3)。
」である。いかなる漢和辞典にも国語辞書にも収められていない、沖縄でしか見られない地域限定の略字であった。こうした地域に顕著な漢字は実は方々に見つけることができ、それらを私は「地域文字」と呼んでいる(*3)。

今回、沖縄に滞在した4日間では、この字体は辛うじて数例を街中で観察できた【写真1・2】。ほかには、60歳くらいのタクシー運転手が領収書に乗車区間として書いた字に見つけることができた【写真3】。年配の方にだけ使用習慣が残っているようで、近年だいぶ減ってきている。地域社会の方言が若者に受け継がれず、地域で全国共通語が浸透しつつある現象を「共通語化」と呼ぶが、漢字にもいわば「共通字化」が進展しているわけである。

【写真1 那覇市内にて】

【写真2 那覇市内にて】

【写真3 タクシーの領収書1】
これが、那覇特有の現象ではないことは、これからこの「漢字の現在」の連載で明らかにしていきたい。景観のうえでも、どこの地方都市も東京と見紛うようになり、地方の田園風景もだいぶ様変わりしつつあるが、それと同様に、伝統的な方言も次第に消えつつある。さらに地域色豊かな地域文字は、さほど注目されることもなく、消滅に向かっているのである。ひとたび書けば地域文字も筆跡として残り、他者の目に入る可能性があるのだが、その存在のユニークさ、いやその存在自体に気付かずに過ごす人は、地元でも少なくない。
「覇」は、戦後の当用漢字に含まれていなかったが、1981年に新たに常用漢字に採用され、種々の活字メディアや教育の場で採り入れられたことが、若者の地域文字離れに拍車をかけたのである。さらに、街中で、パソコンで容易に打ち出せるようになった各種のフォントが、手書き文字に替わって看板に進出していることも、地域文字の衰微に追い打ちをかけたといえよう。


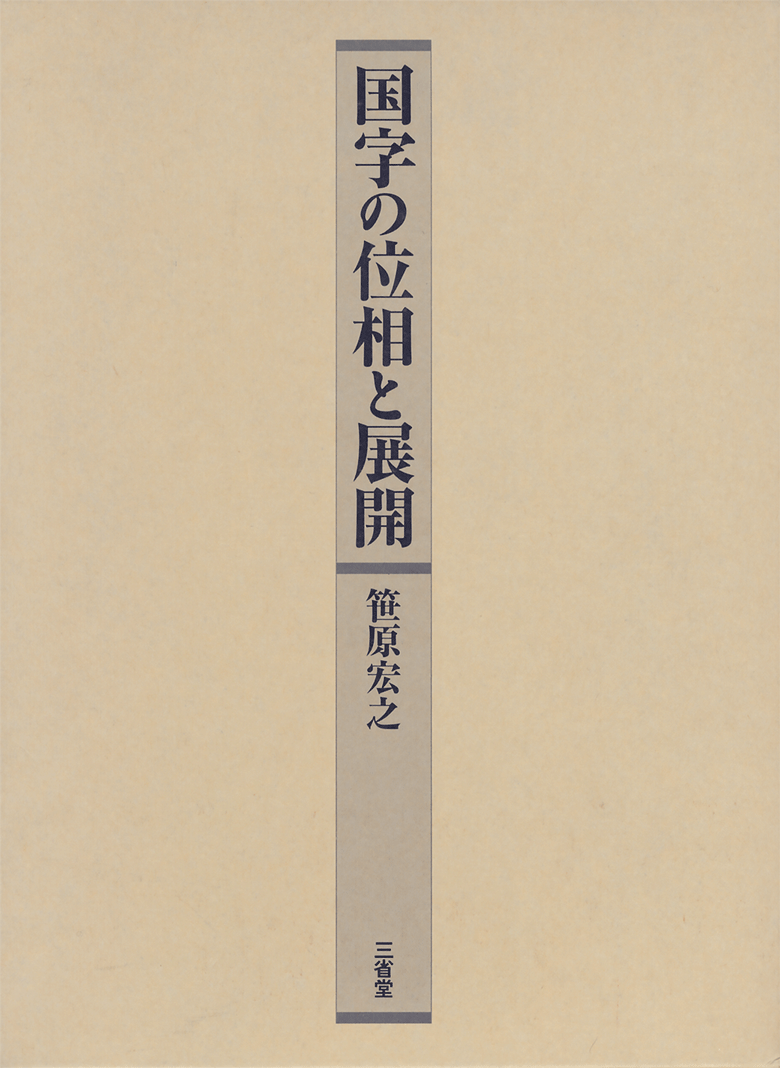
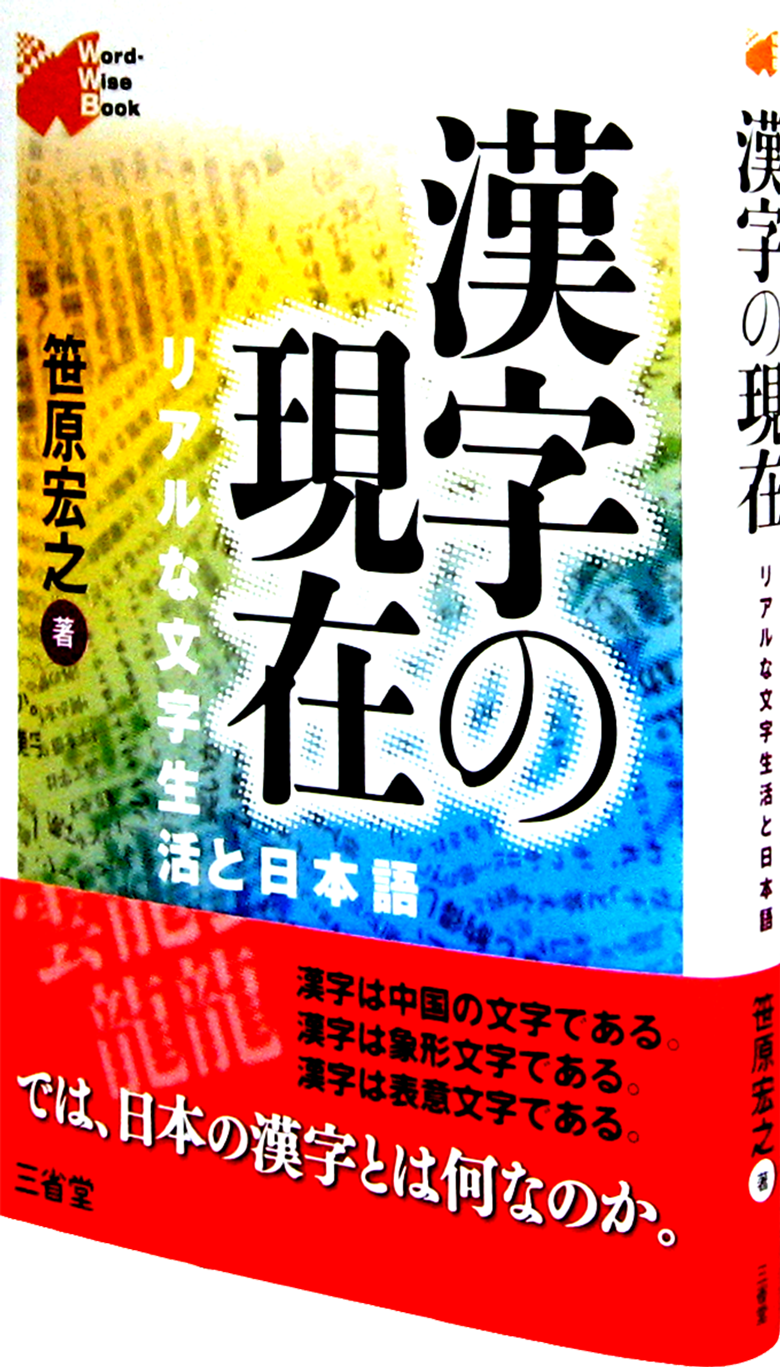




【注】