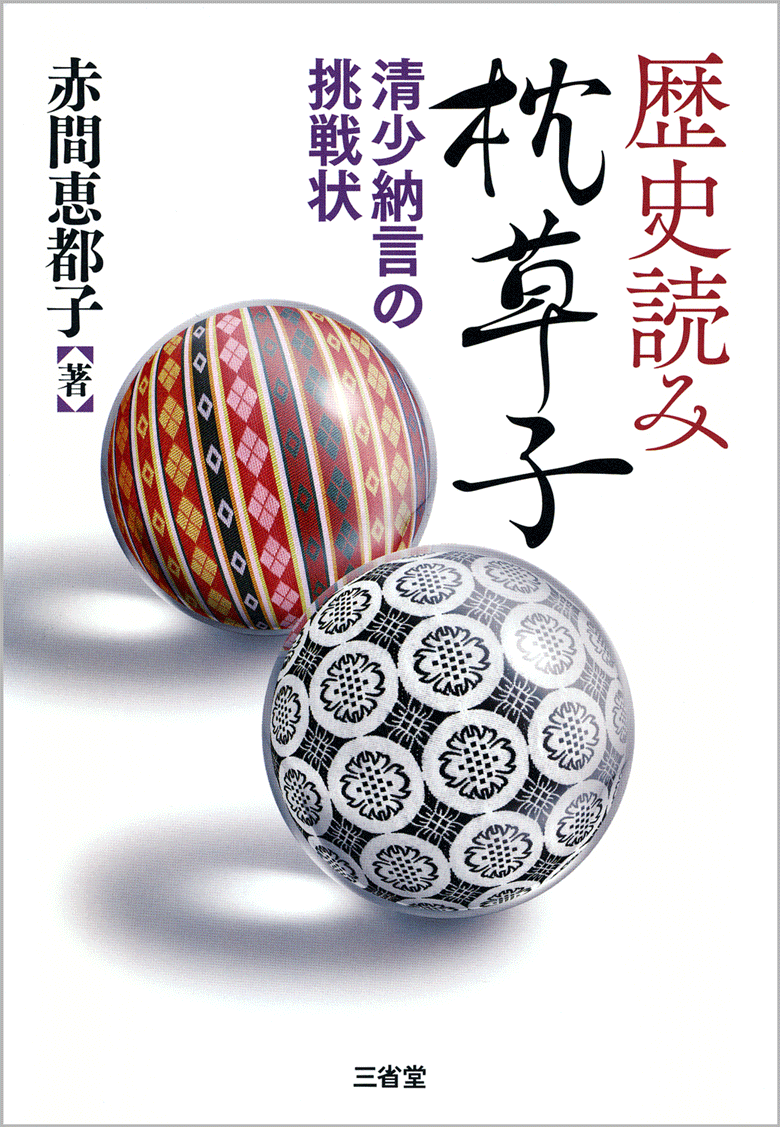『枕草子』には、清少納言が宮仕えする前の出来事で、宮中に語り伝えられていた話がいくつか書き留められています。その中の一つ、村上天皇に仕えていた兵衛の蔵人という女房のエピソードを紹介しましょう。
村上の先帝の御時に、雪のいみじう降りたりけるを、様器に盛らせたまひて、梅の花をさして、月のいと明かきに、「これに歌よめ。いかが言ふべき」と、兵衛の蔵人に給はせたりければ、「雪月花の時」と奏したりけるをこそ、いみじうめでさせたまひけれ。「歌などよむは世の常なり。かくをりにあひたる事なむ言ひがたき」とぞ仰せられける。
(先の村上天皇の時代に、雪がたくさん降っていたので、天皇がそれを容器にお盛らせになり、梅の花をさして、月が大変明るい時に、「これに歌を詠みなさい。どのように言うのがふさわしいかな」と、兵衛の蔵人にお渡しになった時、「雪月花の時」と申し上げたのを、たいそうお褒めになりました。そして、「歌など詠むのは世間なみである。このような折にあった事はなかなか言えないことだ」と仰せになりました。)
さて、『枕草子』にはこの逸話とそっくりな話がもう一つあります。ただし、配役が一条天皇と清少納言に代わります。ある日、宮中の殿上の間から花の散った梅の枝を持った使者が来て、「これはいかが」と言ってきたので、清少納言が漢詩の詩句を利用して答えたところ、一条天皇がお聞きになって、「並みの和歌などを詠んで出すよりずっと優れている。よく答えた」と仰せになったというものです。
まるで清少納言が兵衛の蔵人を演じたような、こんな逸話が記されたのはなぜでしょうか。
ここで、当時の文化的時代背景について、少し考えてみましょう。905年に醍醐天皇の命令で、最初の勅撰和歌集である『古今集』が編纂されました。それまでは、先進国中国の文学である漢詩が公的文学として認められ、男性貴族たちの間で詠まれていたのですが、『古今集』によって、和歌も宮廷文化の表舞台に立ったことになります。仮名文字を使う女性貴族たちにも流行した和歌は王朝文化の中心的存在となりました。
この醍醐天皇の時代と共に、延喜・天暦の治として称えられたのが村上朝でした。村上天皇は一条天皇の祖父にあたり、その文化的逸話は、身近な王朝文化の模範として定子後宮でも大いに語られていました。前回紹介した、村上天皇女御芳子の『古今集』暗誦の逸話はよく知られています。また、二番目の勅撰和歌集である『後撰集』編纂を下命したのも村上天皇でした。
このような観点から見ると、兵衛の蔵人の逸話は、和歌文学隆盛の時代に、和歌で答えるべき場面で漢詩を即答して公に認められたことを語るものであり、時代の流れと逆行していることになります。その逸話をさらに清少納言自身が演じるのは、それが作者個人の問題に関わるからではないかと考えます。
なぜなら、清少納言の父清原元輔は『後撰集』の撰者の一人だったからです。つまり、清少納言は村上朝で活躍した人物の娘という大看板を背負って宮廷入りしたのでした。そのため、宮仕え当初から定子や伊周に興味を持たれ、宮中の注目を一身に集めていたのです。清少納言も自らの立場を十分に自覚しており、家名を汚すまいという思いが強かったようです。漢詩による応答を正当化する逸話の中には、並みの和歌を答えるくらいなら何も言うまいという作者の自意識が働いていると考えられます。そもそも『枕草子』が歌集ではなく散文体の作品であること、作品中に歌枕や歌語を扱いながら、その盲点を突いたり言葉遊びに傾いたりすることも、束縛されていた和歌世界からの作者の脱出願望の表れだったのかもしれません。