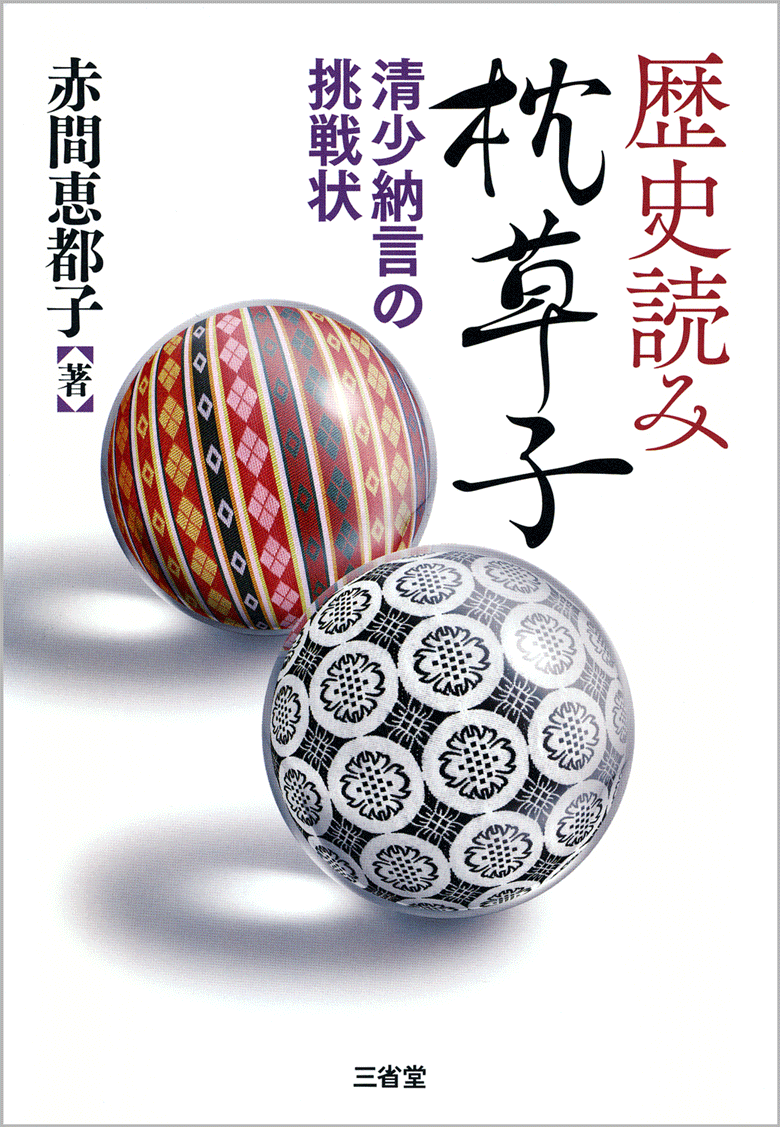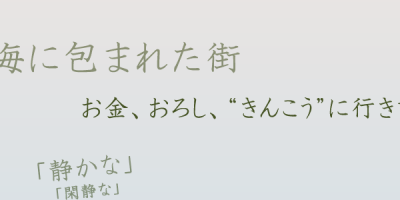長徳2年という年に中宮定子が経験した様々な悲愴な事件についてお話ししてきました。それは、清少納言が宮仕え生活を始めた正暦年間には、誰も考えもつかなかった事だったと思います。中関白家の栄華を描いてきた『枕草子』に、長徳の変前後の定子の悲劇を直接描写する記述はありません。敬愛する主人の悲劇に直面して、作者はどのように感じ、何を考えていたのでしょうか。
実はこのころ、清少納言の身の上にもこれまでにない事態が発生し、長い間里下がりしていたようなのです。宮仕え生活の中で、清少納言もそれまでに何度か里下がりをしたことはありました。そんな時は、すぐに定子から出仕要請の手紙が届き、大急ぎで定子の許に戻っています。しかし、今回の里居はそう簡単に戻れる状況ではありませんでした。この時の清少納言の里居を扱った章段は次のように始まります。
殿などのおはしまさで後、世の中に事出で来、さわがしうなりて、宮もまゐらせたまはず、小二条殿といふ所におはしますに、何ともなくうたてありしかば、久しう里にゐたり。御前わたりのおぼつかなきにこそ、なほえ絶えてあるまじかりける。
(殿様がお亡くなりになった後、世間で事件が起こり、騒がしくなって、中宮様も宮中に参内なさらず、小二条殿という所にいらっしゃる時に、私は何となくうっとうしい事があって、長い間里に下がっていました。中宮様の周辺がとても心配な時に私が出仕しないなど、あってはならないことだったのですが。)
冒頭に関白道隆薨去後から長徳の変にかけての歴史的背景に言及する章段は、『枕草子』でこの段だけです。さらに興味深いのは、歴史資料に見えないこの時期の定子の居場所が、「小二条殿」と記されていることです。二条邸を焼け出された定子が、記録類に再び居場所を記される長徳3年6月までの約1年間をどこでどのように過ごしていたのか、さまざまに推測されていますが、今のところよく分かりません。ただ、『枕草子』に見える「小二条殿」の記述からは、二条近辺の小さな家に居場所を定めて謹慎生活を送っていた定子の様子が想像されます。そして清少納言は、そんな中宮定子のことを心配しながらも、宮仕えに嫌気がさして里下がりしていたというのです。里居の原因について、作者は次のように語っています。
げにいかならむと思ひまゐらする御けしきにはあらで、候ふ人たちなどの、「左の大殿方の人知る筋にてあり」とて、さしつどひ物など言ふも、下よりまゐる見ては、ふと言ひやみ、はなち出でたるけしきなるが、見ならはずにくければ…
(本当に私のことをどのようにお考えだろうと思い申し上げる中宮様のご様子ではなくて、お仕えする女房たちなどが、「(清少納言は)左大臣殿側の人と知り合いだ」といって、寄り集まって話していて、私が下局から参上するのを見ると、ぴたりと話を止め、仲間外れにしている様子がこれまでになく不快なので…)
長徳2年の不穏期は、中関白家の外部から中傷する者、内部から離反する者などが出て、定子を取り巻く女房たちの雰囲気もピリピリしていたことでしょう。そのような状況の中で、清少納言は疑心暗鬼にとらわれた女房たちから爪弾きにされてしまったのです。定子の気持ちを懸念していることから考えると、清少納言が疑われるような何らかの出来事があったのかもしれません。『枕草子』には藤原道長や道長の従弟にあたる源経房が登場し、親近感を持って描かれていますが、清少納言の彼らに対する何気ない言動が増長され、同僚女房たちの憶測を招いたとも考えられます。
清少納言が定子の御前に参上すると、それまで集まって話をしていた女房たちがピタリと口をつぐんで、知らんふりをする。そんなことが度重なると、どんなに気丈な性格でも、気が重くなっていくのは当然でしょう。女ばかりの集団内で、現代にもよくありそうなイジメですね。清少納言は初宮仕え生活の中で、初めて危機に直面したのです。