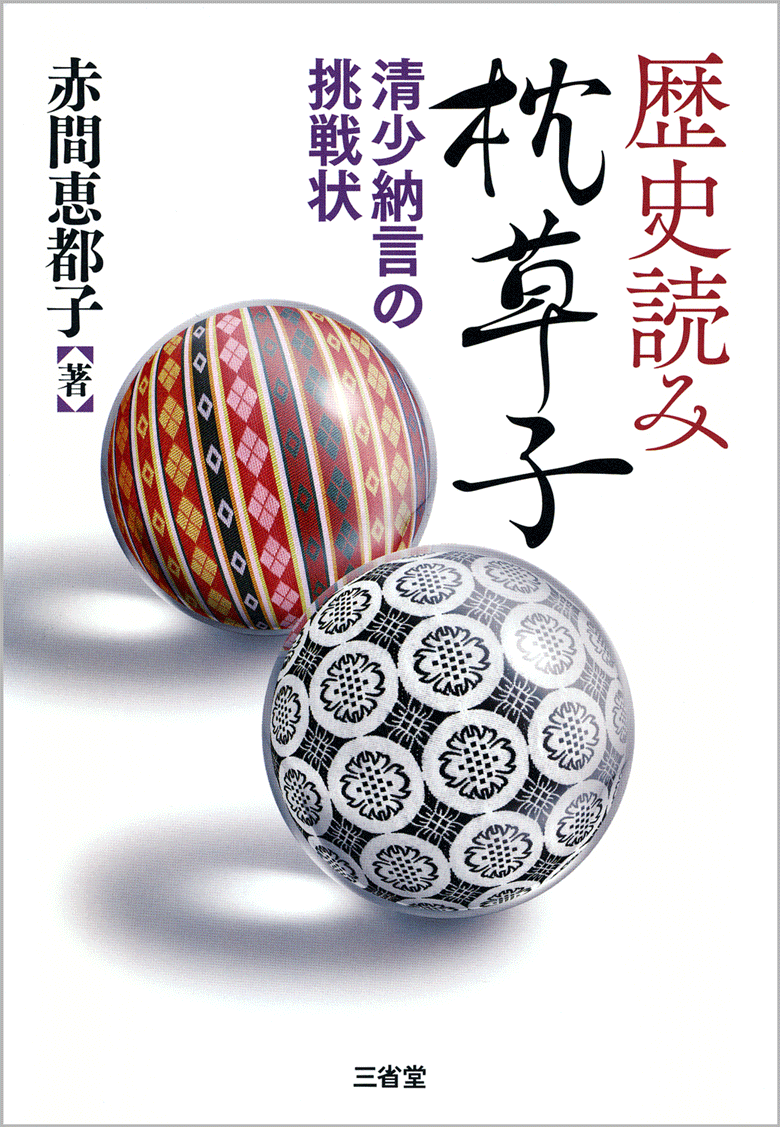長徳2年の清少納言の里居は、その背景に政治的問題が絡んでいたため、長期にわたりました。清少納言が里下がりをすると、普段ならすぐに出仕要請の手紙をよこす中宮定子も、長徳の変直後の悲痛な日々を送っていた最中でした。前回お話した「殿などのおはしまさで後」の段では、「例ならず仰せ言などもなくて、日ごろになれば(いつもと違って中宮様からのお言葉もなくて、何日もたったので)」と書かれていますが、それは定子が置かれていた状況を考えるとやむをえないと思います。
定子のことを心配しながらも出仕できずにいた清少納言の里居先を、右中将源経房が訪ねてきます。経房は清少納言と親しく、道長にも近い人物です。一方、安和の変で左遷された源高明(みなもとのたかあきら)の四男で、没落貴族の悲劇を身をもって体験した人物でもあります。彼は中宮御所を訪問した後に清少納言の所へ来たようで、定子サロンからの伝言を携えていました。
今日、宮にまゐりたりつれば、いみじう物こそあはれなりつれ。女房の装束、裳、唐衣をりにあひ、たゆまで候ふかな。御簾のそばのあきたりつるより見入れつれば、八,九人ばかり朽葉の唐衣、薄色の裳に、紫苑、萩などをかしうてゐ並みたりつるかな。…
(今日、中宮様の御殿に参上しましたら、非常にしみじみとした風情でした。女房の装束は、裳や唐衣が季節に合っていて、気を緩めずにお仕えしていましたよ。御簾の傍らの開いている所からのぞいたところ、八,九人ほどの女房が、朽葉の唐衣、薄色の裳に、紫苑や萩などの襲(かさね)の袿(うちき)を着て、趣のある様子で並んで座っていたことですよ。…)
女房たちが季節に合わせて身につけている朽葉や紫苑、萩などの着物の色目は秋のもので、時節が秋であることを示しています。女房たちはわざと簾の端を開けて、経房に自分たちの怠りない装束姿をのぞかせたのでしょう。経房の報告は続きます。中宮御所の庭の草が生い茂っているので、「どうして、手入れしないのか」と尋ねたところ、「わざわざ露を置かせて御覧になっているのだ」と宰相の君が答えたこと。さらに、「こんな場所に中宮様がお住まいの折には、清少納言は必ず伺候するはずと思っていらっしゃる甲斐もなく、どうして出仕しないのか」と女房たちが言っていたことです。
中宮御所だというのに、雑草が伸びて荒れたままの庭。おそらく手入れする人手がないのでしょう。それを指摘され、不遇を嘆いたり訴えたりするのではなく、わざと露の置く風情を鑑賞しているのだと答える宰相の君。宰相の君は定子サロンを代表する上臈(じょうろう=身分の高い)女房です。経房が伝えているのは、時勢に取り残された状況の中でも、居住まいを正し、凛とした姿勢を保って生きている誇り高き中宮定子の様子です。それは、清少納言に対する女房たちのメッセージに響いてきます。本来ならあなたこそ、定子サロンの先頭に立って私たちのように振る舞っているはずじゃないのと、彼女たちは言いたかったのだと思います。
この後、しばらくして定子本人から清少納言に便りが届き、それを契機に再出仕するという展開になっています。しかし、この里居で清少納言が再出仕に至るまでには、かなりの時間を要したと考えられます。同時期の清少納言の里居を扱った別の逸話が他の章段にありますので、次回、見てみましょう。