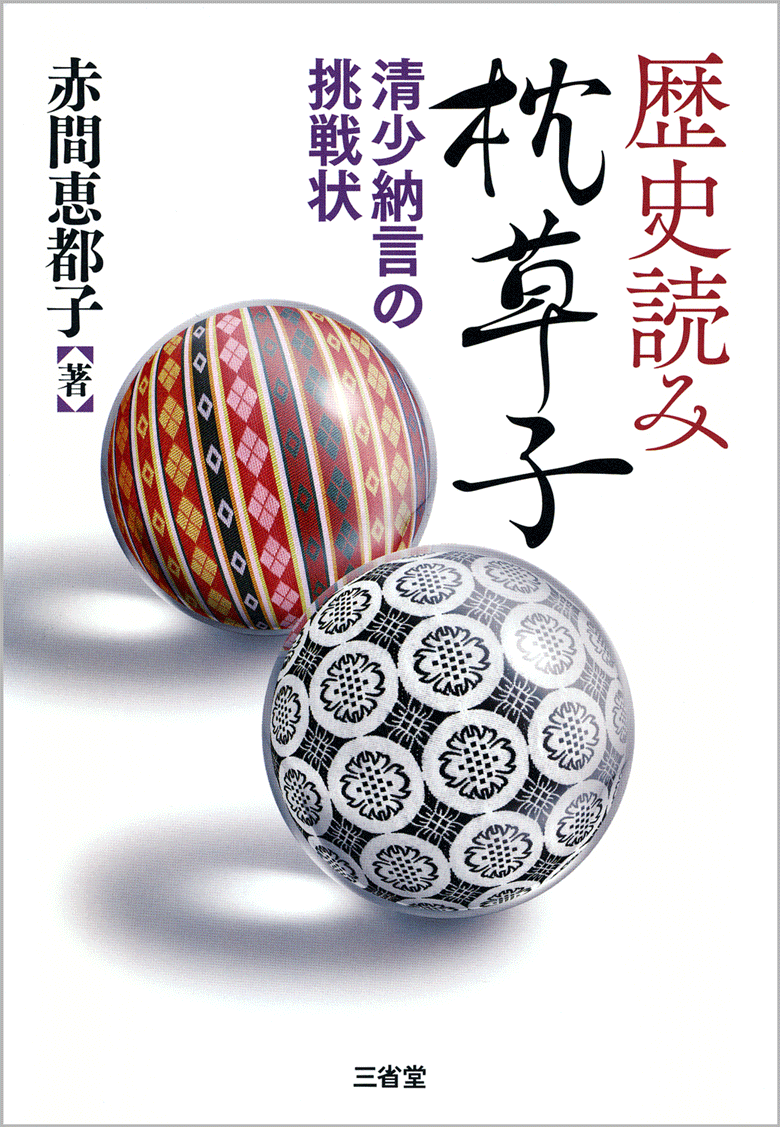清少納言には、宮仕え中に中宮定子や女房たちの前で、折に触れ口にしていることがありました。それは、次のようなことです。
世の中の腹立だしうむつかしう、かた時あるべき心地もせで、ただいづちもいづちも行きもしなばやと思ふに、ただの紙のいと白う清げなるに、よき筆、白き色紙、みちくに紙など得つれば、こよなうなぐさみて、さはれ、かくてしばしも生きてありぬべかんめりとなむおぼゆる。
(世の中が腹立たしく、煩わしくて、ほんのわずかな時間も生きていられそうな心地がしなくて、もうどこへでも行ってしまいたいと思う時に、ただの紙でとても白く美しいものに、上等の筆、白い色紙、みちのくに紙などを手に入れたら、気持ちがすっかり慰められて、まあいいか、このままもうしばらく生きていてもよさそうだなと思われます)
何か非常に嫌なことがあって、もう生きていけそうもないと思うようなとき、自分の気持ちを慰め、前向きにしてくれるもの、そんな自分だけの楽しみに浸って立ち直るというのは、現代人もよく行う処世術です。文筆家清少納言の心をとらえたものは、第一に筆記用具でした。真白な美しい紙と高級な筆が手に入れば、それだけでもう気持ちを切り替えることができるというのです。なんとも手軽な方法だと、定子や同僚女房たちに笑われますが、現在の私たちの感覚では、当時以上にそう思うかもしれません。
白い紙がどこでも簡単に買える現代と比較して、平安時代の紙はなかなか手に入らない高級品でした。さらに和紙は、樹木の皮から繊維を取り出し漉いて作るために薄茶色が本来の色なので、真白な紙は、それを漂白するか白く着色する手間を必要とします。中下流階級の貴族の家ではなかなかお目にかかれない純白の紙や、厚手で白いみちのくに紙も、宮中では日常的に使用できることが清少納言をおおいに喜ばせたでしょう。
紙の他にもう一つ、清少納言が心慰むものとして取り上げたのが、「高麗(こうらい)ばしの筵(むしろ)」でした。「高麗ばし」は畳の縁模様で、白地の綾に雲や菊の模様を黒く織り出したものです。白と黒のすっきりしたデザインは彼女のお気に入りで、こころ魅かれるインテリアだったようです。
さて、本題はこれからです。「さて後ほど経て、心から思ひ乱るる事ありて、里にあるころ」と始まる次の段落から、最初の話からいくらかの時間が経過して、清少納言が里下がりをしていた時の話に移ります。突然、中宮様から高級紙20枚を入れた包みが送られ、早く参上せよという伝言と、これは、以前、耳に止めていた事があったから送るという内容が伝えられました。感激した清少納言は、和歌を定子に返します。
それから二日後、今度は高麗ばしの畳が送られてきました。使者は畳を置いてすぐに去ったので、送り主を確かめることができませんでしたが、もちろん送り手は定子だと思います。念のため、ある女房を介してそれを確認した清少納言は、再度定子に手紙を書きます。しかし、それをこっそり中宮御所の手すりに置かせたところ、使者があわてていたために、手紙が階段の下に落ちてしまったという記述で終わっています。
この章段では、中宮定子が清少納言の好みを覚えていて、彼女の心を最も慰める贈り物をしたのに、清少納言の方は、定子に手紙を書いただけで出仕していません。定子の心遣いを受け取り感激しながら、それでも出仕するに至らなかった清少納言のこの時の里居は、彼女がそれまでになく追い詰められた長徳2年の里居だったと考えられます。