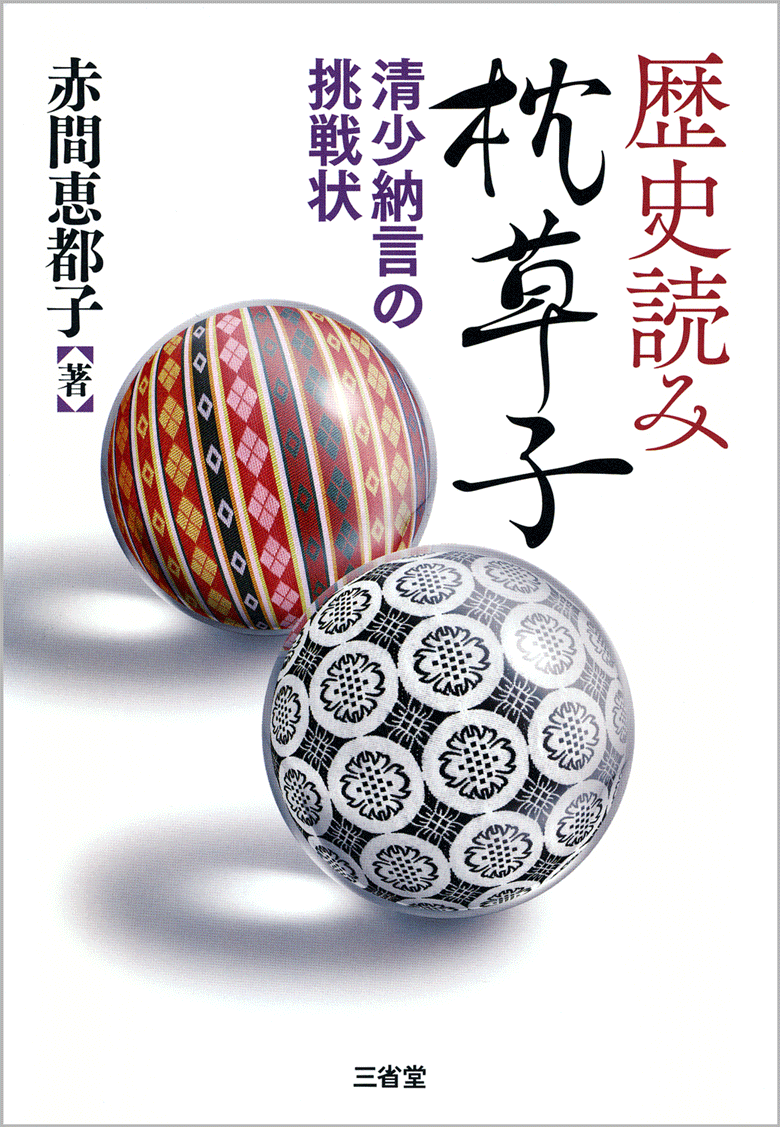長徳2年の里居の時、なかなか再出仕に踏み切れなかった清少納言の気持ちを動かしたのは、やはり中宮定子でした。ある日、定子から送られてきた手紙を開けてみると、山吹の花が一つ包まれていて、その花びらに一言、「いはで思ふぞ」と書かれていました。それは、『古今和歌六帖』という歌集に載っている次の和歌の一句でした。
心には下ゆく水のわきかへり言はで思ふぞ言ふにまされる
(私の心の中には、表面からは見えない地下水がわき返っているように、口に出さないけれど、あなたのことを思っています。その思いは口に出して言うよりずっと優っているのです)
この歌がなぜ山吹の花に書かれていたかを解くには、『古今集』に載るもう一つの和歌を思い浮かべる必要があります。
山吹の花色衣ぬしや誰問へど答へずくちなしにして
(山吹の花のような色の衣に持ち主は誰ですか、と聞いても答えません。それはくちなしだからです)
素性(そせい)という歌僧の詠んだ歌です。「山吹の花色衣」は僧侶の黄色い衣の色です。この歌では、黄色の染料の素になる「梔子(くちなし)」の実に「口無し」をかけ、だから答えがない、としゃれています。すなわち、山吹の花と「言はで思ふぞ」の句は「くちなし」つながりというわけで、定子は山吹の花に「言はで思ふぞ」と書いたと考えられます。
口には出さない、でも口に出して言うよりずっと心の中のあなたへの思いは優っている。それは、何も聞かずに清少納言を信頼し包み込む定子の大きな愛情であり、また、出仕要請に応えられないまま、定子の事を思い続けていた清少納言の気持ちでもありました。主従の思いは重なり、清少納言のそれまでの不安は一瞬にして消え去ってしまいます。初出仕の時に魅了されて以来、ずっと慕い続けてきた中宮定子との絆を確認した時、周辺の女房たちの雑音など、清少納言にはもうどうでもよくなったに違いありません。それから間もなく彼女は定子の許に再出仕します。
では、清少納言の長徳2年の里居がいつ頃始まり、どれくらい続いたのかについて考えてみましょう。前々回、里居中の清少納言に源経房が伝えた話では、定子後宮の女房たちは季節の色目の装束を怠り無く身に着けていたということでした。それは朽葉の唐衣に萩や紫苑などの色目でしたから、時節は秋を意識した7月ころと見るのが妥当でしょう。その際、経房が清少納言に出仕を促していたのは、それより前の夏ころから清少納言の里居が続いていたためと推測されます。ちょうど長徳の変が起きた季節になります。
清少納言が再出仕を決意したのはいつ頃でしょうか。文脈としては、経房訪問の後に、里居の理由について作者の心中表白があり、次に定子から山吹の花が送られて再出仕に至ります。ここで、秋と推測した経房訪問の時節と、再出仕の契機となった山吹の花の季節が相違するという問題が発生します。そこで、山吹は春の花ですが、これは秋の返り咲きの山吹だったのだとか、造花を使ったのだとかいう説が出されています。
しかし私は、定子が送った山吹の花は本来の季節である春に咲いたものだと考えます。経房訪問の後も里居を引き延ばしているうちに季節が移り変わったのです。その場合、清少納言の里居期間は長徳2年夏から翌年春までの一年近くに及ぶことになりますが、この時、清少納言はそれだけの時間をかけて、宮仕え生活断絶の危機をしっかりと乗り越えたのではないかと考えています。