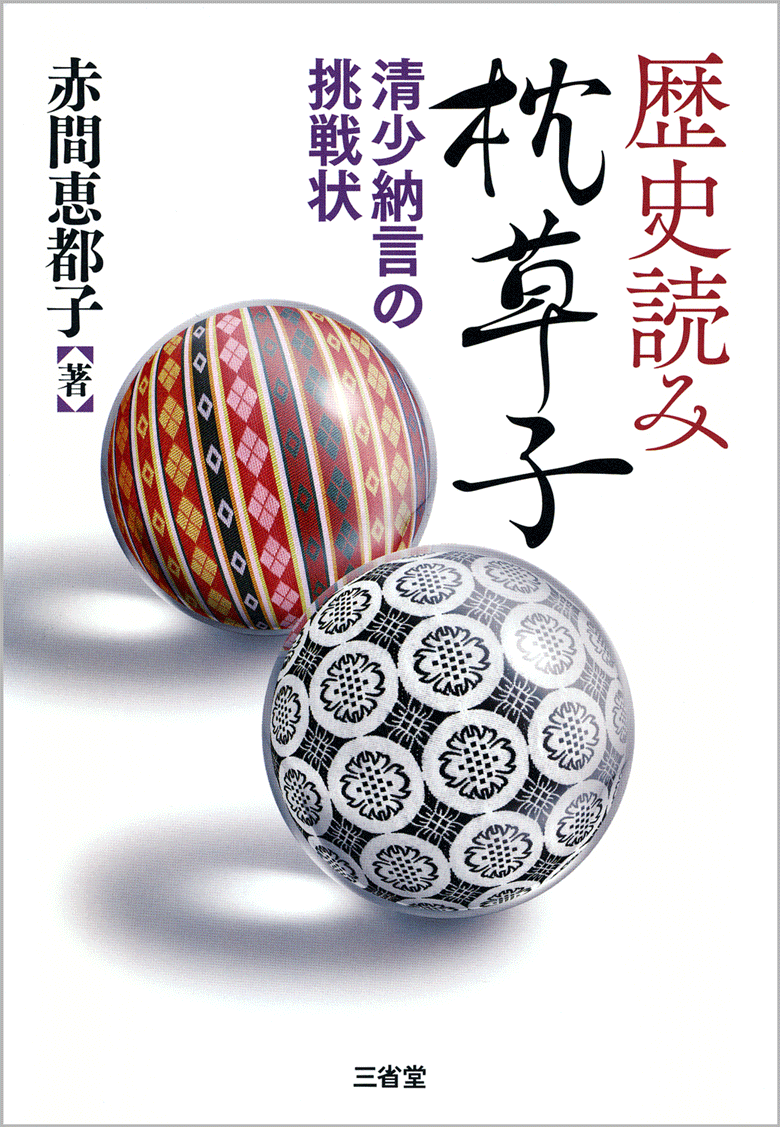ホトトギスの和歌を詠まずに帰った清少納言たちが、中宮定子に今すぐ詠むように言われて詠歌の相談をしていたところに、藤原公信から文が届けられます。彼は、あの卯の花車から引き抜いた枝に和歌を付けてよこしたのでした。返歌は早く返すほどいいというのが貴族社会の常識でしたから、先にこちらの和歌を詠まねばなりません。清少納言は侍女に自分の硯箱を部屋に取りに行かせますが、その様子を見ていた定子はじれったく思ったのでしょう、自らの硯箱を与えます。しかし、宰相の君と詠歌を譲り合っているうちに、降っていた雨が強くなり、ついに雷まで鳴り出しました。
当時は避雷針などの設備もなく、建物も燃えやすい木造建築でしたから、落雷によって家屋が火事に見舞われることも多く、内裏も何度か焼失し建て直しています。とにかく恐ろしくて、格子をすべて引き下ろして回るうちに返歌どころではなくなります。
やっと雷が去り、雨も少し止んできた頃には日暮れになっていました。そこで、あらためて返歌に取り掛かろうとしたところ、今度は雷見舞いに訪れた上達部たちへの対応に追われて取り紛れてしまいます。「今日はつくづく和歌に縁のない日なのだろう、こうなったらホトトギス探訪に出掛けたことさえあまり人に話さないようにしよう」と笑う清少納言ですが、定子の方は、「たった今だって詠めないことがあるものですか」と不満気です。
それから2日ほどたって、ホトトギス探訪の時の話になり、宰相の君が、「どうでしたか、(明順が)自ら摘んだという下蕨(したわらび)のお味は」と清少納言にたずねます。中宮定子はそれを聞いて、「思い出すことといったら(食べ物の話だなんて)」とお笑いになり、紙を投げてよこしました。そこには、「下蕨こそ恋しかりけれ」という連歌の下句が書かれていたので、清少納言は、「郭公たづねて聞きし声よりも」と付けて返しました。その後、清少納言は定子に自分の和歌に対する思いを告白することになります。
…歌よむと言はれし末々は、すこし人よりまさりて、「そのをりの歌は、これこそありけれ。さは言へど、それが子なれば」など言はればこそ、かひある心地もしはべらめ。つゆとりわきたる方もなくて、さすがに歌がましう、われはと思へるさまに、最初によみ出ではべらむ、亡き人のためにもいとほしうはべる
(歌がうまいと言われた者の子孫は、少し人よりは優って、「その折りに詠んだ歌はこれであった。何といってもあの歌人の子なのだから」など言われてこそ、詠んだ甲斐のある気持ちもするでしょう。まったく優れた点もないのに、それでもいい歌だと思って、私こそはと得意な様子で最初に詠み出しますのは、亡き人のためにもふびんです)
清少納言の曽祖父清原深養父(ふかやぶ)は『古今集』歌人、父清原元輔(もとすけ)は『後撰集』撰者であり、清原家は歌人の家としては名門でした。その家名を背負って出仕したであろう清少納言の和歌に対する自負心とプレッシャーが想像されます。『枕草子』には作者の豊富な和歌的知識が盛り込まれていますが、清少納言の歌作自体は少ない理由がそんなところにあったのだろうかと興味をひかれる逸話です。
さて、清少納言は定子から、「歌を詠むか詠まないかは自由にすればよい、こちらからは詠めとは言わない」という詠歌御免の許しを得ることになりました。