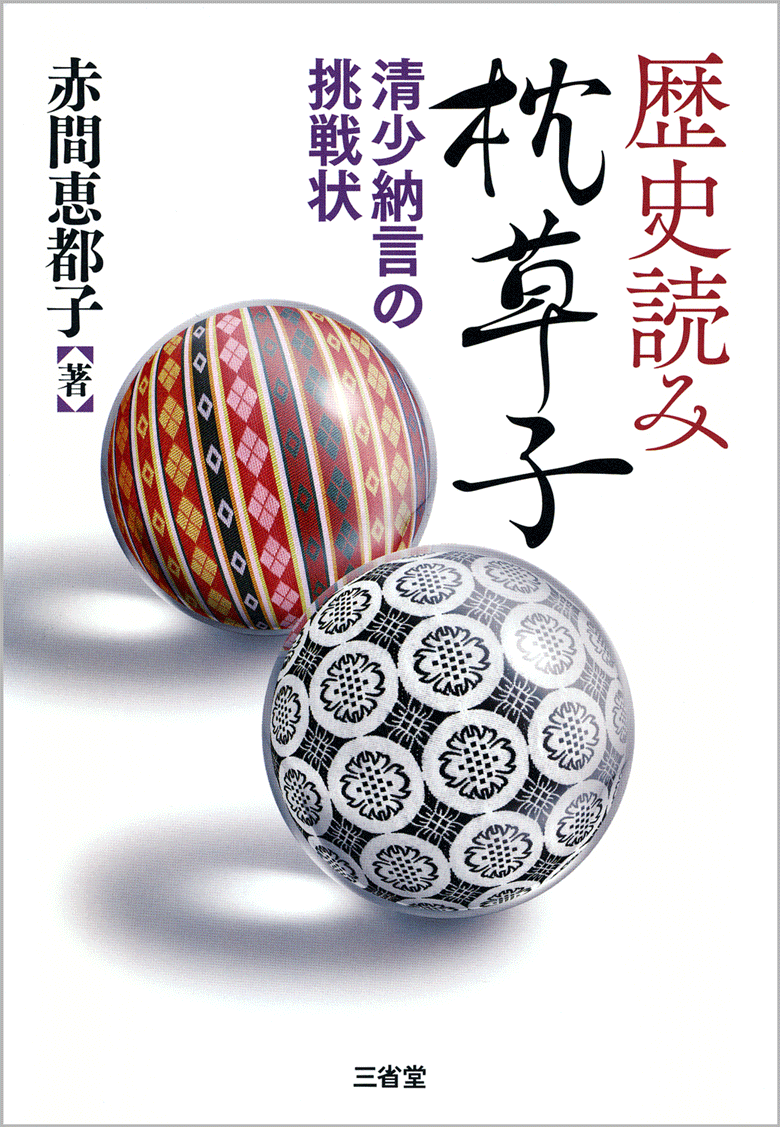『枕草子』に登場する男性貴族のうち、その登場回数と身分で藤原斉信に並ぶのは、藤原行成です。斉信が頭中将から宰相中将に昇進して作品から消えていった代わりに、行成が頭弁(とうのべん)として登場し、職曹司時代の定子後宮に出入りします。ちなみに頭中将と頭弁は蔵人頭という官職で、中将から一人、弁官から一人が就任した蔵人所の長官です。天皇の身近で働く蔵人たちは中宮御所を訪れる機会も多い職柄なので、必然的に後宮窓口の清少納言と直接言葉を交わすことになります。
斉信と行成は平安中期に四納言と称された有能な官僚たちのうちに数えられた人物です。その二人と、中宮の取次ぎ役として接したことは、清少納言の人生の中でどんなに誇らしく、晴れがましい事だったでしょう。清少納言は彼らとの交流を通じて、歌人の娘から才覚ある後宮女房へと、自らの人生を切り開いていく手応えを感じていたに違いありません。では、藤原行成との交流が始まったころ、二人の間に交わされた贈答歌を見ていきましょう。
ある夜、職曹司で清少納言と話し込んでいた行成が、翌日は宮中の物忌だからと言って、子の刻(夜中の11時から1時ころまで)のうちに参内しました。翌朝、行成は、「今日はとても心残りな気分です。昨日は夜通し語り明かしたかったのに、鶏の声にせかされて…」という手紙を送ってきました。
清少納言はその返事に、「たいそう夜更けに鳴いたという鳥の声は、孟嘗君(もうしょうくん)のでしょうか」と書きました。孟嘗君は中国の史書『史記』に見える古代戦国時代の斉(せい)の公族です。奏の兵にとらわれそうになって脱出し、夜半に函谷関(かんこくかん)に至ったところ、関所の門が閉じていました。函谷関は鶏の声を合図に開門することになっていたので、孟嘗君は従者の一人に鶏の鳴き声を真似させて関守をだまし、門を開けさせて無事逃れたという話があります。
行成からは折り返し、「孟嘗君の故事にはそうあるが、私たちの間にあるのは逢坂の関所です」という返事が来ました。函谷関の話から、男女が逢う意を持った逢坂の関に話を変え、戯れかけてきたのです。それを受けて清少納言が詠んだのが、後に百人一首に採られる次の歌です。
夜をこめて鳥のそら音ははかるとも世に逢坂の関はゆるさじ
(夜のまだ明けないうちに鶏の鳴き真似でだまそうとしても、絶対に逢坂の関所は開かないし、そう簡単に私は許しませんよ。)
この後、行成から、「逢坂は越えやすい関所だから鶏が鳴かなくても開けて待っているということですよ(あなたは実は私を待っているのではないですか)」という内容の和歌が来て、清少納言はそれ以上、返歌ができなくなります。しかし、口頭での二人の応酬はさらに続きます。その後訪れた行成が、この時の清少納言の手紙を殿上人の皆に見せたと言うと、清少納言の方では、「すばらしい事が伝わらないのは言った甲斐がないから、むしろお礼を言います。反対に、見苦しいものが散らないようにあなたの手紙はしっかり隠して人には決して見せません」と答えます。他の女房たちとは全く違う清少納言の反応を行成は大変面白がり、彼女のことが気に入ってしまいます。
実は、行成から届いた手紙は、清少納言の手から定子と定子の弟隆円に渡されています。行成は名筆家でもありましたから、彼の書いたものは誰もが欲しがったのです。また、ここで交わされた行成との贈答は恋愛歌であっても個人的なものではなく、後宮女房としての公的な立場における清少納言のデモンストレーションであると考えると分かりやすいと思います。