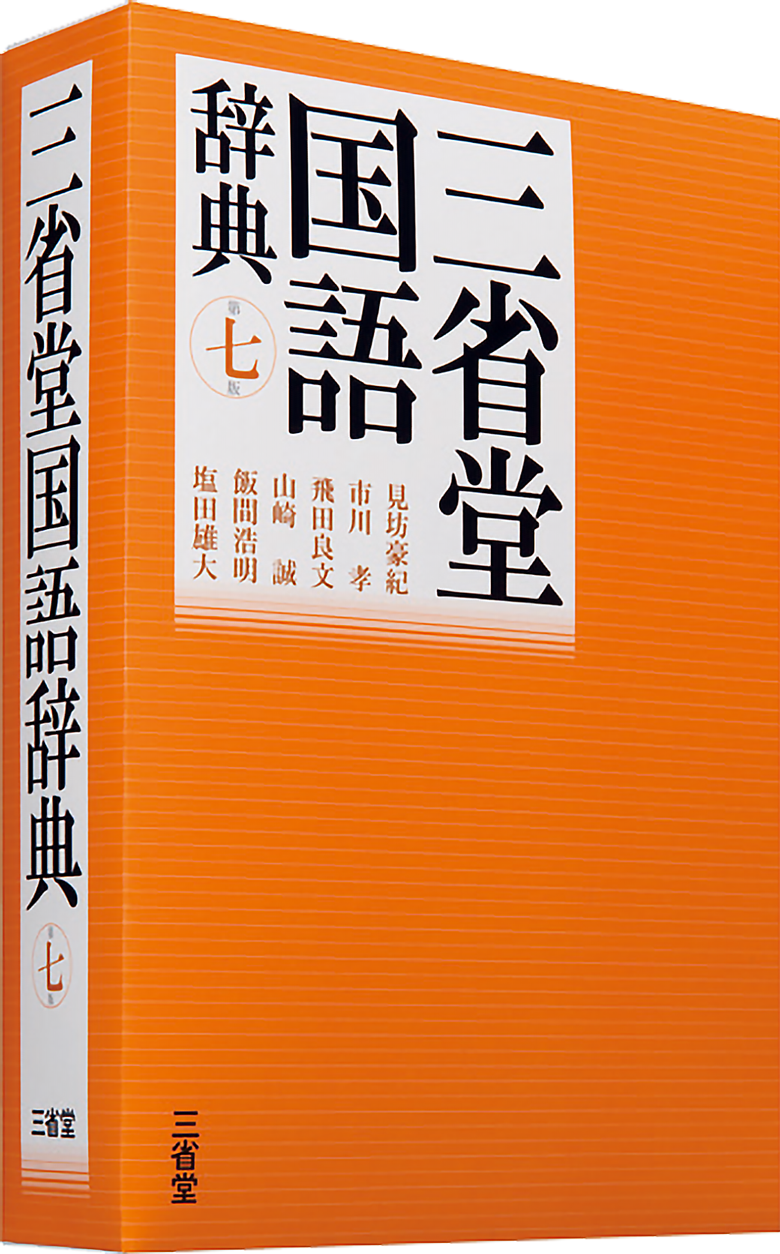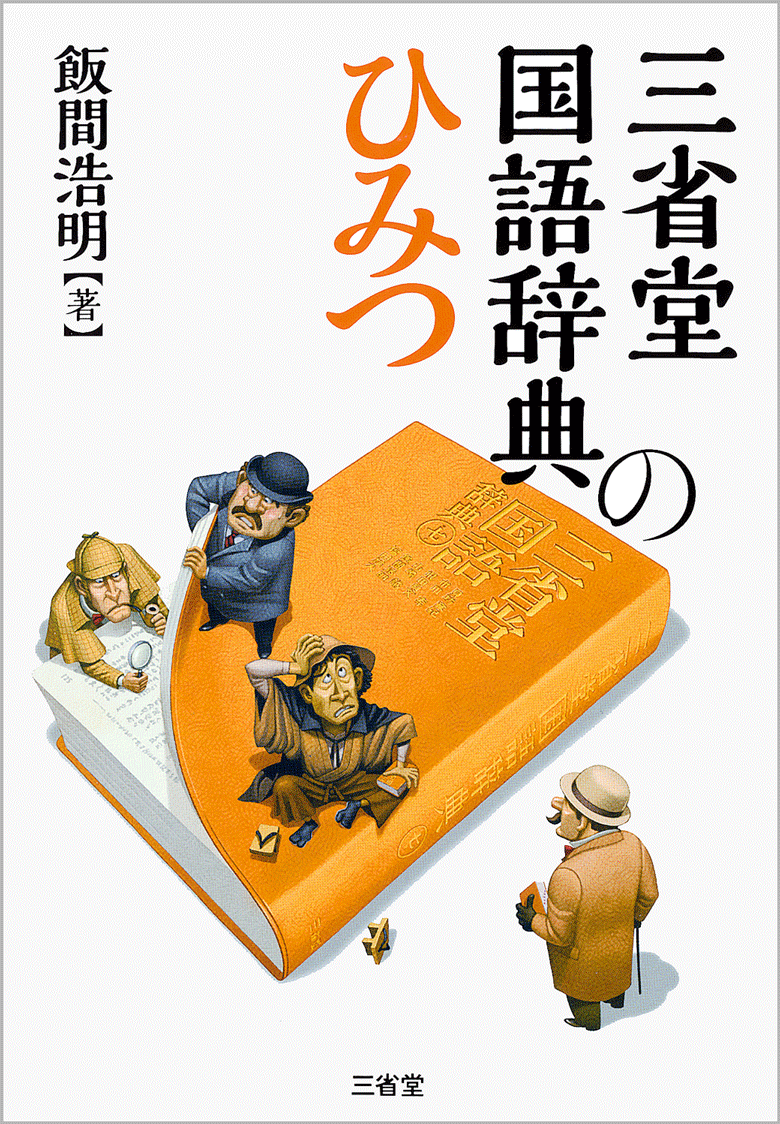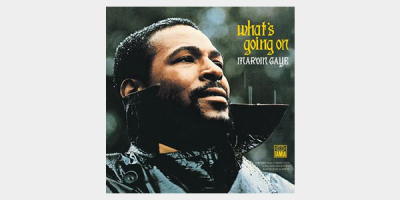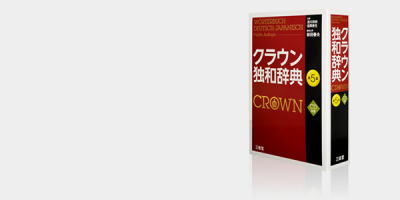『三省堂国語辞典 第六版』のための改訂作業では、すでに載っているむずかしい語の説明も見直しました。たとえば、「寵愛」は、旧版では〈特別に愛すること。〉とありますが、これでは「楽器を寵愛する」と言えるかのようです。修正することになりました。
ほかの国語辞典を見ると、「寵愛」は〈上の人が下の者を〉または〈権力者が身のまわりの特定の者を〉かわいがること、という説明が目立ちます。私も、「寵愛」といえば、『源氏物語』の現代語訳の冒頭にある〈帝の御寵愛を一身に鍾(あつ)めているひとがあった〉(円地文子訳)といった言い回しを思い出します。
ところが、用例を調べると、必ずしも位が上の人が下の人を寵愛している例ばかりではありません。「母が息子を寵愛する」というのはまだその範囲に含まれるとしても、人が鳥や馬を寵愛する場合もあります。芥川龍之介「白」には〈エドワアド・バアクレエ氏の夫人はペルシア産の猫を寵愛している〉と出てきます。

これらの例をすべて覆う動詞を挙げるなら、さしずめ〈かわいがる〉です。今回の第六版の説明では〈特別にかわいがること。〉とした上で、ただし、代表的な使い方を示すものとして、「みかどの ご寵愛」という用例を添えました。

一方、「寵愛」とよく似たことばに「鍾愛(しょうあい)」があります。これは、今回新規項目になりました。むずかしいことばですが、たまに小説などで目にするので、採用したのです。これはどう説明すべきでしょうか。
ふたたび、ほかの国語辞典を見ると、〈深く愛すること〉〈深くかわいがること〉と説明してあるものの、「寵愛」との違いが分かりません。もし、同じ意味ならば、「鍾愛」の項目に同義語として〈……寵愛。〉を記さなければなりません。
そこで、用例を探してみます。「寵愛」は妃などをかわいがる例が多いのに対し、「鍾愛」は、「鍾愛の孫姫」というように、自分の子や孫に使う例が目につきました。また、特筆すべきは、〈〔蹴鞠(けまり)の鞠は〕鍾愛のオブジェ〉〈〔本の〕一冊を鍾愛して〉など、物に使う例が多かったことです。『大辞林』にも、物の用例が挙がっています。
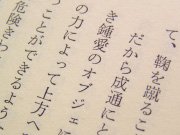
ここから、「鍾愛」の語釈は、〈〔人・物を〕深く愛すること。〉と、あえて「物」を明示しました。「寵愛」は物に対する感情には使いにくいでしょう。