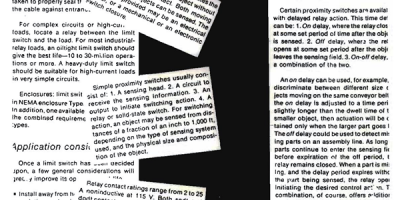西洋における印刷術の発明を解説した後、西先生はそこから生じた出来事について語ります。
西洋右の發明に依りて一千五百年來文華大に開ケ、一千七百年來に至りて liberty of press 印刷自在と云ふこと起れり。則ち下の趣意を以て The free right of publishing books, pamphlets or papers, without previous restraint or censorship, subject only to punishment for rebellious, seditious or morally pernicious matters.
原語の通り一揆動亂を起し、或は風俗を亂たす等の外は、總テ書物新聞の類を自在に世に公ケにするの權を平民に免せり。故に文華益々盛むにして學術大に開ケり。其自在の權を免せしは英國を以て始めとす。唯リ拂國に於ては其權を今尚ホ平民に免すことなし。故に今日ノ國亂に及ふ、猶是等に依る多かるへし。
其他歐羅巴中皆な其の自由を得て、文化益々盛なり。
(「百學連環」第23~24段落)
上記の文中、いくつか本文の左右に言葉が補われているので、まとめて述べておきます。
「文華」の「華」の右には「化」とあり、以下、英単語の左にそれぞれに次のような日本語が添えられています。英語の引用文が長めなだけに、補足も多くなっているようです。
liberty 自在
press 印刷
right 權
publishing 世ニ公ケニスル
pamphlets 書物ノ小ナルモノ
papers 新聞紙ノ類
previous 豫シメ前以テノ
restraint 取極メ
censorship 見改メ
subject 屬シタル
punishment 罰
rebellious 一揆ヲ起ス
seditious 動亂
morally 風俗ノ
pernicious 壊亂スル
matters 事
では、英文を含めて現代日本語に訳してみましょう。
西洋では、右の発明によって1500年来、文化がおおいに開けた。1700年頃にいたって、印刷の自由ということが持ち上がった。つまり、その趣旨は次のようである。「書物、小冊子、新聞を出版する自由な権利。事前の禁止または検閲を受けることなく、ただし反乱〔誹謗〕、煽動、道義上有害な問題に対する処罰のみに従う。」
この英語の引用にある通り、一揆や動乱を起こしたり、風俗を乱すような場合を除いて、あらゆる書物や新聞などを自由に公刊する権利を市民に許した。このため文化はますます盛んとなり、学術もたいへん開けたのである。そうした自由な権利を許したのは、イギリスが初めてであった。フランスでは、そうした自由な出版の権利について、いまだ市民に許していない。今日の国の乱れは、こうした事情によるところが大きい。その他のヨーロッパ各国では、同様の自由を得て、文化がますます盛んとなっている。
活版印刷術の発明・普及に伴って、それまでの写本では考えられないほどの速さと規模で、印刷物を頒布できるようになったわけですが、それはよいことばかりではありませんでした。
反面で、そうした出版の動きに対する規制や禁止も強まったのです。ヨーロッパでは、印刷術の登場以降、ローマ教皇庁を中心とした禁書の動きが強化されます。『禁書目録(Index librorum prohibitorum)』が編まれ、数々の書物が禁書の扱いを受けたのです。これは、20世紀に至るまで続きます。
同じように、国家による出版物の検閲も行われていました。例えば、ここで引き合いに出されているイギリスでは、16世紀に教会や国王によって、書物の事前検閲の統制がしかれたのをはじめ、17世紀においても、言論に対する圧政が取られていました。例えば、『失楽園』で知られるジョン・ミルトン(1608-1674)は、1643年に制定された検閲法に対して、その翌年『言論・出版の自由――アレオパジティカ』を書いて批判を加えています。
ミルトンは、イギリスにおける検閲令が、ローマ教皇庁による禁書政策、異端審問所に端を発していると位置づけて、次のように述べています。
彼らは異端の書物だけではなく、自分の好みに合わないものをすべて禁書処分にし、削除目録という新しい煉獄に投げ込んだのです。さらに蚕食をひろげ全部たべるために最後に発明したのは、いかなる書物、パンフレットあるいは文書も(略)、二人か三人の貪欲な修道士が認め許可しなければ、印刷はまかりならぬという命令でした。
(『言論・出版の自由――アレオパジティカ』、原田純訳、岩波文庫、p.19)
細かいことですが、ここで「書物、パンフレットあるいは文書」と訳されている箇所の原文は、”book, pamphlet, or paper”であり、西先生の講義中で引用されている英文に現れる順序と同じです。
さて、同じイギリスの例では、ミルトンから2世紀後のジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)になると、このように状況が変化しています。彼の『自由論』(1859)を見てみましょう。
腐敗した政府や専制的な政府に対抗するものとして、「出版の自由」を擁護しなければならない時代は過ぎ去った。そう考えてよい。民衆と利害が一致しない議会や政府が、民衆に見解をおしつけたり、民衆の耳に入れてよい学説や意見を限定したりすることには、もはやことさら反対論を展開する必要もないだろう。また、その方面については、過去に多くの論者が何度も、きわめて説得力のある形で論じているので、ここで特に主張したいこともない。
出版の自由にかんして、イギリスの法律は、現在でもチューダー王朝の時代[一四八五~一六〇三]と変わらず抑圧的であるが、内乱の恐怖で大臣や裁判官たちが一時パニックになって冷静さを失うような場合を除けば、この法律が政治的な議論にじっさいに適用される危険性はほとんどない。
(ジョン・スチュアート・ミル『自由論』、斉藤悦則訳、光文社古典新訳文庫、p.42)
ミルは、西先生(1829-1897)の同時代人でもあり、「百学連環」講義でも、後に言及される人物の一人です。西先生は、こうした状況を念頭に置いていたのかもしれません。
また、ここで引き合いに出されているフランスは、「百学連環」講義の当時、いわゆる第二帝政期に当たりますが、言論の自由が実現するのは、その次の第三共和政下で「新聞の自由に関する法律」(1881)が公布されてのことだと言います。
さて、講義に戻りましょう。引用されている英文の出典は、もうお分かりかもしれません。私たちにはお馴染みとなった『ウェブスター英語辞典』(1865年版)の「Press」の項目から取られたものです。
Pressの項目(p.1032)の末尾に、”Liberty of the press”という解説が付されており、西先生が引用しているのとほぼ同じ文章が現れます。ただし、上で見た「百学連環」(甲本)でrebellious(反抗的な、反体制的な)としているところは、『ウェブスター英語辞典』ではlibelous(誹謗中傷、不当に表現する)と見えます。後で気づいたのか、「乙本」では辞書同様にlibelousとなっていました。
出版の自由によって、文化が盛んになるという見立てが述べられているわけですが、皮肉なことに、「百学連環」が講義された少し後、明治8年(1875年)になると、日本では「讒謗律(ざんぼうりつ)」と「新聞紙条例」が公布され、政府による言論弾圧の体制が整えられることになります。
西先生も同人として参加していた学術雑誌の「明六雑誌」では、これを受けて福澤諭吉が「明六雑誌の出版を止るの議案」が提示します。諭吉はこう述べています。
本年六月発行の讒謗律および新聞条例は、我輩学者の自由発論とともに両立すべからざるものなり。この律令をして信に行われしめなば、学者はにわかにその思想を改革するか、もしくは筆を閣して発論を止めざるべからず。
(福澤諭吉「明六雑誌の出版を止るの議案」、『明六雑誌』下巻、岩波文庫、所収)
これはなにも過去の話ではありません。その後も現在に至るまで、さまざまな形でこの問題はくすぶり続けていると言ってよいでしょう。