ここで「帰属」と言うのは社会心理学の用語で,簡単に言ってしまえば事態を「何かのせいにする」ということである。何かのせいにするということは,因果を認めるということである。
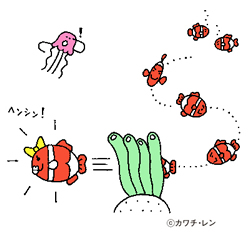
因果は予め与えられているようなものではない。この災害は天災か,それとも人災か。原因を天候の不良に求めるか,それを見逃した人間に求めるか,あるいは天候不良をカバーする技量を持たなかった人間に求めるかは,人間が判断しなければならない。桶屋の繁盛を単に桶の需要増の結果として満足するか,「風が吹けば桶屋が儲かる」の諺よろしく,風にまで原因を追い求めていくかも,同様である。
因果をどう認めるかという問題は,デキゴトの輪郭をどう認めるか,どこからどこまでを一つのデキゴトとして認めるかという問題でもある。そしてそこには人間の心理が関わる。たとえば,或る人物の一連の行動(デキゴト)をビデオに収め,そのビデオを被験者に呈示して,そのビデオに映し出された行動を口頭で報告するよう求めた場合,その人物が被験者にとって上位者と設定されている場合は,下位者と設定されている場合よりも,報告の節の数が多いという実験がある(Darren Newtson 1976“Foundations of attribution”)。つまり同じ行動でも,下位者の行動として観察されれば「1つの行動」と粗くまとめられるものが,上位者の行動として観察されれば細かく分割され,「たくさんの行動の連鎖」になりやすい。
英語なら“This experience taught John how to behave.”と1つの節で表すデキゴトが,日本語では「この経験はジョンに作法を教えた」と言っても何のことやらわからない。日本語では「こういうことがあって」「ジョンは作法が身についた」と2つの節で,2つの小さなデキゴトの因果として表すとよくわかる。よく「英語はどうこうスルの言語。日本語はどうこうナルの言語」と言われるが(寺村秀夫1976「『ナル』表現と『スル』表現」・池上嘉彦1981『「する」と「なる」の言語学』),こういう言語差は,帰属の言語差でもある。
帰属にはまた別の面もある。或るデキゴトを「戦時下だったから」「何しろ突然のことで」のように状況に帰因させるか,それとも人物に帰因させるか。たとえば悪事に関わった或る人間については「不幸な境遇のあまり」と考える一方で,同じ悪事に関わった別の人間については「外国人がまたやった」と考えるとしたら,そこには我々の偏見が隠されていまいか,というのはこういう帰属の問題である。
そして,帰属のこうした面に,新しく登場したのが「キャラ(クタ)」だと考えることもできるだろう。或るデキゴトを状況に帰因させず,人間に帰因させる場合,これまでは「〇〇人だから」「上流階級の人間だから」のような社会的な解答,「女だから」「幼いから」のような生物的な解答の他には,「こういう人格だから」「こういうスタイルをとっているから」という答え方しかなかった。そこに「こういうキャラ(クタ)だから」という新しい答え方が付け加わったということである。
本編の最終回である第100回で,私は「帰属」について次のように述べた。
(1) ここで定義された「キャラ(クタ)」は,「スタイル」「人格」と併せて,本来的には「帰属(attribution)」という社会心理学的な観点からまとめ直せると私は考えている。だが,そのような試みに乗り出す余裕は少なくとも今の私にはない。
本編でまったく述べられなかった帰属について,きちんと述べるだけの余裕は相変わらずないが,今回これをごく僅かながら述べたのは,「キャラ(クタ)」研究の今後を私なりに思ってのことである。
おまえの「キャラ(クタ)」研究は結局何の研究なのかと訊ねてくるような,物わかりの悪い,しかしエライ大先生は,「人物像の研究です」「人間の同一性の研究です」などと答えてもおそらくわかってはくださらないだろう。それで若い研究世代がメゲてしまって,キャラ(クタ)の研究を諦めてしまわないよう,一つの答え方を示しておきたいと思うのだ。大先生に「つまるところ,キミの「キャラ(クタ)」研究は,一体何の研究なのかね」と問われたら,たとえば「そうですね,帰属の研究と言うこともできると思います」と答え,大先生がなお不審げなら「帰属とは社会心理学の,Fritz Heiderのですね……」なんて,ケムに巻いてしまうのはどうかということである。
一般の読者の皆さんには関係のない研究の話が,ついに前面に出てきてしまった。ここらがいい引き上げ時だろう。三省堂の荻野真友子様,木宮志野様,山本康一様,長い間ありがとうございました。市原佳子様,短い間でしたがありがとうございました。皆さん,ありがとうございました。良いお年をお迎えください。







