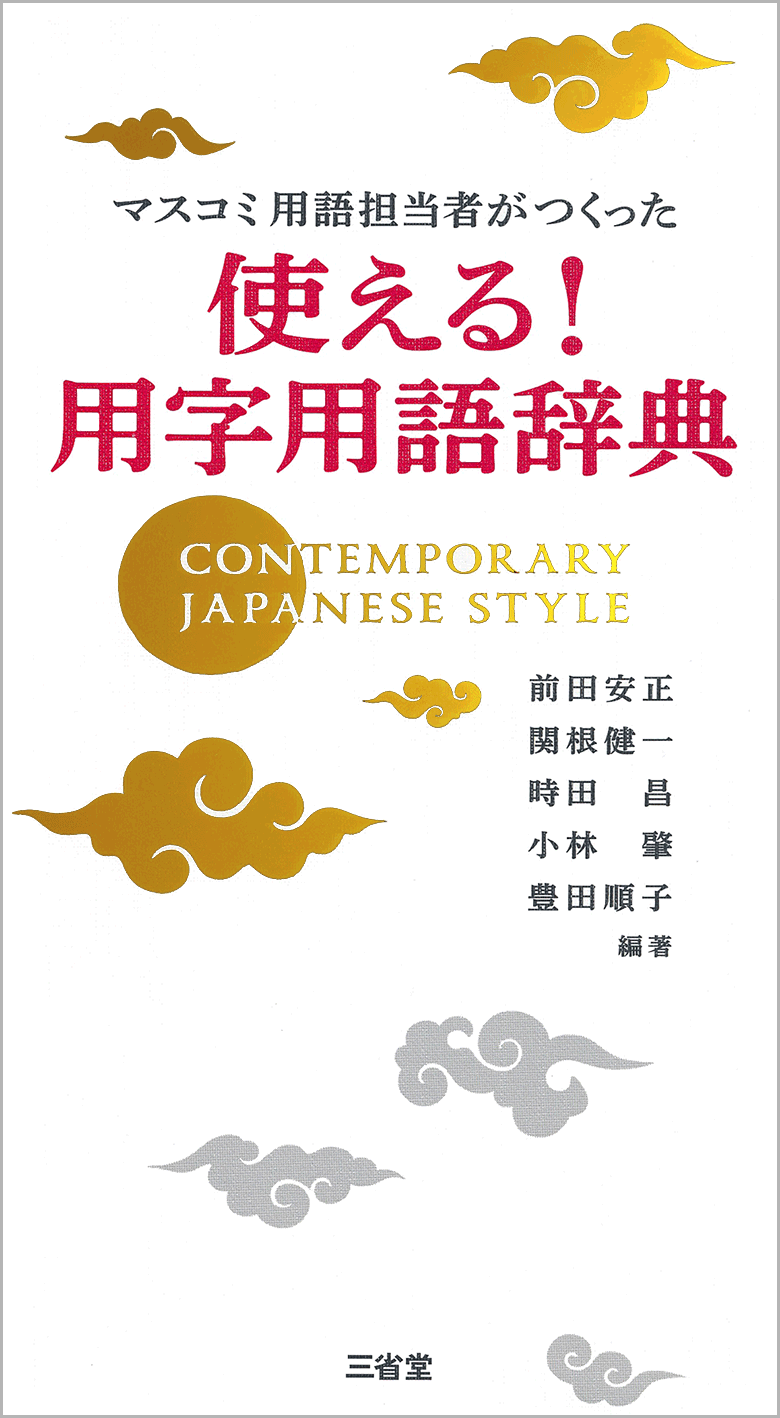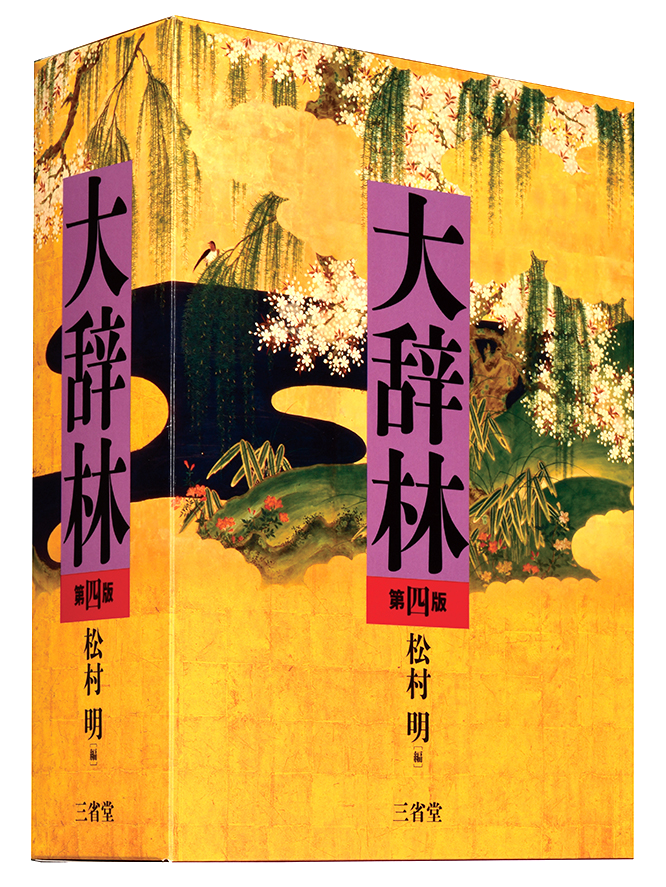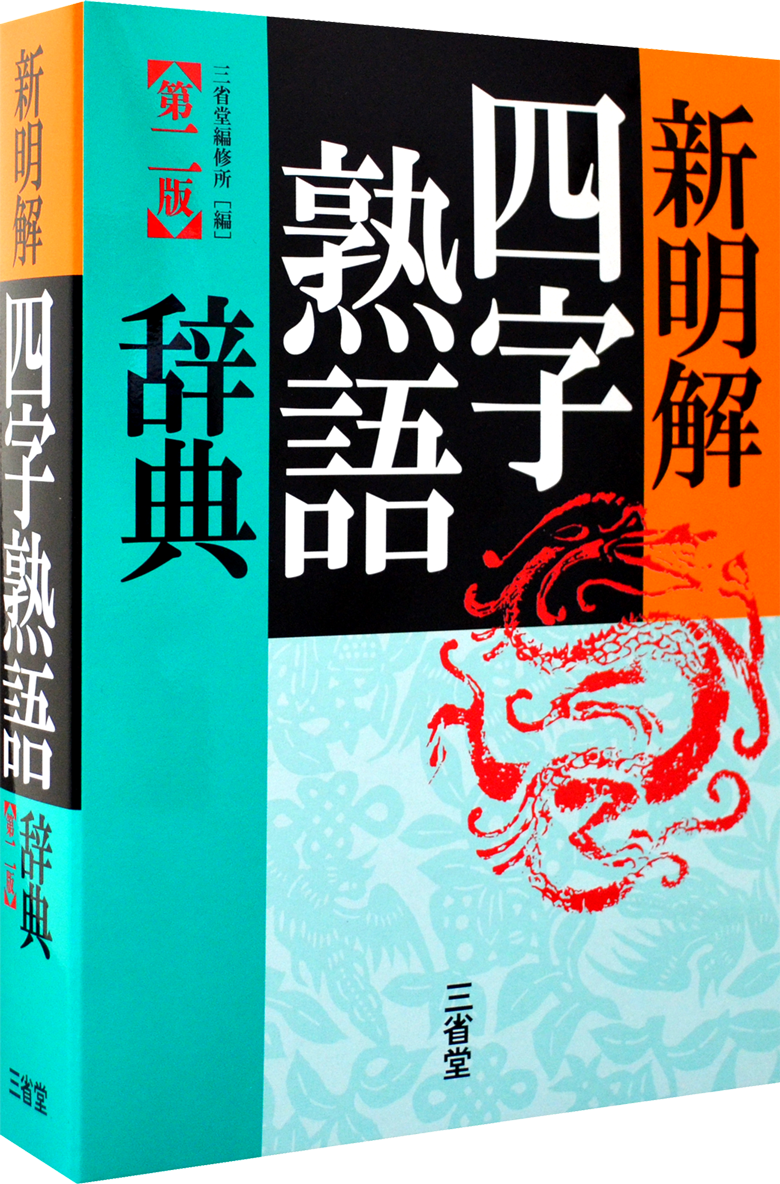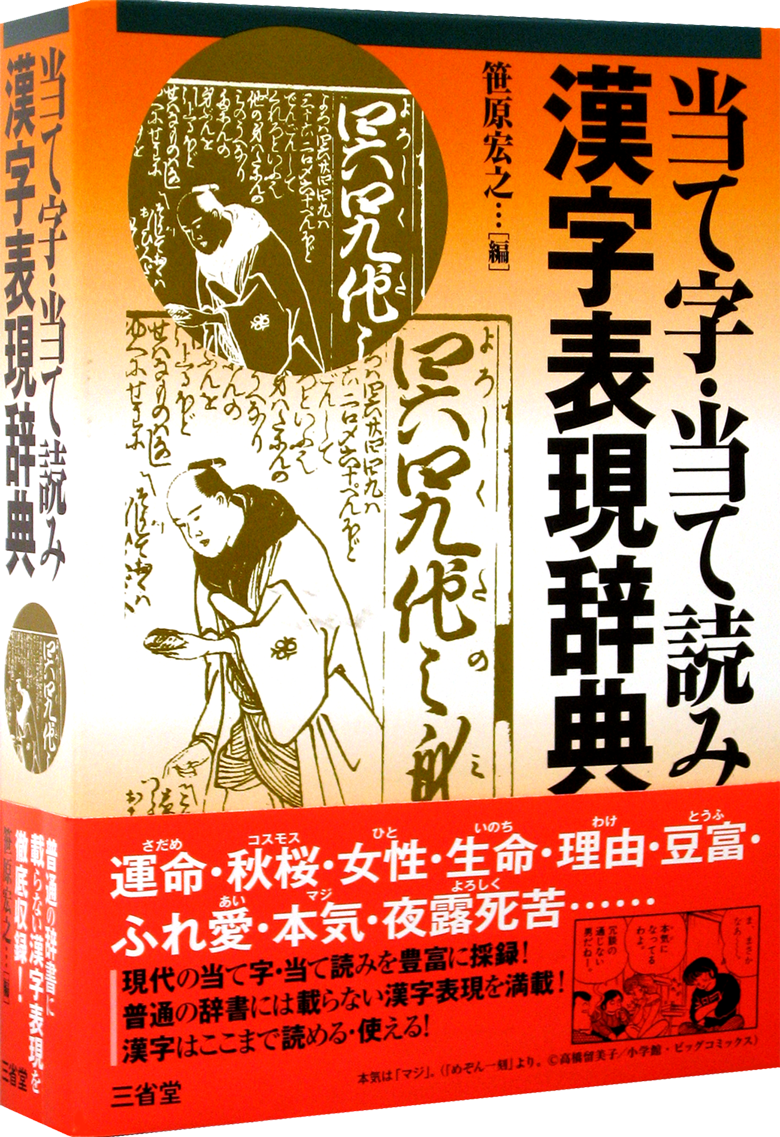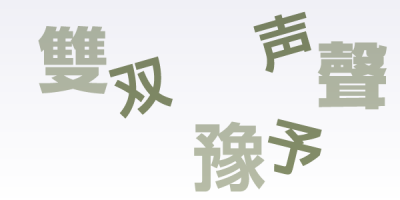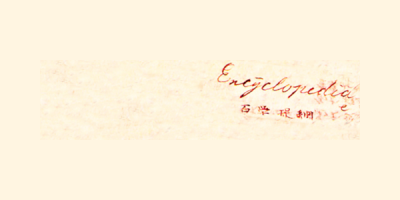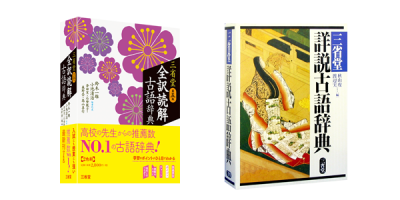[意味]
社会的・経済的な事情や生活環境によって、子供が様々な体験の機会を等しく得られないこと。
*
習い事やスポーツ、自然や文化に触れるといった体験の有無が、子供の人生に強く影響するといわれます。こうした体験は、情操を豊かにし他者理解やコミュニケーション力を育む効果があり、学校の授業だけでは得られない達成感を味わうことで自尊感情が高まるなどとされています。そんな体験の格差が社会問題になっています。
新聞記事データベース「日経テレコン」で検索したところ、日本経済新聞で「体験格差」が初めて紙面に登場したのは2010年8月2日付朝刊教育面の「『体験格差』が生む年収格差」という記事でした。これは「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」を行った国立青少年教育振興機構の研究会座長を務めた明石要一・千葉大学教授(当時)による寄稿。いわゆる「体験格差」は家庭の「経済格差」に起因するもので、将来的に「学歴格差」「年収格差」を生むなどとしています。体験も何でもよいというわけではなく、「動植物とのかかわり」「地域活動」「家族行事」など、子供の成長にあわせた活動をさせることが重要だと説いていました。
とはいえ、体験の重要性は分かったとしても、生活が困窮していたり親が多忙だったりした場合、学校外の活動に参加できない子供たちがどうしても出てきます。こうした問題を少しでも解消できるようにと、昨今は企業や支援団体が美術鑑賞、スポーツ観戦、環境教育、職場見学などを実施する動きが活発になってきました。これを報じる記事も増えています。「体験格差」解消に向けた努力や工夫が今後も続いていくことになるのでしょう。
私が小学校4年生のときの夏休み。親の帰省で田舎に行ったり、家族旅行に行ったりする予定のない同級生のうちの何人かが、担任の先生の自宅にお呼ばれしたことがありました。そのときは何とも思いませんでしたが、体験づくりのための先生なりの配慮だったと思われます。今から50年近く前の、まだ「体験格差」などという言葉のなかった頃のことでした。

* * *
新四字熟語の「新」には、「故事が由来ではない」「新聞記事に見られる」「新しい意味を持った」という意味を込めています。