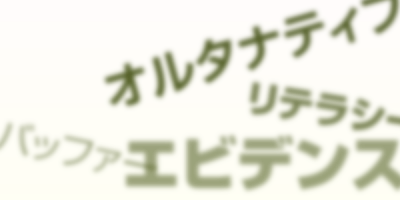分光分析に続いて、今度はまた別の例が出されます。見てみましょう。
又前にもいへることなれと、Botany 此學校は世界のあるとある草木を寄せ集めたれは、其中藥となるあり、毒あり、用あり、不用あり、其毒も不用も悉く集るは皆陰表を求るなり。其陰表を求むるか故に、世界に草木の限りあるを知るなり。
(「百學連環」第41段落第15文~第16文)
このくだりでは、まず Botany の左側に「本草學」と添えられています。また、「校」の字の右側には「〔マヽ〕」とあります。おそらく、「この学は」と読みたくなるところに「この学校は」と書かれていることへの注記でありましょう。乙本を見ても、同じように「校」の字が入っています。詳しくは後で検討することにして、訳してみます。
また、前にも述べたことだが、植物園には、世界に存在する草木を集めている。その中には薬になるものもあれば、毒になるものもある。また、〔人間の〕役に立つものもあれば、役に立たないものもある。なぜ毒になるものや役に立たないものまで、ことごとく集めるのかといえば、これは「消極(negative)」を求めるからである。そして消極を求めるからこそ、世界に存在する植物が有限であることが分かるのである。
今度は植物学の例ですね。西先生は Botany を「本草学」と訳していました。本草学とは、中国から移入されて日本でも発展を遂げた一種の博物学です。「前にも述べた」というのは、第75回「さまざまな専門博物館」で読んだくだりで言及している botanical garden のことでしょう。
ここで問題になるのが「此學校」です。「百學連環」を活字に起こした編者は、上記したように「〔マヽ〕」と、一種の疑義を呈する注記を施していました。〔ママ〕とは、「疑義がある、または誤記である可能性があるが、原文がそうなっている」というほどの意味です。では、ここはどう読んだらよいでしょうか。
といっても、すでに訳文でお示ししたように私は「植物園」と読んでみました。なぜそうしたのか。少しご説明します。
西先生はやはり「此學校」と述べたのではないかと思うのです。というのは、すぐ後で読む箇所には、植物と対比するように動物の話が出てきます。そこでは「Zoology 禽獸園」と言っているのですね。これは当世風にいえば「動物園」となりましょう。
翻って考えると、植物に関して「此學校」というのも、ヨーロッパで16世紀頃から設立される植物園を指しているように思われるのです。それらの植物園は、修道院や大学などが、植物の蒐集と研究のためにつくった、いうなれば一種の学術機関でもありました。西先生の念頭には、そうしたものがあったのではないか。そこで、書かれた通り「此學校」を、「植物に関する学校・研究施設」と読んで、簡単に「植物園」とした次第です。
ちなみに日本でも、江戸幕府が1684年に「御薬園」なる植物園を設けており、後に「小石川植物園」となるのでした。小石川植物園になるのは、1875年といいますから、時間の前後関係でいえば、この「百學連環」講義が行われた後のことです。
さて、ここでの「消極(negative)」は、毒のように人間から見て危険なもの、あるいは役に立たないものを知ることを指しています。これは、先に例に挙げられていた「星雲」と似た用法です。そして、そうした役に立たない植物も集めるからこそ、地上に存在する植物全体が分かってくるのだという具合に、「消極」が別の知識につながる様子を説明しています。
この例はもう少し続きますので見てみましょう。
或は Zoology 禽獸園も亦同し意にして、あるとある禽獸魚類を悉く集め、陰表を求むるに供せり。我か國のサンショ魚とて怪しけなる魚を洋語是を salamander とて、卽ち禽獸園の中に取寄せあるなり。
(「百學連環」第41段落第17文~第18文)
現代語にしてみます。
あるいは、動物園も同じである。ありとあらゆる鳥、獣、魚を集めて、消極を求めているわけである。我が国でいう「サンショウウオ」という奇怪な魚を、ヨーロッパの言葉では「サラマンダー(salamander)」というが、これを動物園に取り寄せたところがある。
「怪しけなる魚」なんていう形容に触れて、思わず井伏鱒二の『山椒魚』を思い出します。あたまがつかえて棲家の岩屋から出られなくなったあの魚ですね。また、「サラマンダー」といえば、山椒魚のことであると同時に、ヨーロッパでは火の中に棲むトカゲという伝説上の生き物につけられた名前でもありました(さらにはこの名前を冠したゲームを思い出す向きもありましょう)。
ちょっと面白いのは、植物のほうでは、特に具体的な植物を挙げていないのに、動物については他ならぬサンショウウオを持ち出しているところ。動物なら他にいくらでもありそうなものなのに!
これは推測なのですが、西先生は、あのシーボルト(Philipp Franz von Siebold, 1796-1866)のことを思い出しているのかもしれません。例えば、次のような一節をご覧ください。
この鰓魚は〔シーボルト〕先生が江戸への旅中に於て大金を出して買ひ取りたるものにして、先生は欧州へ齎らして後私有物として之をライデンの博物館に置きしが、当時欧羅巴に於てそれが如何程珍奇にして且貴重なるものなりしかは、嘉永五年倫敦に開設されたる万国博覧会がその為に千ブンドステルリンクを支払はんと申込みたるにても知るべし。
(呉秀三『シーボルト先生――その生涯及び功業』第2巻、東洋文庫、平凡社、304頁)
これは精神科医の呉秀三(1865-1932)が書いたシーボルトの評伝に見える一節です。ここで「鰓魚」と呼ばれているのは、山椒魚のこと。シーボルトは生きたまま持ち帰り、博物館に置いたというのです。なんとも数奇な運命を辿った山椒魚があったものです。特に裏付けがあるわけではありませんが、西先生はきっとこの一連の出来事を思い浮かべて、サンショウウオを話題に出したのではないかと想像したのでした



![第4回 イフク[息吹]](https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/title_kodaigo-400x200.png)