北海道出身の学生、とくに函館で生まれ育った学生は、「函館」の「函」という字の最初の2画を「了」という形、つまり「 」という字体で手書きする傾向があるようだ。何年か前から、北海道の人々の筆跡を見るにつけ、気になることであった。
」という字体で手書きする傾向があるようだ。何年か前から、北海道の人々の筆跡を見るにつけ、気になることであった。
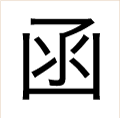
この夏の終わりに、北大で20名弱の受講生に、「函館」と「投函」を書いてもらった。この2語で字体が分かれることはなかった。北海道に住み続けている学生・院生、それ以外の学生・院生ともに「了」形も「函」も出現した。改まってふだんと違うように書いた者もいたことであろうが、函館出身の人は「了」形で記した。
道外の学生も同様に書く者があるのだが、似た構成要素を有する「極」も合わせて書いてもらうと、道外の者には、「極」も「 」と「了」形に書く者がかなりいたのである(*1)。
」と「了」形に書く者がかなりいたのである(*1)。
その函館を地元とする方に聞いてみると、印刷物で見ることはもちろんだが、小学生の頃から年賀状などで皆が書くようになっていて、自分も書き、その字体に慣れているとのこと、貴重な証言である。地元では、地名に用いられており、使用頻度が高く、手書きする機会も多い。「了」など、他の字からの類推も起こしつつ、筆記経済が働き、慣習的な字体が生じる。あるいは後述するように伝統的な字体が簡易な字体として選択される。それがまた目慣れにつながり、いっそう使用に抵抗感がなくなる、という文字生活上での循環が絶え間なく続いてきたのであろう。
活字やそれに沿ったフォントでは、現在、「函」という形が一般に流通している。JIS漢字では第1水準にあり、「了」形を包摂するという規準は設けられていない。第2水準には「凾」という「了」形で、かつ中身の画数が増えている異体字が採用されている。これも俗字とされるものであるが、やはりしばしば見掛けるところである。中身が「口又」となっているのは、「極」の影響を受けて、「下水(したみず)」のような部分がもたらす筆捌きの単調さを回避した結果であろう。北大の先生も、ノートに書誌情報を記す際に、これを手書きされていた。
「了」形で手書きをすると、画数こそ減少しないものの筆を紙から離す回数は1回減る。これは筆記経済につながる。また、見た目にも、「朽」(キュウ・くちる)のたぐいではなく、「了」「子」「丞」(ジョウ)などよりよくある部分字体と近づき、若干すっきりとして感じられるかもしれない。
この「了」形は、『大漢和辞典』には収められていないが、たとえば『全訳漢辞海』には「函」とともに掲載され、『大字典』や『漢語林』では俗字と注記がなされている。実は、唐代の『干禄字書』、宋本『玉篇』などは、「了」形を正字扱いしてきた(テキストなどはここでは詳記しない)。しかし、明代の『字彙』では、見出し字として「函」の字体が掲げられ、さらに、『正字通』では字源説からそれが勧められるようにもなり、俗字の代表としての「凾」との差別化が進められた。ただし、有名な『康煕字典』ですら、注文の中では「了」形が用いられており、また部首として「さんずい」が付された「涵」という字では、「了」形(中身の点の角度も変わっている)をとるといったように、その字体を徹底することは、難しかったようである。
歴代の書家などの筆跡を辿ると、楷書でも行書でも、「函」「凾」ともに「了」形がほとんであり、「函」という明確な字体はなかなか見当たらない。
そもそも篆書体などの古代文字にまで戻れば、『説文解字』の望文生義による字解はそれとして、藤堂明保、白川静両氏の説によると、矢を入れた箱や袋の象形といわれ、落とし穴に人が落ちたところを表す字(陥穽の陥(陷)の旁)にすり替わったとも解されており、成り立ちからみれば、字形の細部にはさほどこだわる必要がなさそうだ。「下水」のような部分の右側の点々は、離して書くのか、接触させるのかと気にする人もあったが、歴代の辞書でも、その形態は、点が4つあるいは何かそれらしいものが記されているだけ、などというように実にさまざまである。
さて、北海道の地では、「函」という字の形はどのようになっているのだろうか。続きは次回に。


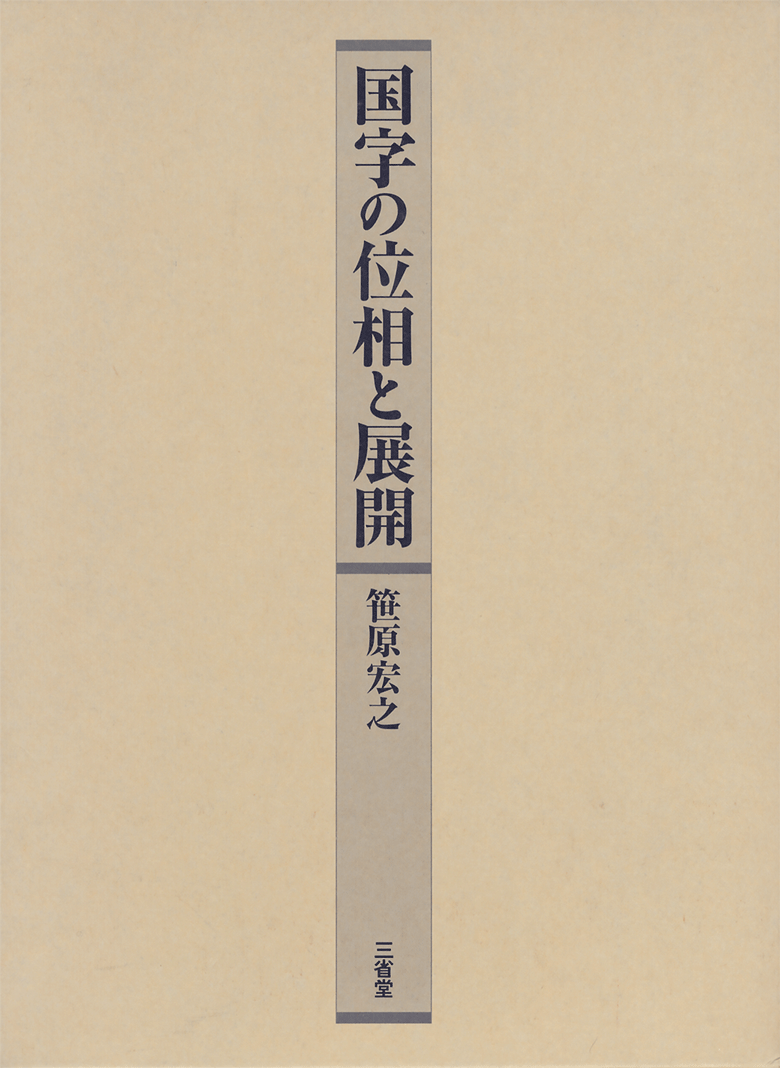
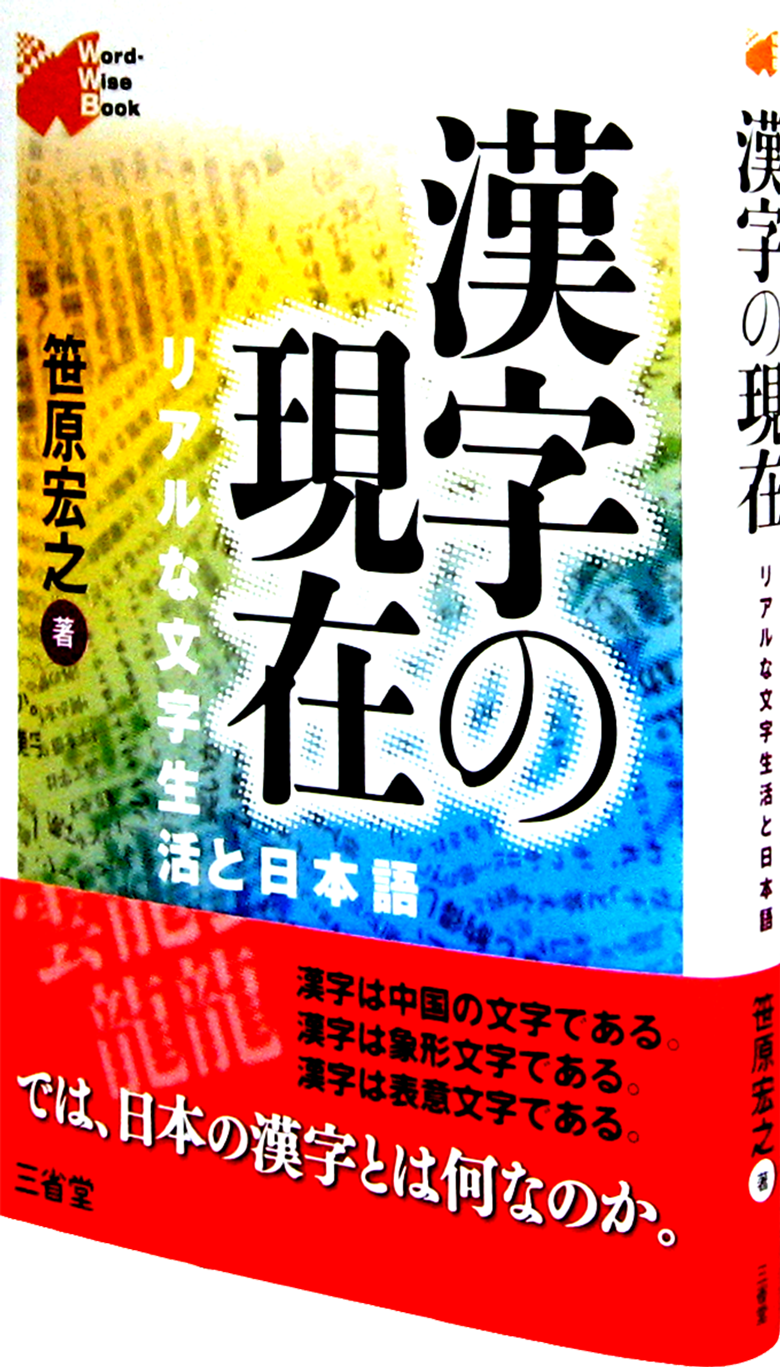
![第2回 イテリス[酡]-日本霊異記の訓釈と片仮名ホの異体字-](https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/title_kodaigo-400x200.png)



【注】