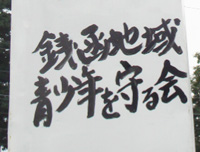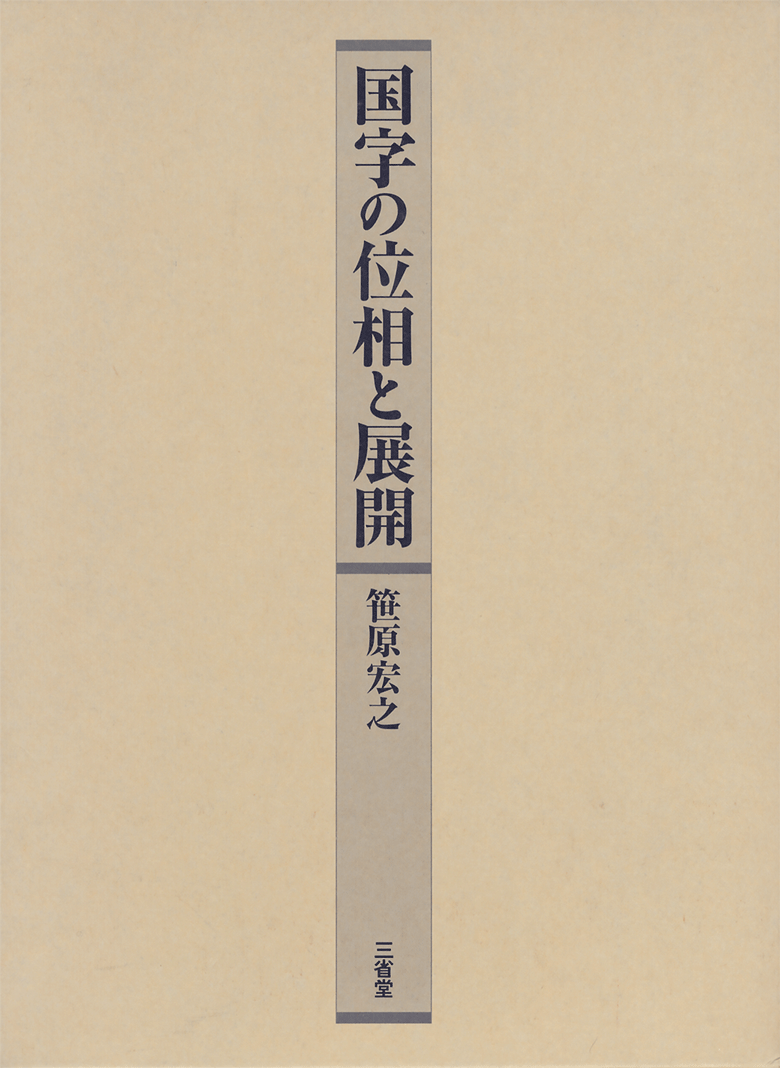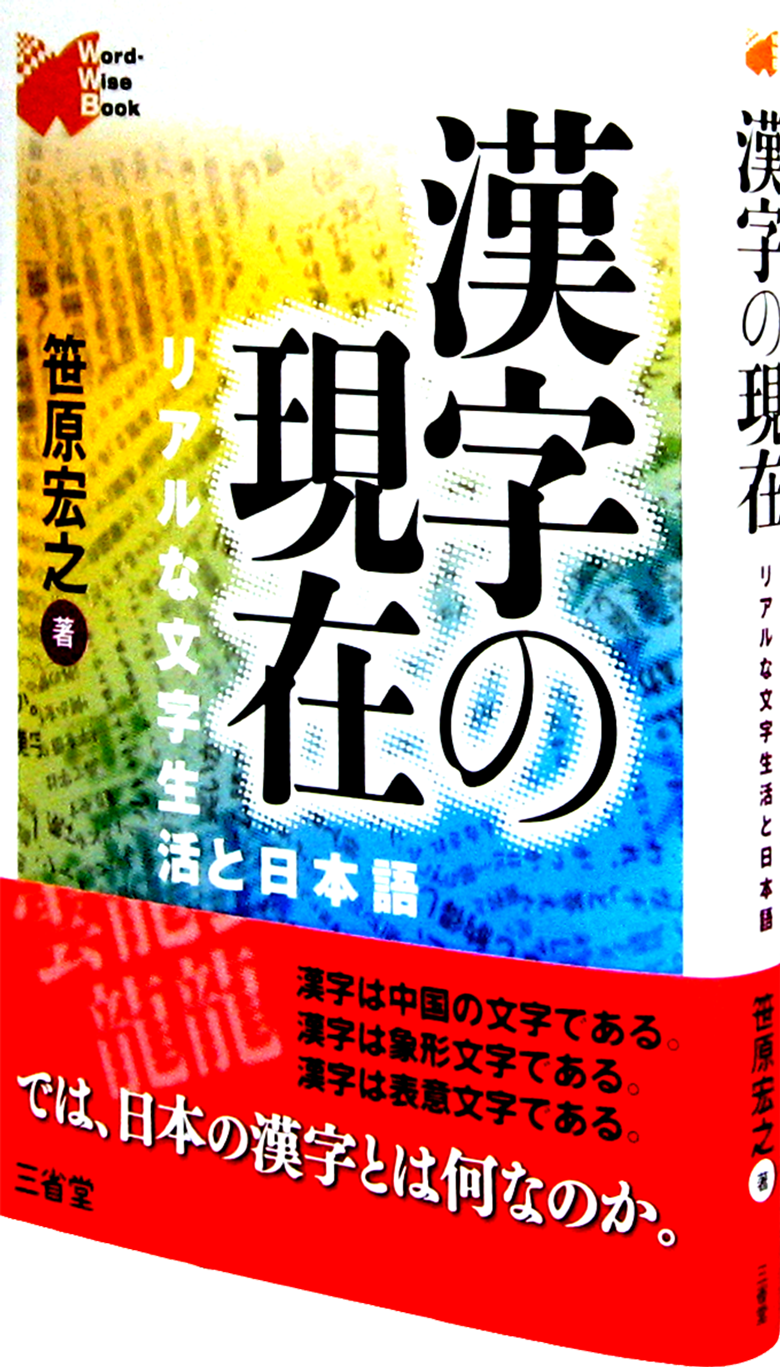札幌で、午前中に集中講義を入れず、時間を空けておいた日に思い立つ。「函」をよく用いる地域では、きっと「了」形が多く用いられていて、たくさん見られるはずだ、という仮説を抱き、それを確認しに出よう、と。
デジタルカメラと裏紙のようなメモ用紙を携えて、ふらりと駅へ出てみる。荷物が重いのは、ぎりぎりになっても遅刻せずに、そのまま講義に向かえるようにと考えると、やむをえない。
函館は思いのほか遠い。片道だけで8,500円以上とあり、これでは往復するだけで6時間以上、3講(東京でいう3限)までに戻れなくなる。北海道だけの地図では錯覚しそうになるが、さすがに広大だ。
そこで、札幌駅にあるJR北海道の路線図を改めて眺めたところ、「銭函」という駅名が目に入った。縁起がいい名前として聞いたことがあったと思う。函館ほどではなかろうが、そこでも必ずや「函」があちこちで使われているはずであり、生活の中で人々が用い、目にしている字体を確かめるには十分である。
実際に銭函駅に着くと、「銭函」の名をPRする看板やパンフレットなどもある。後で、その地はかつては「ごみバコ」とも呼ばれたと聞いた。海岸に打ち寄せる波で、ゴミが流れ着いていたためだという。
海沿いを歩くかぎり文字は少ないが、山側に登っていくと学校もあり、「函」が多数目に入るようになった。概して看板や貼り紙の活字書体は、デザイナーが描いたフォントの通りで、今ひとつ味気ない。きれいはきれいなのだろうが、どこか人間味や個性が感じにくく、誰が打ち出しても、ただ拡大してそこへ飾りを付けても、同じように出力されるかの出来合いのつまらなさから脱しきれない。
一方、手書きや、デザインを施してレタリングをしたような字では、「函」は「了」形ばかりである。繰り返し書かれる文字は、サインのように簡易化するのだ。しかし多くは無意識のうちに生じる。やはり字は、よく使う人ほど、略して書き、さらに自分のものとして使いこなすのである。手書きの味わいは個性の表出にだけあるわけではない。
このような「了」形の使用の状況は、函館も同様なのであろう。その字の使用頻度の高い道産子、特に函館や銭函の人々と、道外の人々とでは、傾向に違いがあるのだろう。東京では、「投函」は見られるが、「当用漢字表」の公布以降、「投かん」という交ぜ書きも増加した。「函館」「銭函」という文字列への接触頻度も使用頻度も、現地には遠く及ばない。無論、「はこ」の表記としては、当用漢字以来、「箱」でほぼ統一され、一般化している。「函」という字を見ることはあるが、記す、特に手書きする機会は少ないので、「函館」や「投函」を自信を持っては書けないという人も少なくないのではなかろうか。
中国の函谷関になぞらえた「函嶺」(かんれい)という表現は、神奈川の箱根の雅称であったが、日常生活の中で多用されるものではなさそうだ。しかし、京都の「函谷鉾町」(かんこぼこちょう)などでは、同様の変化が見られるのかもしれない。また、数学者の中には「関数」を嫌い、「函数」という意訳を兼ねた音訳とされる表記に愛着をいだきつづける向きもあり、その手書きでも同様のことが見られるのではなかろうか。
前回以来述べてきた上記の諸点を押さえた上で、つまり種々の細かいことまで踏まえて言うと、この「函」は字体の細部については目くじらを立てるほどには、こだわる必要性は薄い。「正誤」の基準を独自に設けて、そういうことだけを気にするよりも、もっと考えるべきことが漢字には数多く残されている。
字体は変化し、その結果として地域差までもが生まれているのはなぜか。それは、漢字というものが人間へと近づいていくともいえる性質が、漢字が文字である以上、消えることはないことによる。字画が煩瑣で、かつ必要度の高い字は、自然と書きやすく、分かりやすいようにと、人々によって簡易化されていく。それは、京都の「都」という字(第40回・第41回)と類似する現象であり、沖縄の「那覇」の「覇」という字(第1回・第2回)とも、来歴や字体差の大きさという点で違いを有してはいるものの、根底は通じる現象である。それらと異なり、学校できちんとは教育されない「函」のような字であっても、むしろそれはそれであればこそ、地域文字のようになり、民間で受け継がれていくのである。
そうした変化を妨げる字体、構成上のさまざまな条件もクリアできて、字音、字義などの面でも問題がなければ、全く無秩序になるのではなく、類推の作用など何らかの規則性に基づきながら、それは起こるのである。「俗字」は実用性を求めて生み出された、通俗性に富む文字であり、その真髄は、今なお人知れず受け継がれているといえよう。
【補記】 北海道新聞社の方から、明治から昭和初期にかけて、「函館」(箱館)や「銭函」の「函」には「了形」も用いられていることが各種史料でうかがえる由の情報をいただいた。この簡易な字形は早くから用いられており、やはり人々の間で脈々と受け継がれてきたことも定着の一因とみるのが自然のようだ。