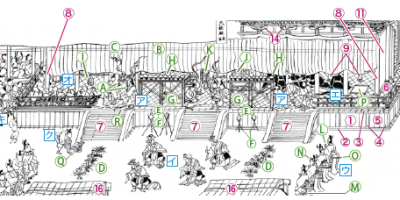書物の世界、言語の世界で、ある対象を追跡していると、当初は思ってもいなかったような場所に迷い込むことがあります。私たちは、「術」の定義の出所を追いかけて、西周⇒ウェブスター⇒ハズリットと辿ってきました。
「術」の定義の連鎖も、ここで話が終わればよかったのですが、実はハズリットの文章も、どうやらよそから持ってこられたもののようなのです。
いろいろあるのですが間は飛ばして、ハズリットの定義からさらに遡ることおよそ100年。辞書編纂者のネイサン・ベイリー(Nathan Bailey, ?-1742)による『The Universal Etymological English Dictionary』(1731年版)を見てみます。例によってARTの項目を覗いてみましょう。なにが書いてあるでしょうか。
定義の冒頭ではラテン語、ギリシア語の語源を示した後で、「アートはさまざまに定義されている」と始まり、スコラ学者(Schoolmen)による定義が提示され、それに続いて次のような文章が現れます。
Others define it a proper disposal of the things of nature by human thought and experience, so as to make them answer the designs and uses of mankind;
(Nathan Bailey, The universal etymological English dictionary, Vol.II, 1731)
またしても見覚えのある文章です。訳してみます。
他にはこう定義する者もある。人間の思考と経験によって自然の事物に適切な処理を施し、人の企図や用途に適うよう仕立てること。
ここではベイコンの名前こそ出ていませんが、前回ご紹介したハズリットの定義とほとんど同じ文章です。比較のために、該当部分を今一度訳文と併せて引用しておきましょう。
ART is defined by Lord Bacon as a proper disposal of the things of nature by human thought and experience, so as to answer the several purposes of mankind;
ベイコン卿は「術」を次のように定義している。人間の思考と経験によって自然の事物に適切な処理を施し、人の各目的に適うように仕立てること。
ハズリットでは、この定義の出典をベイコン卿としている点が加えられていますが、あとの部分はほぼそのままベイリーの定義と同じです。”so as to”以下の言い回しが少し違って、ベイリーが「企図や要素(the designs and uses)」としたところを、ハズリットは「各目的(the several purposes)」とまとめていますね。
こうなると、ベイリーもまたどこかからこうした文章を引用してきたのではないかと考えてみたくなります。ベイコン卿の著書から取ってきたのか、名言集のようなものから持ってきたのか。そこは分かりませんが、少なくともベイリー以後18世紀、19世紀のさまざまな辞書や百科事典その他の書物で、ベイリーと同じ「アート」の定義が掲げられてゆくことになります。
さて、そろそろ「百学連環」に戻らなければなりませんが、その前にもう一つだけ。先に、ウィリアム・ハズリットが『エンサイクロペディア・ブリタニカ』第7版の「アート」の項目に寄せた文章を見ました。
気になったので調べてみたところ、少なくとも『エンサイクロペディア・ブリタニカ』第3版(1797年)の「アート」の項目は、ハズリットによる定義と同じ書き出しになっており、少なくとも冒頭から段落二つ分まではほとんど同じ文章です。ハズリットは1778年生まれの人ですから、第3版は別の執筆者によるものでしょう。
面白いのは、こうした「アート」の定義を本当は誰が書いたのかということとは別に、「ベーコン卿曰く……」とか、「ハズリットの定義では……」という形であちこちに引用されていることです。
一方では、この定義が言い得ていると評価されているからこそ、そのように流通するのでしょうし、他方では、多くの人が本当の出典を気にせず、また、出典を自ら確認してみようとせずに、こうした引用を行っているということが窺えます。これぞまさに伝言ゲームではないでしょうか。
さて、追いかければ切りもないことですが、「百学連環」に戻ることにしましょう