「書体」とはなんだろう?
いま目にしている文字のかたち。コンピューターやスマートフォンの画面に表示されたり、本や雑誌、新聞など紙に印刷された文字を見ると、ある特定の様式でデザインされていると感じないだろうか?
この「ある特定の様式でデザイン」された文字のセットが「書体」だ。似た言葉として「フォント」がある。「フォント(font)」はもともと「同じ書体デザイン・同じサイズの活字のひとそろえ」を指す言葉だったが、コンピューターが身近になるにつれ、文書作成ソフトなどで「フォント」という言葉にふれる機会が増えて、「書体」よりむしろ「フォント」という言葉のほうがひろく知られるようになり、同じ意味で使われるようになってきた。
今回から始める連載には、「『書体』が生まれる」という壮大なタイトルがついている。でもここで取りあげるのは、大正から昭和なかばにかけてのごく限られた時期のできごとだ。
現在は印刷といえばオフセット[注1]が主流だが、明治から昭和のある時期までは、金属活字をもちいた「活版印刷」が中心だった。金属活字とは、金属の角柱の表面に文字が凸刻された、ハンコのようなものを想像してもらえばよいだろうか。コンピューターでは文字はキーボードを打てばすぐさま並べられるが、活版印刷の時代は、金属活字を1本1本組み上げてレイアウト(組版)していた。本1冊ともなれば、何万字分の活字を拾い、組み上げて印刷していたのだ。

金属活字

活字組版
そんな金属活字の時代、印刷にもちいられる書体は最初、「種字彫刻師」というごく限られた天才の頭のなかにのみあるものだった。当時、活字のおおもととなる種字は、マッチ棒ほどの小さな活字材に職人が原寸・逆字で手彫りしており、その仕事は難易度のとても高いものだった。
それがやがて、紙に拡大サイズの正字(そのままの向き)で描いて書体デザインを行なえるようになっていった。現代にもつながるそうした文字デザインの手法が現れた背景には、「ベントン」と呼ばれるアメリカ生まれの機械の導入と、かつての手彫り種字の良さを引き継ぎながら、新たな文字デザインの手法を切りひらき、あたらしい機械を使いこなして美しい文字をつくろうとひたすらに奔走したひとびとの存在があった。きっかけをつくったのは三省堂である。
いったい現場には、どんなひとたちがいて、どんなふうに書体づくりに取り組んでいたのか。どんなひとたちが未知の機械を手に入れ、その技術をひろげていったのか。
“「書体」が生まれる” そのときをめぐる、現場の奮闘をたどっていきたい。
※写真はすべて筆者撮影



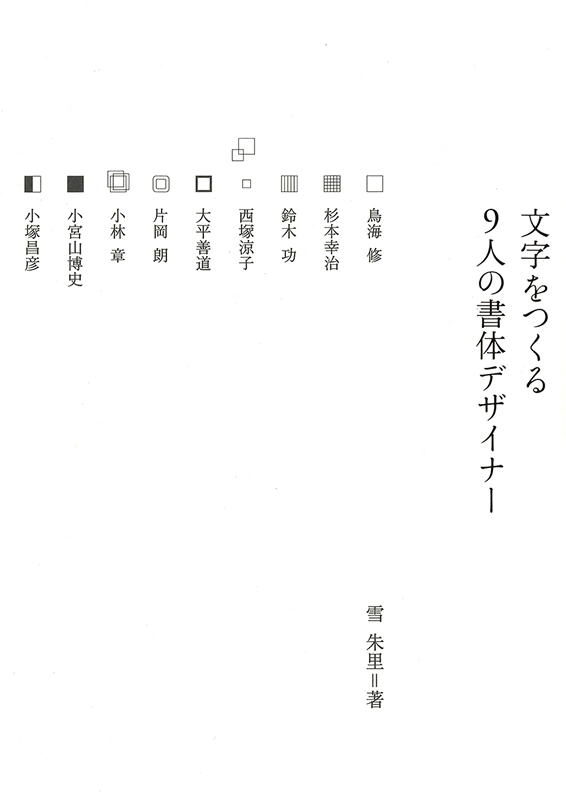

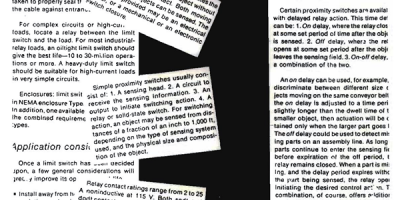



[注]