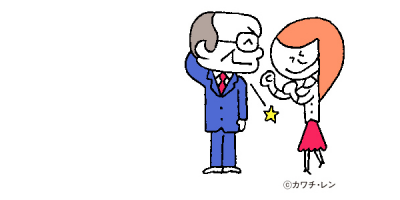「人物の挙動が,その人物のキャラクタにふさわしくないことばで表現される」という例外的な文脈を挙げている。これまでに4つの文脈を挙げたが,他に無いかというと,そんなことはない。
まず考えられるのが遊び・冗談の文脈である。たとえば,椎名誠『哀愁の街に霧が降るのだ(上)』(1981)の一場面を取り上げてみよう。司法試験突破を目指してこれから日夜勉強に明け暮れようとしている木村のもとへ友人の椎名が訪れ,「オレたち仲間でアパートを借りて,毎日一緒に楽しく暮らそうぜ」などと共同生活のプランを持ちかけ,木村を誘惑する。ここで椎名は,自分が行おうとしていること(誘惑)を得意とするキャラクタ(『水商売のお姉さん』キャラ)を発動させ,木村に流し目でにじり寄り,「銭湯なんかに入って,将棋やってカツ丼(どん)食べましょうよ,ネエ」などとあやしく言って,木村のひざをつねった,とある。このように遊び・冗談の文脈では,『男』が『男』に「流し目でにじり寄る」「「~しましょうよ,ネエ」などとあやしく言う」「ひざをつねる」ということは十分あり得る。本編でこれをキャラクタ一般の話として述べたように(本編第10回・第11回),これは発話キャラクタについても,表現キャラクタについても言えることである。

また,否定的な文脈も挙げておかねばならない。「神様がのこのこ出てくるはずがない」は少なくとも一部の話者にとっては不遜で不自然だが(補遺第39回),「男が男に流し目でにじりよるはずがない」なら自然という具合に,表現によって程度の差はあるものの,「人物の挙動が,その人物のキャラクタにふさわしくないことばで表現される」ことの不自然さが,「~はずがない」のような否定的な文脈では吸収されてしまうことがある。
さらに,愛くるしい『幼児』的なキャラクタと,抹殺を楽しむ『殺人愛好家』的なキャラクタが同居している人物が,「はにゃはにゃと川辺にピクニックにやってきて」「抹殺するターゲットのことをうっとりと考える」というように,そもそも「その人物のキャラクタ」が分裂している場合も(補遺第35回),考えようによっては「人物の挙動が,その人物のキャラクタにふさわしくないことばで表現される」場合に含められるかもしれない。
てなことを言っているとキリがないので,例外的な文脈についてはこの辺にとどめ,いよいよ本題に進むことにしよう。これらの例外的な文脈を排除してみると,表現キャラクタとことばの間に,どのような結びつきが見えてくるだろうか?
ここでまず述べたいのは,「表現キャラクタに内外の別なし」ということである。発話キャラクタ(話し手のキャラクタ)には,現代日本語社会に暮らしている《私たち》タイプと,外社会から来た《異人》タイプの区別があり,両タイプはさまざまな点で違っていた(本編第76回~第82回)。だからこそ,発話キャラクタをこれら2つのタイプに分けたわけだが,表現キャラクタには《私たち》タイプと《異人》タイプを分ける必然性が希薄である。つまり,表現キャラクタには《私たち》タイプと《異人》タイプの区別は無い。
発話キャラクタの《異人》タイプには『平安貴族』『侍』『忍者』『関西人』『宇宙人』『ロボット』『イヌ』『ネコ』その他,さまざまな「よそ者」のキャラクタが収まっているが,これらの動作と《私たち》の動作が,表し分けられるということはほとんど無い。
いや,もちろん,まったく無いというわけではない。たとえば,「羽ばたく」のは羽根を持つものに限られるし,「ヒレで泳ぐ」のはヒレを持つものに限られる。「孵る」のは卵生の生物だろうし,「湧く」と言えばウジを代表とする虫である。「単為生殖する」のは単為生殖の生物に決まっている。
だが,物理的に見てしまえば同じ一つの動作であるものが,《私たち》タイプと《異人》タイプで表し分けられるということはほとんど無い。ムカデが這うのも幼児が這うのも「這う」ことに変わりは無いし,人間が起き上がって二本足で直立するのも,馬が起き上がって四本足で直立するのも,あるいは馬が人間並に四つ足状態から後足2本だけで直立するのも,「立つ」ことに変わりは無い。
その意味で,表現キャラクタにおける《私たち》タイプと《異人》タイプの違いとして考えられる語例は,決して多くはない。せいぜいのところ,暮らしを「住む」ではなく「棲む」と表現されるのが(司馬遼太郎『世に棲む人々』のような例外はあるにせよ),基本的には『動物』だということぐらいだろうか。しかし,同音であることもあって,これだけでは《私たち》タイプと《異人》タイプを分ける根拠にはならないだろう。
「さえずる」「吼える」「いななく」「鳴く」のが『人』以外だということも,《私たち》タイプと《異人》タイプを分ける強い根拠にはならないだろう。だが,発声という行動において表現キャラクタが細かく分けられているのは,発話に対する我々の関心の現れと言えるかもしれない。