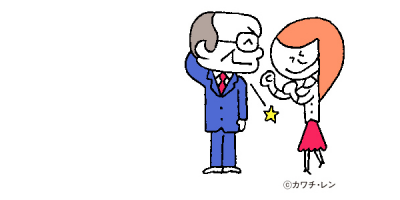前回は、マンガに見られる「変身技法」を取り上げて、キャラクタと身体のつながりを述べた。これは、私たち一人一人の身体によって、似つかわしく周囲に受け入れられやすいキャラクタと、そうでないキャラクタがあるということでもある。
宮尾登美子『寒椿』(2002)には、娼館の新経営者としてやって来た「若い男」が、娼妓たちの前で「小柄な躰を聳(そび)やかして威厳を作った」というシーンがある。この書き方から想像されるとおり、この男は娼妓たちの尊敬を勝ち得ず、まもなく消えてゆく。躰をそびやかして威厳をつくり『ボス』キャラを発動させるには、それなりの貫禄ある体格が似つかわしいということである。
だがこれはあくまで「似つかわしさ」「受け入れられやすさ」の話にすぎない。私たちの身体が私たちのキャラクタを完全に決定してしまうわけではない。
そもそも、身体は決して一義的なものではない。貫禄ある体格は『ボス』の他、『のろま』『愚鈍』『暖かい人柄』『包容力』『金持ち』『体制側』『エピキュリアン』等々、さまざまなイメージと結びつく曖昧なものである。井伏鱒二「掛持ち」(1940)に出てくる、喜十という番頭の「二重生活」は、このことをよく示している。
甲州・湯村の「篠笹屋」では、喜十は酒も飲まずタバコも吸わずにおとなしくして、布団や枕を運び、湯殿で客の背中を流し、掃除まで手伝うのに、女中たちから馬鹿にされ、女中頭に泣かされてしまうことさえある。何の取り柄もないもので、毎年シーズンが終わると、3人いる番頭のなかで喜十1人だけが暇を出されることになっている。つまり『ダメな番頭』でしかない。帰る里も家もないので、8月いっぱいと12月~3月の間、伊豆の谷津にある旅館に出稼ぎに出かけて、番頭の掛持ちをする。
ところが、「妙なもので、喜十さんは、谷津温泉の東洋亭に住み込むとまるで一変した扱いを受ける」。おかみさんや女中たちから「喜十さん」ではなく「内田さん」と呼ばれ、押し出しのきく『気のきいた粋な番頭さん』と見なされる。鷹揚(おうよう)にタバコをくわえて廊下をぶらぶらしたり、帳場机に頬杖をついて新聞の小説を読んだり、酒を飲みに出かけたり、夜遊びで外泊をしたり、ひげを伸ばしたりもしてしまうが、周囲の評価は変わらない。
こうなると、篠笹屋にいる時と東洋亭にいる時で、服装から変えたくなってくる。喜十は伊豆と甲州を往復の途中、熱海に一泊して、甲州湯村に向かう際には三助風に、谷津温泉に向う際には紳士風に身なりを変える。「一たん紳士風に見せたら終りまで紳士風にしたいのが人情である。東洋亭で粋にかまえている最中に、彼が篠笹屋でぺこぺこしながら背中をながした客人に顔を合わせたくないのもまた人情である。甲州では彼は決して伊豆の釣り場の景気について口外しないことになっている」とある。
つまり伊豆では、甲州とは全く切り離した形で『気のきいた粋な番頭さん』キャラクタで通したい。ついては身体もそのキャラに似つかわしいものにしたい。だが、『気のきいた粋な番頭さん』キャラの身体のままで甲州には帰れない。甲州での『ダメな番頭』キャラには、それにふさわしい別の身体がある、といったことを喜十はちゃんと了解しているわけだが、ここで重要なのは、このような二重キャラ生活は喜十が仕組んだものではなく、あくまで他発的に始まったということである。身体は同じでも、喜十について、甲州の人々と伊豆の人々はまったく別のキャラクタを作りあげたということになる。
「部活ではドジな『妹』キャラ。バイト先では『姉御』キャラでぶいぶい言わせてるけど」のように、現代社会にも多重キャラ生活を送る「喜十」はあちこちにいるのではないだろうか。